共通テストに新しく追加された情報Ⅰについて、どう対策をしたら良いのか不安に感じていませんか。
多くの受験生が苦手意識を持つプログラミングの対策や、来年以降は難化するかといった情報など、初めての共通テストで失敗や後悔をしないためにも、正しい知識を身につけることが大切です。
この記事では、私が独学で実際に9割越えを果たした経験をもとに、いつから始めるべきか、インプット教材やアウトプット教材のおすすめ、情報Ⅰの難易度や共テの配点、そしてオススメ勉強法と情報Ⅰの全体像や特徴について解説します。
FAQ形式でよくある質問にも回答していきますので、ぜひ参考にしてください。
- 共通テスト「情報Ⅰ」の概要と配点
- 効率的な学習を可能にするインプットとアウトプット教材
- プログラミング対策や来年以降の難易度予測
- 受験生が抱える疑問を解決する共 テ 情報 参考 書の選び方
共通テスト「情報Ⅰ」を突破する共テ情報参考書の選び方
- 情報Ⅰの全体像と科目の特徴
- 共テの配点と受験戦略上の位置づけ
- 情報Ⅰの難易度は暗記だけでは通用しない
- 対策をいつから始めるか?最適な学習開始時期
- 短期間で結果を出すオススメ勉強法
- 基礎固めに最適なインプット教材3選
- 実践力を養うアウトプット教材(問題集)の活用
情報Ⅰの全体像と科目の特徴

情報Ⅰは、現代社会で不可欠な情報技術の基礎から応用までを網羅する科目として、2022年度入学生から必修化されました。
これは、それまでの選択科目であった「社会と情報」と「情報の科学」の内容を統合・再編したものです。
ITの基礎知識を学ぶだけでなく、それを現実世界の問題解決に応用できる実践的な能力を育成することを大きな目標としています。
学習指導要領では、主に「情報社会の問題解決」「コミュニケーションと情報デザイン」「コンピュータとプログラミング」「情報通信ネットワークとデータの活用」という4つの分野が柱となっています。
この科目の特徴は、単に用語を暗記するだけでは対応できない点にあります。
例えば、プログラミングやデータ分析の分野では、与えられた課題に対して、学んだ知識を組み合わせて論理的に解決策を導き出す力が試されます。
情報モラルや著作権といった分野は、日頃からインターネットに触れている人にとってなじみやすい内容である一方で、論理的な思考を要する問題が大部分を占めるため、表面的な学習では高得点を狙うことは困難です。
深い理解と応用力が不可欠となるため、学習方法の工夫が求められます。
共テの配点と受験戦略上の位置づけ
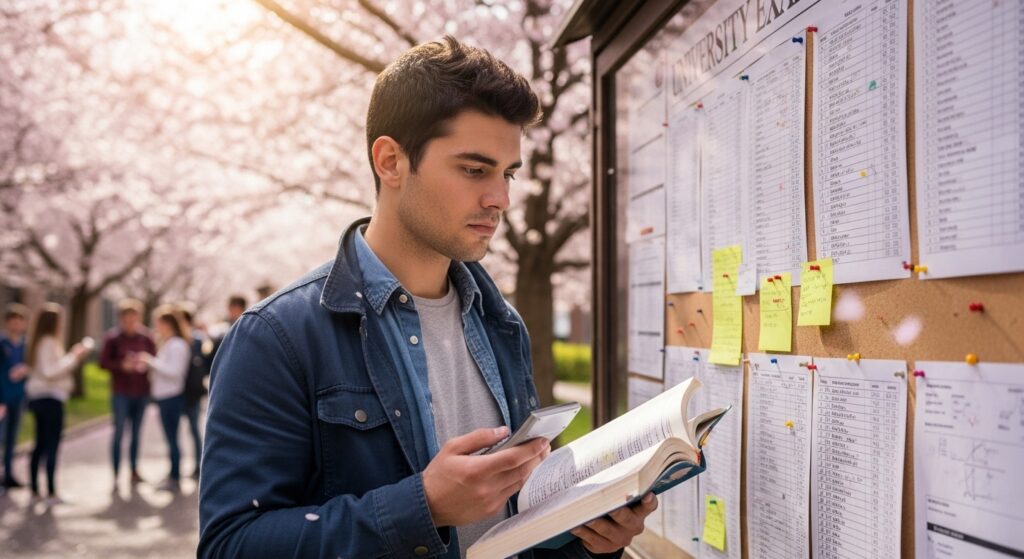
共通テストにおける情報Ⅰは、2025年度から必須科目となりました。国公立大学を志望する多くの受験生にとって、避けては通れない科目です。
しかし、大学や学部によって配点比率が大きく異なり、ほとんどの大学では全体の5%以下と低く設定されています。
このため、受験戦略としては、配点の高い英語や数学といった科目に重点を置く方が、効率的な得点アップに繋がりやすいと考えられます。
その一方で、情報Ⅰの配点比率を高く設定している大学も少数ながら存在するため、志望校の募集要項を事前に確認することが非常に大切です。
私立大学の一般入試でも選択科目として扱われることがありますが、現時点ではまだ出題傾向が確立されていないため、リスクを避ける意味でも慎重に検討する必要があります。
2025年度共通テストの出題構成と配点は、大学入試センターが事前に公表していた内容とほぼ同様でした。以下にその詳細を示します。
| 大問 | 内容 | 配点 |
| 第1問 | 小問集合 | 20点 |
| 第2問 | 領域複合 | 30点 |
| 第3問 | コンピュータとプログラミング | 25点 |
| 第4問 | 情報通信ネットワークとデータの活用 | 25点 |
| 合計 | 100点 |
大問1と2では、特定の分野に限定されない複合的な問題が出題されるため、情報Ⅰの全範囲をバランス良く学習しておくことが得点確保の鍵となります。
情報Ⅰの難易度は暗記だけでは通用しない
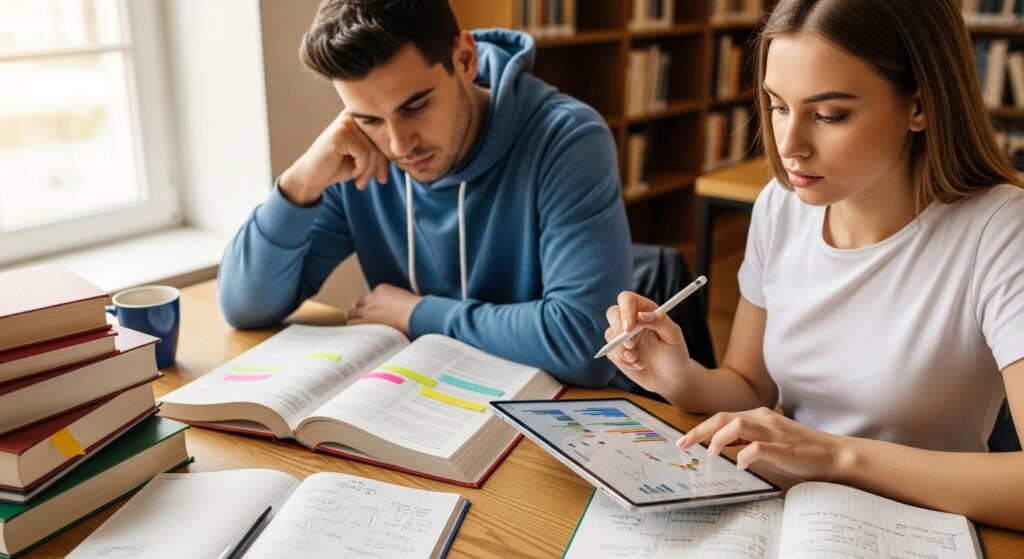
情報Ⅰの共通テストは、単純な知識の暗記だけでは太刀打ちできない思考力や読解力が問われる問題が中心となります。
2025年度の平均点は69.26点でしたが、これはあくまで初年度の傾向であり、過去の他科目の新課程移行時のように、次年度以降に難化する可能性も十分に考えられます。
特に、資料やグラフを読み取って分析する問題や、プログラミングに関する問題は、与えられた情報を正確に把握し、論理的に思考する力が不可欠です。
数学Ⅰで学習する「データの分析」の知識(散布図、箱ひげ図など)が情報Ⅰの問題解決に役立つこともあり、両科目の連携を意識した学習が有効です。
知識の表面的な理解に留まらず、それがどのような状況で活用されるのか、なぜその概念が必要なのかという背景まで深く掘り下げておくことが、安定して高得点を取るための対策となります。
対策をいつから始めるか?最適な学習開始時期
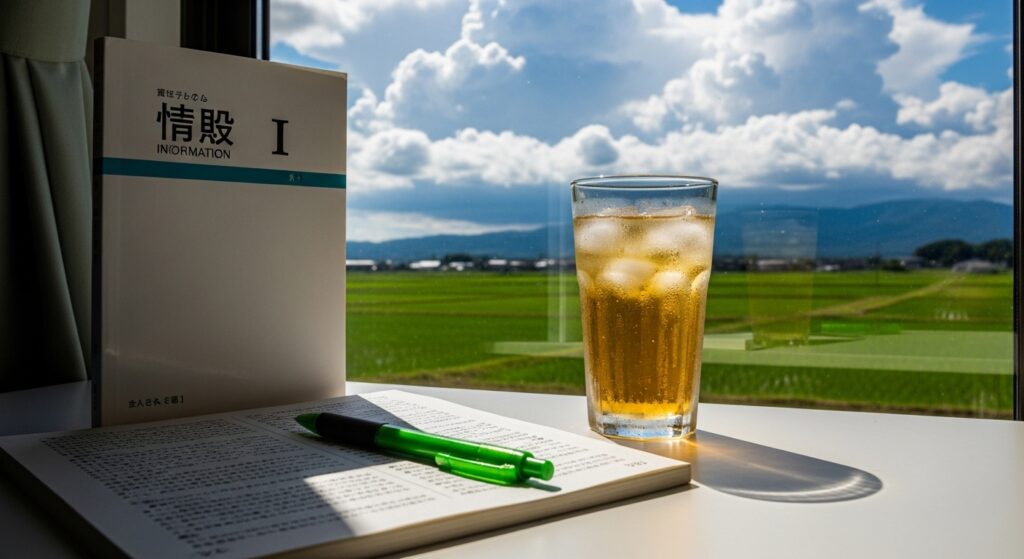
共通テストの情報Ⅰ対策は、多くの受験生が不安に感じている点の一つですが、高校3年生の夏休みごろからでも十分に間に合うと考えることができます。
これは、多くの国立大学が情報Ⅰの配点比率を低く設定しているためで、合格戦略としては、配点の高い英語や数学、国語といった主要科目に時間を費やす方が、より効率的であるためです。
限られた時間を有効に使うことが、受験全体を成功させる鍵となります。
しかし、全く学習せずに受験直前を迎えるのは大きなリスクを伴います。
特に、高校1年生の時点で情報Ⅰを学び終え、それ以降は触れていないという受験生も少なくありません。
情報Ⅰは暗記だけでは通用しない思考力を問われる科目であるため、直前に詰め込む学習では十分な得点に繋がらない可能性があります。
そのため、夏休みごろから少しずつ対策を始め、定期的に知識の定着と問題演習を重ねていくことで、無理なく実力をつけていくことをオススメします。
例えば、1日30分でも良いので、毎日コツコツと学習を継続することが、着実に得点を伸ばすことに繋がります。
短期間で結果を出すオススメ勉強法

情報Ⅰの学習は、闇雲に進めるよりも、効率的なサイクルを確立することが重要です。
短期間で成果を出すためには、以下の3つのステップを順序立てて実践することが効果的です。
この学習法は、インプットとアウトプットをバランス良く組み合わせることで、知識の定着を最大限に高めることを目的としています。
1. 流れを覚えられる参考書で全体を理解する
まずは、情報Ⅰの全体的な流れを把握できる講義形式の参考書を読んで、基礎知識をインプットします。
この段階では、細部にこだわりすぎず、大まかな内容を理解することが大切です。
2. 問題集でインプットとアウトプットを並行する
基礎知識をインプットしたら、問題集を使ってアウトプットを行います。
これにより、知識の定着を図り、テストで点数を取るための力を養います。
3. 苦手な範囲を確認し、再度インプットする
問題演習を通じて、自分の苦手な分野や解けなかった問題を特定します。
そして、その単元を再度インプット教材で確認し、理解を深めていきます。
このサイクルを繰り返すことで、効率的に学習を進めることができます。
基礎固めに最適なインプット共テ情報参考書三選
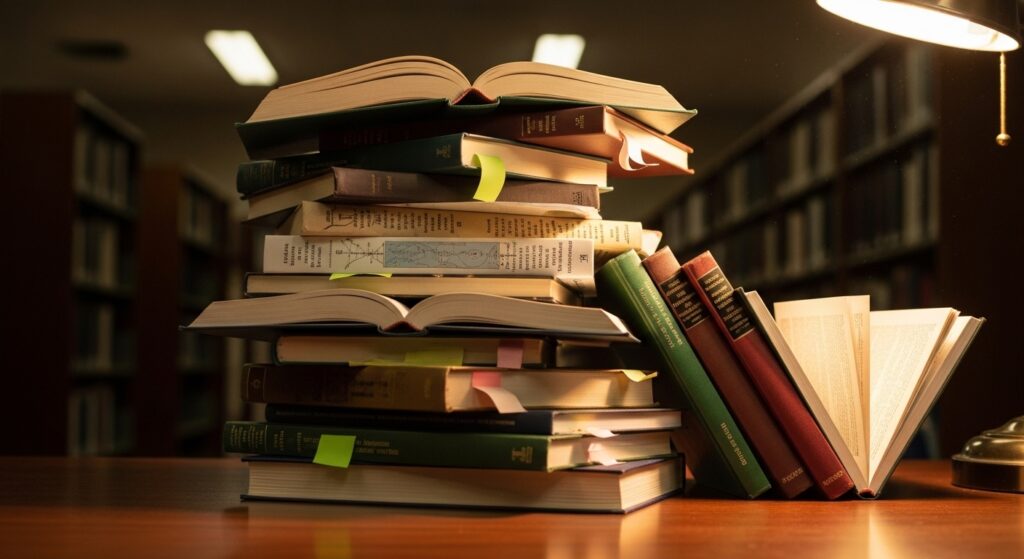
情報Ⅰの学習を始めるにあたり、何から手をつければいいか迷う方も多いでしょう。
特に初学者にとっては、専門用語が多く、とっつきにくいと感じるかもしれません。
そうした不安を払拭し、スムーズに学習をスタートさせるためには、講義形式で分かりやすく解説されているインプット教材を選ぶのが最もオススメです。
ここでは、それぞれの学習スタイルに合わせて選べる3つの教材をご紹介します。
ゼロから始める情報Ⅰ
この参考書は、学校の授業や教科書の内容をさらに分かりやすく解説することに特化しています。
ボリュームも10時間程度で読み終えられるように工夫されているため、短期間で情報Ⅰの全体像を把握したい場合に最適です。
重要なポイントが色分けされていたり、複雑な概念も詳細な図で視覚的に理解できるように工夫されているため、知識の整理がしやすいのが大きなメリットです。
初めて情報Ⅰを学ぶ方でも、つまずくことなく学習を進めることができるでしょう。

私もこの参考書を使って全体像の把握を行ったよ!
きめる!共通テスト 情報Ⅰ
「きめる!共通テスト 情報Ⅰ」は、教科書の内容はもちろんのこと、教科書には記載されていないものの、過去の大学入試で問われたことがあるテーマについても丁寧に解説しています。
この1冊で共通テスト対策に必要な知識を網羅できるため、効率的な学習が可能です。
フルカラーで重要な部分が強調されており、視覚的にも非常に理解しやすくなっています。
また、先生と生徒の対話形式で構成されているため、まるで授業を受けているかのように、サクサクと読み進めることができます。

ゼロから始める情報Ⅰよりも少し発展的な内容を扱っているよ!
渡辺の情報Ⅰをはじめからていねいに
この参考書は、初学者でも情報Ⅰの基礎を体系的に、そして正しく理解できるように設計された講義型の教材です。
IT分野における実務経験が豊富な著者が、現実社会とどのように情報技術が繋がっているのかを意識しながら、実践的に使える知識を解説しています。
単なる暗記に留まらない「思考力・応用力」まで踏み込んでおり、本質的な理解を目指せるのが大きな特徴です。
約300点以上の図やイラストが収録されているため、複雑な内容も視覚的に把握しやすくなっています。特に、共通テストで高得点を狙いたい受験生におすすめできる一冊です。

この三冊から気に入ったものを一冊読んでみてね!
実践力を養うアウトプット教材(問題集)の活用
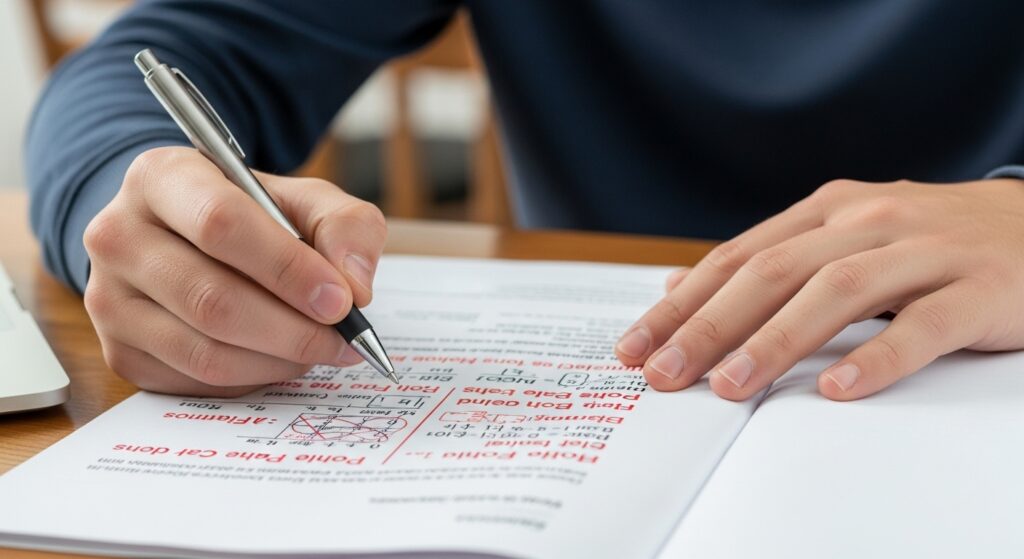
インプット教材で基礎知識を固めた後は、アウトプットを通じてその知識を定着させることが不可欠です。
問題集を解くことで、自分の理解が不十分な箇所を発見し、本番の試験形式に慣れることができます。
ここでは、特におすすめのアウトプット教材を2つご紹介します。
講義形式で学ぶ「情報Ⅰ」大学入学共通テスト問題集
この問題集は、大学入試センターが公表している3種類の問題を徹底的に分析して作成されています。
教科内容の復習と模擬問題によるアウトプットを同時に行うことができ、効率的な学習が可能です。
全体的に難易度はやや高めに設定されていますが、解説が非常に丁寧であるため、インプット教材を終えた後に取り組むことで、飛躍的に実力を伸ばすことができるでしょう。
すべての問題に解説動画が付いているため、一人で学習を進める際も、つまずくことなく理解を深められます。
ライバルに差をつける 情報I 鉄板の100題
この問題集は、基礎的なレベルから共通テスト相当のレベルまで、段階的に難易度が上がっていく構成になっています。
ステップアップ形式で学習を進めることができるため、自分の実力に合わせて着実に力を付けていくことが可能です。
この問題集は、「ゼロから始める情報Ⅰ」と同じ著者によって執筆されているため、インプット教材と合わせて使用することで、より一貫した学習効果が期待できます。
100題という豊富な問題量で、実践的な演習量を確保し、知識を確固たるものにできるでしょう。
弱点克服と未来予測!確実な対策を進めるための共テ情報参考書活用術
- 避けて通れないプログラミングの対策
- 来年以降は難化するか?出題傾向を予測
- 受験生が知りたいFAQ(よくある質問)
避けて通れないプログラミングの対策

共通テストの「情報Ⅰ」において、プログラミングは最も配点比率の高い分野の一つであり、合否を分ける重要な要素となり得ます。
この分野では、特定のプログラミング言語の知識を問うのではなく、共通テスト手順記述標準言語(DNCL)という架空の言語を用いて、論理的な思考力や問題解決能力を評価するのが特徴です。
受験生は、この見慣れない言語に戸惑うかもしれませんが、心配する必要はありません。
DNCLは、既存のプログラミング言語の基本的な概念を抽出し、簡潔にまとめたものだからです。
効果的な対策としては、まずプログラミングの基本的な構文(条件分岐のif文や、繰り返し処理のwhile文、for文など)や、処理の流れを図式化したフローチャートの読み取り方をしっかりと理解することが挙げられます。
これらの基礎は、どのプログラミング言語にも共通する「論理的な考え方」そのものです。
例えば、Python、JavaScript、VBA、Scratchといった主流の言語の中から、どれか一つを深く学習しておくことで、自然とDNCLにも対応できる力が身につきます。
これらの言語に実際に触れてみることで、コードがどのように動き、どのような結果を生み出すのかを体感的に理解することが可能になります。
プログラミングの学習を通じて、与えられた問題を分解し、順序立てて解決策を考える力を養うことが、この分野で得点を獲得する上で非常に大切です。
プログラミングに不安のある人は以下のようなプログラミング専用の参考書で対策するのもオススメです。
来年以降は難化するか?出題傾向を予測
2025年度の共通テスト「情報Ⅰ」は、初の実施ということもあり、全体的に解きやすい問題が多かったとの声が多く聞かれました。
平均点も69.26点と比較的高い水準でしたが、だからといって2026年度以降も同じ難易度が続くとは限りません。
過去に新課程へ移行した科目の傾向を振り返ると、初年度は様子見の出題となり、2年目以降に難化するケースが見られます。
このため、2026年度の共通テストは、より深い思考力や応用力を問う問題が出題される可能性が考えられます。
このような状況を踏まえると、初年度の問題が簡単だったからといって油断することなく、しっかりと対策を進めることが重要です。
単に知識を暗記するだけでなく、問題の意図を正確に読み取り、論理的に解答を導き出す練習を重ねておくことが求められます。
大学入試センターが公表している試作問題や、各予備校から出版されている問題集を解くことで、多様な出題形式に慣れておくと良いでしょう。
受験生が知りたいFAQ(よくある質問)
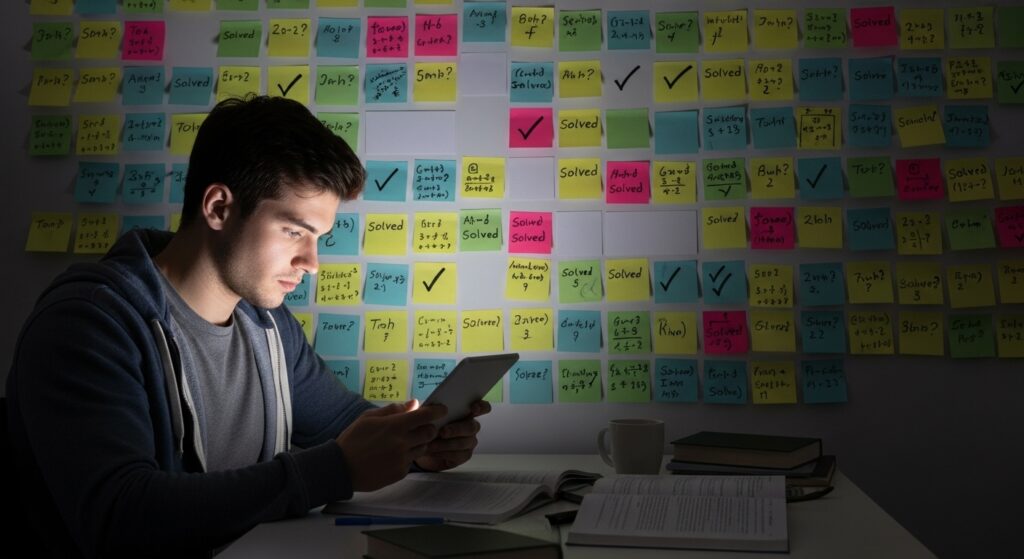
受験生の皆さんが抱えがちな、情報Ⅰに関するよくある質問とその回答をまとめました。
Q1: 共通テスト対策は過去問だけで十分ですか?
A: 2025年度の共通テスト「情報Ⅰ」が初年度であったため、過去問は一年分しか存在しません。
したがって、過去問演習のみに頼ることはできません。
対策としては、大学入試センターが公表している試作問題やサンプル問題が、公式な実践問題となります。
これらの問題を徹底的に分析し、出題形式や傾向を把握することが不可欠です。
それに加えて、大手予備校が作成した共通テスト総合問題集や、模擬試験の問題を解くことで、実践的な演習量を確保し、様々な形式の問題に対応できる力を養うことをオススメします。
Q2: 独学でも共通テストで高得点を取れますか?
A: 独学でも共通テストで高得点を狙うことは十分に可能です。
情報Ⅰは、正しい教材を選び、効率的な学習法を実践すれば、自学自習で力を伸ばしやすい科目です。
重要なのは、インプットとアウトプットのバランスを取りながら、計画的に学習を進めることです。
この記事で紹介したような、全体像を把握するための参考書と、実践的な問題演習のための問題集を組み合わせて使用することで、独学でも着実に実力を積み上げていくことができるでしょう。
自らのペースで学習を進め、苦手な部分を重点的に克服していくことで、高得点を目指すことが十分可能であると言えます。
効率よく学習を完結させるための共テ情報参考書まとめ
この記事のポイントをまとめておきます。
- 情報Ⅰは思考力と読解力を要する科目であり暗記だけでは通用しない
- 共通テストではプログラミングやデータ分析が出題の中心となる
- 共通テストの情報Ⅰ対策は高3の夏休みからでも十分間に合う
- 配点比率が低い大学が多いので他教科とのバランスを考えることが大切
- まずは流れを掴む参考書で全体像を理解するのが効率的です
- 問題演習を通じて知識を定着させ苦手分野を特定することが重要
- インプット教材は授業内容をさらに分かりやすく解説しているものがおすすめです
- アウトプット教材は共通テスト形式の問題に多く触れることが重要です
- プログラミング対策はDNCLに対応できる論理的思考力を養う
- 特定の言語知識ではなく基本的な構文の理解を深めておく
- 2025年度が初年度のため2026年度以降は難化する可能性がある
- 共通テストの過去問がないため試作問題や模試問題を活用する
- 情報Ⅰを独学で学ぶ際は適切な参考書選びが結果を左右する
- 最新の傾向を踏まえた問題集を選ぶことが大切です
- 受験生が抱える疑問はFAQなどを活用して解決しましょう



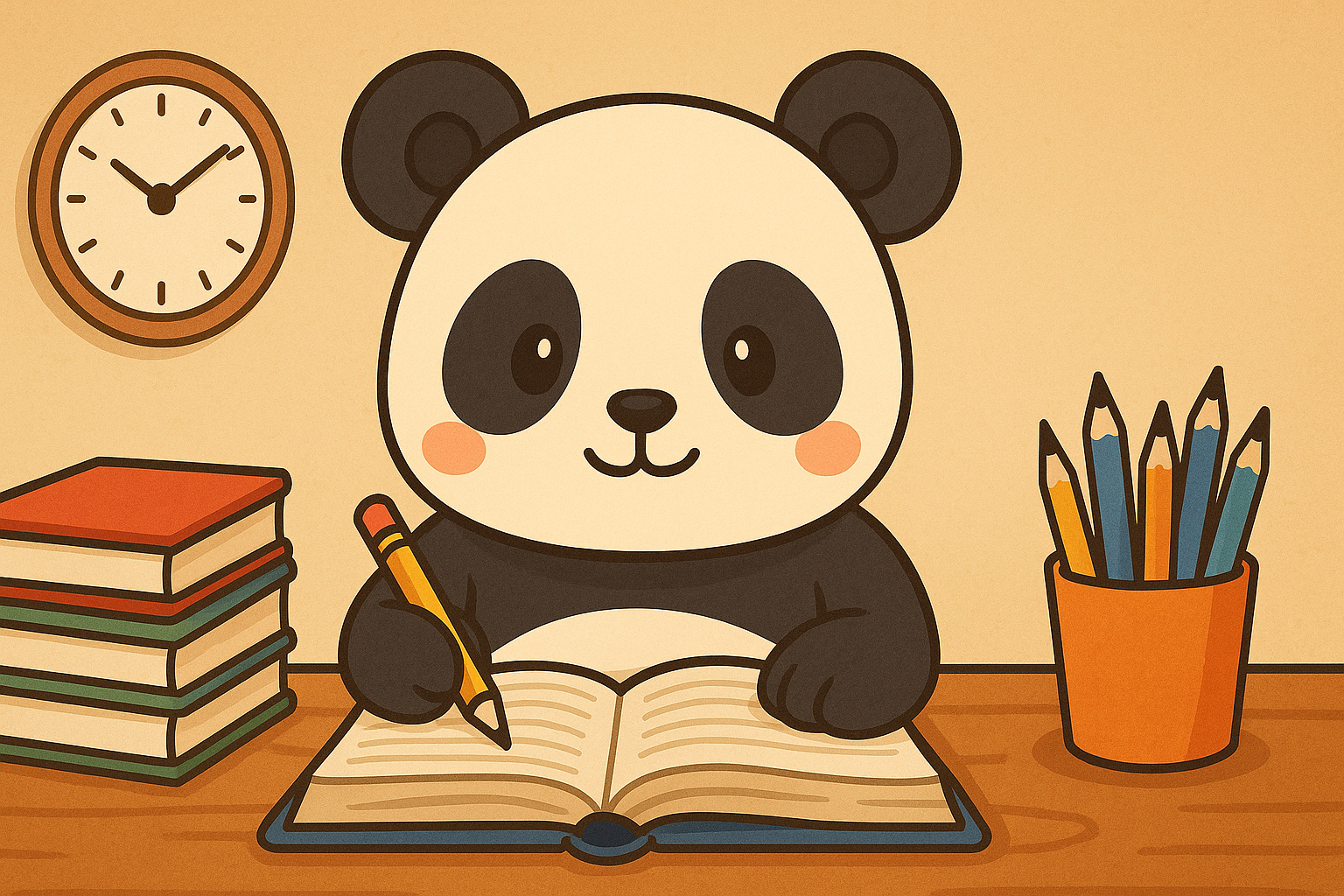


コメント