皆さんこんにちは、このサイトの運営者のパンダです。
「神戸 大学 共通 テスト ボーダー」と検索して、この記事にたどり着いたということは、「神戸大学に合格するためには、共通テストでどれくらいの点数がいるんだろう?」と、具体的な目標ラインを探しているところかなと思います。
神戸大学は関西圏でもトップクラスの難関国立大学ですから、学部によっては共通テストの得点率が85%を超えることもあります。
特に、医学科や人気の高い法学部・経済学部などでは、共通テストのボーダーラインは常に注目されていますよね。
この記事では、最新の共通テストボーダー情報から、神戸大学合格に必要な対策、さらにはキャンパスの特徴や就職実績まで、あなたの受験勉強を強力にサポートする情報を、私の京大生としての経験も踏まえて分かりやすく解説していきますよ!
- 神戸大学共通テストボーダーの具体的な学部別得点率と最新偏差値を把握できる
- 合格に必要な科目別(英語・数学・国語など)の出題傾向と具体的な対策ポイントがわかる
- 神戸大学のキャンパス情報や高い就職実績といった魅力を理解できる
- 神戸大学志望者が想定すべき併願校の候補を知ることができる
まずは、神戸大学の共通テストのボーダーラインが実際どのくらいなのか、具体的な数値からチェックしていきましょう!
- 2026年度 神戸大学共通テストボーダーの全体像
- 神戸大学共通テストボーダー突破のための科目別対策
2026年度 神戸大学共通テストボーダーの全体像
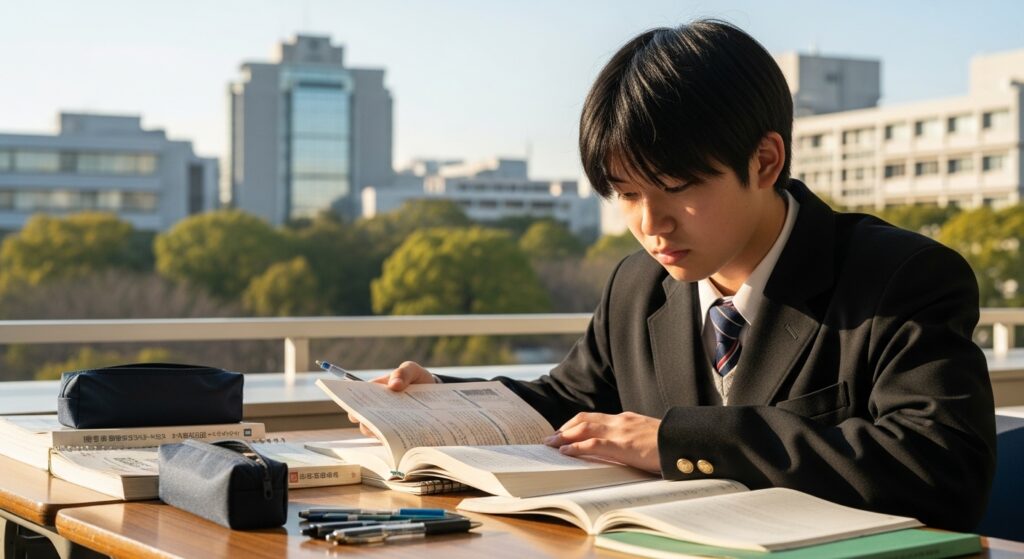
神戸大学合格を目指す上で、まず知っておきたいのが、各学部の共通テスト得点率と最新の偏差値です。
ここでは、具体的な数値を見て、自分の目標ラインを明確にしていきましょう。
学部別 共通テスト 得点率(ボーダー)一覧

神戸大学の共通テスト得点率(ボーダー)は、学部や学科によって大きく幅があり、概ね70%台から85%台前半となっています。
京大や阪大に次ぐ難関大学として、どの学部でも共通テストでしっかりと高得点が要求されることが分かりますね。
文系・理系 主要学部のボーダーライン詳細
文系では、文学部(人文学科)、法学部(法律学科)、経済学部、経営学部といった主要学部の前期日程ボーダーが軒並み約79%を占めています。
これは、共通テストで全科目においてほぼミスが許されない水準、つまり8割近い得点を安定して取らなければ、二次試験に進むための足切りやボーダーラインで苦戦する可能性が高い、ということを意味しています。
特に後期日程となると、これらの学部ではボーダーが約85%まで跳ね上がるため、共通テストで圧倒的な高得点を確保しておくことが必須になりますよ。
理系では、理学部、工学部が前期で72%〜78%程度、農学部が75%〜79%程度と、文系よりはやや幅があるものの、人気の高い学科や後期日程では80%台の得点が必要になります。
そして、やはり最も高いのが医学部医学科で、前期から約87%という超高得点が要求されます。
保健学科でも68%〜78%と学科によって幅があるので、自分の志望学科の数値を正確に把握し、目標点を設定することが何よりも重要です。
主要学部の共通テストボーダー得点率(前期日程の目安)
あくまで目安ですが、主要学部の前期・後期日程のボーダー得点率をまとめました。
| 学部 | 学科 | 共通テスト得点率(前期) | 共通テスト得点率(後期) |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 約79% | 約85% |
| 法学部 | 法律学科 | 約79% | 約85% |
| 経済学部 | 経済学科 | 約79% | ― |
| 経営学部 | 経営学科 | 約79% | ― |
| 理学部 | 学科による | 72%~77%程度 | 82%~85%程度 |
| 工学部 | 学科による | 73%~78%程度 | 84%~86%程度 |
| 農学部 | 学科による | 75%~79%程度 | 80%~83%程度 |
| 医学部 | 医学科 | 約87% | ― |
出典:各種予備校(河合塾や駿台など)の予想ボーダーに基づいています。後期日程の設定がない学部もあります。
医学部医学科はやはり別格の難易度ですが、文系の主要学部は前期で約79%が一つの大きな目安となります。
また、後期日程は、どの学部も前期よりもボーダーが数ポイント高くなる傾向にあるので、特に注意が必要です。
このボーダーを目標点とするのではなく、確実に合格圏内に入るためにも、プラス2〜3%を目指すくらいの気持ちで取り組むのが得策ですよ。
ボーダー偏差値で見る学科ごとの難易度

共通テストの得点率だけでなく、予備校が出しているボーダー偏差値も、難易度を測る上で重要な指標です。
これは、共通テストと二次試験の総合的な合否判定における、50%合格ラインの目安となるものです。
神戸大学の二次試験は難易度が高いため、この偏差値も参考に、二次試験対策の重み付けを考えていきましょう。
文系学部のボーダー偏差値
文系主要学部では、文学部(人文学科)、法学部(法律学科)、経営学部がいずれも前期で62.5という高い水準にあります。
経済学部は60.0~62.5と若干の幅がありますが、この数値からも、神戸大学が関西圏の私立トップである関関同立(偏差値57.5〜65.0程度)よりも頭一つ抜けた難易度であることが分かりますね。
特に文学部の後期日程は67.5と、二次試験対策でさらに高いレベルが要求されます。
偏差値62.5というのは、受験生の上位約10%に位置することを示すため、日々の学習で高精度のインプットとアウトプットが求められますよ。
理系学部のボーダー偏差値と医学科
理系では、理学部や工学部系で57.5~62.5と、学科によって得意・不得意が反映されやすい幅があります。
特にシステム情報学部は60.0~65.0と幅広く、人気のある分野は高めの偏差値となる傾向です。
もちろん、医学部医学科は67.5と、文理を通じて最難関であり、共通テストの得点率だけでなく、二次試験の数学・理科・英語の全てで高得点が必須となります。
ボーダーラインはあくまで「目安」だよ!
共通テストの得点率も偏差値も、予備校が発表するデータは「50%合格ラインの目安」です。募集人数やその年の受験者の動向によって変動します。
また、神戸大学は二次試験の配点比率も高いので、共通テストの点数がボーダーを下回っても、二次試験で挽回できる可能性は十分にあります。
これらの数値に一喜一憂せず、目標点を数パーセント上回ることを目指して、二次対策とバランスを取りながら勉強を進めるのが鉄則ですよ!
正確な情報は、必ず神戸大学の公式入試要項や、最新の予備校の動向分析でチェックするようにしてくださいね。
神戸大学の学部別キャンパス所在地と特徴

神戸大学は一つの巨大なキャンパスではなく、複数のキャンパスに分かれており、それぞれに独自の雰囲気と専門分野に特化した施設があります。
自分の志望学部がどのキャンパスに位置し、どのような環境で学べるのかを知っておくのは、モチベーション維持に非常に大切です。
六甲台キャンパス:主要文理学部が集結する緑豊かな環境
神戸市の灘区に位置する六甲台キャンパスは、第1(法、経済、経営)と第2(文、理、農、工、システム情報)に分かれていますが、全体として六甲山麓の緑豊かな自然に囲まれた環境が特徴です。
京大のある吉田キャンパスとはまた違った、山の中のキャンパス特有の落ち着いた雰囲気と、広大な敷地が魅力です。
六甲台講堂のような歴史的な建物や、自然科学系図書館など、学習環境も充実しています。
医学系キャンパス:最先端の医療を学ぶ楠・名谷
医学部は、医学科が神戸市中央区の楠(くすのき)キャンパスに、保健学科が須磨区の名谷(みょうだに)キャンパスに分かれています。
どちらも都市型のキャンパスで、最新の医療設備が整った附属病院に隣接しているため、実習や最先端の研究に触れやすい環境です。
未来の医療を担う場所として、常に活気がありますよ。
海事・国際系のキャンパス:深江と鶴甲
深江キャンパス(東灘区)には、海事科学部から改組された海洋政策科学部があります。
ここは海沿いに位置しており、国際海事研修センターや海事図書館といった専門性の高い施設が充実しており、まさに海をフィールドにした学びが実現できる場所です。
また、鶴甲(つるかぶと)キャンパスには国際人間科学部などがあり、歴史ある文系学部が中心で、落ち着いた建物が並んでいます。
どのキャンパスも、それぞれの学問分野に最適化された学習環境が整っているのが神戸大学の大きな魅力かなと思います。
就職実績や平均年収など進路傾向

神戸大学の卒業生は、関西圏を中心とした社会で非常に高い評価を得ており、その就職実績は極めて高水準です。
これは、頑張って神戸大学に合格する大きな理由の一つになるはずですよ。
驚異的な就職率と優良な就職先
2023年度の卒業生平均就職率は約92.2%と、難関国立大学の中でもトップクラスの数字を示しています。
特に保健学科(理学療法・看護等)は98.9%、理学部は95.2%と、専門性の高い分野で高い就職率を誇っています。
主な就職先を見ても、関西電力、クボタ、三井住友銀行、富士通、三菱電機、楽天グループなど、関西圏の大手優良企業への就職が目立ちます。
また、神戸大学附属病院や神戸市役所、兵庫県庁といった医療機関や地方自治体への就職数も多く、地域社会に貢献する人材を多く輩出していることが分かります。
文系(経済・経営)は金融・IT企業、理系(工学・理学)は製造業・インフラ系、医学・保健系は医療機関といった傾向が明確に出ており、これは専門性を活かしたキャリアを築きやすいということを示していますね。
長期的なキャリアアップにも強い
さらに注目すべきは、神戸大学卒業生の平均年収が国内主要大学でも上位に位置しているという点です。
これは、卒業後も順調にキャリアを積み重ね、評価の高い職場で活躍していることの裏付けになります。
神戸大学というブランド力と、在学中に培った論理的思考力や専門知識が、卒業後の長いキャリアにおいて大きなアドバンテージとなることは間違いないでしょう。
(出典:神戸大学キャリアセンター『2023年度学部卒業者・大学院(修士・博士前期課程)修了者の主な就職先』)
神戸大学の主な就職先(2023年度実績より抜粋)
- 金融・保険:三井住友銀行、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険、大和証券
- 製造業:富士通、ダイキン工業、パナソニック、日立製作所、クボタ、神戸製鋼所、村田製作所
- インフラ・エネルギー:関西電力、大阪ガス、西日本旅客鉄道(JR西日本)、NTT西日本
- 公務員・医療:神戸大学医学部附属病院、神戸市役所、兵庫県庁、国家公務員(厚生労働省など)
- 商社・流通:伊藤忠商事、丸紅、楽天グループ
出典:神戸大学キャリアセンター
神戸大学を検討する上での想定併願校
神戸大学を第一志望とする受験生にとって、共通テストの得点率や二次試験の負担を考慮した併願校選びは非常に重要です。
適切な併願校を確保しておくことで、精神的な余裕も生まれますからね。
関西の難関私立「関関同立」は必須の併願先
神戸大学志望者が最も多く併願するのは、やはり関西の難関私立大学である「関関同立」(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)です。
共通テスト利用入試や一般入試で、これらの大学の合格を確保しておくのが一般的です。
特に、二次試験の負担を軽くするためにも、共通テストの得点率が高ければ、共通テスト利用で抑えを固めておく戦略は非常に有効です。
併願校選びのポイント
共通テストの得点率が近い大学を選ぶだけでなく、神戸大学の二次試験の科目(特に数学や理科の範囲)と、併願校の受験科目が重なっているかどうかをチェックして、勉強の効率を最大化できる組み合わせを選ぶのがベストです。
無理なく対策できる大学を選ぶことが、神戸大学合格への集中力を高めることに繋がります。
ここからは、いよいよ神戸大学の共通テストボーダーを突破するための、具体的な科目別対策に入っていきましょう!
神戸大学共通テストボーダー突破のための科目別対策

共通テストで求められるのは、全科目の総合力です。
ここでは、最新の出題傾向を踏まえ、各科目で高得点を取るための勉強ポイントを私の目線で解説します。
神戸大学のボーダーラインを突破するためには、得意科目で満点近くを目指し、苦手科目でも大きな失点を避ける戦略が重要ですよ。
共通テスト 英語 の出題傾向と攻略ポイント

2025年度共通テストの英語は、リーディング、リスニングともに傾向の変化が見られました。
特に、リーディングでは評論文やエッセイ、図表読解といったアカデミックな内容が中心となり、会話文や対話形式の問題が出題されないという傾向が際立っています。
リーディング:速読力と精読力の「バランス」が鍵
問題数が減ったとはいえ、一つ一つの文章量は依然として多いため、長文を素早く読みこなす速読力は必須です。
しかし、神戸大学レベルを目指すなら、ただ速いだけでなく、情報を正確に読み取る精読力との両立が求められます。
普段の演習から、必ず時間を計って問題を解き、時間内に解き終わった後も、なぜその答えになるのかを文法的に確認する精読の作業を怠らないでください。
特に、図表やグラフを読み解く問題が増えているので、英文と非言語情報との関連付けを素早く行う練習をしましょう。
詳しくはこちら↓
【完全保存版】共テ英語満点が教える!共テ英語で9割を取る勉強法!
共テ英語リーディングの解き方完全ガイド|時間配分と各大問の攻略法
リスニング:多様な発音への慣れと状況把握力
リスニングでは、アジア系訛りの話者も取り入れられる傾向が続いており、単なるアメリカ英語に慣れているだけでは通用しません。
対策としては、公式の過去問や予想問題はもちろんのこと、英語ニュースやTEDトークなど、アカデミックな内容を多様な発音で聞く機会を日常的に設けて、耳を慣らすことが大切です。
リスニングは「聞き取る力」だけでなく、「状況を把握する力」も問われるので、音声を聞きながら図やグラフ、メモを取る練習も効果的ですよ。
共通テスト 数学 の出題傾向と攻略ポイント
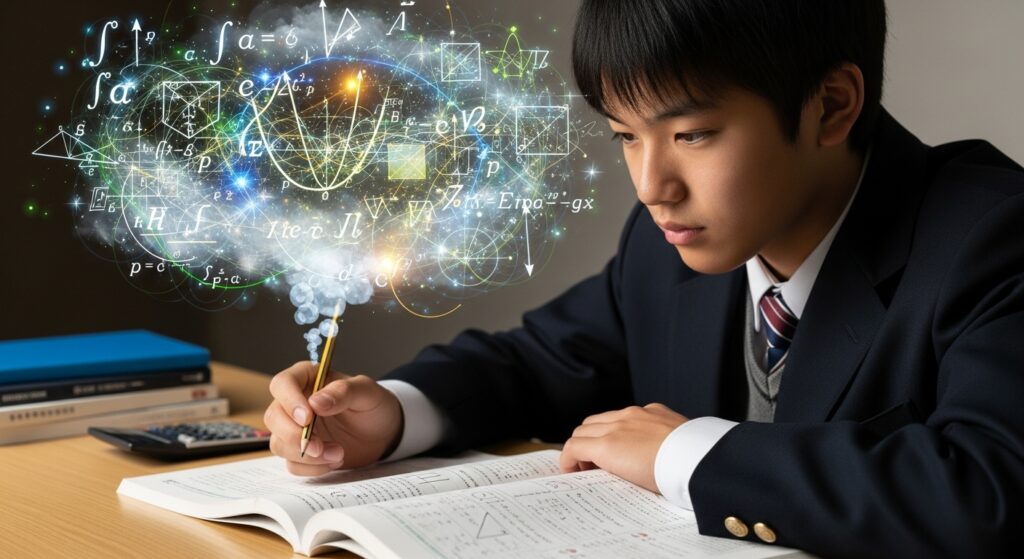
新課程最初の2025年度は、数学I・A、II・Bともに、従来の共通テストよりも数学的思考力が深く試される問題が多く出題されました。
特に新出分野が含まれたことで、基礎概念の理解が不十分な生徒と、しっかり応用できる生徒とで、得点差が大きく開いた印象があります。
基礎概念の徹底理解:「なぜそうなるか」を追求する
「外れ値」「仮説検定」「期待値」といった新分野だけでなく、二次曲線と複素数平面を組み合わせた問題など、応用的な思考を要する問題が増えています。
公式を覚えるだけでは対応できません。
数学の勉強においては、常に「なぜこの公式が成り立つのか」「この解法が使える理由」といった基礎概念を徹底的に深掘りしてください。
これにより、新傾向の問題や見たことのない問題にも、既知の知識を応用して対応できるようになります。
数学で高得点を取るための鉄則
まずは教科書や網羅系参考書で基礎を固めたら、すぐに共通テストの過去問や質の高い予想問題集に取り組み、実戦的な演習を重ねましょう。
また、数学は時間が厳しくなることが多い科目なので、難問にこだわって時間を浪費しないよう、各大問に割り当てる時間を決めておく時間配分練習が非常に重要です。
解けないと判断したら、すぐに次の問題に進む見切り力も養ってください。
関連記事↓
共テ数学ができない人必見!共テ数学で9割とるためのコツと勉強方法
共通テスト 国語(現代文・古文・漢文)の対策法
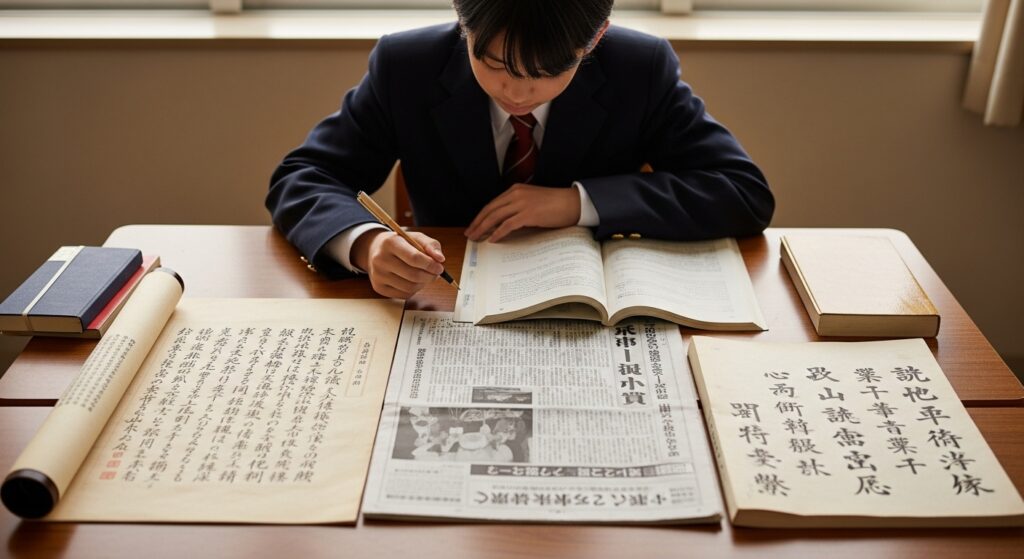
国語は新形式として第3問に「資料総合」が導入され、試験時間が90分となりました。
この時間内で現代文3題(実質)、古文1題、漢文1題の合計5題を解ききるには、非常に戦略的なアプローチが必要です。
現代文:時間戦略と新形式への対応
新設された第3問の資料総合は、グラフや複数の文章を読み比べて解く形式で、慣れが必要です。
読解力そのものを高めることは大前提ですが、本番で90分を最大限に活用するために、第1問・第2問・第3問それぞれにどれくらいの時間をかけるかを事前に計画し、模試や演習でその計画通りに解く練習をしてください。
資料問題はパターンが限られるため、予備校の資料や模試などで形式に慣れておきましょう。
古文:主体の整理と反復練習
物語文や日記文が出題されやすい傾向があります。
特に、登場人物が多い場合は、系図を書いて整理するのが非常に効果的です。
また、古文は主語だけでなく、客体(「誰に」)も省略されやすいので、常に「誰が誰に何をしたか」という動詞の主体・客体を意識して読む練習を積むことで、読解の精度が格段に上がります。
一度正確に読めた文章を反復し、スラスラ読める速読力を養ってください。
漢文:白文読解と基本文法
出題は常に書き下し文のない白文です。
問題は、返読文字や句形、対句といった基本文法知識で解けるものが大半を占めます。
まずは、「再読文字」「使役・受身の句形」など、基本的な文法を完璧に身につけることが得点への近道です。
また、設問同士には文章全体を貫く一貫した論旨があるので、各設問の答えが全体の文脈と整合するかを意識して解くと、正答率が向上しますよ。
関連記事↓
【2026年度最新版】共テ国語の時間配分と解く順番を完全ガイド
共通テスト 理科(物理・化学・生物)の対策法

理科は、基礎知識の定着に加えて、実験考察や資料の読み取りといった応用力が問われます。
神戸大学のボーダーを狙うなら、理科で大きな失点をするわけにはいきません。
物理:グラフ・図表の徹底マスター
物理ではグラフ読解問題が非常に頻出しています。
教科書の基本原理をしっかり押さえた上で、問題集や過去問で、グラフや図表から物理現象を読み解くタイプの問題に重点的に取り組んでください。
現象を視覚的に理解できることが、難問を解く鍵となります。
関連記事↓
共通テスト物理の原子を捨てるとどうなる?後悔しないための判断基準
化学:網羅的な学習と基礎知識の定着
化学は範囲が広いため、全分野を満遍なく学習することが重要です。
「ここだけは捨てる」といった戦略は通用しにくいです。
教科書と網羅系問題集で基礎知識を固めたら、分野横断的な問題や計算問題にも慣れて、知識を応用する力を身につけましょう。
関連記事↓
【完全保存版】京大生が厳選する共テ化学のオススメ参考書ルート
生物:実験事象の理由・仕組みまで理解する
生物は例年難度が高く、単なる知識問題だけでなく、実験事象の背後にある理由や仕組みまで深く理解しているかが問われます。
教科書レベルの知識はもちろん、なぜその実験結果が得られたのか、という考察力を養うことが、他の受験生に差をつけるポイントになります。
実験考察問題に特化した問題集にも取り組むことをおすすめします。
共通テスト 社会 の対策と知識定着のコツ

地理・日本史・世界史・倫理・政治経済の社会科目は、暗記が中心です。いかに正確に知識を定着させ、本番で素早く引き出せるかが勝負です。
教科書・用語集による基礎知識の徹底
社会科の基本は、教科書と用語集です。
まずはこれらの教材で、基礎知識をしっかり頭に入れ、抜けがない状態を目指してください。
特に、教科書に載っている図表や資料、注釈まで目を通すことで、単なる用語の暗記を超えた、深い理解が得られます。
インプットとアウトプットの繰り返し
知識を定着させるためには、インプット(覚える)とアウトプット(問題を解く)の繰り返しが不可欠です。
過去問や一問一答形式の問題集で繰り返し演習を行い、知識の引き出しを早くする練習をしましょう。
歴史科目などは、時代の流れや因果関係を意識して覚えると、知識が繋がり、応用力が身につきます。
暗記科目の効率的な勉強法
暗記科目は、一度に集中してやるよりも、毎日少しずつ反復するほうが知識が定着しやすいです。
通学時間や休憩時間など、スキマ時間を活用して用語集や一問一答を確認するルーティンを取り入れると効果的ですよ。
関連記事↓
共テ地理はたつじん地理で9割安定!最短最速の共テ地理の勉強方法!
神戸大学 共通テストボーダー突破に向けた学習計画
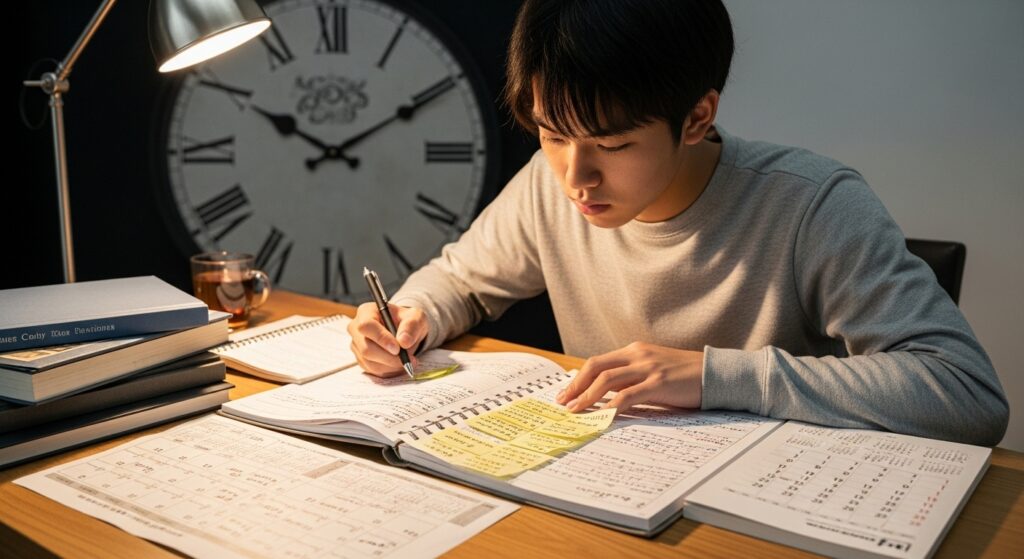
神戸大学の共通テストボーダーラインをクリアするためには、長期的な計画と日々の確実な実行が必要です。
特に共通テストと二次試験のバランスが重要になります。
夏までの重要フェーズ:基礎の完成と二次対策の開始
高校3年生の夏までには、遅くとも主要科目の教科書レベルの基礎固めを完了させることを目標にしてください。
これは、共通テストだけでなく、神戸大学の二次試験対策の土台にもなります。
特に、二次試験の配点が高い科目(例えば理系なら数学・理科)は、夏休み中に基礎から応用へのステップアップを図り、二次試験対策を本格的に開始する必要があります。
秋以降のフェーズ:共通テスト演習の徹底
夏休み以降は、共通テストの過去問や予想問題集を使った実戦形式の演習を本格的に開始してください。
この時期から、常に本番と同じ時間配分で解く練習を取り入れ、自分の弱点分野を特定し、集中的に潰していくことが重要です。
特に、共通テストは独特な問題形式が多いので、形式慣れがそのまま得点に直結します。
京大生パンダからのアドバイス
神戸大学合格者は、共通テスト直前の1〜2ヶ月間は、共通テスト対策に集中しつつも、二次試験で使う科目(特に記述力の必要な科目)の対策も週に数回は継続しています。
共通テストの点数がボーダーを超えても、二次試験で思うように点が取れなければ合格できません。
共通テスト対策と二次対策のバランスを、最後まで意識して勉強を進めるのが成功の秘訣ですよ!
2026年度 神戸 大学 共通 テスト ボーダーまとめと今後の対策
ここまで、2026年度入試に向けた神戸 大学 共通 テスト ボーダーの具体的な情報と、それを突破するための科目別対策を解説してきました。
改めて、神戸大学の共通テストボーダーは、人気の学部で79%前後、医学科では87%と非常に高い水準にあります。
この高得点を安定して取るためには、特定の科目だけでなく、全科目の穴をなくし、最新の出題傾向に合わせた対策を徹底することが重要です。
私が京大受験で培った経験から言えるのは、ボーダーラインはあくまで「目安」だということです。
目標点を数パーセント上回る高い目標を設定し、日々の学習でそれをクリアしていくことこそが、最終的な合格に繋がります。
この情報が、あなたの受験勉強の明確な道標となり、神戸大学合格への大きな一歩となることを願っています。
あなたの神戸大学合格を、心から応援しています!何か質問があったら、いつでもコメントで聞いてくださいね。

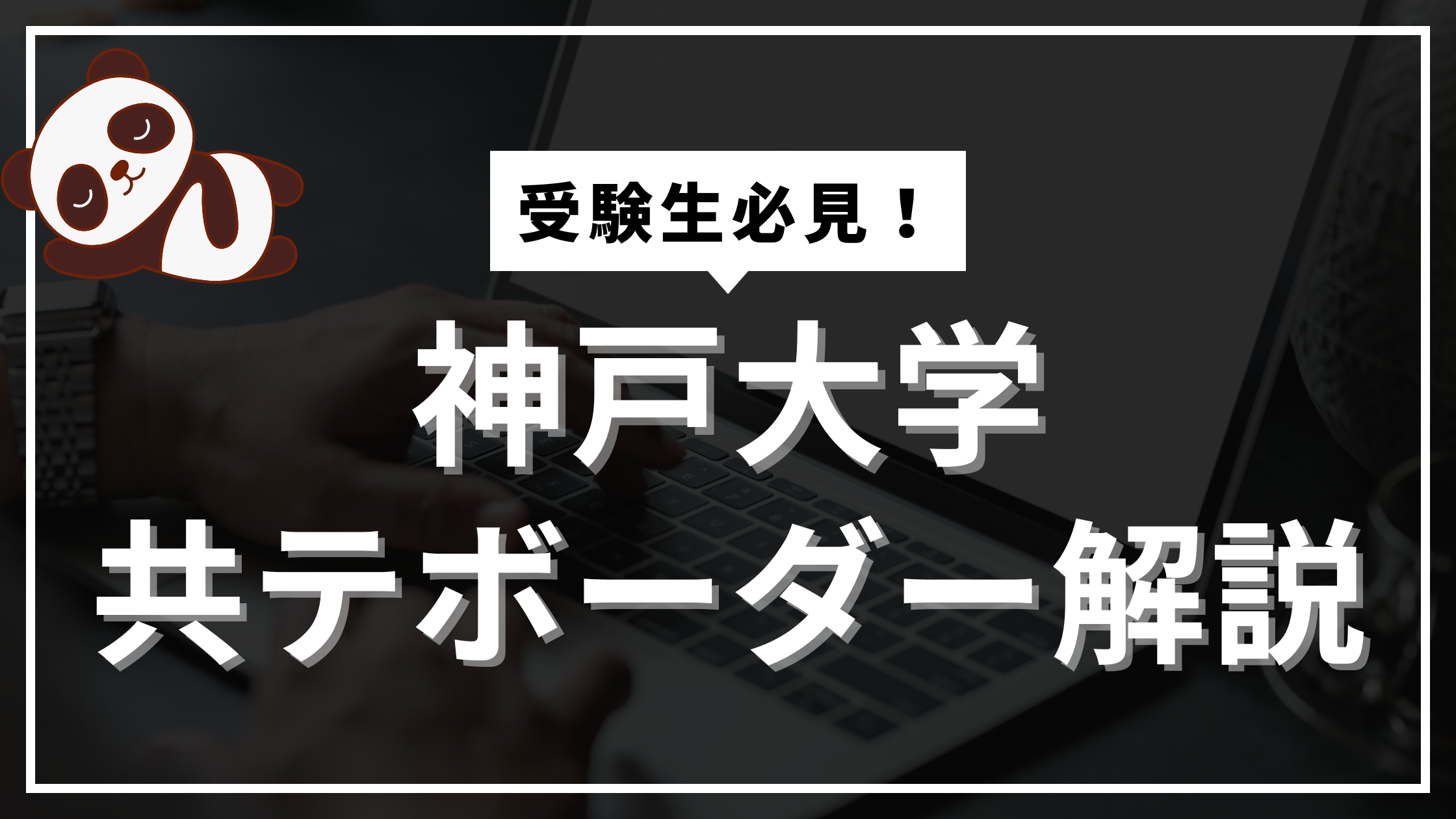

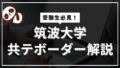
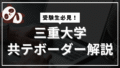
コメント