こんにちは。現役京大生の受験バイブル、運営者の「パンダ」です。
静岡大学、通称「静大」。
中堅国立大学群として知られる「5S(埼玉・信州・静岡・滋賀・新潟)」の一角として、毎年多くの受験生が志望する人気大学ですね。
「地元で安定した生活を送りたい」「そこそこの難易度で就職が良い大学に行きたい」と考えているあなたにとって、静岡大学は非常に魅力的な選択肢に見えているはずです。
しかし、実際のところ共通テストでどれくらいの点数を取ればいいのか、そのボーダーラインや難易度の「中身」まで詳しく理解できているでしょうか?
特に2025年度入試(令和7年度)からは、新学習指導要領への移行に伴い「情報I」が共通テストに加わったり、英語リスニングの難易度傾向が変わったりと、過去の偏差値データだけを見ていては判断できない要素が山積みです。
「ネットで偏差値50って書いてあったから余裕かな?」なんて油断していると、思わぬ落とし穴にハマって涙を飲むことになりかねません。
この記事では、そんな静岡大学を目指すあなたが絶対に知っておくべきボーダーの真実と、偏差値の数字裏に隠された合格のための戦略について、私の経験と最新データを交えて徹底的に解説しますよ。
- 2026年度入試における合格ボーダーの具体的な得点率目安
- 偏差値50台という数字に隠された国立大学特有の難しさ
- 意外と知らないキャンパスごとの文化の違いと生活環境
- 合格を勝ち取るために今すぐ始めるべき具体的な科目別対策
2026年静岡大学の共通テストボーダーと難易度推移

まずは、静岡大学全体の入試難易度や共通テストのボーダーラインがどのように推移しているのか、その全体像を把握していきましょう。
単に「7割とればOK」といった大雑把な目標ではなく、なぜその点数が必要なのか、どのラインを超えると安心できるのか、その構造を理解することが合格への第一歩ですよ。
ボーダー得点率は65%から75%が目安

結論として、合格ボーダー得点率は概ね65%〜75%(650〜750点)と予測されます。
| 学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
| 人文社会科学部 | 66% ~ 77% | 47.5 ~ 52.5 |
| 教育学部 | 50% ~ 68% | 47.5 ~ 50.0 |
| 理学部 | 64% ~ 75% | 50.0 ~ 55.0 |
| 工学部 | 62% ~ 71% | 47.5 ~ 55.0 |
| 農学部 | 65% ~ 75% | 50.0 ~ 55.0 |
| グローバル共創科学部 | 64% ~ 68% | 47.5 ~ 52.5 |
| 情報学部 | 62% ~ 78% | 47.5 ~ 57.5 |
(出典:河合塾)
【10%の幅が示す意味と戦略】 この得点差は、学部ごとの「勝負の性質」を表しています。
- 守りの受験(農学部・理学部など)
- 人気や基礎学力重視のため、ボーダーが72〜73%と高くなる傾向。共通テストでの失敗は許されません。
- 逆転の受験(工学部など)
- 二次試験(個別学力検査)の配点が高いため、ボーダーが65%程度と低めに出ることがあります。
- これは「入りやすい」わけではなく、共通テストで失敗しても記述力(特に数学・理科)で大逆転が可能であることを意味します。
よって、自身の志望学部が「共通テスト逃げ切り型」か「二次試験逆転型」かを見極めることが重要です。
後者の場合、共通テストリサーチがC・D判定でも十分に合格圏内といえます。
「とりあえず7割」は正しい目標ですが、農学部志望なら「7割は死守ライン」、工学部志望なら「7割あれば大きなアドバンテージ」と捉え方が変わります。
志望学部の特性に合わせて、共通テストの重み付けを調整しましょう。(出典:静岡大学『入試案内・入試データ』)
偏差値50から55でも油断禁物な理由
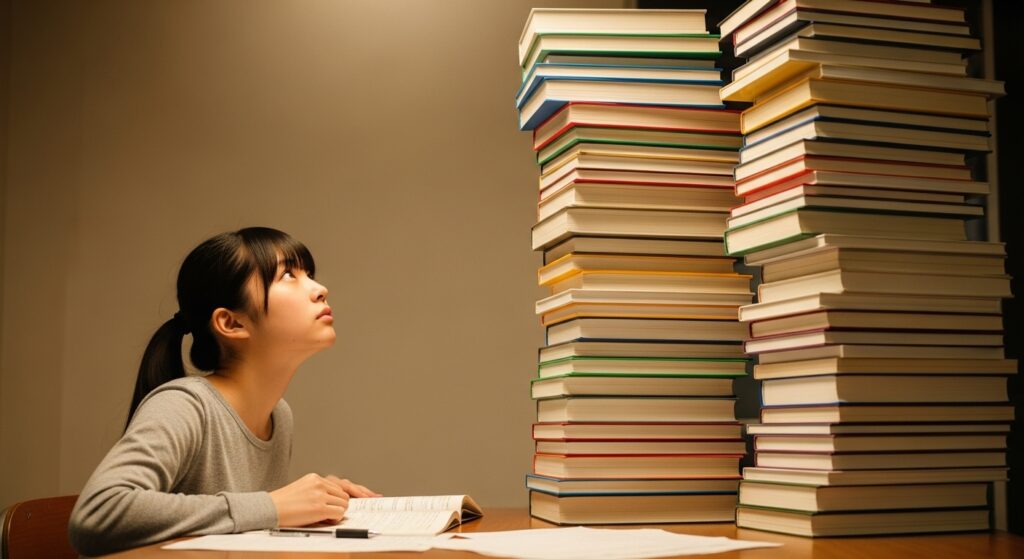
大手予備校の偏差値ランキング表を見ると、静岡大学の偏差値は大まかに「50.0〜55.0」と記載されていることが多いですよね。
この数字を見て、「これなら私立のMARCH(偏差値60前後)や、あるいは日東駒専(偏差値50〜55)と同じくらいだから、そこまで難しくないんじゃない?」と感じてしまったあなた。
その感覚は非常に危険かもしれません。
なぜなら、国立大学と私立大学では、偏差値の算出基準となる「母集団」と「科目数」が根本的に異なるからです。
私立大学の入試は基本的に3科目(文系なら英・国・社、理系なら英・数・理)で受験できますが、静岡大学を含む国立大学は、原則として共通テストで5教科7科目(または6教科8科目)が課されます。
想像してみてください。
英語と国語だけが得意な学生が集まる試験での「偏差値55」と、数学も理科も社会も、苦手科目から逃げずに全教科を勉強してきた学生が集まる試験での「偏差値55」。
どちらが取るのが大変でしょうか?
間違いなく後者ですよね。国立大学の偏差値50〜55は、私立大学の偏差値に換算すると、おおよそ+5〜+10ポイント程度の上乗せが必要だと言われています。
つまり、実質的な学力レベルとしては、私立大学の偏差値60〜65相当の層と競うことになるのです。
また、静岡大学は「5S」と呼ばれる中堅国立大学グループに属しており、地元のトップ進学校の生徒たちが「確実に合格を手にするための防衛ライン」として受験してきますし、首都圏や関西圏からの流入も多いです。
全教科をバランスよく仕上げる総合力が問われるため、たった一つの苦手科目が足を引っ張って不合格になるケースも少なくありません。
「偏差値50」という数字を「平均レベル」と侮らず、「5教科を万遍なくこなせる優秀層の中での平均」と正しく認識して対策を進めてくださいね。
WEB検索で「静岡大学 偏差値 低い」といったキーワードが出ることがありますが、これは科目数の負担を考慮しない誤解に基づくことが多いです。
5教科7科目の準備は、3科目の勉強の2倍以上の時間がかかると覚悟しておきましょう。
情報Iが必須化された入試科目の変更点

2025年度入試からの変更点で共通テストにおける新教科「情報I」が導入されました。
これまで国立大学文系であれば5教科で済んでいたところ、これからは「情報」を含めた6教科がスタンダードになります。
静岡大学においても、多くの学部でこの「情報I」が必須化され、合否を分ける重要な要素となってきます。
特に注目すべきは、情報学部と工学部での扱いです。
これらの学部では、大学での学びそのものが情報科学やプログラミングに直結するため、共通テストの「情報I」のスコアを重視する傾向にあります。
配点については学部・学科ごとに異なりますが、単なる「足切り」程度に軽く見ていると痛い目を見るでしょう。
「でも、過去問が一年分しかないから対策しようがない…」と不安に思っている人も多いですよね。
確かに過去問は多くないですが、大学入試センターが公表している問題を見る限り、単なる用語の暗記だけではなく、与えられた条件やデータに基づいて論理的に考えを進める「プログラミング的思考」や、グラフや表から情報を正確に読み取る「データリテラシー」が問われる内容になっています。
対策としては、まずは教科書レベルの知識を完璧にすること。
そして、各予備校が出している予想問題集や模試を積極的に活用して、「初見の問題」に対する対応力を養うことが不可欠です。
特にプログラミングの基礎(変数の考え方や条件分岐、繰り返し処理など)は、一度理解してしまえば得点源にしやすい分野でもあります。
食わず嫌いをせずに早めに取り組むことで、周りの受験生に差をつけることができますよ。
関連記事↓
【2026年】共通テスト「情報Ⅰ」のオススメ参考書や勉強法を紹介

この記事では、情報Ⅰを実際の勉強方法やオススメ参考書について紹介しているよ!
足切りはある?二段階選抜の実施状況

国公立大学を受験する際に気になるのが、「足切り(二段階選抜)」の存在です。
せっかく二次試験の対策をしてきたのに、共通テストの点数が足りずに受験票すら届かない…なんて事態は絶対に避けたいですよね。
静岡大学の募集要項を確認すると、多くの学部・学科で「入学志願者が募集人員の〇倍(例えば約3倍や約4倍など)を超えた場合、共通テストの成績により第1段階選抜を行うことがある」という記載があります。
いわゆる「予告倍率」というやつですね。
では、実際に足切りは頻繁に行われているのでしょうか?
近年の傾向を見ると、静岡大学で大規模な足切りが実施されるケースはそれほど多くはありません。
少子化の影響もあり、予告倍率を超えるほどの志願者が殺到することは稀だからです。
しかし、だからといって「絶対にない」と言い切れないのが怖いところ。
特に注意が必要なのは、近年人気が急上昇している情報学部や、隔年現象(前年度の倍率が低かった翌年に志願者が急増する現象)が起きた際の他の学部です。
また、共通テストの平均点が極端に高かった年などは、受験生が強気に出願してくるため、予期せぬ高倍率になることもあります。
足切りライン自体は公表されていませんが、一般的には共通テスト得点率で50%〜60%を下回ると危険水域に入ると考えられます。
「足切りは基本ないだろう」と楽観視せず、最低でも6割以上は確保しておくことが、精神衛生上も合格戦略上も重要です。
前期と後期で異なる合格最低点の特徴
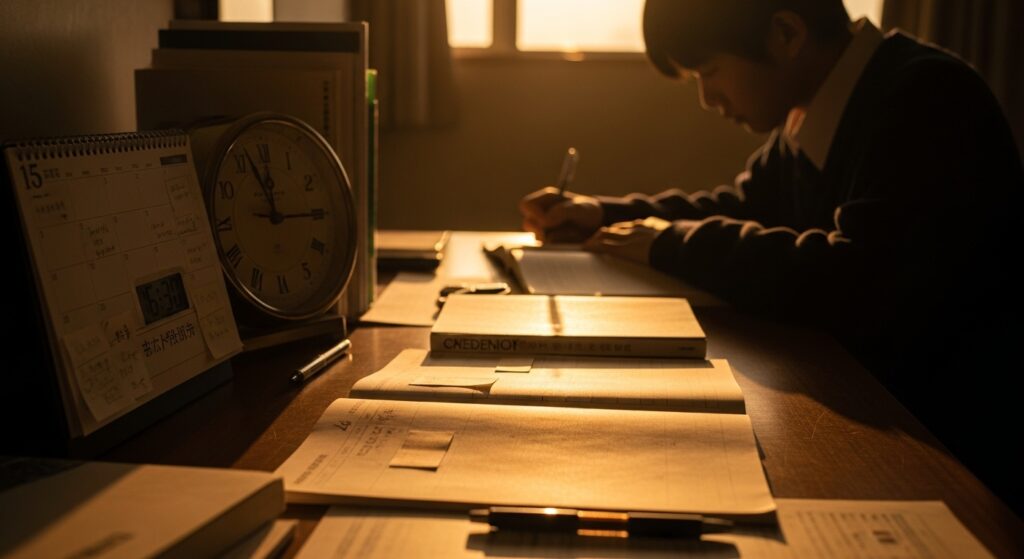
国公立大学入試には「前期日程」と「後期日程」がありますが、静岡大学においてこの二つの難易度は天と地ほどの差があることを理解していますか?
多くの受験生が第一志望として挑む前期日程に対し、後期日程は定員が非常に少なく、かつ受験者層のレベルが格段に上がります。
なぜなら、後期日程には「前期で旧帝大(名古屋大学や東北大学など)や、横浜国立大学、筑波大学といった上位校に不合格だった受験生」が、滑り止めとして大量に流れてくるからです。
彼らは基礎学力が非常に高く、共通テストでも8割近い得点を持っていることが珍しくありません。
そのため、静岡大学の後期日程におけるボーダーラインは、前期日程よりも5%〜10%程度跳ね上がることがあります。
特に、後期日程では面接や小論文のみを課す学部や、共通テストの配点比率が極端に高い学部が多く、「一発逆転」が起きにくい構造になっています。
「前期がダメでも後期で静大に受かればいいや」という考えは、正直かなり甘いです。
後期合格は前期合格よりも遥かに難しいミッションだと認識してください。
あくまで「前期日程で確実に合格を決める」という強い意志と準備が必要です。
学部別静岡大学の共通テストボーダー対策と配点

ここまで全体的な傾向を見てきましたが、静岡大学攻略の真髄は「学部ごとの個別対策」にあります。
静岡大学は、学部によって求めている学生像(ペルソナ)が明確に異なり、それが如実に入試の「配点」に表れています。
ここからは、主要学部ごとの配点の秘密と、そこから導き出される具体的な合格戦略を深掘りしていきます。
自分の志望学部だけでなく、併願を考えている学部の特徴もしっかりチェックしてくださいね。
数学重視の工学部は傾斜配点に注意
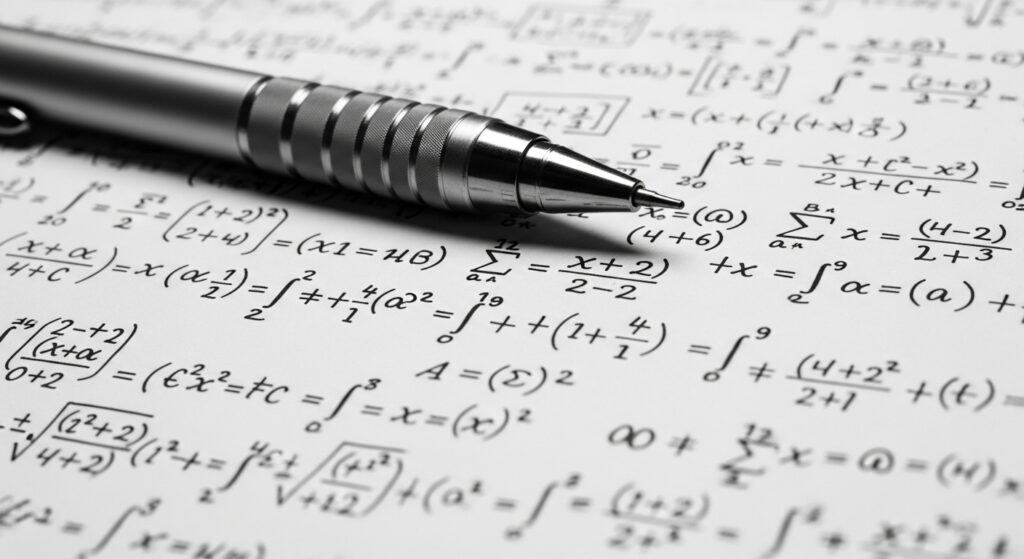
浜松キャンパスに拠点を置く工学部は、ものづくり県・静岡の象徴とも言える看板学部ですが、ここの入試配点は全国的に見てもかなり特徴的、いや「尖っている」と言っても過言ではありません。
もしあなたが「全教科まんべんなく勉強して、総合点で勝負しよう」と考えているなら、その戦略は工学部に関しては根本から見直す必要があります。
最大の特徴は、二次試験における数学の配点が異常に高いことです。
学科や年度にもよりますが、例えば機械工学科や電気電子工学科などでは、二次試験の総点のうち数学だけで400点を占めるケースがあります。
英語や理科の配点と比べても圧倒的で、まさに「数学ができる奴が欲しい」という大学側の強烈なメッセージが読み取れますね。
これが何を意味するかというと、共通テストでボーダーに届かない点数を取ってしまったとしても、数学で圧倒的な記述力を持っていれば、E判定からの大逆転合格が十分に可能だということです。
実際に、共通テストは6割そこそこだったのに、二次試験の数学で満点近い点数を叩き出して合格していく「数学オバケ」みたいな受験生が毎年一定数存在します。
逆に言えば、どれだけ共通テストで高得点を取ってA判定が出ていたとしても、記述式の数学で部分点を稼げない(論理的に答案を書けない)受験生は、容赦なく不合格になります。
工学部の数学は、単に答えが合っていればいいマーク式とは違い、「なぜその式になるのか」「条件をどう整理したのか」というプロセスそのものが採点対象になります。
特に、大学入学後の専門課程(流体力学や電磁気学など)で必須となる微積分計算のスピードと正確性は、徹底的に鍛え上げておく必要がありますよ。
工学部志望者は、共通テスト対策も大切ですが、学習時間の比重を「二次試験の数学」に大きく振るべきです。
特に現役生がおろそかにしがちな数III・Cの演習量が合否を分けます。
| 教科 | 科目詳細 | 配点例 | 合格へのアプローチ |
|---|---|---|---|
| 数学 | 数I, II, III, A, B, C | 400点 | 最重要科目。共通テストの失敗を帳消しにできる破壊力がある。計算力と論証力の両方が必須。 |
| 理科 | 物理・化学 | 150点〜 | 数学に比べると配点は低いが、基礎知識は必須。物理は標準的な良問が多いので取りこぼし厳禁。 |
| 英語 | コミ英, 英語表現 | 200点 | 他大学と比較して標準的な配点。数学で差がつかない場合の勝負所になる。 |
情報学部は文系受験可能で就職も強い

日本で最も早い時期に設立された歴史を持つ静岡大学の情報学部は、文系・理系の枠を超えた「文理融合」の教育を掲げており、入試制度にもその柔軟性が表れています。
「情報は理系のものでしょ?」と思っている文系のあなた、実は情報学部こそが、文系から理系就職(エンジニアやデータサイエンティスト)を目指せる最強のキャリアパスなんですよ。
情報学部の入試配点の特徴は、工学部のような一点突破型とは対照的に、全体的にバランスが取れていることです。
特筆すべきは、学科や入試方式によっては理科の配点が低めに設定されている(50点〜75点程度)場合があること。
また、共通テストの理科を「基礎2科目」で受験可能な方式もあり、バリバリの理系科目が苦手な文系学生でも、数学(数I・II・A・B・C)と英語、そして「情報I」さえしっかり対策すれば、十分に合格を勝ち取ることができます。
そして、情報学部を推す最大の理由はその「就職実績(ROI:投資対効果)」の凄まじさにあります。
浜松キャンパス周辺に集積するスズキ、ヤマハ発動機、浜松ホトニクスといった世界的メーカーはもちろん、NTTデータやNEC、日立製作所といった首都圏のIT大手企業への就職実績も豊富です。
今の時代、どこの企業もDX(デジタルトランスフォーメーション)人材を喉から手が出るほど欲しがっていますから、静大情報学部卒というブランドは、就職活動において「プラチナチケット」並みの威力を発揮します。
ただし、2026年度入試では共通テストの「情報I」の配点比率が高まることが確実視されています。
文系科目が得意でも、プログラミング的思考やデータの扱いにアレルギーがあると苦戦します。
「文系だから」と甘えず、情報Iの対策を早期に固めること。これが情報学部合格への絶対条件です。
「地方大学だと就職が不利?」そんな心配は無用です。
特にIT・情報通信業界において、静岡大学情報学部の卒業生は「実務に強い」と高く評価されており、東京の有名私大生と互角、あるいはそれ以上に戦えます。(出典:静岡大学情報学部『就職・進路データ』)
農学部と理学部の難易度と人気学科

静岡キャンパス(大谷)にある農学部と理学部は、それぞれの分野を探求したい「好き」を仕事にしたい学生が集まる、非常にアカデミックな学部です。
まず農学部ですが、ここは静岡大学の中でもトップクラスの人気を誇ります。
バイオテクノロジー、食品科学、環境保全といったテーマは、近年のSDGsブームも相まって志願者が減ることがありません。
そのため、共通テストのボーダー得点率も65%〜75%と、静大の中では高めの水準で推移しています。
農学部の入試は、工学部のような極端な傾斜配点がない分、共通テストでの失敗が致命傷になりやすい「先行逃げ切り型」の勝負になります。
苦手科目を極力なくし、全教科で安定して7割以上をキープする「優等生的な学習」が求められます。
一方、理学部は少し毛色が違います。
理学部が求めているのは、特定分野への深い愛と専門性を持つ「スペシャリスト」です。
そのため、二次試験の配点において、理科1科目に200点という重みを持たせている学科があります。
さらに特筆すべきは、国立大学としては数少ない「地学」での受験が可能な点です。
地学専攻や地球科学科を設置している大学は限られており、地学愛好者(地学徒)にとって静岡大学理学部は、まさに聖地のような存在。
もしあなたが地学が得意なら、ライバルの少ないこのニッチな土俵で勝負することで、合格率をグッと引き上げることができるかもしれません。
教育学部の倍率と数学が必要な理由

静岡県の教員養成を一手に担う教育学部。
「先生になりたい」という明確な夢を持つ人が集まる学部ですが、ここにも知っておくべき入試の罠があります。
それは、「文系だから数学はやらなくていいよね」という甘い考えが通用しないことです。
教育学部の入試(学校教育教員養成課程など)では、文系型の受験生であっても、二次試験で数学(数I・II・A・B・C)が課されるケースがあります。
配点は150点程度と、国語や英語と同等、あるいはそれ以上の比重を占めることも。「数学を捨てて教育学部へ」という戦略は、静岡大学では完全に悪手です。
なぜこれほど数学を課すのか?
それは、入学後のカリキュラムや教員採用試験の現実に即しているからです。
小学校の先生になるなら算数の指導力は必須ですし、論理的思考力はどの教科を教えるにしてもベースとなる能力です。
大学側は「教員として最低限必要な数学リテラシー」を入試の段階で求めているわけですね。
また、教育学部は地元就職における最強の安定株でもあります。
静岡県や浜松市の教員採用試験において、静大教育学部出身者は圧倒的なシェアを持っていますし、教員だけでなく、県庁や市役所といった地方公務員への就職にも非常に強いです。
「地元静岡で、安定して長く働きたい」と考えるなら、教育学部で数学から逃げずに努力する価値は十分にありますよ。
教育学部の数学は、工学部のような難問奇問は出ません。
教科書の章末問題レベルを「正確に」「素早く」解く基礎力が問われます。
青チャートや標準問題精講などの基本的な参考書を仕上げれば十分に対応可能です。
それでも不安ならトウコベの無料相談がオススメ
静岡大学の共通テストボーダーや学部ごとの詳細な配点戦略を解説してきましたが、いかがでしたか?
「ボーダーは65%〜75%か、意外といけそうかも?」
「いや、工学部の数学400点は正直ビビった…」
「情報Iの対策、全然やってないからヤバい!」
など、記事を読んで新たな希望が見えた人もいれば、逆に焦りを感じてしまった人もいるかもしれません。
大学入試、特に国公立大学の受験は情報戦です。
単に模試の偏差値や判定だけを見て一喜一憂するのではなく、志望学部の配点構造を理解し、「どの科目で何点取れば合格最低点を超えるか」という緻密なシミュレーションを立てることが合格への最短ルートです。
しかし、自分一人で膨大な入試要項を読み込み、最適な戦略を立てるのはなかなか難しいものですよね。
「今の自分の成績で、本当に静大に届くんだろうか?」
「共通テストと二次試験、どっちの対策を優先すべき?」
「併願の私立大学、どこにすればいいのか分からない…」
もしあなたが今、そんな不安を少しでも抱えているなら、ぜひ一度受験のプロに相談してみてください。
トウコベの無料相談では、現役の東大生講師陣が、あなたの現状の成績や志望学部を分析し、合格に向けた具体的な学習プランを提案してくれます。
オンラインで自宅から気軽に相談できますし、無理な勧誘もありません。
「話を聞いてもらうだけ」でも、やるべきことが明確になってスッキリしますよ。
一人で悩んで立ち止まっている時間が一番もったいないです。
プロの知恵を借りて、自信を持って静大合格への道を突き進んでください!
東大生のオンライン個別指導『トウコベ』まとめ:静岡大学共通テストボーダー突破のために
この記事のポイントをまとめておきます。
- 2026年の共通テストボーダー得点率の目安は65%〜75%
- 偏差値50〜55の数字に騙されず、私大偏差値60〜65相当の5教科対策が必要
- 新科目「情報I」は必須化され、特に工学部・情報学部で合否に直結する。
- 工学部は二次試験の数学配点が最大400点と極めて高く、数学での大逆転が可能。
- 情報学部は文系科目でも受験可能で、大手企業への就職実績が非常に高い。
- 農学部や理学部は共通テストのウェイトが高く、7割以上の得点が安心ライン。
- 教育学部は文系志望であっても、二次試験で数学が課される場合が多い。
- 後期日程は上位大学からの流入があるため、前期よりも難易度が跳ね上がる。
- 学部ごとに配点が全く異なるため、志望学部に特化した戦略とプロへの相談が有効。

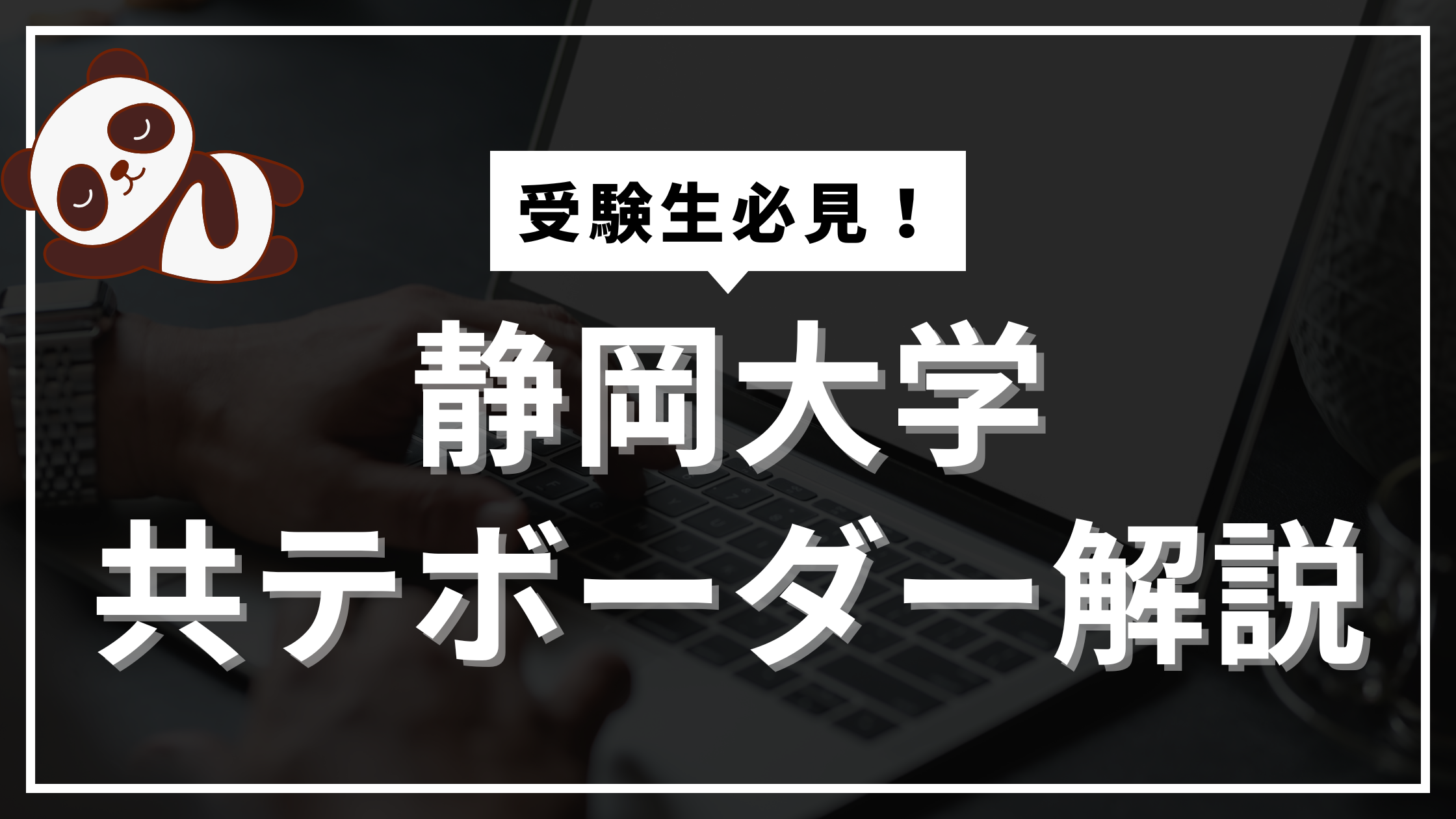
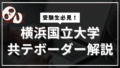
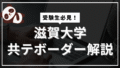
コメント