皆さんこんにちは、パンダです。
私は現役で京都大学に不合格となった後、1年間の宅浪生活を経て、無事に京大工学部へと合格することができました。
宅浪生活では、予備校に通わず、すべてを自分一人で決めて勉強する必要がありました。勉強の計画、スケジュール管理、そして何より、使用する参考書の選定もすべて自分でやる必要があります。
これがかなーり大変です。
これは、独学で勉強している人にも同じことが言えると思います。参考書を選ぶ基準が分からなかったり、自分のレベルに合っているかどうかが判断しづらかったりして、教材選びにかなり悩んでしまうという声をよく耳にします。
そして今、どのような教材を使えばよいか分からないという人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、私自身が宅浪時代に実際に使って「これは独学の人こそやるべき!」と思った参考書を、英語・数学・国語・化学・物理の5科目に分けてご紹介します。
どれも「予備校の授業を受けたかのような深い学び」が得られる、再現性の高い参考書ばかりです。独学・宅浪を成功に導く一助になれば幸いです。
独学・宅浪生におすすめする参考書
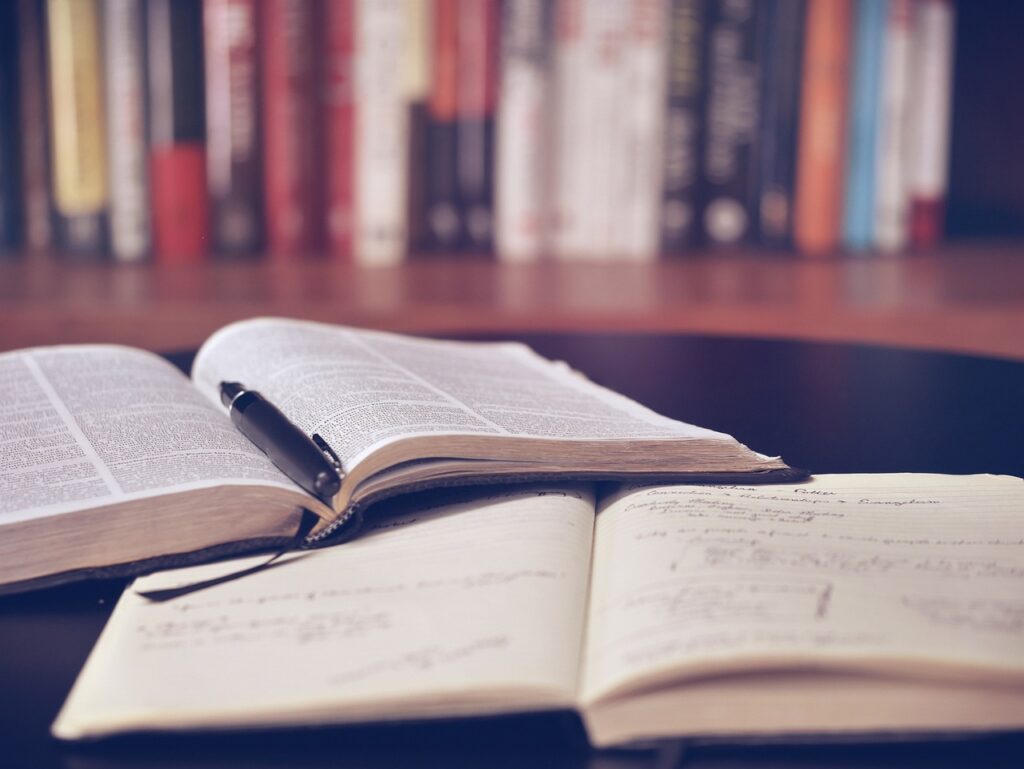
英語:関正生のThe Rules 英語長文問題集
独学者にとって、英語長文読解は特に悩みどころではないでしょうか?単語力や文法は鍛えているつもりなのに、なぜか長文が読めない。そんなときに出会って救われたのが、この参考書です。
この参考書は、英語長文を読む際の「読み方」自体を教えてくれる数少ない参考書です。単語・文構造の丁寧な解説はもちろん、文の論理構造、どこに着目して読むべきか、といった点が“ルール”として体系的に解説されています。
また、通常の参考書のように「問題→解答解説→全文訳」で終わるのではなく、「なぜその答えになるのか」「その解答を導くためにどう読むべきか」といった考え方までも含まれており、独学者でも論理的な読解力が身につけられる内容です。
実際に読んでみると、まるで関先生の授業を受けているかのような臨場感があり、読解に対するアプローチが根本から変わります。受験英語を“読み方”から立て直したいという人にはぜひ手に取ってほしい一冊です。
数学:世界一わかりやすい京大の理系(文系)数学合格講座
この参考書の特徴はなんといってもめーーーーーっちゃわかりやすい解説です。(まさに世界一わかりやすい!です(笑))
数学の問題を見て「解法は理解できるけれど、自分では思いつけない」と感じたことはありませんか?
この参考書では、問題を解くプロセスを「思考の流れ」として詳細に解説してくれます。単に「こう解けばいい」というのではなく、「この問題を見たときにどう考え始めるか」「どういう発想を経て答えにたどり着くのか」まで丁寧に書かれており、思考の道筋が見える構成になっています。
また、著者自身が「こういう間違いもあるよね」といった実際の思考の失敗例まで紹介してくれるため、自分の思考と照らし合わせながら読み進めることができます。
独学者にとっては、解法の暗記ではなく「自力で正解にたどり着く力」を養う必要があるので、こういった参考書は非常に貴重です。京大数学に特化しているとはいえ、応用力を養いたい人には広くおすすめできます。
国語:新版 現代文読解の基礎講義
現代文という科目は不思議な科目です。小学校のころからずっとやっているにもかかわらずいまいちどのような科目か分からない。
さらに他の科目と異なり先生によっていうことはバラバラ。
そういった事情から現代文という科目に、どこか苦手意識を持っている人も多いのではないでしょうか?特に理系の人にとっては、「読めるけれど答えが選べない」「何を根拠にすればよいか分からない」といった声もよく聞きます。
この本は、そういった悩みに真正面から答えてくれます。著者は駿台の現代文講師で、受験現代文を一つの論理的プロセスとして再構成しており、「現代文とはそもそも何なのか」「設問の意図とは何か」といった根本から丁寧に説明してくれます。
また、文章をどう読むかという具体的な手順を「客観的速読法」と、設問にどう答えるかという手順を「論理的解答法」と名付けて解説しており、どちらも実戦に使える手順として落とし込まれています。
さらになぜその手順を踏むことで正しい解答にたどり着けるのかというところまで解説が及んでいるので納得感をもって解答することができます。
この本を読んだとき私は「ここまで文章は論理的に分析できるものなのか!」と強い衝撃を受けました。皆さんにもこの感覚を味わっていただきたいです。
特に、論理的思考力はあるが文章読解に自信がないという理系の方に強くおすすめしたい1冊です。
化学:原点からの化学 化学の理論
化学の勉強で「基本的な問題はなんとなく解けるけど、難しい問題になると何がわからないのかもわからなくなる」という経験をしたことはありませんか?
この本は、そんな“モヤモヤ”を解消してくれる参考書です。解法を単に提示するのではなく、「なぜそのように考えるのか」「どのように情報を整理すればいいか」といった、問題を解く“視点”を提供してくれます。
解法が非常に体系的にまとまっており、特に気体の分野のところと、化学平衡のところがおすすめです。
大学初級レベルに踏み込んだ内容も含まれており、一部難しい箇所もありますが、それでも得られるものは非常に大きいです。わからない部分は一旦飛ばしてしまっても問題なく、後に大学で学び直せば十分だと割り切ることも大切です。
独学で、より高いレベルの理解を目指す人におすすめの一冊です。
物理:名問の森
物理は、独学が最も難しい科目だと私は思っています。ですが、それでも独学したいという人におすすめしたいのが『名門の森』です。
この本の最大の特徴は、解説の丁寧さにあります。解答に至るまでの物理的原理や考え方を、段階を追って詳しく解説してくれます。また、章ごとのはじめに「チェックポイント」が設けられており、公式や基本事項を確認してから問題に取り組む形式になっています。
難易度も適度で、良問の風→名門の森というレベルの接続もスムーズです。
また物理という科目は少ない問題数を深く原理から理解するという演習方法が有効だと考えています。
その点、名問の森は問題数が多すぎないため、反復学習もしやすく、物理の原理を深く理解しながら問題演習を進めていけます。
とはいえ、やはり物理は他科目と比べて独学が難しい部分があるので、映像授業などで基礎を固めた上でこの参考書を使う、という流れがベストです。
以下でおすすめの物理の映像授業を紹介しています。
これらの参考書に共通していること
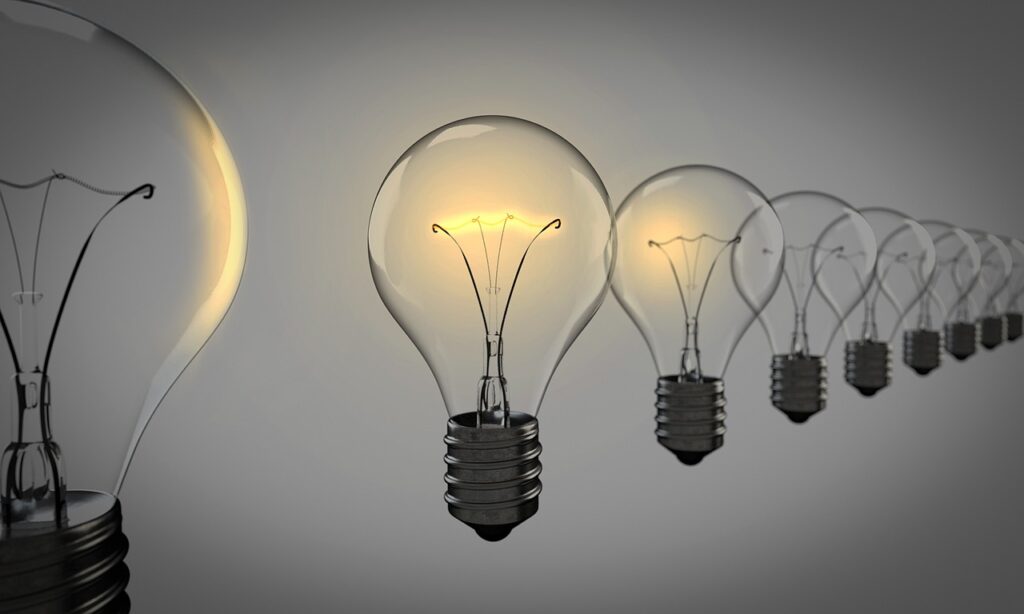
今回ご紹介した参考書には共通点があります。それは、「解法の再現性」が非常に高いことです。
つまり、一度理解した解法や考え方が、他の問題でも応用できるように丁寧に体系化されているという点です。
独学者が一番困るのは「実際の解答から他の問題でも通用する本質的部分を抜き出すこと」つまり抽象化だと思います。
だからこそ、思考プロセスや解答への道筋を明確にしてくれ、それを他の問題でも適用できる形にまとめてくれる参考書は、独学者にとって非常に心強い味方になります。
また、そういった「再現性のある思考法」を学べる参考書こそが、限られた時間と労力の中で成果を上げるために必要だと私は考えています。
最後に
独学や宅浪という勉強スタイルは、自由であると同時に、孤独でもあります。だからこそ、自分の学びの土台となる「信頼できる教材選び」がとても大切です。
今回紹介した参考書は、私自身が「独学者の視点」で選び、実際に成果を上げることができた教材です。
これから受験を迎えるみなさんが、少しでも迷わずに、そして前向きに勉強に取り組めるよう、この記事が参考になれば幸いです。
以上パンダでした。

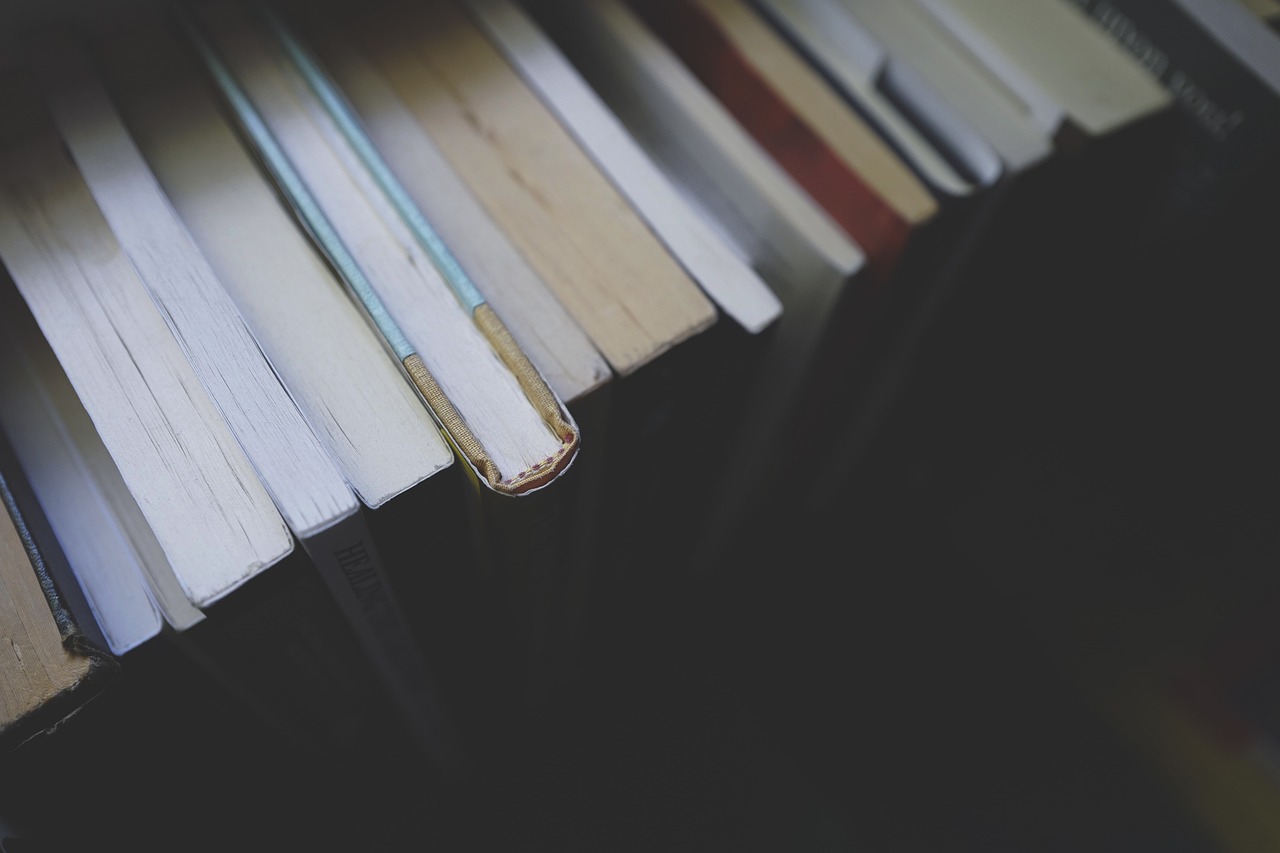
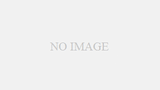


コメント