共通テストの目標点数を75%としている皆さん、合格できる国立大学や合格できる私立大学の目安、上位何パーセント・偏差値の感覚、各科目の難易度や取り方を知りたくないですか。
特に数学・英語・国語・理科・社会といった科目ごとの得点力の差が合否に直結するため、科目別の対策が不可欠です。
本記事では、共通テストで75パーセント前後を狙うための大学の目安と科目別学習法を、具体的な戦術と実践的な勉強法を中心に整理していきます。
これから紹介する方法は、出題形式への慣れや時間配分の最適化を重視した構成になっており、短期での得点底上げにも役立ちます。
まだ六割に達していない人は以下をご覧ください。
・共通テスト75パーセントで狙える大学の目安と傾向
・科目別(数学・英語・国語・理科・社会)の具体的対策
・過去問・模試を使った得点戦略と時間配分の作り方
・共通テスト後の受験戦略と進路選択に必要な判断基準
「あと少しで75%に届くのに…」「模試で6割台から抜け出せない…」と焦っていませんか?
実は、今の実力のままでも「解く順番」や「時間の使い方」を変えるだけで、スコアは伸びます。 私が京大合格のために実践した「試験当日の朝見るだけで+5点を拾うリスト」などを公開しました。
共通 テスト 75 パーセントで狙える大学の目安

- 共通テスト75%で合格できる国立大学
- 共通テスト75%で合格できる私立大学
- 共通テスト得点率75%前後で合格が狙える大学・学部一覧
- 共通テスト75%の上位何パーセント・偏差値
- 共通テスト75%ラインの難易度分析
- 共通テスト75%を達成するための取り方戦略
共通テスト75%で合格できる国立大学
共通テストで75%の得点率を安定して確保できる受験生は、国公立大学の中堅から上位ゾーンに十分進出可能です。
これは、旧帝国大学の医学部や一部の理工系など、最難関とされる学部を除けば、多くの文系・理系学部で合格者の平均得点率に達する水準だからです。
この得点帯は、多くの国公立大学で出願基準を満たすだけでなく、合格可能性を具体的に高める目安となります。
例えば、旧帝国大学である東北大学や九州大学の教育系・理学系学部、筑波大学の理工学群、北海道大学の一部学科などは、合格者の共通テスト平均点が74〜76%前後であることが多く、75%は合格ラインの明確な目安として意識できます。
この得点率を安定して取れることは、これらの大学を射程圏内に収める大きな強みとなります。
地域性や学部の人気度も考慮すると、地方国立大学の文系中堅学部では、共通テストで75%前後から合格するケースが多く見受けられます。
これらの大学では、共通テストの配点比率が高めに設定されていることが多く、共通テストの得点力が直接的に合否に影響します。
一方、東京大学や京都大学のような都市部の難関国立大学では、共通テストの配点が二次試験に比べて低く設定されていることが一般的です。
この場合、共通テスト75%はあくまでも出願条件を満たすための通過点に過ぎず、二次試験での高得点が不可欠となります。
そのため、志望校を選定する際には、単に共通テストの得点率だけでなく、大学ごとの入試方式、二次試験との配点構造、過去の合格者データなどを詳細に分析することが求められます。
さらに、国立大学の入試では、共通テストで複数の科目をバランスよく得点する総合力が重要です。
特定の科目に偏ることなく、全体として75%のラインを確保することが、幅広い大学への出願を可能にします。
この得点帯は、単にボーダーライン上に位置するだけでなく、二次試験で多少のミスがあっても挽回できる余地を与えてくれる、非常に価値ある水準と言えるでしょう。
共通テスト75%で合格できる私立大学
私立大学では、合格可能性が共通テスト得点の利用方式に大きく左右される傾向があります。
特に注目したいのが、共通テスト利用入試で、特定科目の得点を重視する方式を採用する大学です。
この方式では、得意科目の得点率が高ければ、全体の75%というラインが非常に強力な武器になります。
例えば、MARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)や関関同立(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)といった大学群では、共通テスト利用入試で「英語と数学の合計点」や「得意科目2科目」に重みを置く方式が見られます。
そのため、もし英語や数学が得意で、それらの科目で高得点を稼げているのであれば、共通テスト全体の得点が75%であっても、合格可能な学部が少なくありません。
ただし、早慶上智(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学)のような最難関私立大学になると、全科目の得点合計で80%以上が求められるケースが通例であり、75%では出願自体が難しいか、合格が極めて困難になります。
複数の私立大学の公式サイトや募集要項を調べると、例えば中央大学法学部や法政大学経済学部では、共通テストの英語と国語の配点比重が高く設定されており、得意な科目で高得点を上げることで合格ラインに達する可能性があります。
一方、得意科目がない、あるいは満遍なく得点したいと考える受験生にとって、全科目が一律配点される方式では、すべての科目で安定した得点が求められるため、75%はギリギリ合格圏となることが多いです。
このように私立大学を狙う際には、志望校ごとの「共通テスト利用方式」「一般入試方式」「独自方式」それぞれの特色を明確に把握し、自分にとって最も得点が伸ばせる仕組みを選ぶことが、75%ラインを活かす鍵となります。
単に共通テストの得点率だけで判断するのではなく、各大学の入試制度を深く理解し、自身の強みを最大限に活かせる戦略を立てることが、合格への近道と言えるでしょう。
共通テスト得点率75%前後で合格が狙える大学・学部一覧
以下の表は、共通テスト得点率75%前後で合格が狙える可能性のある大学・学部の目安をまとめたものです。
この情報は、河合塾のkeinetにもとづいたものであり、各大学・学部の合格最低点が変動することをご理解の上、参考としてご活用ください。
| 大学名 | 学部名 | 共テ得点率(目安) |
| 北海道大学 | 水産学部、歯学部 | 74% |
| 東北大学 | 教育学部、歯学部 | 74% |
| 筑波大学 | 理工学群(数学)、芸術専門学群 | 74% |
| 埼玉大学 | 理学部(物理)、工学部(情報工) | 74% |
| 千葉大学 | 情報データ科学部 | 74% |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部(言語文化)、生活科学部(心理) | 74% |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部(アフリカ) | 74% |
| 横浜国立大学 | 経済学部、都市科学部、理工学部 | 74% |
| 神戸大学 | 理学部(化学・生物)、工学部(応用化学) | 74% |
| 九州大学 | 教育学部、法学部、経済学部(経済工)、理学部(化学・生物) | 74% |
| 富山大学 | 薬学部(薬) | 74% |
| 金沢大学 | 理系一括、医薬保健学域(薬) | 74% |
| 名古屋工業大学 | 工学部(社会工学、電気・機械工、情報工) | 73-74% |
| 大阪大学 | 外国語学部(ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語) | 74% |
| 広島大学 | 教育学部、法学部、歯学部 | 73-74% |
| 岡山大学 | 歯学部 | 72% |
| 熊本大学 | 薬学部(創薬・生命薬科学) | 68% |
| 琉球大学 | 医学部(保健学科) | 71% |
| 早稲田大学 | 政治経済学部(共通テスト利用) | 85-90% |
| 慶應義塾大学 | 法学部(共通テスト利用) | 85%以上 |
| 上智大学 | 文学部(共通テスト利用) | 80-85% |
| 明治大学 | 文学部(共通テスト利用) | 78-83% |
| 青山学院大学 | 経済学部(共通テスト利用) | 77-82% |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部(共通テスト利用) | 78-83% |
| 中央大学 | 法学部(共通テスト利用) | 77-82% |
| 法政大学 | 経済学部(共通テスト利用) | 75-80% |
| 関西大学 | 文学部(共通テスト利用) | 75-80% |
| 関西学院大学 | 経済学部(共通テスト利用) | 75-80% |
※本表の数値は、複数の予備校データや過去の入試結果を総合的に判断した目安です。年度や入試方式、個別試験の配点によって大きく変動する可能性があります。詳細は必ず各大学の公式サイトをご確認ください。
共通テスト75%の上位何パーセント・偏差値

共通テストで75%という得点率が、全国レベルでどの位置に相当するかは、年度ごとの平均点、受験者層の変化、そして問題の難易度によって変動します。
しかし、過去の傾向から大まかな目安を推定することは可能です。
75%は、概ね上位20〜30%に位置し、偏差値に換算するとおおよそ60前後であると考えられます。
この推定は、大学入試センターや模試機関が公開している「得点率別順位分布」や「偏差値対応表」に基づいたものです。
年度によっては、問題が難化した年には75%が偏差値約62程度まで上昇し、逆に易化した年には偏差値約58程度に下がる傾向が見られます。
この変動を理解しておくことは、自己の位置を正確に把握する上で重要です。
実際のところ、全国模試の結果と共通テストの得点率を比較すると、75%程度の得点を安定して確保できている受験生は、二次試験でも得点が安定し、本命校の合格可能性が高まる傾向が確認されています。
これは、共通テストで75%を獲得できる学力は、基礎知識の定着だけでなく、応用力や時間配分能力など、二次試験にも通じる総合的な学力を示しているからです。
そのため、共通テストで75%を目指す学習戦略は、単に共通テスト対策に留まらず、順位・偏差値ともに実りある方向性となるといえます。
得点率をさらに向上させるためには、模試や過去問演習で間違えた問題の原因を詳細に分析し、改善に結びつけることが肝要です。
なぜ間違えたのか、知識不足か、時間配分ミスか、読解ミスか、その原因を分解して明確にすることで、効果的な対策を立てることができます。
最後の数ヶ月で得点が急上昇する受験生も多く、適切な反省と計画的な実行が得点差を埋める最大の要因となります。
共通テスト75%を取るための科目別対策
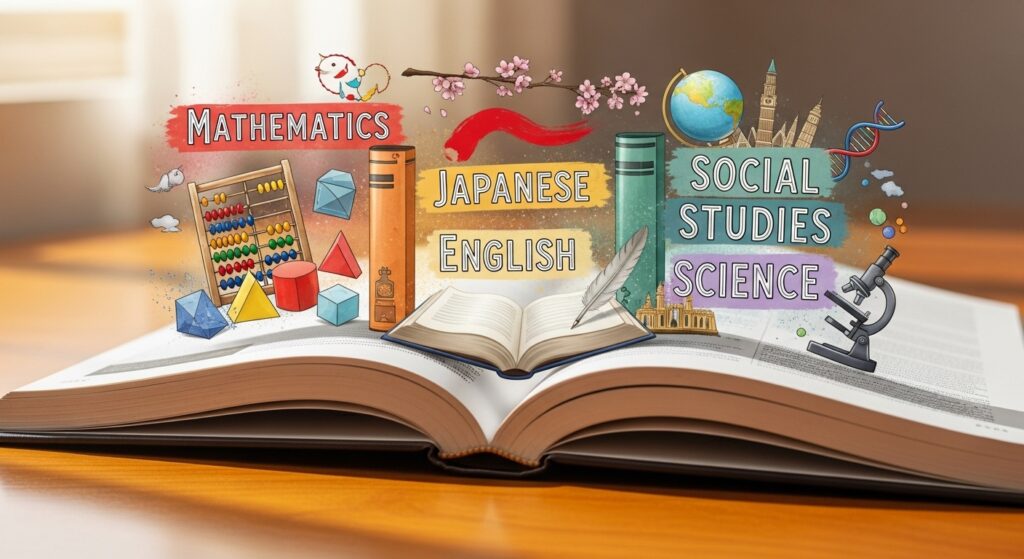
- 共通テスト75%を目指す数学の勉強法
- 共通テスト75%を目指す英語の勉強法
- 共通テスト75%を目指す国語の勉強法
- 共通テスト75%を目指す理科の勉強法
- 共通テスト75%を目指す社会の勉強法
- それでも勉強戦略に不安がある人へ
- 共通テスト75%達成後の進路の選び方
共通テスト75%を目指す数学の勉強法
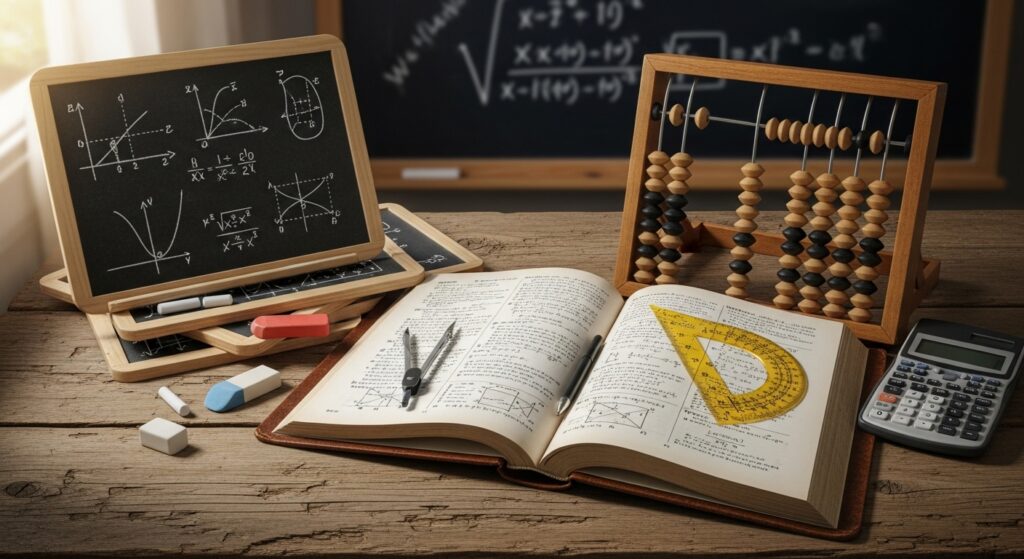
数学は、共通テストにおいて問題量と時間管理が最大の課題となります。
75%の得点を確実にするためには、まずは教科書的な基礎と、網羅系の参考書に掲載されている典型問題を、考えなくても手が動くレベルまで徹底的に磨き上げることが不可欠です。
具体的な目安としては、「青チャート」や「Focus Gold」といった参考書の中堅〜上級問題(例えば、星2〜星3レベル)を確実に解答できる水準を目指します。
この段階で重要なのは、単に答えを出すだけでなく、問題を解くスピードとミスの減少です。
過去問演習においては、「何分でどの問題を解き終えたか」「実際にかかった時間と理想時間の差」を詳細に記録する訓練が非常に有効です。
共通テストの数学は、すべての問題を解く必要はありません。時間がかかる最難問は潔く飛ばし、確実に得点できる問題から手をつけていく戦略が重要です。
模試や過去問を通じて、問題の難易度を瞬時に見分け、どの問題から解くべきかという「問題選択の精度」を高め、自分だけの得点戦略を定着させてください。
この段階的な学習法は、基礎固めから応用、そして実戦的な時間管理能力の習得へとつながり、結果として75%という目標を達成するための土台を築きます。
共通テスト75%を目指す英語の勉強法
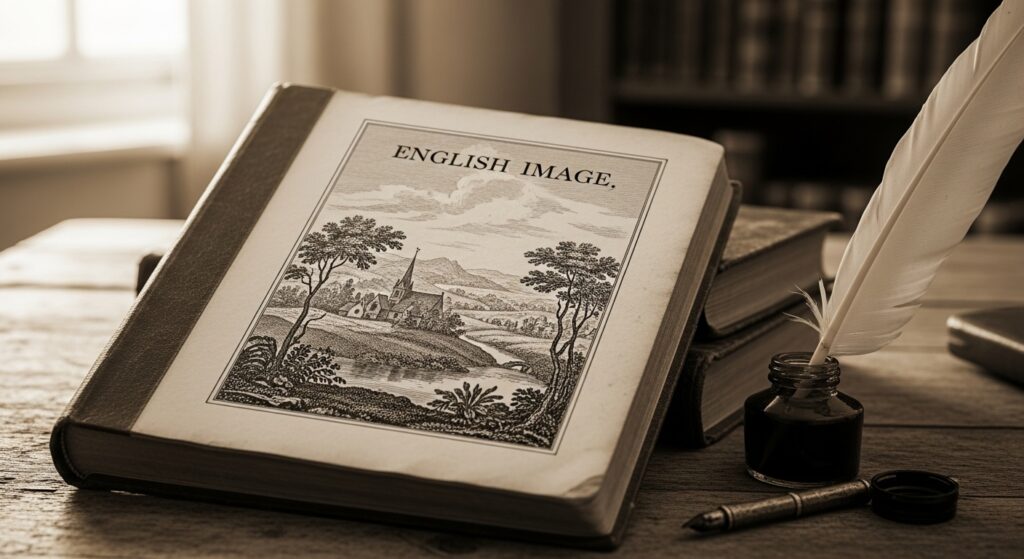
英語は、共通テストにおいて語彙力、文法力、読解力、そして速読力といった総合的な力が問われる科目です。
75%という目標を達成するためには、まず土台となる語彙力と文法力の徹底的な強化が不可欠です。
語彙力が不足していると、長文読解が滞り、正確な意味把握に時間を要します。
また、文法に弱点があると、複雑な構文の訳出に苦労し、結果的に時間切れに陥る可能性が高まります。
基礎固めが完了したら、次に長文を時間を意識して読む訓練を積んでいきます。
長文の読み方としては、設問を先に読んでから本文を読む「設問先読み」、段落ごとに要旨を把握していく「段落要旨把握」、そして重要語句や接続詞に迅速に注目する「キーワード着目」などのスキルを磨くことが有効です。
英語は、共通テストの科目の中でも比較的得点しやすい科目の一つであり、80〜90%を狙えるように仕上げることで、全体の底上げに大きく貢献します。
定期的に模試で時間を計測し、本番を想定した練習を行うことで、時間配分を体得し、実戦的な読解力を高めてください。
単に問題を解くだけでなく、なぜ間違えたのか、どうすれば時間を短縮できたのかを分析することが、得点力向上への鍵となります。
共通テスト英語についてもっと知りたい人は↓
共通テスト75%を目指す国語の勉強法

国語は、得点の安定化が難しい科目として知られています。
しかし、適切な対策を行うことで、75%の得点率を十分に狙うことが可能です。
まず、時間の配分を自分なりに確立することが重要です。
目安としては、評論・小説にそれぞれ20分、資料の読みとり問題に10分、古文・漢文にそれぞれ15分程度を基準とし、自身の得意・不得意に合わせて調整してください。
現代文では、論理の流れを掴む読解法を徹底的に磨きます。
段落ごとの関係性や、筆者の主張、結論に至るまでの根拠を正確に把握する練習を重ねてください。
そのためにオススメの参考書として以下の本を挙げておきます。
また、近年増加傾向にある資料問題では、本文と資料をいかに効率よく読み解き、情報を結びつけるかの判断力が求められます。
古文は、単語と文法を完璧に定着させた上で、古典特有の読み方の訓練が必要です。
助動詞の意味や敬語、登場人物の心情の変化を読み解くパターンを参考書で学び、多くの演習を通じて実践することで、安定した得点に繋がります。
オススメの参考書を挙げておきます。
漢文は、句形や漢字の多義性を素早く引き出す練習が中心となります。
句形を覚え、再読文字や返り点のルールを徹底的に身につけることで、短時間で高得点を狙うことができます。
共通テスト75%を目指す理科の勉強法

理科は、科目選択によって戦略が大きく異なりますが、共通して言えるのは、基礎知識の体系化と、資料やグラフの正確な読み取り能力が鍵となることです。
物理や化学では、単に公式を暗記するのではなく、その公式が導出される過程や適用される場面を深く理解することが重要です。
問題演習を通じて、公式を使いこなせるようにしてください。
生物や地学では、膨大な用語や概念を整理し、頭の中で体系化することが求められます。
また、共通テストでは、実験結果のグラフや図表から情報を即座に読み取る問題が多く出題されるため、日頃から図表を読み解く訓練を積んでおくことが不可欠です。
近年は、複数の分野の知識を組み合わせて思考させる複合的な設問も増えています。
単なる暗記に留まらず、知識を応用して考える力を養うことが必要です。
定期的な過去問演習を通して、実際の出題形式に慣れ、どのような形式の問題でも対応できる力を身につけてください。
共通テスト75%を目指す社会の勉強法
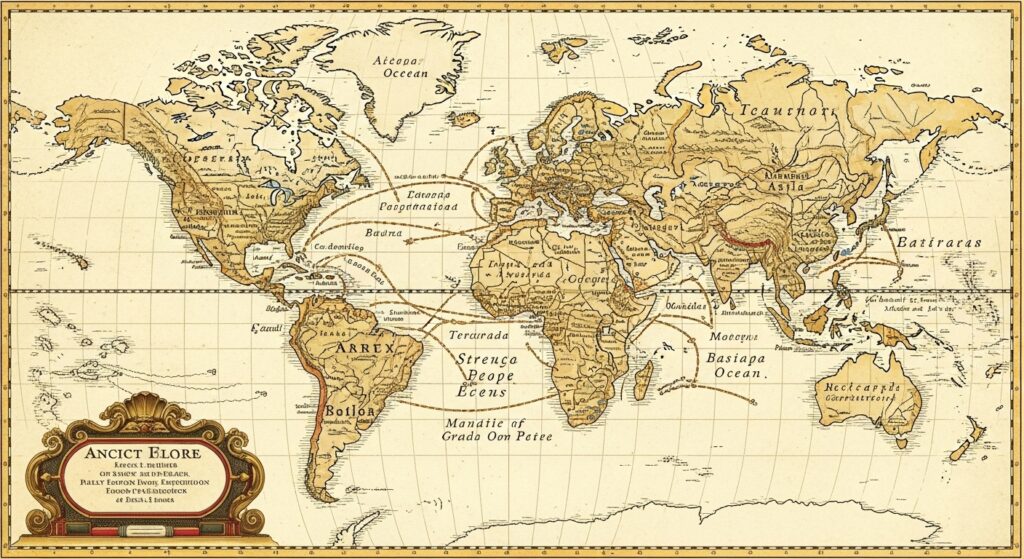
社会科目は、地理歴史(世界史、日本史、地理)と公民(倫理、政治・経済、現代社会)に分かれますが、いずれの科目においても、幅広い知識の整理と、資料を短時間で正確に読み解くスピードが鍵となります。
75%の得点率を確保するためには、まず教科書や参考書に記載されている重要事項を、年表や地図、統計資料などを用いて体系的に整理し、関連事項を結び付けて理解することが不可欠です。
地歴では、単なる用語の暗記に留まらず、出来事の因果関係や、時代ごとの流れを大きな視点で捉えることが重要です。
公民では、現代社会の課題や制度について、多角的に考察する力を養う必要があります。
また、共通テストでは、図やグラフ、表といった資料から情報を読み取らせる問題が頻繁に出題されます。
日頃から資料を短時間で正確に読み解くトレーニングを重ねることで、本番での対応力を高めることができます。
さらに、社会科目は知識の紐付けが得点力に直結します。
頻出テーマを繰り返し学習し、設問の形式に応じた解法(選択肢の比較、資料からの逆算など)を身につけることが有効です。
それでも勉強戦略に不安がある人へ
ここまで、共通テストで75%を取るための勉強戦略について詳しく解説してきました。
それでも、勉強計画の最適解というのは個人ごとに異なり、その戦略ミスはそのまま不合格に直結してきます。(私が一回落ちたのも勉強戦略のミスが大きな原因です。)
とは言え、予備校に通うとなるとかなりのお金もかかるし、個人ごとに丁寧に見てくれるかといわれるとそうでもありません。
そこで、私はトウコベというオンライン塾をオススメしています。
この塾の最大の利点は、現役東大生のマンツーマン指導が受けられることです。
しかも、東大生に勉強を教えてもらえるだけでなく、受験戦略まで一緒に考えてもらえます!
- 無料で体験授業や相談ができる
- 予備校よりも経済的
- 個人に合った指導が受けられる
- 勉強の内容だけでなく勉強方法についてもサポートが受けられる
- 分からない問題は24時間LINEで質問し放題(他のサービスでは問題数に制限があったりするところが多いのでとても魅力的)
- 講師が東大生か京大生であり、講師の質もいい
勉強について困っていることがある人は、とりあえず以下のリンクから無料相談だけでも受けてみてはいかがでしょうか。
東大生のオンライン個別指導『トウコベ』
ここだけの話、勉強戦略に不安がある人は、とりあえず無料の相談会だけ受けて、戦略を立ててもらい、後は自分で勉強するのも結構ありだと思うよ!
合格のために使えるものは使っていこう!
共通テスト75%達成後の進路の選び方
共通テストで75%という得点率を達成した後は、合格可能性のある大学をリストアップするだけでなく、学部の専門性、将来のキャリア、二次試験の負担などを総合的に検討することが大切です。
ここでは、これまでの内容を踏まえ、進路選択に役立つ主要ポイントをまとめます。
- 志望校と受験計画の具体化と実行: 共通テスト75パーセントという得点を基準に、自身が目指せる大学の具体的なリストを作成し、二次試験に向けた詳細な学習計画を立てて実行に移します。
- 得意科目で得点配分を有利に: 得意科目を徹底的に伸ばし、そこで高得点を稼ぐことで、全体の得点配分を有利にする戦略を立て、そのための学習計画を細かく設計します。
- 苦手科目の基礎固めと問題選択: 苦手科目は無理に満点を目指すのではなく、基礎を固めて確実に得点できる問題を見極め、安定した得点力をつける訓練を行います。
- 過去問演習による実戦力強化: 過去問を解くことで、各大学の出題傾向と時間配分を体得し、本番での実戦力を高めます。
- 模試結果の詳細な分析: 模試の結果を詳細に分析し、自分の弱点を特定し、優先順位をつけて効率的に学習を進めます。
- 二次試験との配点バランス: 共通テストと二次試験の配点比率を考慮し、どちらに重点を置くべきか戦略的に判断します。
- 英語の学習: 語彙力と速読力の両立を目標に、実戦的な読解力を強化し、高得点を狙えるように学習計画を立てます。
- 数学の学習: 典型問題の反射的な解法と、本番での問題選択の精度を上げる訓練を重ね、時間内に得点を重ねる練習を行います。
- 国語の学習: 現代文の論理把握と古典読解の読み方を徹底的に習得し、安定して得点できる力を養います。
- 理科の学習: 基礎知識の体系化と資料解釈力を養い、複合的な問題にも対応できる力を身につけます。
- 社会の学習: 年表や統計資料の整理を通じて、資料読み取りの速度と正確性を高めます。
- 共通テスト利用の戦略: 受験方式の違いを理解し、自分の強みを活かせる共通テスト利用の出願戦略を有利に設計します。
- 受験直前期の集中学習: 受験直前期は、苦手分野を絞り込み、短期集中で得点力を最大化する復習を行います。
- 本番のメンタル管理: 本番で実力を最大限に発揮するため、生活リズムと睡眠を整える習慣をつけ、メンタル面も管理します。
- 長期的な視点での選択: 合格後は、学部の専門性や将来性を比較検討し、長期的な視点で自分の進路を選択します。
最後に必要なのは、「取れる問題を確実に取る力(ケアレスミス撲滅)」と「捨て問の判断スピード」です。 このnoteには、そのための具体的な手順を全て詰め込みました。最後のひと押しが欲しい人はぜひ手に取ってください。
次のレベルに進みたい人は↓




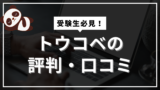




コメント