「九州大学共創学部は何をする学部?」という疑問を持ち、検索された皆さまは、このユニークな名称の学部に強い関心があることでしょう。
2018年に設置された共創学部は、既存の学問分野の枠を超え、複雑化する地球規模の課題に対し、自ら問いを立てて解決策を導き出す「共創的課題解決力」の獲得を目指す新しいリベラルアーツ系の学部です。
まだ設置されてから日が浅いため、その教育内容や卒業後の進路、そして入学の難易度や入試科目、倍率といった具体的な情報について知りたいと考えている方も多いはずです。
特に、特定の専門分野に特化する伝統的な学部と比較して、「自分に向いているのか」「将来の就職に失敗や後悔はないか」といった不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、共創学部がいつからスタートしたのかという基本情報から、偏差値や難易度といった受験情報、さらに具体的な入試科目、倍率や受かるためには何が必要かまで、多角的に解説します。
九州大学共創学部の真の「評判」と、そこで得られる資格や就職の可能性を深く理解し、あなたの進路選択の一助としてください。
- 共創学部が目指す「共創」の概念と具体的な学習内容がわかります
- 同学部が「いつから」設置され、どのような特徴を持っているかがわかります
- 入学「難易度」や「偏差値」「倍率」といった具体的な受験情報がわかります
- 共創学部に向いている人、向いていない人の特徴や卒業後の「就職」の可能性がわかります
九州大学共創学部は何をする学部か

共創学部は、地球規模の複雑な課題に対して、既存の専門分野の枠を超えて解決策を創造する人材を育成するために設立されました。
このセクションでは、共創学部がどのような理念のもと、何を学ぶ場であるのかを具体的に解説します。
- 九州大学共創学部はいつからある?
- 九州大学共創学部の「共創」の評判と真意
- 卒業後の進路と主な就職先
- 九州大学共創学部の取得を目指せる資格
九州大学共創学部はいつからある?
九州大学共創学部は、平成30年4月(2018年4月)に設置された、比較的新しい学部です。
この設立は、100年以上の歴史を持つ総合大学である九州大学が、その総力を結集して行った「新たな挑戦」として位置づけられています。
複雑化・多様化するグローバル社会、特に既存の学問分野だけでは解決が難しい地球規模の課題に対応するために、従来の大学教育の枠組みを超えた「共創」というコンセプトを掲げて誕生しました。
この学部が設立された背景には、環境問題、食糧危機、人権、経済的格差、パンデミックといった、地域や国境を超えた人類共通の「答えのない問題」が山積しているという現状認識があります。
これらの問題は、一つの専門分野の視点だけで解決できるものではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。
共創学部は、このような課題に対し、文系・理系の枠にとらわれずに能動的に知識を組み合わせ、多様な人々と協働しながら革新的な解決策(イノベーション)を創出できる人材を育成することを目指しています。
これは、単なる知識の習得に留まらず、未来に起こりうる課題に対してアプローチできる思考様式と、それを行動に移す能力を養うための、現代社会に不可欠な教育改革の一環であると言えます。
九州大学共創学部の「共創」の評判と真意

共創学部が標榜する「共創」とは、単に協力し合う「協働」や、意見を出し合う「討議」を超えた、課題解決に向けた「新たな知」を創造するプロセス全体を意味しています。
この学びは、既存の専門分野に囚われず、学生自らが課題の発見から解決までを主導する態度を養うことに焦点を当てています。
共創のプロセスは、以下の3つの段階を循環することで成り立っています。
共創を構成する3つの重要なプロセス
- 構想: 答えが明確でない複雑な課題に対し、自ら深く考え、多角的な視点からアプローチし、解決策を創造的に構想する力。
- 協働: 一人では考えが及ばない領域や専門性について、多様な背景を持つ他者と連携し、知見を出し合いながら共に進める力。
- 経験: 構想と協働を通じて得た知を、実社会の現場で実際に活用し、フィードバックを得る実践的な経験を積むこと。
共創学部では、この「構想」「協働」「経験」というプロセスを絶えず繰り返すことで、「課題に応じ自ら必要なことを学ぶ態度や志向性」(能動的学習能力)を身につけ、異なる知識を組み合わせた「新たな知」(創造的構想力)を生み出し、それを実社会の中で活用できる能力の獲得を目指します。
この学び方の最大の特徴は、従来の「これを学んだから将来これをする」という、専門分野が先行する受け身の学習ではなく、「これをしたいから、そのために必要なこれを学ぶ」という、課題解決を起点とする能動的な学習態度にあります。
学生は、まず自分が取り組みたい地球規模の課題や社会問題を見つけ、その解決に必要となる知識や専門性を、文系・理系の区別なく自由に組み合わせて学んでいきます。
具体的に涵養を目指す態度・能力は、「創造的構想力」「能動的学習能力」「国際コミュニケーション力」「課題検討力」「協働実践力」の5つに分類され、これらを通じて「共創的課題解決力」の獲得を目指します。
教員構成においても、その学際性が反映されています。
理学部系(物理学、化学、数学、生物学、岩石・地球科学など)の専門家と、人文社会系(哲学、経済学、考古学、歴史学など)の専門家がバランスよく配置されており、学生が幅広いリベラルアーツ的な学びを深く追求できるよう、指導体制が整えられています。
卒業後の進路と主な就職先

共創学部で育成される「共創的課題解決力」は、社会のあらゆる分野で求められる汎用性が非常に高い能力です。
常に課題を意識し、自ら能動的に学び、多様な専門性を統合できるという資質は、変化の激しい現代社会において、企業や組織が最も必要とする人材像と重なります。
共創学部の学びは特定の職種に限定されるものではありませんが、その学際的なバックグラウンドを活かし、国内外の多岐にわたる分野で活躍が期待されます。
例えば、国際的な課題に関心を持つ学生は国際公務員や外交官、環境問題に取り組む学生は関連する企業や研究機関、データ分析に関心を持つ学生はデータサイエンティストなど、多様なキャリアパスが想定されています。
目指せる仕事の例としては、国家公務員、政治家、法学・政治学研究者、国際公務員、外資系スタッフ、外交官、国連スタッフ、データサイエンティスト、生物学研究者、教育学研究者などが挙げられています。
これらの例は、考古学、言語学、法学、情報学、心理学、物理学など、同窓生が横断的に学んだ幅広い学問分野の成果が反映された結果と言えます。
実際の卒業生の就職実績を見ると、日本のトップクラスの企業やコンサルティングファーム、金融機関など、幅広い業界に就職していることが確認できます。
| 企業・団体名 | 分野(主な業種) |
| 三菱重工業 | 重工業、製造業(社会インフラ、防衛、エネルギーなど) |
| 福岡銀行 | 金融(地方銀行) |
| アクセンチュア | コンサルティング(グローバルファーム) |
| 三菱電機 | 電気機器、製造業 |
| レバレジーズ | IT、人材(IT・Webサービス系) |
| 野村総合研究所 | シンクタンク、コンサルティング |
| 全日本空輸(ANA) | 航空 |
| デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー | コンサルティング(会計系ファーム) |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | コンサルティング(会計系ファーム) |
| 日本電気(NEC) | IT、電気機器 |
これらの就職実績は、製造業や金融といった伝統的な産業から、コンサルティングやIT、航空といった最新のサービス産業まで、共創学部の卒業生が持つ課題解決能力と柔軟性が高く評価されていることを示しています。
特定の専門分野に限定されず、自らキャリアを切り開いていく能力が、就職市場において大きな強みとなっていると考えられます。
(出典:九州大学『共創学部』)
九州大学共創学部の取得を目指せる資格
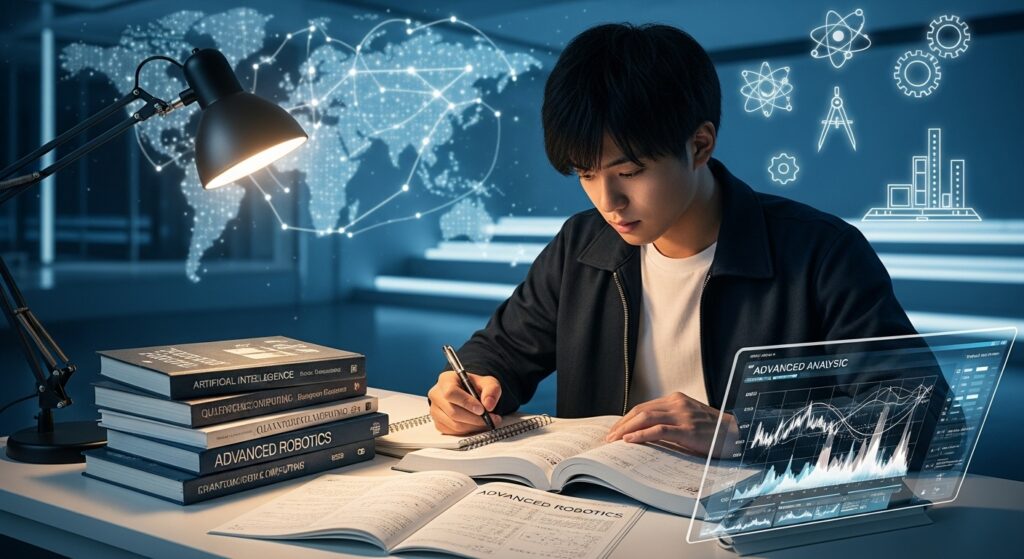
九州大学共創学部は、特定の職業に直結する資格の取得を主な目的とする学部ではありません。
むしろ、既成の学問分野を横断的に学び、独自の視点から課題解決能力を養うことに重きを置いています。
しかし、学生が自ら選択した専門分野の学びを深めることで、将来のキャリアに必要な資格取得を目指すことは可能です。
例えば、学部のカリキュラムには教育学関連の科目が含まれているため、特定の要件を満たすことで、将来的に教員免許状の取得に必要な科目を履修できる場合があります。
また、情報学やデータサイエンス系の学問分野も提供されているため、IT関連の資格やデータサイエンティストとしての専門性を高めるための知識を身につけることが可能です。
共創学部の教育の根幹は、学生が「これをしたいからこれを学ぶ」という姿勢に基づいて、必要な知識や技能を自律的に習得していく点にあります。
したがって、目指すキャリアに応じて、必要な学問分野を選び、その分野で求められる資格や専門性を能動的に構築していくことが、共創学部の学び方となります。
学生は、入学後に自身の問題意識や将来の目標を明確にし、その目標達成のためにどの分野を深掘りし、どのような資格取得を目指すかを、指導教員と相談しながら計画的に進めていくことになります。

自分から学ぶ内容を決めるという能動的な学習姿勢が必要になるね!
九州大学共創学部に入学するには何をする?

共創学部が目指す理念や教育内容が魅力的であっても、入学するには高い壁を乗り越える必要があります。
このセクションでは、入学を志す方が知っておくべき、難易度、偏差値、倍率、入試科目といった受験に関する具体的な情報を解説します。
- 九州大学共創学部の難易度と受験の壁
- 九州大学共創学部の最新偏差値情報
- 九州大学共創学部の入試倍率はどれくらい?
- 九州大学共創学部の入試科目は何?
- 共創学部に受かるための心構えと対策
九州大学共創学部の難易度と受験の壁
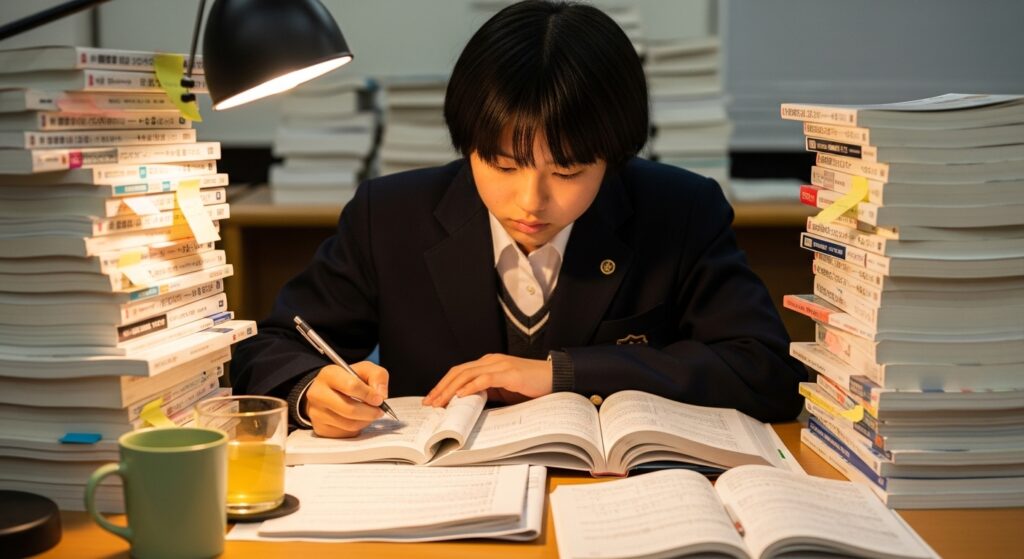
九州大学共創学部は、旧帝大という括りの中でも、近年設置された新しいコンセプトを持つ学部であるため、その入学難易度は非常に高い水準にあります。
一般の大学受験予備校が示すデータによれば、偏差値は概ね60.0から64程度、大学入学共通テストのボーダー得点率は74%から77%程度とされており、これは九州大学の全学部の中でも、トップクラスの難関グループに位置づけられます。(出典:パスナビ)
難易度を押し上げている要因は、単に要求される学力の高さだけではありません。
共創学部は、既存の専門分野に特化する伝統的な学部とは異なり、文理融合の幅広い知識と、それらを論理的に統合し、複雑な課題解決へと導く高度な思考力が求められます。
そのため、受験生には、高等学校までに培うべき基礎的な知的体力に加えて、個別試験(二次試験)で課される小論文や論述形式の問題を通じて、「自ら問いを立てる力」「構想力」「表現力」といった、学部が掲げる「共創的課題解決力」の基盤となる資質が厳しく試されます。
特定の科目知識の暗記だけでは通用しない、多角的な対策が不可欠となるため、受験の壁は非常に高いと言えます。
九州大学共創学部の最新偏差値情報

九州大学共創学部の偏差値は、その難易度を裏付けるように、大手予備校のデータでは概ね60.0〜64.0の間で安定して推移しています。この水準は、九州大学の文系学部のトップ層(文学部、法学部、経済学部など)と並ぶか、年度によってはそれらを上回る位置にあります。
最新の入試データに基づく具体的な数値の目安は以下の通りです。ただし、これらの数値は予備校や判定時期によって変動する「合格可能性の目安」であり、出願時の参考情報として捉える必要があります。
| 評価指標 | 数値の目安 | 補足事項 |
| 偏差値(河合塾・前期) | 60.0 | 合格可能性50%のボーダー偏差値 |
| 偏差値(東進・前期) | 64 | 合格難易度の客観評価 |
| 共通テスト得点率(ボーダー) | 74%〜77% | 合格に必要な共通テストの得点率の目安 |
このような高い偏差値と共通テスト得点率は、共創学部が持つユニークな教育コンセプトと、旧帝大ブランドへの強い志望動機を持つ受験生が集中していることを示しています。
受験を考える際は、この数値をクリアできる学力を身につけるとともに、単なる学力だけでなく、学部が求める知的好奇心や能動性をアピールできる準備を進めることが大切になります。
九州大学共創学部の入試倍率はどれくらい?
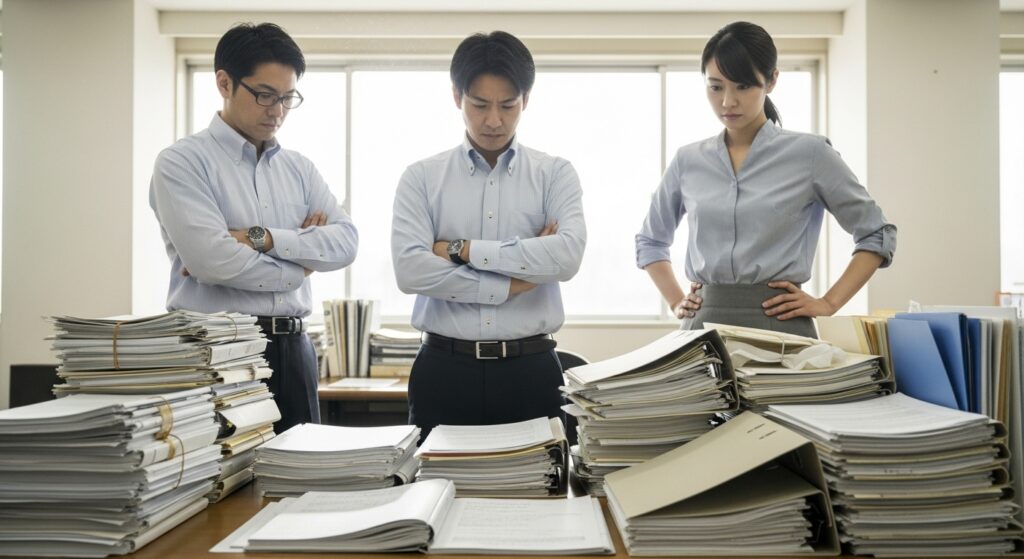
九州大学共創学部は、全募集定員が105名と、旧帝大の学部としては比較的小規模な体制であり、そのうち一般選抜(前期日程)の定員は65名程度と狭き門になっています。
この少ない定員に対し、毎年多くの志願者が集まるため、競争率は高くなる傾向にあります。
過去の入試結果を見ると、一般選抜の募集人員に対する倍率は例年3倍台から4倍台で推移しており、これは九州大学の他の学部と比較しても、高めの競争率となっています。
倍率が高くなる背景
- ユニークなコンセプトへの関心: 既存の枠に収まらない「共創」という新しい学びのコンセプトに、特に意識の高い受験生や、文理選択で迷っている優秀な層が惹きつけられています。
- 旧帝大ブランド: 旧帝大である九州大学の学部であるというブランド力と、将来の多様なキャリアパスへの期待から、多くの受験生が志願します。
- 定員の少なさ: 一般選抜の定員が65名程度と少ないため、志願者数のわずかな増加でも倍率が大きく変動しやすく、競争が激化しやすい構造があります。
正確な入試倍率や志願者数は年度によって変動しますので、出願に際しては、必ず大学が公表する最新の募集要項や入試結果(出典:九州大学『令和7年度(2025年度)入学者選抜概要』)を確認することが極めて重要です。
高い競争率を勝ち抜くためには、共通テストと個別学力検査の両方で、ボーダーラインを大きく超える盤石な高得点を安定して取れる実力が求められます。
九州大学共創学部の入試科目は何?
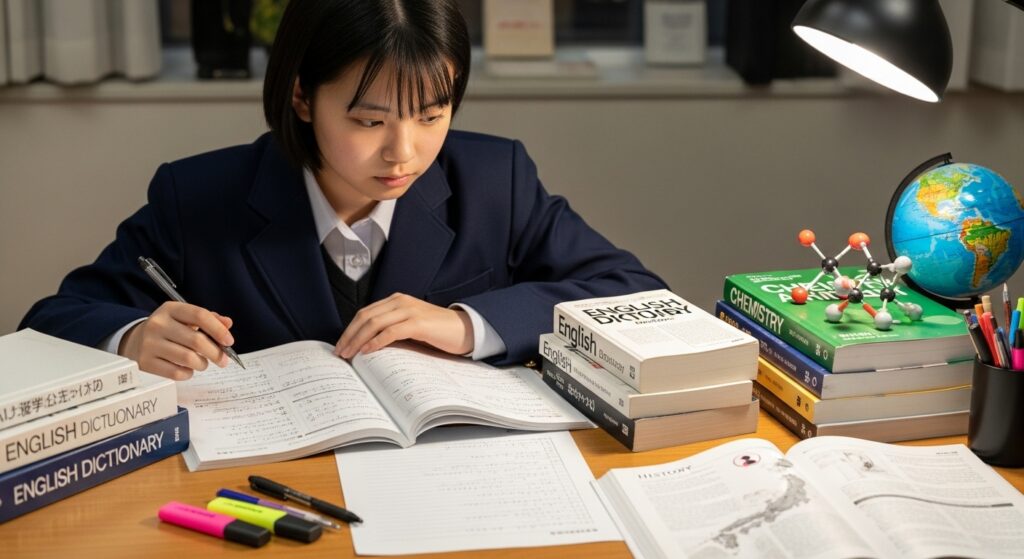
九州大学共創学部の一般選抜(前期日程)における入試は、共通テストと個別学力検査(二次試験)の合計1525点満点で評価されます。
個別学力検査(二次試験)の配点比率が約65%と非常に高いため、二次試験対策が合否の鍵を握ります。
1. 共通テストの科目構成(合計525点満点)
共通テストでは、文理の枠を超えた幅広い知識を測るため、6教科7科目または6教科8科目が課されます。
- 国語: 必須(100点)
- 数学: 数ⅠA、数ⅡBC 必須(計100点)
- 外国語: 英語、独、仏、中、韓から1科目(リスニングあり)必須(計100点)
- 情報: 情報Ⅰ 必須(25点)
- 地歴・公民: 選択(50点)
- 理科: 選択(50点)
2. 個別学力検査(二次試験)の科目構成(合計1000点満点)
個別学力検査は、合計1000点満点で、特に共創学部が重視する能力が試されます。
- 外国語: 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(400点)
- 数学: 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列)、数C(ベクトル)が出題範囲(300点)
- 小論文: (300点)
- 本人記載の資料等: 評価対象
特に注目すべきは、「小論文」に300点という高い配点が設けられている点です。
これは、単なる文章作成能力ではなく、複雑な情報の中から課題を発見し、論理的な解決策を構想し、それを明確に記述する力が合否を大きく左右することを意味しています。
外国語(英語)の配点が最も高く、国際コミュニケーション力の基礎となる語学力も重視されています。(出典:九州大学『令和7年度(2025年度)入学者選抜概要』)
共創学部に受かるための心構えと対策
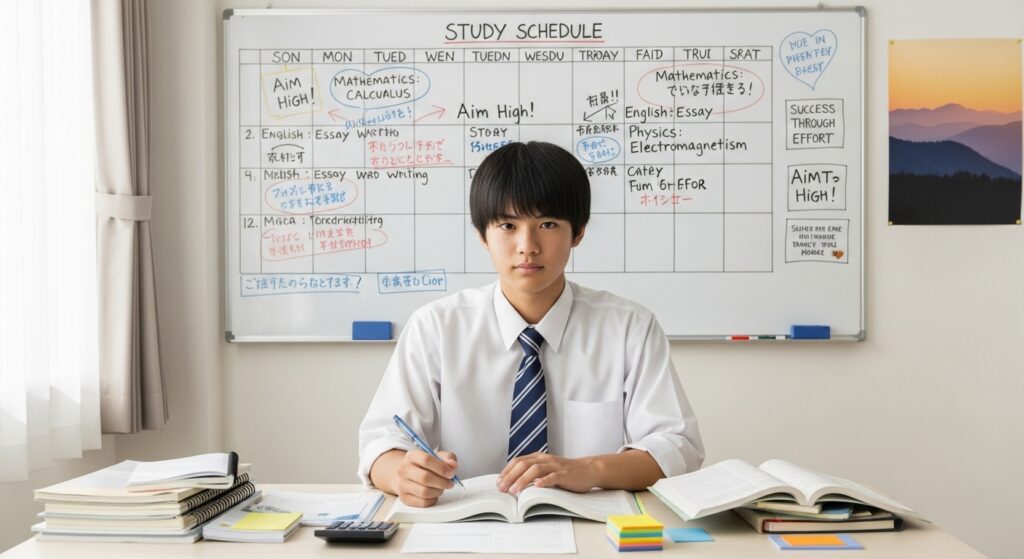
九州大学共創学部に合格するためには、一般的な学力向上に加えて、学部が求める「共創的課題解決力」の資質を備えることが不可欠です。
1. 能動的学習態度の確立と継続
共創学部の教育理念は「これをしたいからこれを学ぶ」という能動的な学習姿勢に基づいています。
このため、受験勉強においても、単に与えられた問題集をこなすのではなく、「なぜこの知識が必要なのか」「どうすればこれを社会の課題に活用できるのか」を常に意識する姿勢が求められます。
日頃からニュースや社会問題に関心を持ち、自分なりの問いを立て、その答えを探す習慣を身につけることが、入学後の学びの姿勢、ひいては合格に繋がります。
2. 個別試験での小論文対策の徹底と深化
配点300点という小論文は、合否の鍵を握る最重要科目です。小論文対策は、特定の知識を暗記する作業ではなく、思考力そのものを鍛える訓練として捉える必要があります。
- 過去問を分析し、出題の意図(どのような社会的な問いに対する見解を求めているか)を深く理解してください。
- 論理的な文章構成(序論・本論・結論)の訓練を徹底し、自分の主張を明確に、かつ論拠に基づいて記述する力を養う必要があります。
- 社会や科学に関する幅広いテーマに触れ、自分の専門外の分野の知識も統合して考える練習を重ねることが、創造的構想力を高める上で非常に有効です。
3. 伝統的な学部との比較検討を通じた志望動機の明確化
共創学部は、工学、農学、法学、経済学といった特定の専門分野を深く極めたい人には、残念ながら向いていません。
その代わり、幅広い教養と分野横断的な知を求める人にとって最適です。
受験に際しては、自身の将来の夢や目標を真剣に見つめ直し、「高度な専門知識を追求する伝統的な学部」と、「リベラルアーツ的に広く学び、課題解決力を養う共創学部」のどちらが本当に自分に合致しているのかを深く考えるべきです。
安易な気持ちで志望することは、入学後に「学びたいことが見つからない」という後悔につながる可能性があるため、注意が必要です。
4. 文理の枠を超えた学習とバランスの確保
個別試験の数学は文系範囲(数Ⅲの範囲は含まれない)ですが、共通テストでは理科や地歴・公民を含めた幅広い科目が課されます。
共創学部が求める人材は、文系・理系のどちらにも偏ることなく、多様な知識を組み合わせられる人です。
したがって、文系だからといって理科を疎かにする、理系だからといって国語や社会科の対策を怠るという姿勢は禁物です。
全教科をバランス良く、かつ高い水準で仕上げることが、合格に繋がる総合力を築くことになります。
結局、九州大学共創学部は何をするべき人のための学部か
九州大学共創学部は、従来の学問分野の枠を超えて「共創的課題解決力」を身につけ、社会に新たな価値を創造したいと強く願う人のための学部です。
この記事では、九州大学共創学部は何をする学部なのか、その理念、教育内容、そして難易度や入試科目といった受験情報を詳しく解説してきました。
九州大学共創学部への入学を目指す人が理解しておくべきポイントは以下の通りです。
- 共創学部は2018年4月に設置された新しいリベラルアーツ系の学部である
- 「共創」とは「構想」「協働」「経験」を繰り返す課題解決のプロセスを意味する
- 能動的学習能力と創造的構想力を持つ人材の育成を目指している
- 学問分野は考古学、情報学、物理学など文理を横断して非常に幅広い
- 卒業後はコンサルティング、IT、金融など多様な業界で活躍できる
- 入学者定員は105名で、うち一般選抜は65名と少数精鋭である
- 入試の難易度は偏差値60.0〜64.0、共通テストボーダーは74%〜77%と高水準である
- 一般選抜の入試倍率は例年3倍台から4倍台で競争率が高い
- 個別試験では小論文が300点と高い配点を占めるため対策が不可欠である
- 特定の専門分野(工学、農学、法学など)を極めたい人には向いていない
- 文系・理系の枠を超えて広く学びたいという強い意志を持つ人が向いている
- 常に課題を意識し、自ら必要なことを学べる態度や志向性が求められる
- 工学や農学といった専門職への道は大学院でも難しい可能性があるため覚悟が必要である
- 国際コミュニケーション力や協働実践力も養うことを目標としている
- 芸術工学部など、他のユニークな学部との比較検討も重要である
その他の大学の情報を知りたい方はこちら!


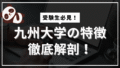

コメント