
パンダさん!夜遅くまで勉強するのと、朝早く起きて勉強するのどっちがいいの?

学習スタイルは人それぞれだから、人によって適切な学習時間帯は変わるよ!
今回は自分に合った学習スタイルの見つけ方を紹介するね!
「勉強しなきゃいけないのは分かっているけど、夜遅くまで起きていたら次の日に響くし、かといって朝早く起きるのもつらい……」と感じたことはありませんか?
真面目な人ほど、夜遅くまで勉強するか、朝早く起きて勉強するか悩み、結局どうしたら良いか分からず時間だけが過ぎてしまうこともありますよね。
この悩みは、本記事で解決できます。
結論からお伝えすると、自分に合った勉強法は、あなたのタイプによって異なります。
朝勉強と夜勉強のメリット・デメリットを理解し、自分の性格や生活スタイルに合わせて使い分けることが最も効率的です。
そのための診断も用意しています。
この記事では、朝と夜それぞれの時間帯に合わせた効果的な勉強法や、生活リズムの整え方を解説します。
最後まで読むことで、あなたにぴったりの学習スタイルが見つかり、迷いなく勉強に取り組めるようになります。
もう「朝か夜か」で悩む必要はありません。
自分に合った方法で効率よく勉強を進め、目標達成へ着実に近づきましょう。
- 朝勉強と夜勉強のそれぞれのメリットとデメリット
- 朝や夜の勉強に向いている学習内容
- 自分に合った学習スタイル(朝型・夜型・ハイブリッド型)を見つける方法
- 早起きするための具体的な方法や質の高い睡眠を確保する重要性
勉強するならどっち?夜遅くまで勉強するか朝早く起きて勉強するか
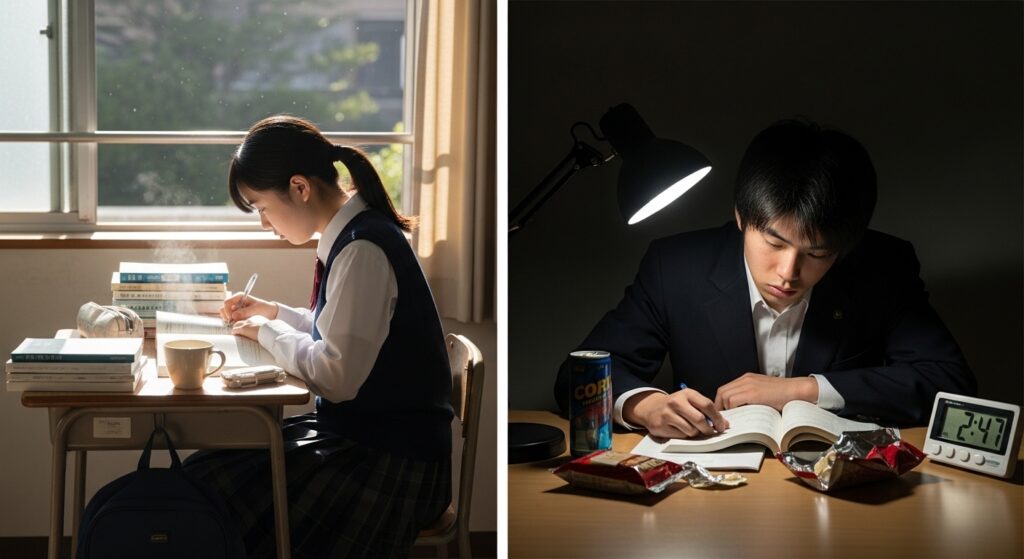
- 結局どっちがいいのか
- 朝勉強のメリット・デメリット
- 朝に向いている勉強内容
- 夜勉強のメリット・デメリット
- 夜に向いている勉強内容
結局どっちがいいのか
朝勉強と夜勉強は、それぞれに利点と注意点があります。
どちらか一方が絶対的に優れていると断言することはできませんが、結論から述べますと、朝勉強をメインに据えることがオススメです。
その理由は、受験本番や多くの試験が午前中に行われるからです。
日頃から朝に脳を働かせる習慣をつけておくことで、試験当日に最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。
もちろん、夜にしか勉強時間を確保できない方もいらっしゃいます。
そのような場合は、夜勉強の利点を最大限に活用し、暗記科目に絞って集中的に取り組むのが良いでしょう。
また、朝と夜のメリットを組み合わせるのも効果的です。
夜は暗記に時間を使い、朝は思考力を要する問題演習に充てるなど、時間帯に応じて学習内容を使い分けることで、効率の良い勉強が実現します。
いずれにしても、最も重要なのは睡眠時間をしっかり確保することです。
睡眠不足は、どれだけ勉強しても学習効率を下げ、体調を崩す原因にもなります。無理のない範囲で、ご自身の生活スタイルに合った方法を見つけることが大切です。
朝勉強のメリット・デメリット

朝に勉強することには多くのメリットがあります。
主に脳がリフレッシュされているため、集中力や思考力が高い状態で学習に取り組める点が挙げられます。
脳科学者の茂木健一郎氏も、目覚めてからの約3時間は「脳のゴールデンタイム」と称し、最も効率よく働く時間帯であると述べています。
朝はドーパミンやアドレナリンが多く分泌されるため、やる気や集中力が高まり、難しい問題にも取り組みやすくなるでしょう。
また、早朝は物音や話し声が少なく、SNSの通知なども気になりにくい静かな環境で勉強に集中できることも大きな利点です。
さらに、登校時間や出勤時間という締め切りがあるため、「この時間内に終わらせよう」という意識が働き、高い集中力を維持できます。
一方で、朝勉強にはデメリットも存在します。
まず、朝が苦手な人にとって、早起き自体が大きなハードルとなります。特に夜型の生活に慣れている方は、いきなり朝型に切り替えるのは難しいかもしれません。
無理に早起きを続けると、睡眠不足に陥り、かえって日中のパフォーマンスを低下させてしまう可能性があります。
また、登校時間などで勉強時間が限られることもデメリットの一つです。
夜のように時間を延長することが難しいため、計画的に学習を進める必要があります。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 脳の状態 | ・脳がリフレッシュしている ・集中力や思考力が高い ・ドーパミンやアドレナリンが分泌され、やる気が出る | ・早起きが苦手な人にはハードルが高い ・睡眠不足になる可能性がある |
| 環境 | ・静かな環境で集中できる ・SNSなどの誘惑が少ない | ー |
| 時間 | ・登校時間などの「締め切り効果」で集中力が高まる | ・勉強時間が限られる ・夜のように時間を延長できない |
朝に向いている勉強内容
朝の脳は思考力やひらめきに優れているため、複雑な思考を必要とする学習内容がオススメです。
具体的には、国語や英語の長文読解、数学や理科の計算問題や応用問題などが挙げられます。
これらの科目は、論理的に物事を考えたり、新しい知識を組み合わせて答えを導き出したりする力が求められるため、脳が冴えている朝に集中して取り組むと効率が上がります。
また、前日の夜に暗記した内容を、朝に確認するアウトプットの時間に充てるのも効果的です。
睡眠中に整理された記憶を、問題演習や小テスト形式で呼び起こすことで、知識の定着度を高められます。
朝起きてすぐは頭がぼーっとする方もいらっしゃるかもしれません。
その場合は、ウォーミングアップとして簡単な計算問題や音読から始めると、徐々に脳が活性化し、本格的な勉強モードへと移行しやすくなります。
夜勉強のメリット・デメリット
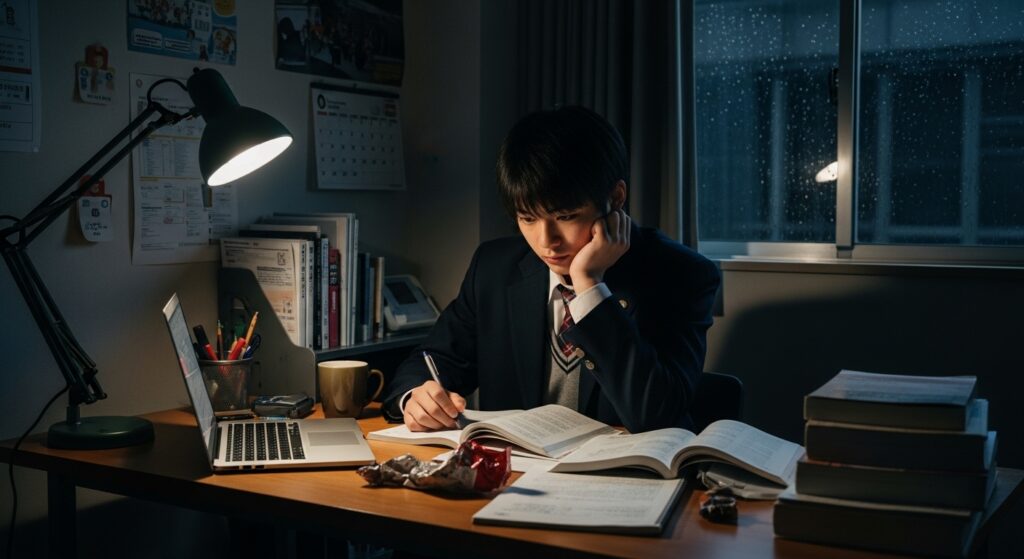
夜に勉強することには、朝勉強とは異なる利点があります。
まず、最も大きなメリットは、まとまった時間を確保しやすいことです。
学校や仕事が終わった後なので、朝のように登校時間といった明確なタイムリミットがなく、夜は自分のペースで学習時間を調整できます。
特に試験前などで集中的に勉強したいときには、夜の時間を活用できるでしょう。
また、深夜の時間帯は家族が寝静まり、SNSの通知も減るため、外部からの妨害を受けにくい静かな環境で集中できる点も魅力です。
一方で、夜勉強にはいくつかの注意すべき点があります。
最大のデメリットは、睡眠不足に陥りやすいことです。
勉強時間を確保するために睡眠時間を削ってしまうと、翌日の集中力が低下し、授業中に眠くなるなど日中の活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、生活リズムが崩れてしまう危険性も高まります。
毎日夜更かしを続けていると、朝なかなか起きられなくなり、体調を崩す原因にもなりかねません。
夜に勉強する場合でも、健康を維持するためには、毎日決まった時間に寝起きすることが大切です。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 時間 | ・まとまった時間を確保しやすい ・自分のペースで学習時間を調整できる | ・睡眠不足に陥りやすい ・生活リズムが崩れる危険性がある |
| 環境 | ・静かな環境で集中できる ・外部からの妨害を受けにくい | ー |
| 体への影響 | ー | ・日中の集中力低下や体調不良につながる可能性がある |
夜に向いている勉強内容
夜は、朝と比べて頭が疲れている状態になりがちです。
そのため、新しい概念を理解したり、複雑な思考を必要としたりする勉強よりも、暗記や復習といったインプット系の学習に向いていると言えます。
その理由は、人間の脳が睡眠中にその日の記憶を整理し、定着させる働きがあるからです。
就寝前の1〜2時間に学習した内容は、特に記憶に残りやすいと言われています。
したがって、夜に勉強するなら、英単語や歴史の年号、古文・漢文の単語といった暗記科目が非常に効果的です。
また、日中に学習した内容を復習する時間としても適しています。
夜に新しい知識を頭に入れ、睡眠中に脳に整理させて、翌朝にアウトプットの練習をするという学習サイクルは、効率的に知識を定着させるのに役立ちます。
ただし、寝る直前までスマホで動画を観たり、SNSをチェックしたりすると、ブルーライトの影響で脳が覚醒し、睡眠の質が低下してしまいます。
夜勉強の効果を最大限に引き出すためにも、寝る前はデジタル機器から離れるよう心がけましょう。
あなたに合うのは?夜遅くまで勉強するか朝早く起きて勉強するか

- あなたにぴったりの学習スタイルを診断
- 朝起きるためには
- 質の高い睡眠を確保しよう
あなたにぴったりの学習スタイルを診断
まずは、どのような学習スタイルの選択肢があるか確認しておきましょう。
- 朝早く起きて勉強するタイプ←理想ではある
- 夜遅くまで勉強するタイプ(ただし試験前2週間は試験が朝から行われるので朝にも勉強すること)
- 両方組み合わせたハイブリットタイプ
「朝に勉強した方がいいって聞くけど、どうしても夜の方が集中できるんだよな…」
「みんなと同じ時間に勉強しなきゃいけないのかな?」
そんな風に悩んでいませんか?実は、勉強するのに最適な時間帯は、あなたの性格や生活スタイルによって全く異なります。
ここでは、いくつかの質問に答えるだけで、あなたが「朝型」「夜型」、または「ハイブリッド型」のどの学習スタイルに当てはまるか診断できます。
自分にぴったりの方法を見つけて、学習効果をグッと高めましょう!
※この診断は朝型-夜型質問票 自己評価版(MEQ-SA)を参考に作っています
以下の質問に、最も当てはまる選択肢を1つずつ選び、合計点を出してください。
【1】朝の気分はどうですか?
- とてもすっきりしている(5点)
- まあまあ良い(4点)
- あまり良くない(2点)
- かなりだるい(1点)
【2】朝起きる時間を自由に選べるとしたら?
- 午前6時~7時(5点)
- 午前7時~8時(4点)
- 午前8時~9時(3点)
- 午前9時以降(2点)
【3】夜22時頃に勉強や仕事を始めたら、どれくらい集中できますか?
- ほとんど集中できない(5点)
- あまり集中できない(4点)
- 普通(3点)
- よく集中できる(2点)
- 非常によく集中できる(1点)
【4】休日に目覚ましをかけずに起きるとしたら?
- 午前6~7時頃(5点)
- 午前7~8時頃(4点)
- 午前8~9時頃(3点)
- 午前9時以降(2点)
【5】どの時間帯が最も頭が冴えていると感じますか?
- 朝(5点)
- 昼前(4点)
- 午後(3点)
- 夜(2点)
- 深夜(1点)
合計点の判定
| 合計点数 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| 21–25点 | 朝型(モーニングタイプ) | 早寝早起き、午前中が得意、夜は弱い |
| 15–20点 | 中間型(ニュートラル) | 朝晩の差が小さい、日中に最も調子が良い |
| 5–14点 | 夜型(イブニングタイプ) | 夜遅くまで活動、朝が苦手、集中は夕方以降に高まる |
最後に一つだけ、大切な注意点
普段は夜型の人でも、試験の2週間前からは、朝に勉強する習慣をつけましょう。
なぜなら、実際の試験は朝に行われるため、朝から頭を働かせることに体を慣らしておく必要があるからです。
最も大切なのは、自分の体調や生活リズムに合った学習スタイルを見つけ、無理なく続けること。 この診断をきっかけに、あなたにぴったりの勉強法を見つけてくださいね。

朝起きて勉強できるのが理想ではあるけど、体質もあるから自分に合わせた方法をとるのが一番だよ!
朝起きるためには

朝早く起きて勉強する習慣を身につけるには、いくつかのコツがあります。
まず、目覚まし時計を上手に使いましょう。
どうしても起きられないという方は、スマホのアラームではなく、大きなアラーム音が鳴る目覚まし時計を用意するのも一つの手です。
スヌーズ機能を使うと二度寝の原因になりやすいので、目覚ましは1回で起きるように工夫するのがおすすめです。
遠くに目覚ましを置くことで、一度ベッドから出なければならない状況を作り出すと、スムーズに起きられるかもしれません。
それから、朝起きたらすぐに日光を浴びることが大切です。
カーテンを開けたり、軽く散歩に出かけたりして太陽の光を浴びると、覚醒効果のある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が促されます。
これにより、体が目覚めモードに切り替わり、気持ちの良い一日をスタートできます。
また、週末も平日と同じ時間に起きるように心がけることで、生活リズムが崩れるのを防ぐことができます。
たまには疲れているときにゆっくり寝る日があっても良いですが、毎日のリズムをなるべく一定に保つことが、早起きの習慣化につながります。
質の高い睡眠を確保しよう

朝早く起きるためには、早寝が不可欠ですが、ただ早く寝るだけでなく、質の高い睡眠をとることが重要です。
睡眠の質を高める工夫をすることで、短い時間でも脳と体をしっかりと休ませることができます。
まず、寝る前の行動を見直してみましょう。
寝る30分前にはスマートフォンやパソコンの使用を控えるのがオススメです。
これらの画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させ、スムーズな入眠を妨げる原因になります。
代わりに、読書をしたり、リラックスできる音楽を聴いたりして過ごすと良いでしょう。
また、適度な運動も質の高い睡眠につながります。日中に体を動かすことで適度な疲労感が生まれ、夜ぐっすり眠れるようになります。
ただし、就寝直前の激しい運動はかえって眠りを妨げるため注意が必要です。
温かいお風呂にゆっくり浸かって体を温めるのも効果的です。
入浴で高まった体温が徐々に下がるタイミングでベッドに入ると、自然な眠りにつきやすくなります。
あなたに合ったのは?夜遅くまで勉強するか朝早く起きて勉強するか
この記事のポイントをまとめておきます。
- 朝勉強は脳が最も効率よく働く「ゴールデンタイム」を活用できる
- 朝は集中力を高めるドーパミンやアドレナリンが多く分泌される
- 早朝は静かで、SNSなどの誘惑が少なく集中しやすい
- 登校時間などの締め切り効果で、限られた時間でも集中できる
- 朝は国語や英語の長文読解、数学・理科の計算問題など思考力が必要な勉強に向いている
- 朝勉強は受験本番に合わせた生活リズムを作るのに役立つ
- 夜勉強はまとまった時間を確保しやすく、自分のペースで学習できる
- 夜は暗記や復習といったインプット系の学習に向いている
- 夜勉強は家族が寝静まった静かな環境で集中できる
- 夜に覚えたことは睡眠中に整理され、記憶として定着しやすい
- 夜型の人は試験の2週間前から朝型に切り替えるのが望ましい
- 無理な夜更かしは睡眠不足を招き、日中のパフォーマンスを低下させる
- 最も重要なのは睡眠時間を削らないこと
- 朝が苦手な人でも、日光を浴びる、目覚ましを工夫するなどして早起きの習慣をつけられる
- 質の高い睡眠のためには、寝る前のスマホを控え、適度な運動を取り入れると良い




コメント