皆さんこんにちは、パンダです。
地方の公立高校から京大を受験し不合格だった後に、一年間宅浪して京大に受かった経験をもとに受験生向けのブログを書いています。
さて、大学受験を控えたあなたにとって、模試は自分の実力を測る重要な機会です。
しかし、「どの模試を受ければいいのか」「模試の難易度順はどうなっているのか」と疑問に感じていませんか。
多くの予備校が様々な模試を実施しており、それぞれの模試によって問題の傾向や難易度が異なります。
この記事では、まず模試を受ける目的を再確認し、あなたの学習にどう活かすべきかを解説します。
そして、主要な模試を模試の難易度順に紹介し、それぞれの特徴や「偏差値・判定の出方」を詳しく比較していきます。
特に、多くの受験生が利用する河合塾、駿台、東進、進研といった予備校の模試に焦点を当て、それぞれの難易度の違いを分かりやすくお伝えします。
また、共通テスト模試と志望校別模試の選び方や活用法についても触れ、模試の結果と「本番との比較」を踏まえた上で、どうすれば模試を最大限に活用できるかをお話しします。
この記事を読んで、自分に最適な模試を選べるようにしましょう!
- 各予備校の模試の難易度順と特徴
- 模試の種類とそれぞれの出題形式
- 模試を受ける目的と効果的な活用方法
- 模試の偏差値や判定と実際の入試結果との関連性
大学受験の模試の難易度を順に解説!

- 模試を受ける目的を再確認しよう
- 模試の種類と出題形式
- 主要模試の難易度と特徴
- 河合塾の模試:標準レベル
- 駿台模試:最難関レベルの模試
- 東進模試:分析重視の模試
- 進研模試:基礎固めに最適な模試
模試を受ける目的を再確認しよう
模試は、単なるテストだと思っていませんか。
大学受験を控える高校生や既卒生にとって、模試は自身の現在地を確認し、志望校合格への道筋を明確にするための重要なツールです。
多くの方が、模試を受ける意味を深く考えずに臨んでしまい、その効果を十分に引き出せていないことがあります。
ここでは、模試を最大限に活用するために、その目的を改めて考えてみましょう。
まず、模試を受ける最大の目的は、自身の立ち位置を知ることにあります。
日々の勉強で参考書を読み込んだり、問題集を解いたりしていても、それが全国のライバルの中でどの程度のレベルにあるのかを正確に把握することは難しいものです。
高校内の定期テストでは学内順位は分かりますが、高校ごとのレベルやテスト内容が異なるため、全国規模での客観的な実力は測れません。
模試は、高校生だけでなく既卒生も受験するため、大学受験に求められる総合的な学力を正確に測定できます。
これによって、同じ大学を目指す競合の中で自分がどの位置にいるのかを把握し、「次の模試までに合格判定をCからBに上げる」といった具体的な目標を設定することで、学習へのモチベーションを向上させることができるでしょう。
次に、苦手分野を把握することも模試の重要な目的の一つです。
模試の結果を詳細に分析すると、普段の勉強では気づきにくい、自分の弱点や苦手な単元が浮き彫りになります。
例えば、数学が苦手だと漠然と感じていても、実際には二次関数の問題は得意なのに、確率の問題で点数を落としている、といった具体的な課題が見えてくるのです。
ここで大切なのは、単に点数だけを見て判断しないことです。
多くの受験生が正解できないような難問や奇問に時間を費やす必要はありません。
むしろ、平均点と自分の点数の差に着目することが肝要です。
平均点を下回っている科目や単元こそが、あなたの克服すべき苦手分野なのです。これらの弱点を一つずつ克服していくことが、受験成功の大きな鍵となります。
模試を受けた後は、その結果を細かく分析し、今後の学習計画に役立てることが不可欠です。
最後に、模試は入試本番に慣れるための実践練習としての意味合いも持ちます。
普段学校や塾で行うテストは、解答を直接記入する形式がほとんどかもしれません。
しかし、大学入学共通テストはマークシートを塗りつぶして解答するマーク式です。
マーク式特有のケアレスミスを防ぐためには、模試で場数を踏んで慣れておく必要があります。
また、本番の独特な雰囲気に慣れておくことも非常に重要です。
試験会場では、話し声や大きな騒音こそありませんが、他の受験生がペンを走らせる音や咳払い、ため息など、意外と気が散る雑音が多いものです。
このような環境に事前に慣れておくことで、本番当日に普段と違う環境に戸惑い、実力を十分に発揮できないといった事態を避けることができます。
つまり、入試という「試合」に勝つためには、模試という「練習試合」が不可欠なのです。

模試が持っている意味は意外と多いよ!ちゃんと確認できたかな?
模試の種類と出題形式
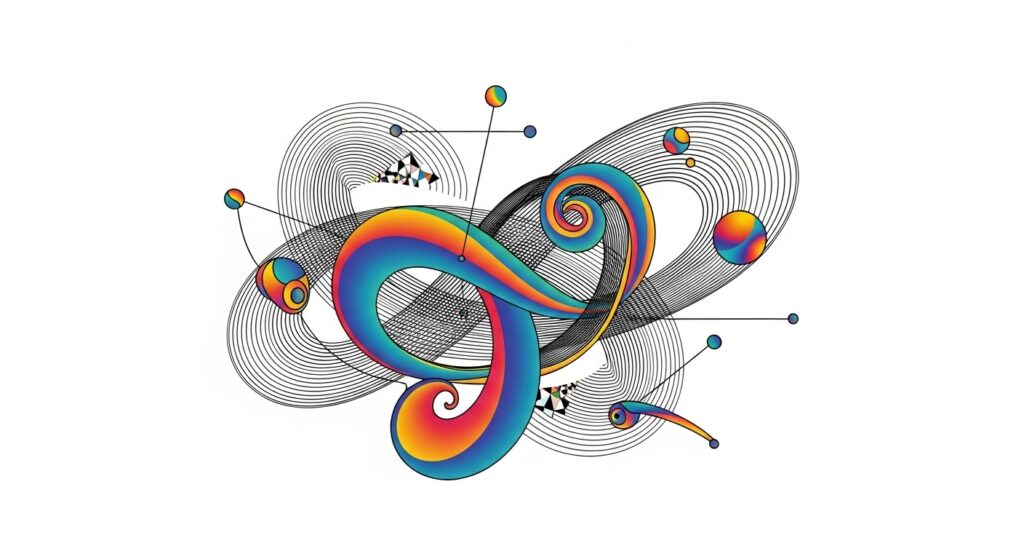
大学受験に向けた模試には、さまざまな種類が存在します。
大きく分けると「マーク式」「記述式」「大学別」の3つの形式があり、それぞれに異なる目的と特徴があります。
これらの違いを理解し、自分の学習状況や志望校の入試形式に合わせて適切な模試を選ぶことが、効率的な学習を進める上で非常に重要です。
まず、マーク式模試は、その名の通りマークシートを塗りつぶして解答する形式の模試です。
大学入学共通テスト対策に最も有効な模試と言えるでしょう。
共通テストと同じマーク形式であり、難易度も共通テストと同程度に設定されているため、受験者数が非常に多いのが特徴です。
受験者数が多いということは、全国順位や偏差値の信頼性が高く、現時点での自分の実力を客観的に知る上で非常に役立ちます。
大学入学共通テストは、高校で学習する範囲の標準レベルを理解していれば解ける問題が中心ですが、問題数が多いため、短時間で問題を読み解く能力や適切な時間配分、問題を解く順番を見極める力が求められます。
これらは模試を通して養うべきスキルです。
ただし、マーク形式の性質上、問題を深く理解していなくても、偶然正解してしまうケースもあるため、結果を分析する際には注意が必要です。
次に、記述式模試は、国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験と同じ形式の模試です。
国公立大学の入試では、共通テストの点数と大学が独自に行う二次試験の点数を合計して合否が判断されます。
私立大学の場合も、大学独自の個別試験のみを行う一般入試と、共通テストの点数を利用する共通テスト入試に分かれます。
共通テストがマーク形式であるのに対し、二次試験や個別試験では記述式の問題が出題されます。
記述式の問題とは、「下線部が指す事象について、具体的に説明しなさい」といったように、文章での解答が求められる問題です。
国語や英語、数学などあらゆる科目で多様な記述問題が出題されます。
問題の傾向を探りにくく、具体的な対策を講じにくいことから、難易度は非常に高いと言えます。
記述問題で高得点を狙うためには、実際に多くの問題を解いて慣れるしかありません。
模試を効果的に活用し、記述問題でも得点力を高めることが目標となります。
最後に、大学別模試は、特定の大学の出題傾向を反映した模試です。
全ての大学に実施されるわけではなく、主に旧帝大や有名難関大学が対象となります。
過去の入試出題傾向を分析し、各大学の特徴に合わせて作成されているため、実際の入試にかなり近い問題が出題されるのが特徴です。
東京大学や京都大学といった全国的に有名な難関大学では、単に難易度が高いだけでなく、他大学とは異なる個性的な問題が出題されることもあります。
そうした独特の問題形式に慣れるためにも、大学別模試は非常に有効です。
したがって、自分の志望校の大学別模試がある場合は、必ず受験することをおすすめします。
同じ大学を目指すライバルたちの中で、自分がどの程度の位置にいるのかを知る良い機会にもなるでしょう。
主要模試の難易度と特徴
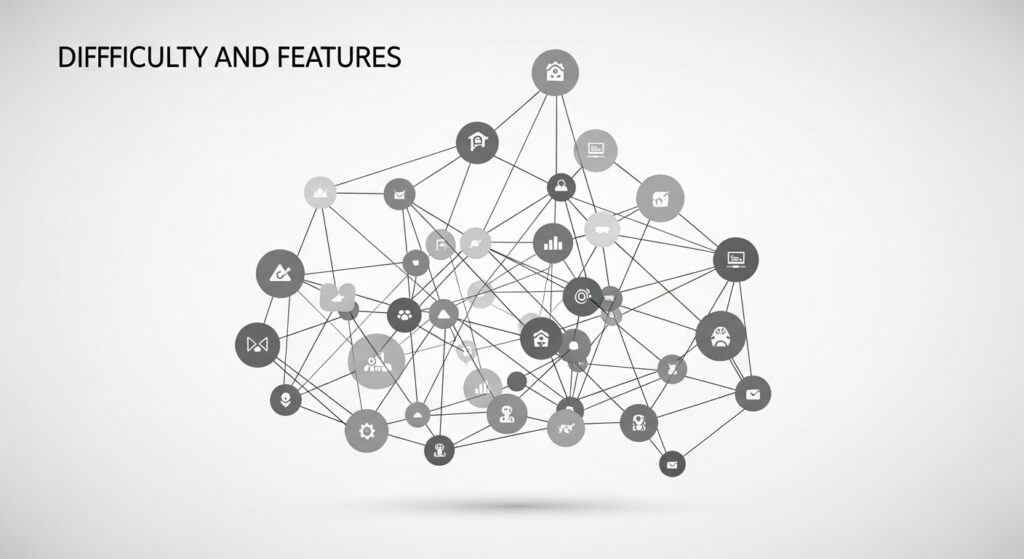
大学受験において、自身の学力や志望校との距離を測る上で、模試の選択は非常に重要です。
しかし、多くの予備校が様々な模試を実施しており、それぞれに難易度や特徴が異なります。
ここでは、とくに受験生に広く利用されている主要な4つの模試、「全国統一模試(河合塾)」「駿台全国模試(駿台予備校)」「東進模試(東進ハイスクール)」「進研模試(ベネッセ)」について、それぞれの難易度と特徴を詳しく解説していきます。
まず、河合塾の「全国統一模試」(全統模試)です。
この模試は、なんと言っても受験者数が最も多く、日本最大規模の模試として知られています。
その難易度は「標準レベル」と言えるでしょう。
受験者数が非常に多いため、算出される順位や偏差値、合格判定の信頼性が高く、現時点での自分の学力を正確に把握するのに非常に有効な模試です。
ほとんどの受験生が一度は受ける模試であり、迷ったらまずはこの全統模試から始めるのがおすすめです。
中堅から難関大学を志望する幅広い層に適しています。
次に、駿台予備校の「駿台全国模試」についてです。
この模試は、主に東京大学や京都大学といった最難関大学を目指す受験生が受験する傾向にあります。
そのため、その難易度は「最高レベル」と評されており、「残酷模試」という異名を持つほど難しいとされています。
難しいからこそ、この模試で高い順位や良い成績を収めることができれば、それは受験勉強に対する大きな自信となるでしょう。
難関大学を目指す方にとって、自身の真の実力を試す絶好の機会となります。
ただし、基礎固めが不十分な受験生にとっては、全く歯が立たないと感じる可能性もあります。
続いて、東進ハイスクールの「東進模試」です。
中でも、入試本番を想定した「共通テスト本番レベル模試」が人気を集めています。
この模試の難易度は「やや高いレベル」と言えるでしょう。
河合塾の全統模試よりは難しいものの、駿台全国模試と比較すると比較的取り組みやすい難易度です。
東進模試の大きな特徴は、WEB上で詳細な解説を確認できる点にあります。
これによって、模試の結果をその後の学習に効率的に活かすことができます。
質の高い問題に触れ、自分の成績を細かく分析して今後の勉強計画を立てたいと考える受験生におすすめです。
最後に、ベネッセの「進研模試」です。
この模試は、個人での申し込みができないため、主に高校で学校のカリキュラムの一環として実施されることが多いです。
難易度は「かなり易しいレベル」に設定されています。
これまでの模試の中で最も易しいため、高得点や高偏差値を狙いやすいという特徴があります。
大学入学共通テストの受験者数とほぼ同じくらいの人数が受験しますが、大学受験をしない生徒も含まれることや、既卒生が受験できないことから、その信頼度は他の模試に比べてやや低めです。
有名・難関大学を目指す受験生は、進研模試の結果をそのまま自分の実力と捉えないよう注意が必要です。
基礎的な力の定着を確認したい場合や、入試の雰囲気に慣れておきたい場合に適しています。
河合塾の模試:標準レベル

河合塾が実施する模試は、多くの受験生にとって非常に馴染み深いものではないでしょうか。
「全統模試」という名称で広く知られており、その受験者数は圧倒的に多く、日本最大規模の模試として君臨しています。
これだけの規模であるため、模試の難易度は「標準レベル」に設定されています。
全統模試の大きなメリットは、その信頼性の高さにあります。
受験者数が多ければ多いほど、全国順位や偏差値、そして合格判定の数値はより正確なものになります。
これにより、現在の自分の学力が全国の受験生の中でどの位置にあるのかを客観的に把握できるため、志望校合格への具体的な距離を知る上で非常に役立ちます。
中堅大学を目指す方から、早慶や難関国公立大学といった上位を目指す方まで、幅広い層の受験生が利用しており、多くの高校で採用されていることからも、その汎用性の高さがうかがえます。
ただ、標準レベルであるがゆえに、最難関大学を目指す受験生にとっては、これだけで十分な対策になるとは限りません。
例えば、東京大学や京都大学といった、より特殊な出題傾向を持つ大学を志望している場合、全統模試で高得点を取れたとしても、それがそのまま志望校の合格に直結するとは言えないケースもあります。
そのため、自身の学力を測るための「定点観測」としては非常に優秀ですが、特定の難関大学対策としては、後述する大学別模試などと併用することが推奨されます。
多くの方が最初に受ける模試として適していますが、自身の目標レベルに合わせて、その活用方法を検討することが大切です。
駿台模試:最難関レベルの模試
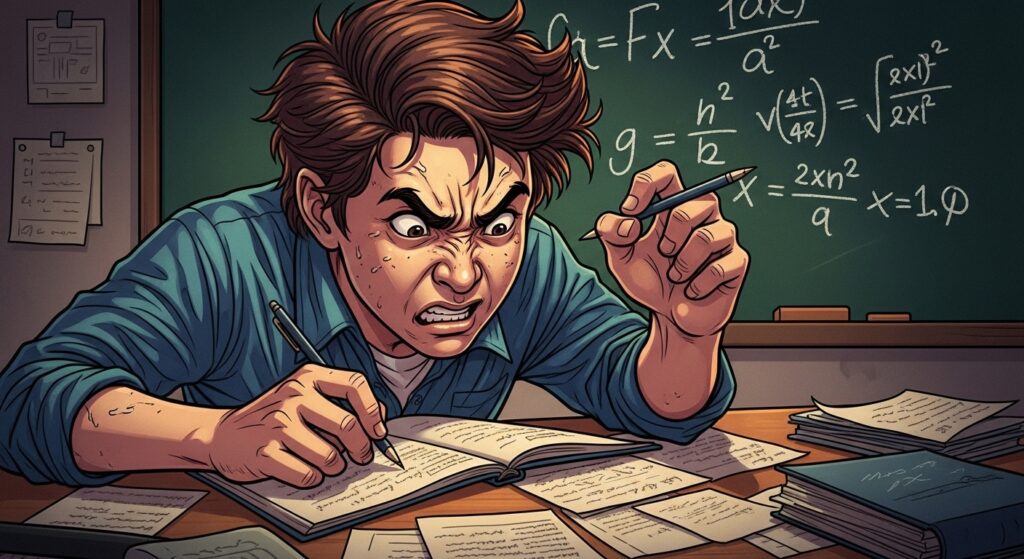
駿台予備校が提供する模試は、その「難しさ」で知られています。
特に「駿台全国模試」は、別名「残酷模試」とも呼ばれるほど、非常に高い難易度を誇ります。
この模試は、東京大学や京都大学、医学部医学科といった最難関大学を目指す受験生がこぞって受験する傾向にあります。
駿台模試が難しい理由の一つに、問題の質とレベルが非常に高いことが挙げられます。
思考力を深く問われる問題や、高度な応用力が求められる問題が多く出題されるため、基礎力が固まっていない段階で受験すると、まったく歯が立たないと感じるかもしれません。
しかし、だからこそ、この模試で良い成績を収められれば、それは自身の学力に対する確かな自信につながります。
難関大学の入試問題を突破するためには、駿台模試のようなハイレベルな問題に慣れておくことが不可欠だと言えるでしょう。
一方で、偏差値が低めに出やすいという注意点もあります。
これは、受験者層が非常にハイレベルなためです。
現役生よりも浪人生が多く受験することもあり、相対的に偏差値が厳しく算出される傾向にあります。
そのため、「E判定だったからもう無理だ」と落ち込む必要はありません。
むしろ、駿台模試でE判定でも、他の標準レベルの模試であればC判定やB判定が出る可能性も十分にあります。
重要なのは、出た結果に一喜一憂するのではなく、難度の高い問題に挑戦し、自分の弱点や課題を明確にすることです。
難関大学を志望する受験生にとっては、自身の限界を知り、さらなるレベルアップを図るための「試金石」となる模試だと言えるでしょう。
東進模試:分析とスピード重視の模試

東進ハイスクールが提供する模試は、他の予備校の模試とは一線を画す特徴を持っています。
特に「共通テスト本番レベル模試」が有名ですが、その難易度は「やや高いレベル」と位置づけられています。
河合塾の全統模試よりは難しく感じるかもしれませんが、駿台全国模試ほどではないため、難関私立大学や国公立大学を目指す層に幅広く対応しています。
東進模試の最大の魅力は、返却速度の速さです。
他の予備校の模試では、模試を受けてから返却されるまでに早くても一か月ほどかかります。
それに比べて東進は、約一週間ほどで返却を行っておりとても復習がしやすいです。
さらに、詳細な成績分析という特徴もあります。
成績表は、受験科目ごとの得点や偏差値だけでなく、単元別の正答率、弱点分野の明確な指摘、さらには今後の学習指針まで具体的に示してくれます。
これは、単に自分の実力を測るだけでなく、「どのように勉強を進めていけばいいのか」という具体的なアクションプランを立てる上で非常に役立つ情報です。
質の良い問題に触れつつ、自分の学習状況を徹底的に分析したいと考える受験生には、まさにうってつけの模試と言えるでしょう。
ただし、東進模試は受験者数が他の大手予備校に比べて少ないという側面も持ち合わせています。
ほとんどの受験者が東進ハイスクールの在籍生であるため、全国的な母集団の偏りが生じやすく、算出される偏差値や合格判定の信頼度は、河合塾の全統模試などと比べるとやや低くなる傾向があります。
そのため、模試の結果を「レベルを測るため」というよりも「成績を向上させるための指針」として活用するのが賢明です。
加えて、学校の進度をあまり考慮せずに出題されるため、高校のカリキュラムによっては未習範囲が出題されることもあります。
しかし、早い段階から入試本番レベルの問題に触れたい高校1年生や2年生にとっては、自身の学力を試す良い機会にもなるでしょう。
進研模試:基礎固めに最適な模試

進研模試は、ベネッセグループが実施している模試で、他の主要模試とは異なる特徴をいくつか持っています。
この模試の大きな特徴は、個人での申し込みができないという点です。
そのため、多くの場合は高校のカリキュラムの一環として、学校単位で受験することになります。
その難易度は、他の大手予備校の模試と比較して「かなり易しいレベル」に設定されています。
この難易度の設定には理由があります。
進研模試は、全国の高校で幅広く実施されており、大学受験を考えていない生徒も多く受験します。
これによって、受験者数が非常に多くなる一方で、受験者層の学力範囲が広いという特徴が生まれるのです。
結果として、平均点が高くなり、相対的に自身の偏差値が高く出やすい傾向にあります。
そのため、「進研模試で偏差値が高かったから大丈夫」と過信してしまうと、実際の大学入試で思わぬ結果に直面する可能性もあります。
難関大学を目指している場合は、進研模試の偏差値をそのまま自分の実力と捉えるのではなく、10〜15程度差し引いて考えるのが現実的と言われることもあります。
しかし、進研模試には明確なメリットもあります。
一つは、基礎力の定着度を確認するのに最適であるという点です。
問題が比較的基礎的な内容に焦点を当てているため、共通テスト対策における基礎固めができているかを確認するのに非常に役立ちます。
また、高校1年生や2年生の段階から定期的に受験することで、自身の学力の変化を長期的に追跡できるという利点もあります。
これは、今後の学習計画を立てる上で貴重なデータとなるでしょう。
したがって、難関大学を目指す受験生であれば、河合塾や駿台の模試と併用し、進研模試はあくまで基礎学力の確認と、共通テスト対策の足がかりとして活用することが望ましいと言えます。
模試の難易度順を知って合格へ活かす

- 共通テスト模試の選び方
- 志望校別模試の活用法
- 模試の偏差値・判定と本番との比較
共通テスト模試の選び方
大学入学共通テストは、多くの受験生にとって最初の大きな関門となります。
その対策として共通テスト模試は不可欠ですが、どの模試を選べば良いのか迷うこともあるかもしれません。
共通テスト模試を選ぶ際には、いくつかのポイントを考慮する必要があります。
まず重要なのは、問題の傾向と難易度が共通テスト本番にどれだけ近いかという点です。
共通テストは、従来のセンター試験から思考力や判断力を問う問題が増え、出題形式も独特です。
そのため、模試がこれらの新しい傾向をしっかりと捉えているかを確認することが大切です。
多くの予備校が共通テスト対策模試を実施していますが、それぞれの予備校で問題作成のアプローチに違いがあります。
例えば、東進の「共通テスト本番レベル模試」は、実際の共通テストに限りなく近い問題形式と難易度を目指しているとされています。
次に、受験者数(母集団)の多さも重要な選択基準です。
共通テストは全国の高校生・既卒生が受験するため、模試の受験者数が多ければ多いほど、自分の実力が全国レベルでどの位置にあるのかをより正確に把握できます。
河合塾の「全統共通テスト模試」は、その受験者数の多さから、偏差値や判定の信頼性が高いとされています。
正確な立ち位置を把握できれば、今後の学習計画を立てる上で、どの科目にどの程度力を入れるべきか、より具体的に考えることができるでしょう。
また、復習のしやすさも考慮すべき点です。
模試は受けっぱなしにしても意味がありません。結果が返却された後、自分の弱点や課題を明確にし、それらを克服するための学習に繋げることが重要です。
詳細な解説や、弱点分析が充実している模試を選ぶと、効率的な復習が可能です。
前述の東進模試のように、成績分析が手厚い模試は、その後の学習計画を立てる上で大きな助けとなるでしょう。
これらの点を総合的に判断し、自分の学習状況や目標に合った共通テスト模試を選ぶことが、効率的な対策に繋がります。
志望校別模試の活用法

志望校別模試、通称「冠模試」は、特定の大学の入試傾向に特化した模試です。
全ての大学に用意されているわけではなく、主に旧帝大や早慶といった難関大学が対象となります。
これらの模試をいかに活用するかが、志望校合格への鍵を握ると言っても過言ではありません。
まず、志望校別模試の最大の利点は、入試本番とほぼ同じ形式とレベルの問題に挑戦できることです。
各大学の過去の出題傾向や問題形式を徹底的に分析して作成されているため、実際の入試に限りなく近い形で実力を試すことができます。
例えば、東京大学であれば独特の記述問題、京都大学であれば論述形式の問題など、大学ごとに異なる「癖」のようなものがあります。
冠模試を通してこれらの癖に慣れておくことで、本番で戸惑うことなく、自身の力を最大限に発揮できるようになります。
次に、同じ大学を目指すライバルたちの中での自分の立ち位置を把握できることも重要な活用法です。
冠模試は、その大学を第一志望とする受験生が多く集まるため、非常に精度の高い合否判定や偏差値が得られます。
全国規模の模試では分からなかった、特定の大学に特化した競争環境における自身の相対的な位置を知ることで、今後の学習において、どの分野を重点的に強化すべきか、あとどれくらいの点数を伸ばせば合格圏内に入れるのかといった具体的な目標を設定しやすくなります。
ただし、志望校別模試は実施回数が限られていることが多いです。
そのため、申し込み時期を逃さないよう、事前に情報収集しておくことが大切です。
志望校模試を受け始めるタイミングですが、高校三年生は必ず受け、高校一、二年生でも範囲学習が終わったら受け始めることをオススメします。
というのも、早めに志望校の傾向をつかんでおくことでより正確な勉強方針を立てることができるからです。
模試の結果が悪くても、それは弱点発見のチャンスと捉え、徹底的に復習し、本番までにその課題を克服していくことが、合格への最短ルートとなるのです。
模試の偏差値・判定と本番との比較

模試の結果が返却されると、多くの受験生がまず目にするのが偏差値や合格判定ではないでしょうか。
A判定が出れば喜びに沸き、E判定であれば深く落ち込む方もいることと思います。
しかし、模試の偏差値や判定は、入試本番の合否と必ずしも一致するわけではありません。
この事実を理解することは、模試の結果に一喜一憂せず、冷静に今後の学習に繋げる上で非常に重要です。
まず、模試の偏差値は「その模試を受けた受験生の中での相対的な位置」を示す数値に過ぎません。
つまり、受験した模試の母集団のレベルによって、同じ偏差値であっても実際の学力レベルは大きく異なる可能性があります。
例えば、前述した駿台模試のように、主に難関大学志望者が集まる模試で偏差値55を取れた場合、これは非常に高い学力を持っていることを示唆します。
一方で、進研模試のように、幅広い学力層の生徒が受験する模試で偏差値70を取れたとしても、それが必ずしも最難関大学に合格できるレベルを意味するとは限りません。
母集団のレベルが低い場合、偏差値は高く出やすい傾向にあるのです。
このような理由から、「模試の偏差値=本番の実力」と単純に捉えるのは危険です。
次に、模試の合格判定もまた、あくまで「現時点での目安」であることを理解しておく必要があります。
模試の判定は、過去の受験生のデータに基づき、その模試を受けた時点での学力と志望校の合格ラインを比較して算出されます。
しかし、大学入試は水物であり、本番の試験問題の傾向や、他の受験生の出来、さらにはその年の倍率など、様々な要因によって結果は変動します。
実際、「模試ではE判定だったが、最終的に志望校に合格した」という逆転合格の事例は枚挙にいとまがありません。
逆に、A判定だったにもかかわらず不合格になってしまうケースも存在します。
これは、模試の判定に過度に安心し、その後の学習を怠ってしまったり、本番のプレッシャーに負けてしまったりすることが原因として考えられます。
では、模試の偏差値や判定をどのように活用すれば良いのでしょうか。
重要なのは、その結果を「過去問の得点率」と照らし合わせて分析することです。
模試の判定に振り回されるよりも、志望校の過去問を実際に解いてみて、その大学の合格最低点に対して自分がどれくらいの得点が取れているかを確認する方が、はるかに現実的な合格可能性を測る指標となります。
例えば、早慶レベルの大学を志望するのであれば、過去問で安定して7割以上取れるか、MARCHレベルであれば6割以上、日東駒専レベルであれば5割以上といった具体的な目標を設定し、それを達成できているかを確認することが大切です。
模試は、あくまで自分の弱点を発見し、学習計画を見直すためのツールです。
結果に一喜一憂するのではなく、常に冷静に、本番で合格点を取るための具体的な課題を見つけ出し、その克服に向けて努力を続けることが、合格を勝ち取るための最も確実な道と言えるでしょう。
模試難易度順:効果的な活用で合格を掴む
この記事のポイントをまとめておきます。
- 模試は自己の立ち位置と苦手分野を把握し、本番に慣れるための重要ツール
- 模試にはマーク式、記述式、大学別があり、それぞれ目的が異なる
- マーク式模試は共通テスト対策に有効で、受験者数が多く信頼性が高い
- 記述式模試は国公立二次や私立個別試験対策で、難易度が高い
- 大学別模試は志望校の出題傾向に特化し、本番に近い実践練習になる
- 河合塾の全統模試は受験者数が最も多く、標準レベルで幅広い層に適している
- 駿台全国模試は最難関レベルで、東大・京大志望者向けであり、偏差値が低く出やすい
- 東進模試は問題がやや難しく、詳細な成績分析が学習計画に役立つ
- 進研模試は学校実施が主で難易度が易しく、基礎力確認に適している
- 模試の偏差値は母集団により異なり、本番の合格を保証するものではない
- 模試の合格判定はあくまで現時点の目安であり、結果に一喜一憂しないことが大切
- 模試の活用は復習が重要で、間違えた問題の分析と克服に繋げるべき
- 模試の結果は過去問の得点率と照らし合わせ、客観的に評価する
- 志望校別模試は実際の入試傾向に慣れ、ライバルとの位置関係を知るのに役立つ
- 自身の学習状況と目標に合わせ、戦略的に模試を選ぶことが重要


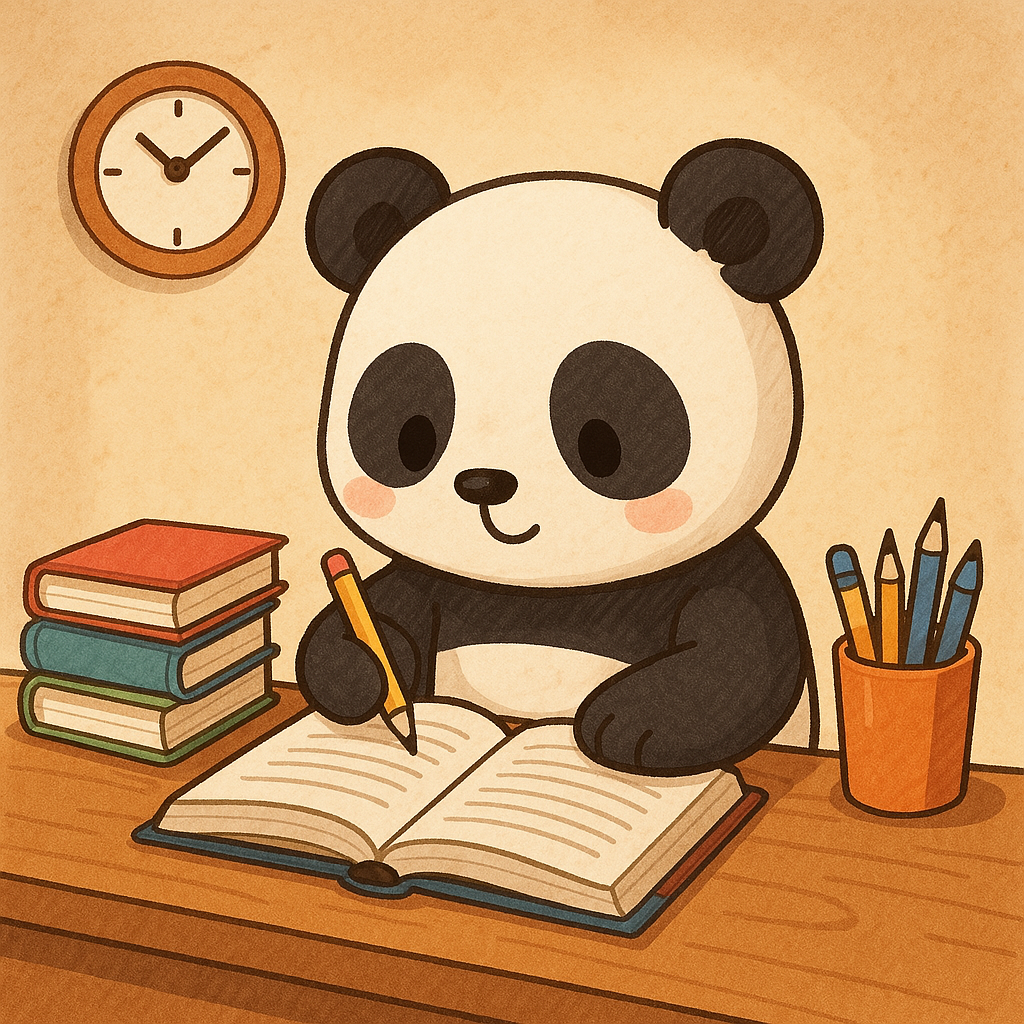





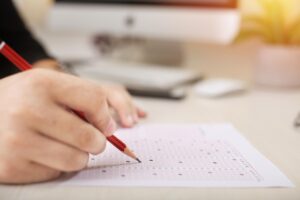

コメント