2026年度の大学入学共通テストは難化が予想され、受験生の皆さんは不安を感じているのではないでしょうか。
新課程が始まり、2025年度がどうだったか、そしてこれから難化するのか、対策は必要かなど疑問は尽きません。
結論から言うと、2026年度の共通テストは昨年度の難易度に比べて、難化することが予想されます。
そこで、この記事では2026年度の共通テストが難化すると予想する理由、難化に対策するための具体的な方法を紹介したいと思います。
この記事を読むことで、共通テスト2026年難化と検索した方が以下の点について理解を深められます。
- 2026年度共通テストが難化する理由
- 科目別の難化予想と2025年度の傾向
- 各科目の具体的な対策方法
- 難化を見据えて今からすべきこと
共通テスト2026年は難化するのか?
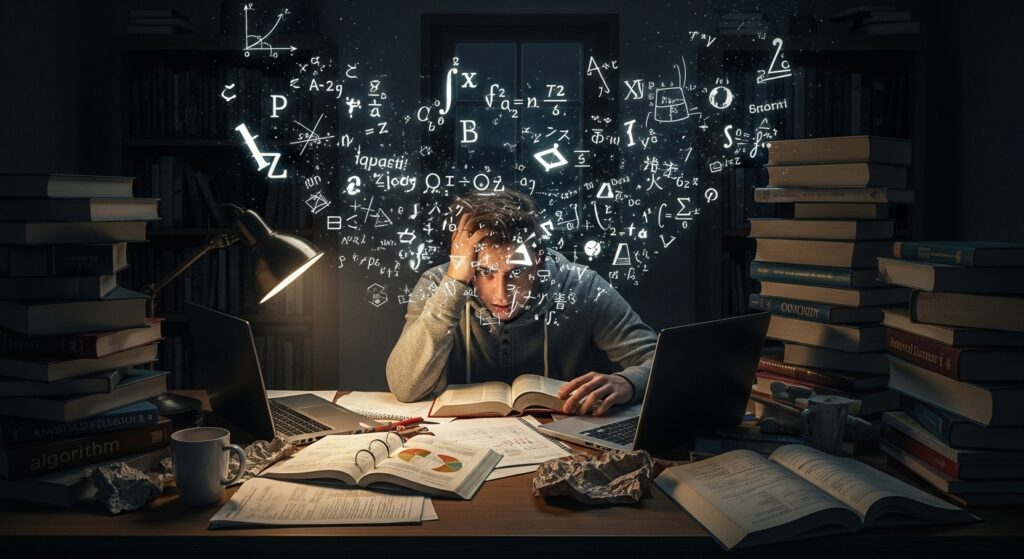
- 2025年度はどうだったか?
- 共通テストが難化する要因とは
- 科目ごとの難化予想
2025年度はどうだったか?
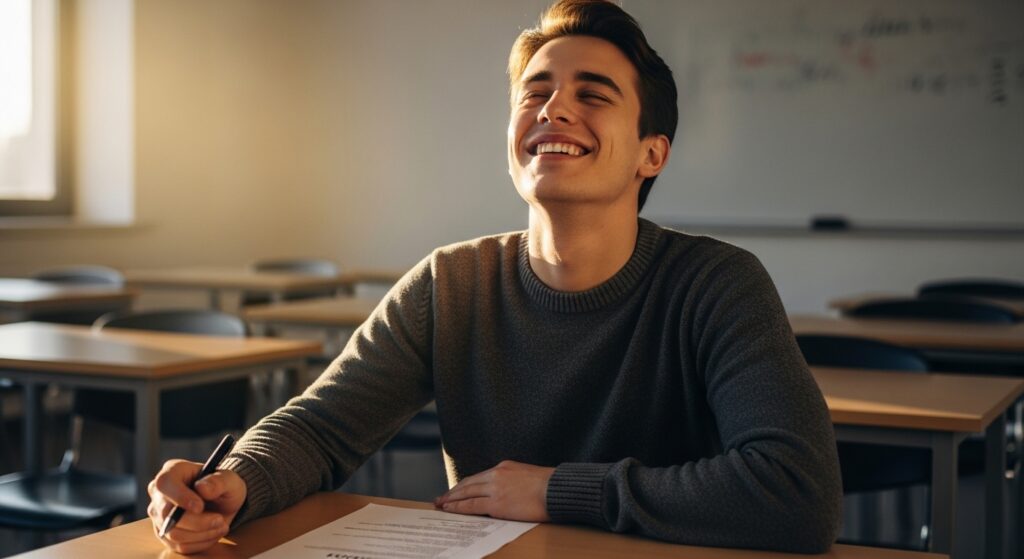
新課程が始まった2025年度の共通テストは、全体的に難易度を抑えた「ソフトランディング」と見られています。
これは、大学入試センターが新課程への移行に伴い、多くの受験生に過度な不安を与えないよう配慮した結果だと考えられます。
特に、情報Ⅰが初出題であったにもかかわらず平均点が高かったことや、国語で選択肢が5つから4つに減り平均点が大きく上昇したことは、多くの受験生にとって追い風となりました。
また、英語のリーディングでは、大問数が8つに増えたものの総語数が減少したため、読解の負担が軽減されたと言えるでしょう。
一方で、すべての科目が易化したわけではありません。
化学や日本史など、平均点が低かった科目もあり、科目によって難易度の差が見られました。
特に化学は、センター試験を含めて過去最低の平均点を記録しており、問題の分量が多く、読解力や応用力を問う問題が増えたことが原因とされています。
科目別の難易度は、主要な予備校の見解をまとめると以下の通りです。
2025年度の共通テストの難易度
| 教科 | 科目 | 2025年度平均点 | 2024年度平均点 | 難易度(前年比) |
| 外国語 | リーディング | 57.7 | 51.5 | やや易化 |
| リスニング | 61.3 | 67.2 | 昨年並 | |
| 数学 | 数学ⅠA | 53.5 | 51.4 | 昨年並 |
| 数学ⅡBC | 51.6 | 57.7 | 昨年並 | |
| 国語 | 国語 | 126.7 | 116.5 | やや易化 |
| 理科 | 物理 | 59.0 | 63.0 | 昨年並 |
| 化学 | 45.3 | 54.8 | 難化 | |
| 生物 | 54.8 | 52.2 | 昨年並 | |
| 地学 | 56.6 | 41.6 | 易化 | |
| 物理基礎 | 28.7 | 24.8 | やや易化 | |
| 化学基礎 | 27.3 | 27.0 | 昨年並 | |
| 生物基礎 | 31.6 | 31.4 | 昨年並 | |
| 地学基礎 | 35.6 | 34.5 | 昨年並 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 69.3 | – | やや易 |
| 地理歴史 | 地理総合、地理探求 | 57.5 | – | 昨年並 |
| 歴史総合、日本史探求 | 57.0 | – | やや難化 | |
| 歴史総合、世界史探求 | 66.1 | – | やや易化 | |
| 公共、倫理 | 59.7 | – | 昨年並 | |
| 公共、政治・経済 | 62.7 | – | 易化 |
河合塾の「2025年度共通テスト概況」より
このように、2025年度は全体として大きな混乱はなかったものの、一部の科目では難易度の調整が図られていたことがわかります。
このデータは、2026年度の傾向を予測する上で非常に重要な参考となります。
共通テストが難化する要因とは
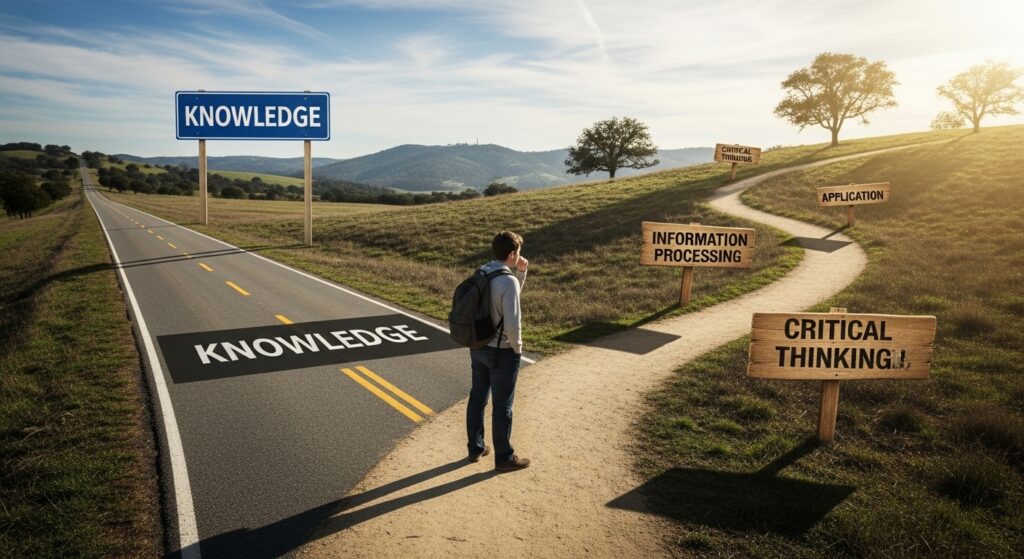
共通テストの難化は、時代が求める学力と密接に関わっています。
単に知識の有無を問うのではなく、膨大な情報から必要なものを取捨選択し、論理的に思考し応用する力が求められるようになりました。
この傾向は、多くのグラフや図表、イラストが用いられる共通テストの問題形式に顕著に表れています。
過去の大学入学共通テストの英語リーディングにおける総語数を見ると、2020年のセンター試験が約4,200語だったのに対し、2024年の共通テストでは約6,300語まで増加しており、情報処理能力の重要性が増していることがわかります。
また、過去のデータから、大きな制度変更があった初年度は易化傾向にありますが、その翌年、つまり2026年度は難化することが予想されます。
これは、出題者側が「本来の難易度」を追求し、より本格的に思考力・判断力を問う問題へとシフトするためだと考えられます。
この変化は、文部科学省が提唱する「生きる力」を育む教育の一環であり、単なる知識の暗記ではない多角的な思考力を測るためのものです。
科目ごとの難化予想
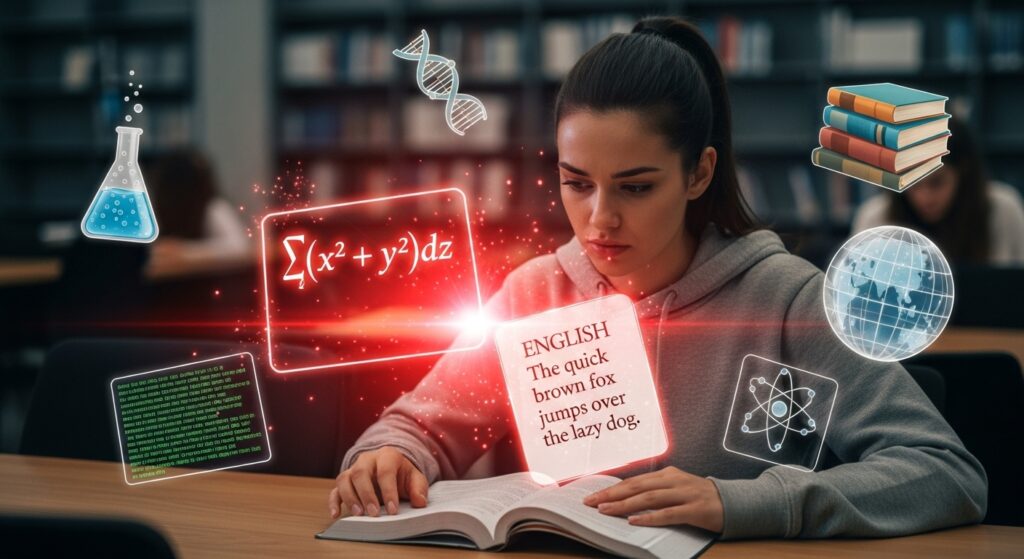
2026年度の共通テストでは、特定の科目が特に難化する可能性があります。
文系なら英語と国語、理系なら英語と数学が難化の中心になると予想されます。
これは、受験生の多い基幹科目で難易度調整を行うことで、科目間の公平性を保つためです。
また、前年度に平均点が高かった科目は、翌年に難化する「反動」が起こることもあります。
特に2025年度に平均点が高かった情報Ⅰや国語、政経などは、難化する可能性が特に高いと考えられます。
| 教科 | 2025年度の平均点概況 | 2026年度の難化予想 |
| 情報Ⅰ | 69.26点(初の必須科目) | 平均点調整のための難化が濃厚。特にプログラミング問題が複雑化する可能性あり。 |
| 国語 | 126.67点(前年比+10.17点) | 選択肢が減り易化傾向だった反動で、新傾向問題の思考負荷が高まる。 |
| 英語 | リーディング易化(前年比+6.15点) | 2025年の総語数減少から一転、本来の分量に戻るか、さらに増加する可能性。速読力が鍵。 |
| 数学 | 数学ⅠA/ⅡBCは昨年並 | 日頃から教科書の発展的な類題を演習しておくことが極めて有利に働く。 |
| 化学 | 45.34点(過去最低平均点) | 2025年に難化したが、再び難易度調整で易化する可能性も。しかし、読解力や処理能力を問う傾向は継続。 |
| 地理歴史・公民 | 倫理・政経で易化傾向 | 2025年に易化した公共・政治・経済は難化する可能性あり。資料読解や応用力が引き続き問われる。 |
このように、科目ごとに難化・易化の傾向は異なります。
自分の得意・不得意や志望校の配点を踏まえ、どの科目で点数を取るか戦略を立てることが重要です。
共通テスト2026年難化を見据えた対策は?

- 今からできる具体的な対策は?
- 難化する共通テスト2026年に備える
今からできる具体的な対策は?
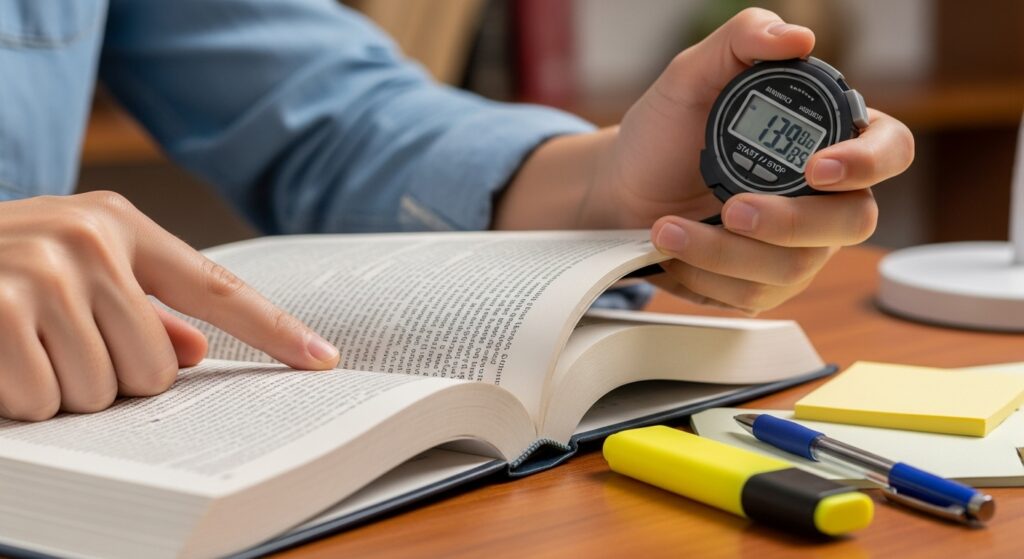
難化が予想される2026年度の共通テストに対応するためには、早期からの対策が不可欠です。
単に過去問を解くだけでなく、出題傾向の変化を意識した学習が求められます。
英語の速読対策が鍵
英語のリーディングでは、2026年度に総語数が元に戻るか、さらに増加する可能性があり、速読力が大きな差を生む要因となります。
高校生の平均的な読解速度は1分間に75語と言われますが、共通テストに対応するには毎分140~150語のスピードが必要です。
日頃から時間を測って長文を読み、英文を速く正確に処理する力を養いましょう。
国語は新傾向問題への対応を
2025年度の国語現代文で出題された新傾向の問3は、2026年度に難化する可能性が高いと見られています。
これまでの知識だけでなく、情報リテラシーを問う問題形式に慣れることが重要です。
予想問題や模試を活用し、様々な形式の問題に触れておくことが効果的な対策となります。
数学は応用的な演習を
数学の難化に備えるためには、日頃から教科書の発展的な類題に取り組むことが非常に有効です。
基礎知識を固めた上で、それを応用する力を養うことが求められます。
過去問や模試の演習を通じて、問題の背景にある構造を読み解く練習を重ねることが重要です。
情報はプログラミングを強化
2025年度に平均点が高かった情報Ⅰは、来年度に大幅な難化が予想されます。
特にプログラミング分野は、実際に手を動かしアルゴリズムの動きを追うなど、実践的な演習をしっかりと行うことが不可欠です。
共通テストの詳しい対策について知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

難化する共通テスト2026年に備える

共通テストは、知識を前提として思考力・理解力・応用力を問う試験へと変化しました。
難化が予想される2026年度に向けて、単に暗記に頼るのではなく、情報を正確に処理する能力を養うことが合格への鍵となります。
| 教科 | 2025年度の概況 | 2026年度の予想と対策 |
| 英語 | リーディングは語数減で易化。リスニングは昨年並 | リーディングは語数増加で難化。速読練習を強化する |
| 数学 | 数学ⅡBは難化傾向が継続 | 発展的な類題演習や応用問題への対応力を高める |
| 国語 | 選択肢減で平均点上昇。新傾向問題は比較的容易 | 新傾向問題の難化が予想される。予想問題で形式に慣れる |
| 情報 | 平均点が高く、必須科目としての初出題 | 大幅な難化が予想される。プログラミング演習を強化する |
難化はネガティブな要素ではなく、日々の努力が点数に表れやすくなるチャンスでもあります。
早期から戦略的に対策を進めることで、他の受験生より圧倒的に有利な立場に立つことができます。
以下に共通テスト対策に特化したオススメ教材を挙げておきます。
 パンダ
パンダ特におすすめは英語のリーディングの本で、私はこの本を使ってリーディング満点を取ることができたよ!
また、受験勉強には個人ごとの戦略もとても大切です。
とは言え、予備校に通うとなるとかなりのお金もかかるし、個人ごとに丁寧に見てくれるかといわれるとそうでもありません。
そこで、私はトウコベというオンライン塾をオススメしています。
この塾の最大の利点は、現役東大生のマンツーマン指導が受けられることです。
東大生に勉強を教えてもらえるだけでなく、受験戦略まで一緒に考えてもらえます。
- 無料で体験授業や相談ができる
- 予備校よりも経済的
- 個人に合った指導が受けられる
- 勉強の内容だけでなく勉強方法についてもサポートが受けられる
- 分からない問題は24時間LINEで質問し放題(他のサービスでは問題数に制限があったりするところが多いのでとても魅力的)
- 講師が東大生か京大生であり、講師の質もいい
勉強について困っていることがある人は、とりあえず以下のリンクから無料相談だけでも受けてみてはいかがでしょうか。
東大生のオンライン個別指導『トウコベ』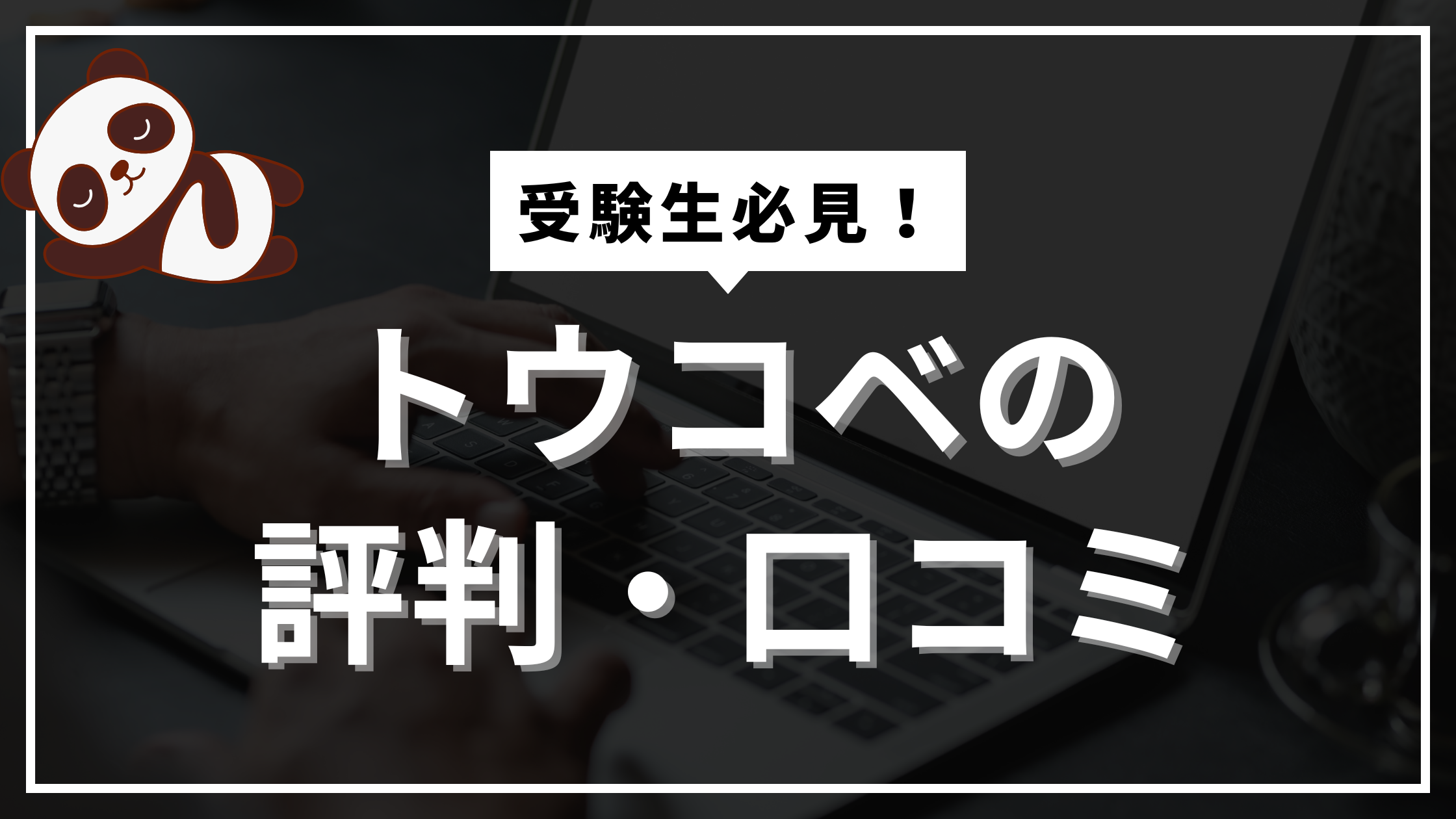
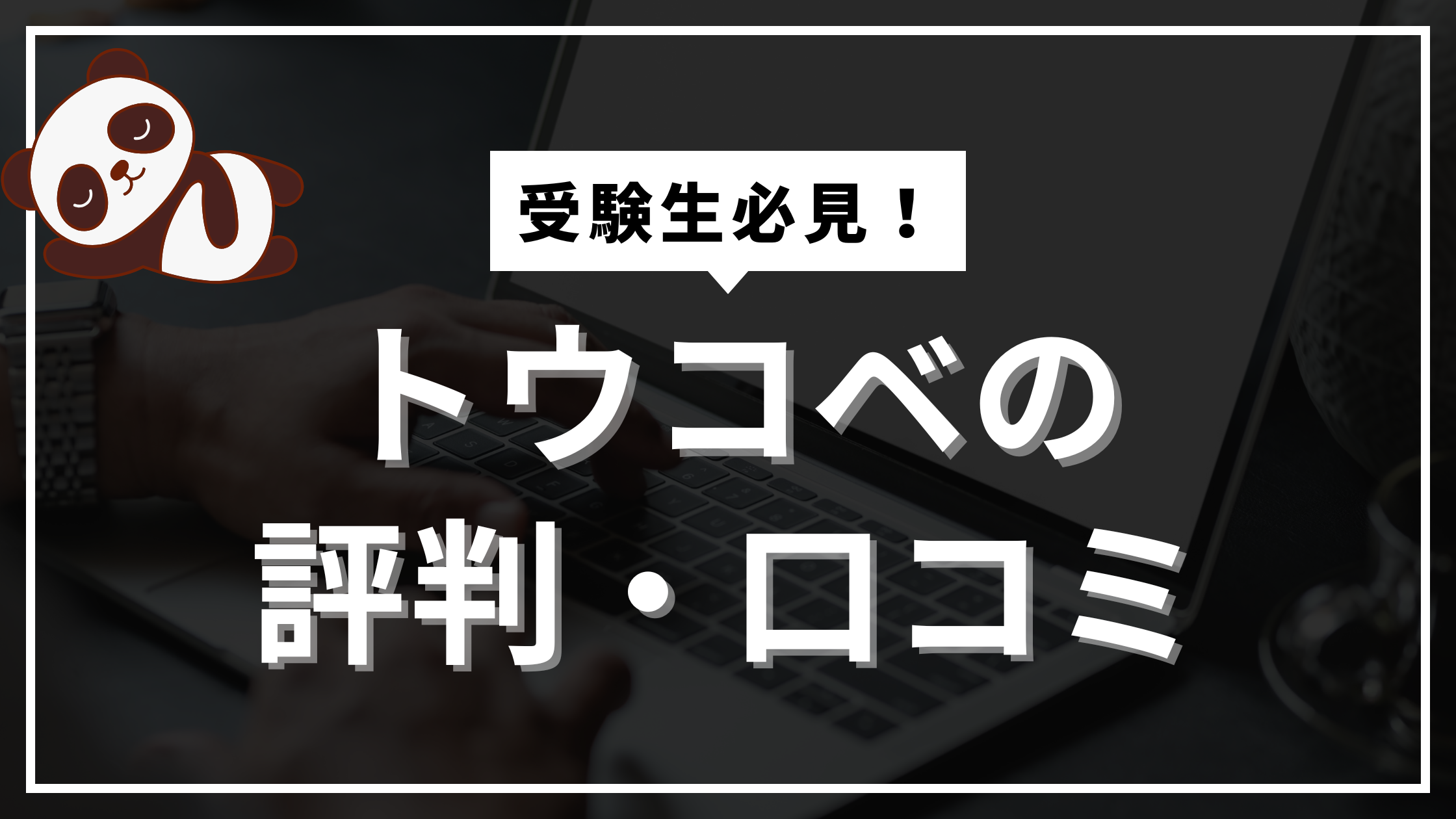
この記事のまとめ
この記事のポイントについてまとめておきます。
- 共通テストは情報処理能力を問う試験へ変容
- センター試験時代の勉強法だけでは対応が困難
- 難化傾向は今後も続くと考え早期対策が必要
- 文系は英語と国語、理系は英語と数学が特に難化
- 2025年に易化した科目は反動で難化する可能性
- 英語リーディングは総語数増加に備え速読力を養成
- 国語は新傾向問題の難化を想定した対策が重要
- 情報は必須科目の二年目で大幅な難化が予想される
- 難化した化学のように分量が増える可能性も考慮
- 膨大な情報から必要なものを素早く見つける力が不可欠
- 基礎知識の定着は前提として応用力を養う
- 予想問題や模試で実践的な演習を数多くこなす
- 志望大学の傾斜配点を考慮した戦略も大切
- 難化は努力が報われるチャンスだと捉える
- 難化する共通テスト2026年に向けた準備は今すぐ始めるべき
難化傾向の予想を見て、不安が大きくなってしまったかもしれません。
ですが、「難しい問題が出た時の捨て方」や「パニックになった時のメンタル復旧法」を知っているだけで、+20点は変わります。
参考書1冊より安い値段で、本番の「お守り」を手に入れませんか?
\今だけ980円/ 👉 【京大生直伝】共通テスト直前対策マニュアルを読む


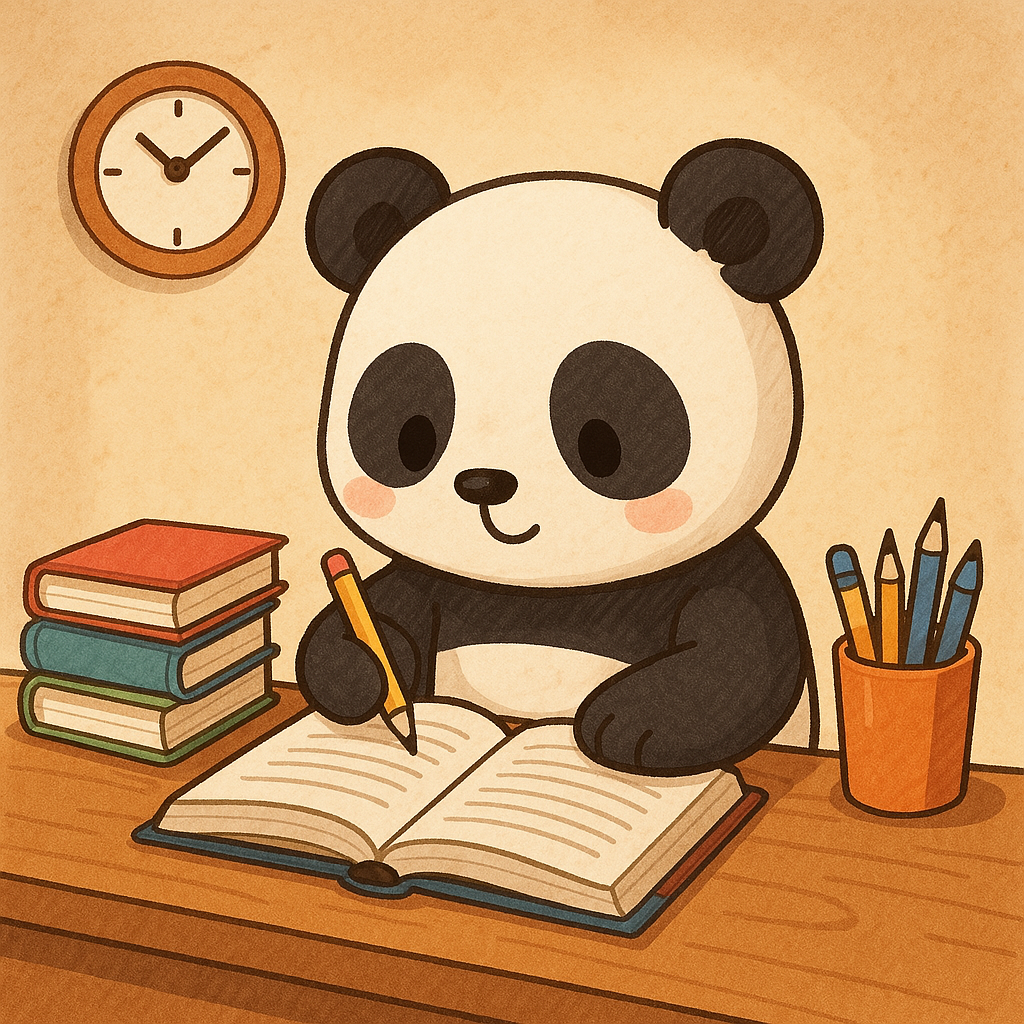








コメント