皆さんこんにちはパンダです。
私は今京大工学部に通っていますが、現役の時は不合格で一年宅浪したのちに合格をつかみ取ることができました。
この記事では、その現役時代の過ごし方や当時の思い、そして今になって思うことを赤裸々に話していこうと思います。
この記事を読むことで、今受験を頑張っている皆さんのヒントやモチベーションになれると、とてもうれしいです。
目標は東大?高2の初め受験勉強というものを知る
私は高校に入学して一年生のころはテスト前以外勉強はせず部活に精を出していました。学校での成績も悪くはないものの地方の公立高校の中で半分より少し上ぐらいととても京大に行けるような成績ではありませんでしたし、京大に行こうとも考えていませんでした。
しかし私にも転機が訪れます。
きっかけは仲良くしていた部活の先輩が京都大学を目指すという話を聞いたことです。
そのころの私は地方の国公立大学に行こうかなとぼんやり考えていたので、京都大学に進学するという発想すらありませんでした。
身近にそういう人がいたことにとても衝撃を受け、そこで初めて大学受験について調べました。
それまで私は京大や東大には小さいときから頑張って勉強してきて、私立の名門中高一貫校に進学してきたような人ばかり行くものと思っていました。
テレビで紹介されていた東大生や京大生はそのような人ばかりだったからです。
小学校・中学校時代遊んでばかりだった私には無理だと、そしてそれは当たり前のことだと思っていたのです。
しかし調べてみて地方出身で高校二年生から勉強を始めた人でも東大・京大に進学している人もいるのだと知り自分にもできるのではないかと思いました。
そこで私は東大を目指してみようと決めたのです。というのも大学についてよくわからなかったので東大にいける学力があれば三年生になったときに大学は選び放題だと思ったからです。
ここから私の長い受験勉強が始まったのです。
いざ東大へ。周囲への宣言から始まった受験生活
高校2年生の春、私は「東京大学に進学する」と目標を掲げ、自身が継続的に勉強に取り組むために思い切ってその決意を周囲に宣言しました。友達からは「頑張ってね!」と応援の言葉をもらいましたが、最も驚いたのは母でした。
というのも、私は昔からとても影響を受けやすく、ゲームなども新しいものに手を出してはすぐに飽き、また次へ――そんな飽き性な性格だったため、まさか本気ではないだろうと思われていたそうです。
しかし、私が日々真剣に机に向かう姿を見て、母もようやく「本気なんだ」と感じてくれるようになりました。
スタート地点はE判定。圧倒的に足りなかった実力
高校1年生の間、私はほとんど勉強をしておらず、当然のように成績は振るいませんでした。高校2年の最初に受けた模試の結果は、東京大学E判定。合格の可能性が最も低い判定でした。
そんな中でも私が継続して勉強を続けられたのは二年生になってクラスが同じになり仲良くなった友人の影響が大きかったように思います。
その友人は、すでに東大模試でA判定を取るほどの実力者で、学校でも常にトップをキープしている人でした。
彼と話をする中で刺激を受け、私はモチベーションを落とさずに勉強できました。良い仲間に恵まれたことは、私の受験生活において本当に大きな意味を持っていたと思います。
部活との両立と焦りとの戦い
勉強の意欲が高まる中、部活の活動も本格的になってきました。2年生の夏が始まると、いよいよ私たちの世代が主力となり、忙しさは一気に増します。
「部活を辞めようか」と真剣に悩んだこともありました。しかし、支え合える仲間たちとのつながりを手放すのは惜しいと感じ、私は部活も勉強も両立する道を選びました。
学校、部活、帰宅後に夜7時や8時から勉強という日々。それでも、東大や京大を目指すライバルたちと比べると明らかに勉強時間は不足しており、成績もまだまだ追いついていませんでした。私は常に「このままでは間に合わない」と焦りを感じながら過ごしていました。
模試の判定が少しずつ上昇。手応えと限界
努力を重ねる中で、模試の結果には少しずつ変化が現れてきました。E判定だった模試がD判定、そして調子の良い時にはC判定を取れるようになってきたのです。
「もしかしたら、届くかもしれない」――そんな希望が芽生え始めたのもこの頃です。
しかし、2年生の夏に受けた「東大本番レベル模試」では、衝撃を受けました。ほとんどの問題に手がつかず、自分の実力の足りなさを痛感しました。
正直、心が折れかけました。それでも、すぐに諦めることはせず、「もう少しだけ頑張ってみよう」と踏みとどまりました。
京大への方向転換。そして、新たな目標へ
2年生の終わりには、再び東大模試を受け、加えて京大模試にも挑戦しました。この頃から、私の中に「京都大学」という選択肢が浮かび上がってきました。
方向転換の理由は2つあります。
1つは、東京大学の進振りという制度により、自分の学びたい分野に進めない可能性があったこと。
もう1つは、東大の試験問題は対策しなければならないことがかなり多く、合格可能性が低いと判断したことです。
自身が一年間勉強してきた感覚をもとに自分の伸びしろや残された時間を総合的に考え、最終的に京都大学を目指すことを決めました。
京大模試でB判定でスタート。確かな手応えと新たなスタート
高校3年生になって初の京都大学本番レベル模試を受けました。結果はB判定。今までの努力が少しずつ形になってきたと感じた瞬間でした。
そして、春が終わり、部活動の引退試合を迎えました。いよいよ勉強一本に集中できる環境が整い、「ここからが本当の勝負だ」と覚悟を新たにしました。
受験か行事か。運動会準備に参加した理由
とはいえ、私の高校では「3年生が学校行事をリードする」という伝統があり、私たちもその例外ではありませんでした。
中でも最も大きな行事が「運動会」でした。運動会の準備は、参加しないという選択肢もありました。しかし私は悩んだ末、あえて積極的に参加することを選びました。
「本当はやりたかったのに、やらずに受験も失敗したら、それが一番後悔する。」
「準備に参加したところで、大きく勉強時間が減るわけではない。」
そう考え、夏休み中も週に何度か学校に行き、仲間たちと一緒に準備をしました。
この選択には今でも後悔はなく、かけがえのない思い出となっています。
停滞する成績。伸び悩んだ夏と秋
勉強面では、春に取ったB判定からさらに上を目指し、A判定を目標に努力を続けていました。
しかし、思うように成績は伸びず、結局1年間を通して模試ではずっとB判定止まりでした。どんなにやっても「あと一歩」が届かないもどかしさ。焦りと不安がじわじわと募っていきました。
そして季節は秋へと移り変わり、共通テスト対策が本格化。
「受験」がいよいよ現実味を帯びてきて、毎日の勉強にも一層緊張感が走るようになりました。
共通テスト本番、満足のいく結果で出願へ
迎えた共通テスト本番。私は体調もメンタルも万全に整えて臨みました。
その結果、これまでの模試の中で最も良い点数を取ることができ、無事に京都大学への出願基準を満たすことができました。
ようやく「土俵に立てた」という安心感とともに、最後の山場、二次試験対策へとシフトしていきます。
試験までの40日間、重圧と向き合った日々
共通テストから京都大学の二次試験までは約40日。この期間は、いつもの40日以上に長く感じました。
毎日が「試験まであと◯日」というカウントダウン。プレッシャーを強く感じながら、自分のできる対策を続けました。
中でも私は数学が苦手で、これをどう攻略するかが鍵だと考えていました。
京大試験本番。そして、不合格
そして、いよいよ京都大学の入試本番。緊張の中で迎えたその日、私が苦手だった数学が難化し、手応えを得ることができませんでした。
「まずいかもしれない」――そんな不安を抱えたまま、試験を終えました。
そして、運命の合格発表の日。結果は「不合格」。
点数開示を見ると、合格まであと「4点」でした。
他大学の受験はしておらず、私の進路は「浪人」へと決まりました。
人生における初めての大きな挫折

私は、それまでの人生で「試験」や「挑戦」において、明確な“失敗”を経験したことがありませんでした。
もちろん小さなつまずきや悔しさはあったものの、「ここ一番」という場面では、いつも何とかなってきた。
だからこそ、京都大学の合格発表を見たときも、どこか現実味がなく、すぐには結果を受け入れられませんでした。
正直なところ、どこかで「今回もなんとかなるだろう」という甘さが心の奥にあったのです。
これまでうまく乗り越えてきた自分が、今回もギリギリで合格しているのではないか――そんな根拠のない期待が、最後の最後まで頭を離れませんでした。
しかし、それは淡い幻想でした。
試験の現実は非情で、そして残酷で、努力と実力以外には通用するものがない。
「甘さ」が通用しない世界を、私はこの時、初めて真正面から突きつけられたのです。
そうしてはっきりとした実感がないまま浪人生活がスタートしていくこととなります。
次回は、浪人期の生活について書いていく予定です。
興味があれば、ぜひ読んでみてください。

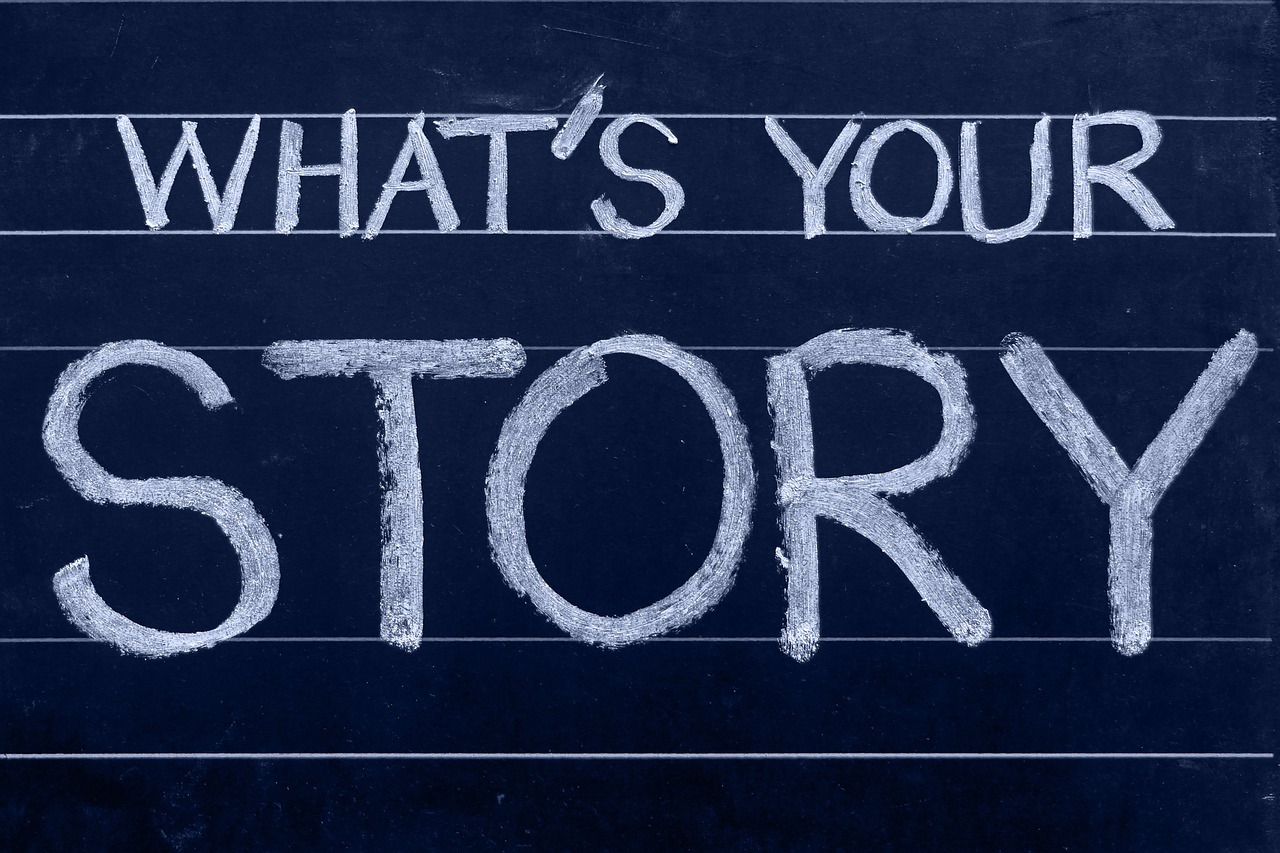


コメント