大学受験を控えた高校生にとって、「定期テストの勉強は時間を無駄にするのではないか」「いっそ定期テストを捨てるべきではないか」という悩みは尽きません。
限られた時間をすべて志望校対策に注ぎ込みたいと考えるのは自然なことです。
しかし、定期テストを安易に捨ててしまうと、後で受験の選択肢を狭めたり、進級に影響が出たりするリスクがあるのも事実です。
本記事は、そうした受験生の皆さんの悩みに寄り添い、一般選抜、推薦入試、総合型選抜など、受験タイプ別に定期テストへの最適な向き合い方を徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたが取るべき行動と勉強計画が明確になり、迷いなく目の前の勉強に集中できるようになります。
現役京大生が自身の経験も踏まえ、それぞれのタイプに合わせた戦略を示すことで、時間を効率的に使い、志望校合格というゴールに一歩近づくための道筋を提供します。
- 定期テストを「捨てる」ことの具体的な意味と危険性
- 一般選抜受験者が定期テストを活かすべき科目と捨てるべき科目
- 推薦入試・総合型選抜受験者が高得点を取るべき時期
- 定期テストを大学受験の演習として活用する具体的な方法
大学受験で定期テストを「捨てる」ことの真の意味とリスク
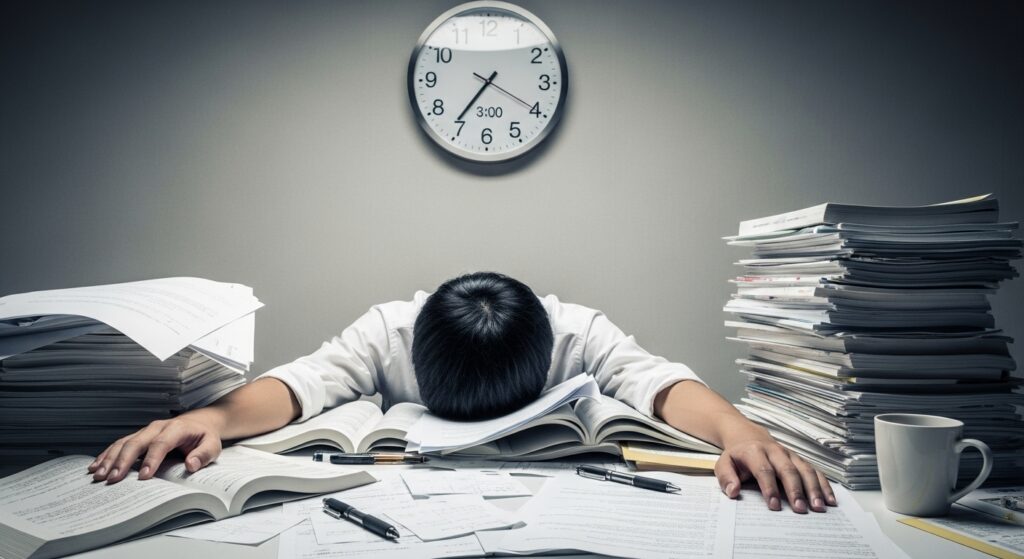
「定期テストを捨てる」とはどういうことか?
多くの受験生が口にする「定期テストを捨てる」という言葉は、極端な意味で捉えられることがあります。
しかし、実際には定期テストを完全に欠席したり、意図的に0点を取ったりすることを意味しているわけではありません。
高校に在籍している以上、進級や卒業のための単位取得は必須であり、極端に悪い点数を取ると欠点(赤点)となり、補習や追試の対象になってしまいます。
この補習や追試こそが、受験生にとって最も避けたい時間のロスに繋がります。
したがって、「定期テストを捨てる」ことの現実的な解釈は、「時間をかけずに最低限の勉強しかしない」こと、具体的には「欠点を取らない程度の対策に留める」ことを意味します。
この解釈に基づき、受験に直結しない科目や、丸暗記で点数が取れてしまう受験科目の一部の問題に対して、費やす時間を大幅に短縮し、その時間を大学受験の勉強時間として確保することが真の目的となります。
大切なのは、進級・卒業という足元の条件を満たしつつ、効率的に受験勉強の時間を最大化することです。
定期テストを捨てることで生じる深刻なデメリット
定期テスト対策を最低限に留める、あるいは捨てると判断した場合、その行動がもたらすデメリットを正しく認識しておく必要があります。
最も分かりやすいデメリットは、高校での成績、すなわち評定平均値が下がってしまうことです。
評定平均値の低下は、特に大学受験の選択肢を狭める大きなリスクとなります。
まず、近年受験者数が増加している学校推薦型選抜(指定校推薦・公募制推薦)や総合型選抜といった、一般入試以外の受験方法が利用できなくなる可能性があります。
これらの入試形態は、高校1年生から3年生の1学期までの評定平均値が調査書に記載され、出願基準や選考基準に大きく影響します。
高1・高2の早い段階から定期テストを捨ててしまうと、後から推薦を視野に入れたくなっても、基準を満たせなくなる事態が起こり得ます。
次に、成績が極端に悪くなると、進級や卒業ができなくなるリスクが生じます。
高校3年生の1月に追試を受けることになれば、入試直前の貴重な時間を失うことになりますし、高1・高2で単位を落とせば留年の可能性も否定できません。
さらに、奨学金を借りる予定がある場合、日本学生支援機構(JASSO)の第一種貸与奨学金など、奨学金の種類によっては学力基準(例:評定平均値3.5以上)が設けられているため、定期テストを捨てて成績が下がると、奨学金が借りにくくなる可能性も考えられます。
| デメリット | 具体的な影響 | 対策の必要性 |
| 高校の成績(評定)が下がる | 推薦入試、総合型選抜の出願資格を失う | 高3の1学期までは要注意 |
| 進級・卒業が危うくなる | 欠点(赤点)で補習・追試となり時間が取られる、最悪留年 | 全学年で欠点回避は必須 |
| 奨学金が借りにくくなる | 奨学金の種類によっては学力基準(評定)がある | 奨学金利用予定者は特に注意 |

定期テスト=悪のような風潮があるけど、捨てるということのデメリットを理解しておかないといけないよ!
【タイプ別】定期テストの最適な向き合い方

大学受験で定期テストを捨てるべきかどうかは当然入試の形態ごとに変わっていきます。
そこで、ここからは受験タイプごとに適切な定期テストへの向き合い方を解説します。
一般選抜(テスト入試)を目指す受験生の戦略
一般選抜を目指す受験生にとって、定期テストの目的は「高得点を取ること」ではなく「受験科目の基礎固めと演習」に切り替えるのが基本戦略となります。
特に公立高校の生徒で、高校3年生になっても受験科目の教科書内容が終わっていない場合は、定期テスト対策がそのまま受験範囲の学習に直結するため、定期テストを捨てるべきではありません。
一方、中高一貫校など先取りカリキュラムの学校で、高2までに教科書範囲が終わり、高3で入試演習が始まっている場合は、定期テストを実力試しと演習の機会として活用できます。
受験科目以外の科目は、欠点回避を最優先とし、必要以上に時間をかけない割り切りが重要です。
ゴールは一般受験の合格であり、受験に使わない科目の勉強時間は、合格というゴールに近づいていないと認識すべきです。
ただし、最低限の対策は行い、補習や追加課題といった受験勉強の足を引っ張る事態は避けなければなりません。
また、志望校への合格スケジュールに余裕がなく、本来のルートからショートカットが必要な場合は、背に腹は代えられないため、欠点回避のみに絞って定期テストを「捨てる」判断も必要となります。
その際も、学校の先生に必死に努力している姿勢を示すことで、追加課題などを受験後にずらしてもらえる可能性もあるでしょう。
学校推薦型選抜・総合型選抜を目指す受験生の戦略
学校推薦型選抜(指定校推薦・公募制推薦)や総合型選抜を目指す受験生は、定期テストを捨てるという選択肢は基本的にありません。
これらの選抜方式では、高校1年生から3年生の1学期までの評定平均値が非常に重要であり、出願基準や選考に大きく影響するからです。
- 高校3年生の1学期まで
この期間は、全科目において高得点を取ることを目指し、しっかりとした対策を行う必要があります。
1・2年生の評定で基準を満たしていても、より高い評定平均値を持つ方がライバルに差をつけられ、有利に選考を進められるため、決して手を抜いてはいけません。
評定は、これらの入試における最重要要素の一つと認識しましょう。 - 高校3年生の2学期以降
推薦入試の出願は通常10月頃に行われるため、2学期以降の定期テストの評定は受験には直接関係しないケースが多いです。
そのため、2学期中間テスト以降は、一般選抜の受験生と同様に、定期テスト対策の時間をセーブし、面接対策や小論文対策といった推薦入試の準備、あるいはもしものための一般入試の勉強に時間を割く判断をしても問題ないと考えられます。
ただし、卒業に関わる単位の取得は引き続き最重要です。
内部進学を目指す受験生の戦略
大学附属高校からの内部進学を目指す受験生は、所属する学校独自の進学基準に厳密に従って、定期テストに取り組む必要があります。
内部進学の基準は、大学や学部によって異なり、定期テストの点数、全科目の評定平均値、あるいは特定の科目の成績などが複合的に評価されるのが一般的です。
進学基準が不明確な場合は、まずは全科目の定期テストで高い点数を目指すのが安全策です。
内部進学も、学内での競争となるため、高い評定を維持することは、希望する学部・学科への進学を確実にするための鍵となります。
附属高校向けの個別指導塾などの情報によると、内部進学対策においては、学校のカリキュラムと定期テスト対策をペースメーカーとして活用し、日々の学習を積み重ねることが成功の秘訣とされています。
学校の先生や進路指導の情報を活用し、自分の目標とする学部への進学に必要な条件を正確に把握し、それに合わせた戦略的な勉強を進めることが大切です。

まだ受験形式が決まっていない人は、可能性をつぶさないために定期テストの勉強をすることをオススメするよ!
大学受験に活かせる科目・捨ててもいい勉強
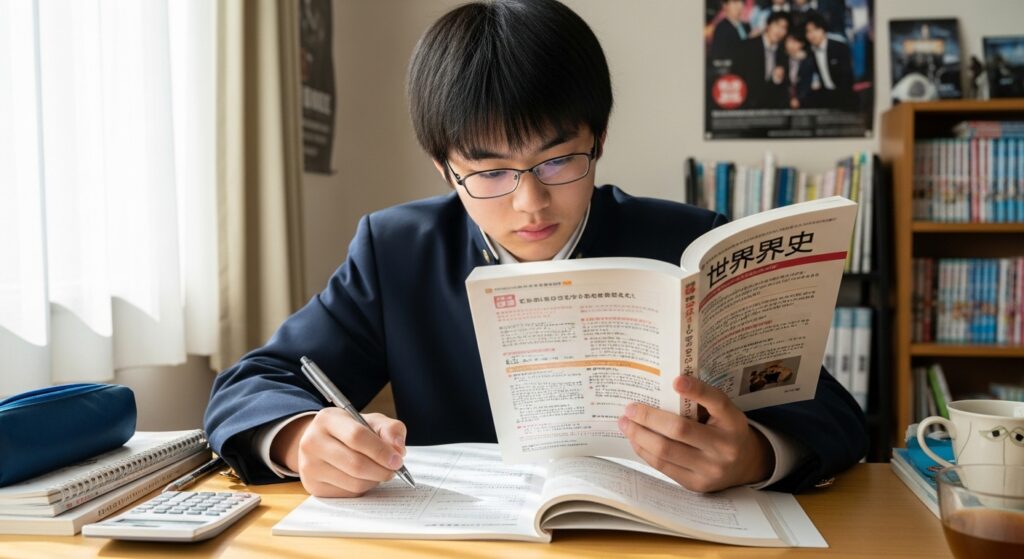
ここからの話は大学受験のために定期テストを捨てると判断した人のための話です。
定期テストを取らなければいけない人はすべての科目を全力で勉強してください!
受験科目の定期テストを「復習・演習」として活用する
一般選抜を目指す受験生の場合、英語、数学、社会、理科といった受験科目の定期テストは、大学受験の基礎固めや復習、演習の機会として最大限に活用できます。
これらの科目は、定期テストの範囲が大学入試の基礎知識と重なる部分が多く、学校で習った範囲の理解度を確認する絶好の機会となります。
活かせる科目の具体的な活用法
| 科目 | 受験に活かせる要素 | 定期テストでの目標と向き合い方 |
| 英語(文法) | 英文法の独立問題、長文読解の基礎 | 満点を取る勢いで対策。参考書の復習として位置づける。 |
| 数学・理科・社会 | 基礎公式・概念の定着、演習の機会 | 参考書で習った範囲は満点近くを狙う。未習範囲は欠点回避。 |
| 国語 | 古文単語・文法、漢文の句形、漢字 | 体系化された参考書での学習を優先し、定期テストは補助的に。 |
特に、数学や理科は、授業内容を理解しただけで終わらず、演習を通じて手を動かすことで初めて実力が定着します。
定期テストを、参考書での学習後のアウトプットの場と捉え、満点近くを狙う意識で取り組めば、それはそのまま質の高い受験対策となります。
ただし、注意すべきは、考査時点ではまだ参考書で学習していない範囲や、前提知識が必要な理系科目について、順番を飛ばしてまで定期テスト対策に集中するのは避けるべきという点です。
勉強の順番を間違えないよう、あくまでも受験勉強のルートに沿った復習・演習として位置づけることが肝要です。
科目ごとにどのように勉強すればよいか分からない人は科目・形式別勉強法をご覧ください。
定期テストで「丸暗記に終始する勉強」は捨てる
定期テスト対策として、大学受験に結びつきにくい「丸暗記に終始する勉強」は、思い切って時間を削減するか、完全に捨てる判断をするべきです。
これに該当するのは、主に初見の文章読解力が求められないタイプの問題に対する対策です。
例えば、英語の長文問題で「教科書の本文と和訳を全て暗記すれば解ける」タイプの空欄補充問題や、国語の古文・漢文で「授業中に習った本文が出題されるため、文法構造や読解をせず丸暗記する」といった勉強方法がこれに該当します。
実際の大学入試では、初見の文章を限られた時間内に正確にリーディング・読解していく力が要求されます。
意味や構造を理解せず、ただ丸暗記で点数を取っても、大学受験に必要な本質的な学力は向上しません。
したがって、これらの科目の定期テスト対策では、本文の丸暗記を避ける代わりに、長文を通して英文法や構文の理解を深める、古文単語や文法、漢文の句形といった体系的に整理できる基礎知識に時間を割くことが、受験に直結する賢明な判断となります。
定期テストを最大限に活用し受験に繋げる方法

大学入試の練習として定期テストに取り組む
定期テストを単なる学校の評価ではなく、大学入試本番を想定した実践的な練習の場として位置づけて取り組むことは、受験生にとって非常に有意義です。
定期テストは、普段の授業や参考書での学習では得られない、緊張感のある環境で時間配分を考えて問題を解く経験を提供してくれます。
具体的には、定期テストで出題された初見の問題や難易度の高い問題に挑むことで、現時点での自分の実力を客観的に試すことができます。
また、時間内に全問を解ききるための時間管理能力を養う練習にもなります。
大学入試においても、限られた時間の中で最大のパフォーマンスを発揮する力は不可欠です。
定期テストを通して、自分の弱点分野や時間配分の癖を認識し、その後の受験勉強の計画に反映させることができます。
日々の学習、復習、そして定期テストでの実践という一連の流れを、大学受験に向けた計画的な学習習慣の一部として組み込むことが、実力を着実に伸ばすことに繋がると考えられます。
授業を聞くだけ、参考書を解くだけでなく、「テスト」という形式で自分の力が発揮できるかを定期的に試すことが、自信にも繋がります。
定期テストの時期を勉強のモチベーション維持に繋げる
長い受験期間を乗り切る上で、モチベーションの維持は大きな課題となります。
定期テストの時期は、学校やクラス全体に「勉強をしなければならない」という雰囲気が自然と生まれるため、これを自分の勉強意欲を高める環境要因として活用することが可能です。
定期テストは1年の間に複数回実施されます。
テスト開始の1~2週間前から集中的に勉強する期間を設けることで、強制的に学習量を増やし、ダレがちな時期に活を入れることができます。
また、テスト後に点数という具体的な結果が出ることで、自分の成長を実感したり、苦手な分野を明確にしたりすることができ、次の学習への具体的な目標設定に役立てられます。
ピリピリとした緊張感のある環境に身を置くことで、普段よりも集中力が高まり、質の高い勉強ができる可能性もあります。
定期テストの時期を単なる義務と捉えるのではなく、自分の学習習慣をリセットし、モチベーションを再点火させるための短いターニングポイントとして戦略的に利用することが、受験勉強全体を成功に導くための工夫となります。

まとめ:迷いを断ち切り志望校合格を目指す

大学受験生が定期テストとどう向き合うかは、それぞれの受験タイプや状況によって判断が分かれます。
定期テストを安易に捨てることで選択肢が狭まるリスクがあるため、自分にとってのベストな選択を見極めることが重要です。
- 定期テストを捨てることは「欠点を取らない最低限の対策」と解釈すべき
- 進級・卒業、奨学金の基準を満たすため欠点回避は全受験生に必須
- 高校の成績(評定)が下がり推薦入試などの選択肢が狭まるデメリットがある
- 一般選抜受験者は定期テストを「受験科目の基礎固め・演習」として活用する
- 受験科目以外の科目は欠点回避のみに時間を留め効率を最優先する
- 時間に余裕がない場合は欠点回避の最低限対策に絞り割り切って捨てる判断も必要
- 学校推薦型・総合型選抜の受験生は高3の1学期まで全科目高得点を目指す
- 推薦・総合型選抜は評定が重要なので高3の2学期以降にセーブを検討する
- 内部進学者は学校独自の進学基準に従い全科目の高得点を目指す
- 英語・数学・理社は参考書で習った範囲の復習として定期テストを活用する
- 受験に直結しない国語の丸暗記や本文理解に終始する勉強は時間を割くべきでない
- 定期テストは時間配分や緊張感に慣れる「大学入試の練習」として活用できる
- テスト結果を分析することで自分の苦手分野や効果的な勉強法を認識できる
- 定期テスト期間の「勉強ムード」を自己のモチベーションアップに繋げる
- 自分のゴールは何かを常に考え「捨てる部分」「捨てない部分」を見極める

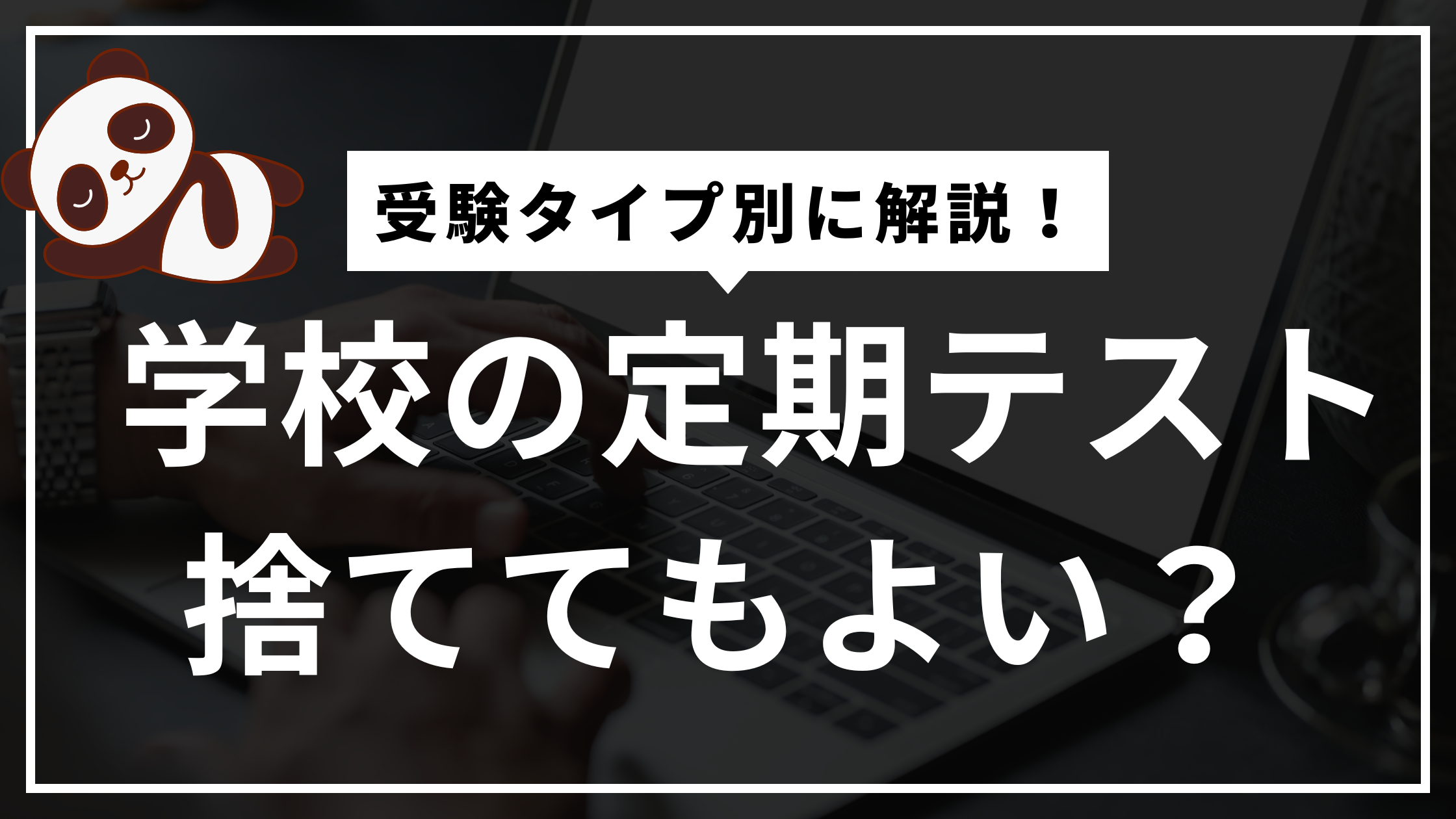
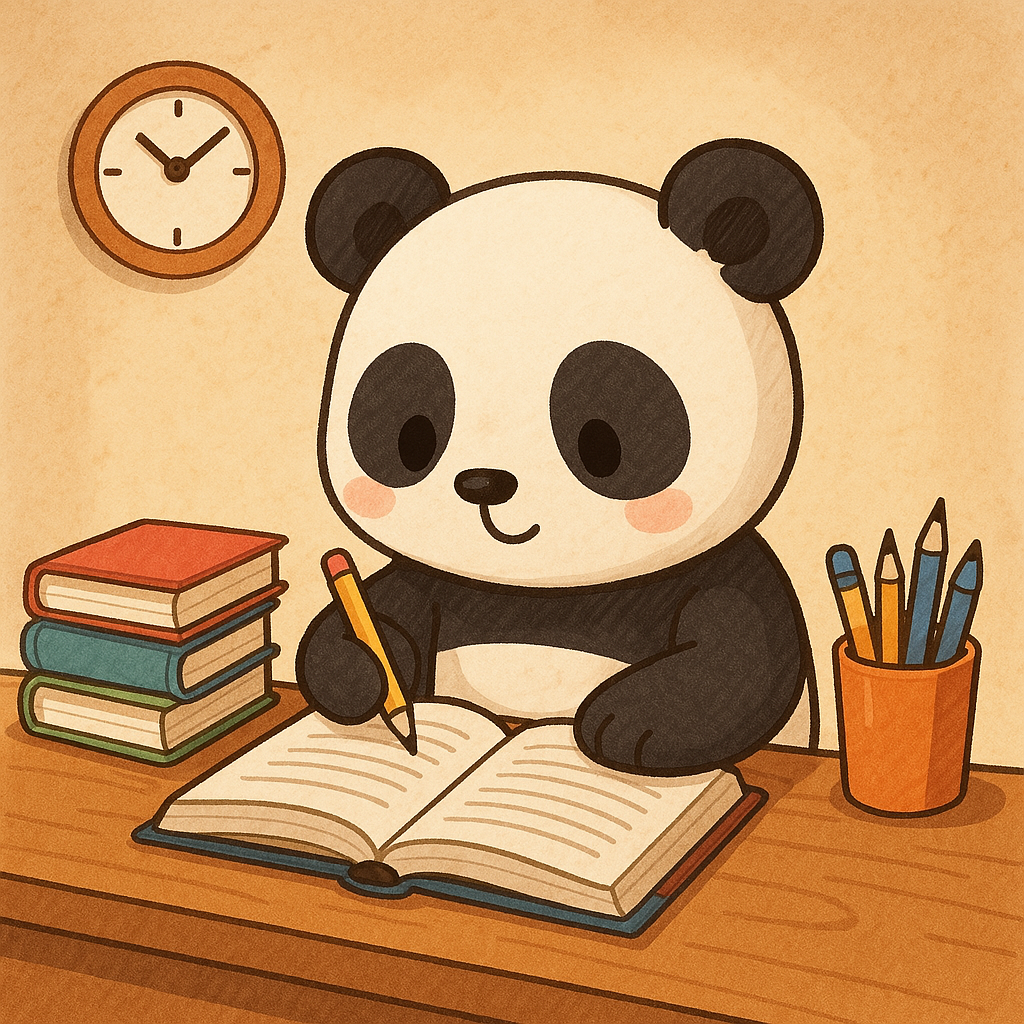



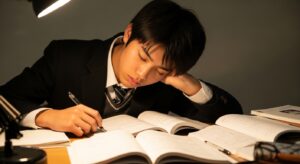




コメント