
パンダさん!共テの数学が全然できなくて困っているんだよ~

共テ数学は問題形式も特殊でなかなか手ごわいよね!
今回は共テ数学ができない人向けに共テ数学のコツをお話しするよ!
共通テスト数学でなかなか点数が伸びず、苦手に感じている方は多いのではないでしょうか。
2021年に導入されてから、センター試験とは異なる形式に戸惑う受験生も少なくありません。
特に問題文の量が増え、長文を読み解きながら解答を進めるスタイルは、多くの受験生が「時間が足りない」「誘導に乗れない」といった悩みを抱える原因になっています。
この記事では、共通テスト数学の基本情報から、なぜつまづいてしまうのかという原因、そして具体的な対策や勉強法まで、徹底的に解説します。
この記事に書いてあることを実践することで、私は模試や本番の共テ数学で9割を取ることができました。
この記事を通して、共通テスト数学の苦手意識を克服し、得点アップにつなげるヒントを見つけてください。
- 共通テスト数学の出題形式や配点などの基本情報
- なぜ共通テスト数学で誘導に乗れないのかという原因
- 苦手な分野や計算力を克服する具体的な対策
- 共通テスト対策に役立つ参考書と過去問の活用法
なぜ共通テスト数学ができない?その原因と対策

- 共通テスト数学の基本情報と出題形式
- 共通テスト数学で誘導に乗れない原因とは
- 問題文の読解力不足で誘導に乗れない
- 数学の根本的な力が低くて誘導に乗れない
- 共通テストの数学IAを攻略する
- 共通テストの数学IIBCを攻略する
共通テスト数学の基本情報と出題形式
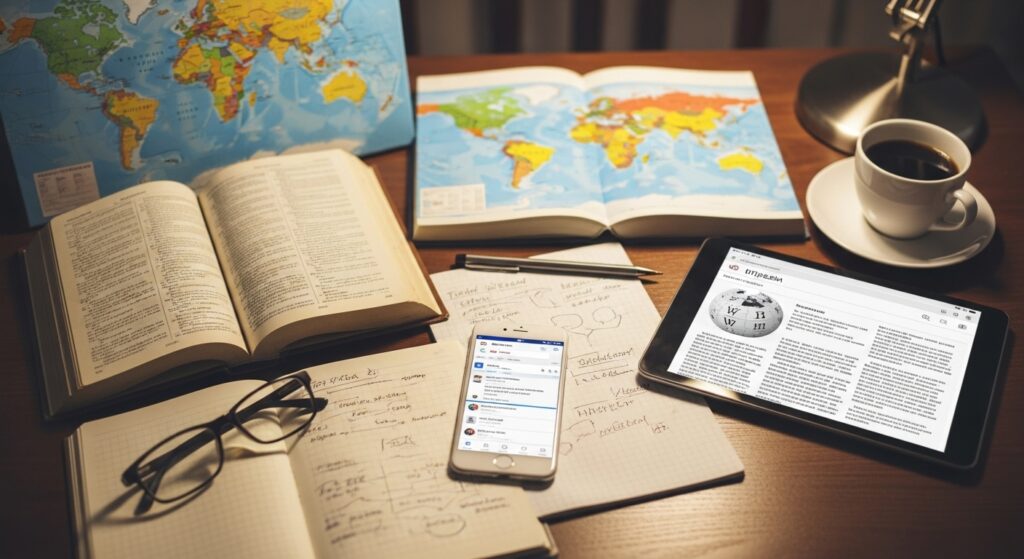
共通テスト数学は、大学入試における重要な科目の一つであり、従来のセンター試験とは異なる形式で受験生の思考力や判断力を測ります。
まず、試験の全体像を把握するために、科目構成や試験時間、配点といった基本情報を詳しく見ていきましょう。
共通テスト数学は、「数学Ⅰ・数学A」と「数学Ⅱ・数学B・数学C」の2科目に分かれています。
数学Ⅰ・数学Aの試験時間は70分、数学Ⅱ・数学B・数学Cは60分と設定されており、いずれも配点は100点です。
注目すべきは、数学Ⅰ・数学Aの試験時間がセンター試験より10分延長されている点です。
この時間延長は、単純な計算問題の減少と、思考力を問うための長い問題文や資料の読み解きに時間を要する問題が増えたことに対応するためと考えられます。
内容面では、センター試験が主に公式の適用や定型的な計算処理能力を問う問題が中心だったのに対し、共通テストでは、日常生活や社会の事象を題材にした、より複雑な設定の問題が出題される傾向が強くなっています。
これにより、受験生は与えられた情報を整理し、論理的に思考しながら解答を導き出す力が求められます。
単に知識を暗記しているだけでは対応が難しく、初見の問題に対する柔軟な対応力が得点の鍵となります。
また、共通テスト数学の大きな特徴として、科目内の選択方式が挙げられます。
数学Ⅰ・数学Aでは、「図形の性質」と「場合の数と確率」の2項目をすべて解答する形式となっています。
一方、新課程となる「数学Ⅱ・数学B・数学C」では、「数列(数学B)」「統計的な推測(数学B)」「ベクトル(数学C)」「平面上の曲線と複素数平面(数学C)」の4項目の中から3項目を選択して解答することになります。
この選択方式により、受験生は自身の得意分野を活かした戦略を立てることが可能ですが、一方で選択しなかった分野についても最低限の知識は求められる可能性があります。
| 科目名 | 試験時間 | 配点 | 内容の特徴 |
| 数学I・数学A | 70分 (センター試験より10分延長) | 100点 | 思考力や判断力を問う長い問題文や資料の読み解きが必要な問題が増加。「図形の性質」と「場合の数と確率」の2項目をすべて解答する形式。 |
| 数学II・数学B・数学C | 60分 | 100点 | 日常生活や社会の事象を題材にした複雑な問題が出題される傾向が強い。「数列(数学B)」「統計的な推測(数学B)」「ベクトル(数学C)」「平面上の曲線と複素数平面(数学C)」の4項目から3項目を選択して解答する形式。 |
共通テスト数学で誘導に乗れない原因とは
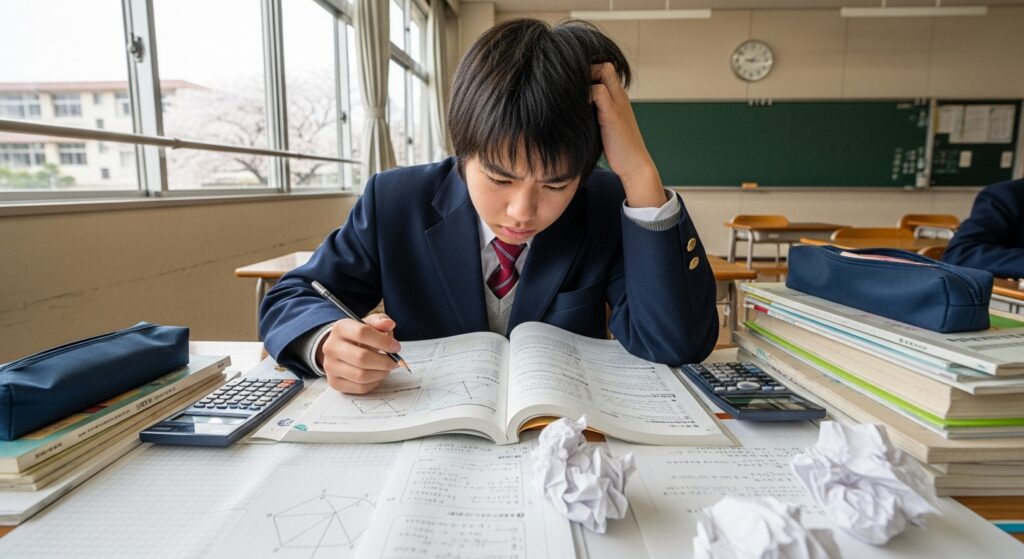
共通テスト数学で高得点を目指す上で、出題者が意図的に配置した「誘導」にスムーズに乗ることが不可欠です。
しかし、多くの受験生がこの誘導の途中でつまずき、時間だけが過ぎてしまうという状況に陥りがちです。
この問題の根本には、複数の要因が絡み合っていると考えられます。
まず、最も大きな原因は、問題文全体を俯瞰的に把握する力の不足にあります。
共通テストの問題は、物語や実験の描写といった導入部分が長く、その中に解答に必要な情報やヒントが散りばめられています。
この長い導入文の中から、どの情報が必要で、どの情報が補足的なものなのかを正確に読み解く力がなければ、問題の全体像を把握することができません。
数学が苦手な受験生ほど、目の前に与えられた個々の数式や小問にのみ集中してしまう傾向が見られます。
その結果、問題全体の流れや、各設問がどのように関連しているかという文脈を見失ってしまいます。
このような状態に陥ると、ある設問でつまずいた際に、次に進むべき道筋が見えなくなり、パニックを引き起こすことがあります。
さらに、小問同士の関連性を見抜く力も重要です。
共通テストの問題は、多くの場合、前の設問の結果が次の設問のヒントや前提条件となっている丁寧な誘導が施されています。
しかし、この関連性を意識せずに問題を解き進めてしまうと、せっかくのヒントを活かせず、結果的に遠回りな解法を選んでしまったり、途中で行き詰まってしまったりする可能性があります。
問題文の読解力不足で誘導に乗れない
共通テスト数学の誘導に乗れない原因として、問題文の読解力不足は無視できない要素です。
特に、理系科目に注力するあまり国語の学習がおろそかになりがちな受験生は、この点で苦労するケースが多いようです。
共通テストの数学では、問題文が長文化していることが顕著であり、単なる数式だけでなく、複雑な状況設定や会話文、図や表が含まれることも珍しくありません。
これらの文章の中から、解答に必要な数値を正確に抜き出し、条件を整理する力は、まさに国語力に直結する能力です。
読解力が不足していると、問題の意図を正しく把握することができず、見当違いの解法を試みて時間を浪費してしまったり、解答に必要な情報がどこに書かれているかを見つけられなかったりします。
例えば、「ある状況下での平均値の変動」を問う問題であれば、その状況設定がどういう意味を持つのか、どのような数学的モデルを適用すべきなのかを文章から理解する必要があります。
この理解が曖昧だと、適切な解法にたどり着くのは困難になります。
数学の根本的な力が低くて誘導に乗れない
共通テストの誘導に乗れない原因は、単なる読解力や問題文の分析力だけではありません。
その根本には、数学そのものの基礎力不足が横たわっている可能性があります。
誘導は、いわば問題の解き方をステップごとに丁寧に示してくれる道しるべのようなものですが、その道を進むためには、その分野の基礎的な知識が深く理解されていることが前提となります。
教科書に載っている公式や定理をただ暗記しているだけでは、誘導されたステップの意味を正しく理解し、その指示通りに計算を進めることは難しい場合があります。
誘導に乗るためには、与えられた情報から「この問題は〇〇の定理を使えば解けるはずだ」「この式変形は〇〇という公式が背景にある」といった、問題の本質を見抜く力が求められます。
これは、日頃から教科書レベルの典型問題を素早く正確に解けるだけの力が身についていなければ、いくら誘導があってもそのヒントを活かしきれないということです。
誘導に乗れない原因を、テクニック的な問題だと考えがちですが、まずは自分の基礎学力が盤石であるかを見直すことが、得点力向上の第一歩となります。
共通テストの数学IAを攻略する

共通テストの数学IAは、共通テスト数学の中でも特に問題文の文章量が多く、日常的な場面設定や実験データなどを題材にした問題が出題される傾向が強いです。
そのため、問題の意図を正確に把握する読解力が特に重要になります。
この科目を攻略するためには、以下のポイントを意識した学習が不可欠です。
誘導を意識した過去問演習
過去問や予想問題集を解く際には、単に正解を出すだけでなく、出題者がどのような意図で各小問を配置したのかを深く考察する練習をしましょう。
例えば、「なぜこの設問がこの位置にあるのか」「前の設問の答えが次の設問にどのように繋がるのか」といった、誘導の構造を意識して問題を解くことで、本番で初見の問題に直面した際も、スムーズに思考の糸口を見つけられるようになります。
計算力と基礎固めの徹底
数学IAでは、「図形の性質」や「場合の数と確率」など、思考力だけでなく、計算に時間を要する問題も多く出題されます。
読解に時間をかけつつ、計算を素早く正確に行うことが求められるため、日頃から基礎的な計算練習を欠かさないことが大切です。
教科書や基礎問題集に掲載されている典型的な問題を反復して解き、計算力を磨いておきましょう。
共通テストの数学IIBCを攻略する

共通テストの数学IIBCは、数学IAに比べて文章量が少なく、より数学的な思考力や応用力を問う問題が多い傾向があります。
この科目を効果的に攻略するためには、以下のポイントを意識した対策が有効です。
選択問題の対策
数学IIBCの最大の特徴は、科目内の選択問題です。
「数列(数学B)」「統計的な推測(数学B)」「ベクトル(数学C)」「平面上の曲線と複素数平面(数学C)」の中から、3項目を選択して解答する必要があります。
そのため、自分の得意・不得意を早期に把握し、どの分野で得点を稼ぐかを戦略的に決めることが重要です。
統計的な推測の対策
新課程から新たに加わった「統計的な推測」は、初見では難しく感じるかもしれませんが、一度パターンを理解してしまえば、得点源にしやすい分野です。まずは教科書や基礎問題集で概念をしっかりと理解し、基本的な問題は確実に解けるようにしておきましょう。基本的な問題は確実に解けるようにしておきましょう。
共通テスト数学ができないと悩む人がやるべき具体的な対策

共通テスト数学がうまくいかないと感じている場合、その原因を特定し、効果的な対策を講じることが重要です。ここからは、具体的な学習方法や心構えについて解説します。
- 誘導に乗るための問題演習と時間配分
- 読解力を鍛えるには国語の勉強が有効
- 計算力を高める対策と反復演習
- おすすめ参考書と問題集の選び方
- 共通テスト数学に関するよくある質問
- なかなか共通テスト数学ができない人へのアドバイス
誘導に乗るための問題演習と時間配分

共通テスト数学を攻略するためには、単に問題を解くだけでなく、問題文の意図を汲み取る練習が不可欠です。
数学が得意な人は、問題文を読みながら自然と解法を思いつくことが多いですが、苦手な人はこの「思いつく」プロセスを意識的にトレーニングする必要があります。
解法を「思いつく」ための思考訓練
問題を解く際には、まず問題文を注意深く読み、与えられた条件や情報を整理しましょう。
そして、その情報から「どの公式や定理を使えば良いか」「どのような式を立てるべきか」を考える習慣をつけます。
この思考プロセスを繰り返すことで、解法パターンが自然と身につき、初見の問題にも対応できる力が養われます。
時間配分を意識した演習
問題演習を行う際には、常に時間を意識することが大切です。
特に、本番よりも少し厳しい時間設定で問題を解く練習をすることで、本番での時間的な余裕を生み出すことができます。
時間内に解き終わらなかった問題も、すぐに答えを見るのではなく、納得がいくまで自分で考え抜くことが、思考力を鍛える上で非常に重要です。
以下に時間配分の一例を載せておきます。
【数学ⅠA】
| 大問 | 推奨時間配分 |
| 大問1 | 20分 |
| 大問2 | 20分 |
| 大問3 | 15分 |
| 大問4 | 15分 |
【数学ⅡBC】
| 大問 | 推奨時間配分 |
| 大問1 | 10分 |
| 大問2 | 10分 |
| 大問3 | 15分 |
| 選択問題(3問) | 10分ずつ |
これをベースにして、自身の得意不得意に合わせて調整してみてください。
読解力を鍛えるには国語の勉強が有効
共通テスト数学の長文問題に対応するには、国語力を高めることが間接的ながらも非常に有効な対策となります。
理系科目に集中しがちな受験生は、国語の学習を後回しにしがちですが、文章を正確に読み解く力はすべての科目の基礎となります。
普段から問題文を丁寧に読むことを心がけ、主語や述語、指示語が何を指しているのかを明確にしながら読み進める習慣をつけましょう。
国語の問題演習を通じて文章の構造を理解することで、数学の問題文から必要な情報を効率的に抜き出す力が向上し、結果として誘導に乗る力も養われます。
計算力を高める対策と反復演習
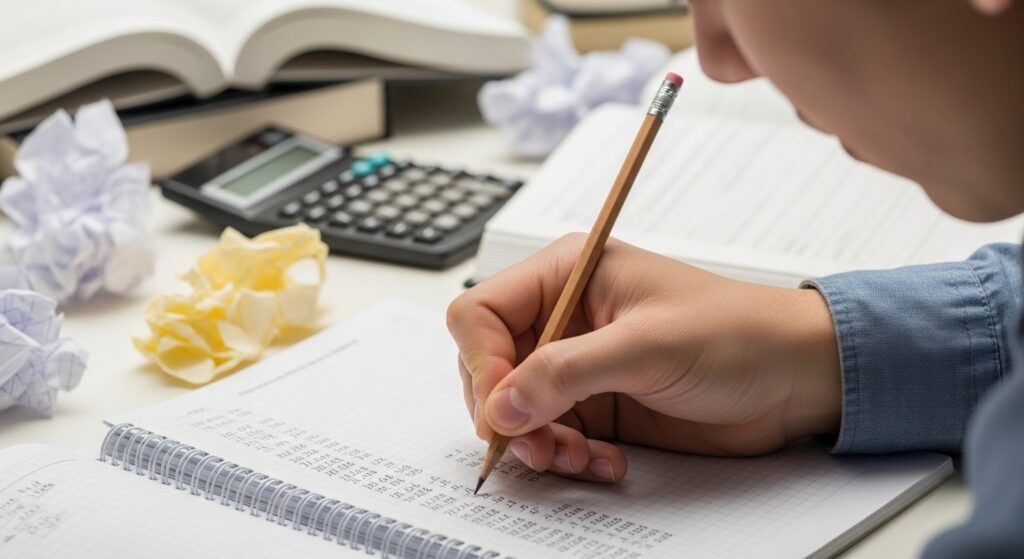
共通テスト数学は、問題文の読解に加え、正確かつ素早い計算力も求められます。
読解に時間を割く分、計算は迅速かつ正確に行う必要があります。
計算ミスが多い、あるいは計算に時間がかかると、最後まで問題を解ききることが難しくなります。
計算力を高めるためには、日頃から計算練習を繰り返すことが不可欠です。
計算ミスをなくす方法については↓
特に、因数分解、三角関数、定積分など、頻出分野の計算は、教科書の練習問題や学校のワークを活用して反復練習しましょう。
良問の多いセンター試験の過去問も、計算問題の練習に非常に適しています。
おすすめ参考書と問題集の選び方
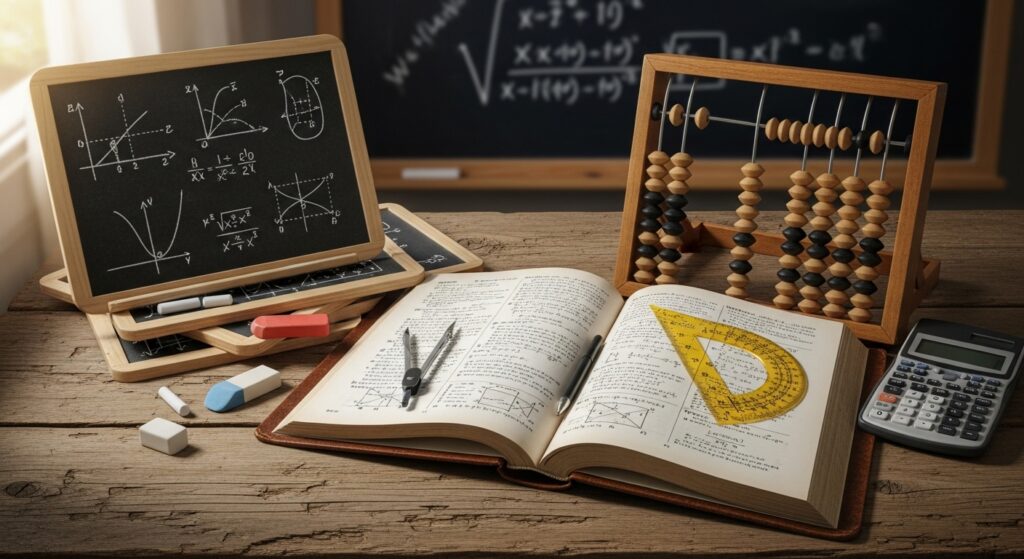
共通テスト数学の対策を進める上で、自分に合った参考書や問題集を選ぶことは、学習効果を最大化するために重要です。
基礎固めにおすすめの参考書
『短期攻略 大学入学共通テスト』は、基礎から応用まで幅広いレベルに対応しており、多くの受験生に利用されています。
特に、新課程の共通テストに対応した短期攻略 大学入学共通テストは、共通テスト対策の導入としておすすめです。
共通テスト形式に慣れるための問題集
共通テストの形式に慣れるためには、大手予備校が出版している実践問題集や、教学社の共通テスト過去問研究シリーズが有効です。
これらの問題集は、共通テスト特有の出題形式や時間配分に慣れるための最適な教材となります。
センター試験過去問の活用
形式は異なりますが、問われている数学の本質は共通テストとセンター試験で大きく変わるわけではありません。
良問揃いのセンター試験の過去問は、演習量を確保する上で非常に有用です。
特に、分野ごとにまとめて解くことで、苦手な分野を重点的に克服するのに役立ちます。
共通テスト数学に関するよくある質問
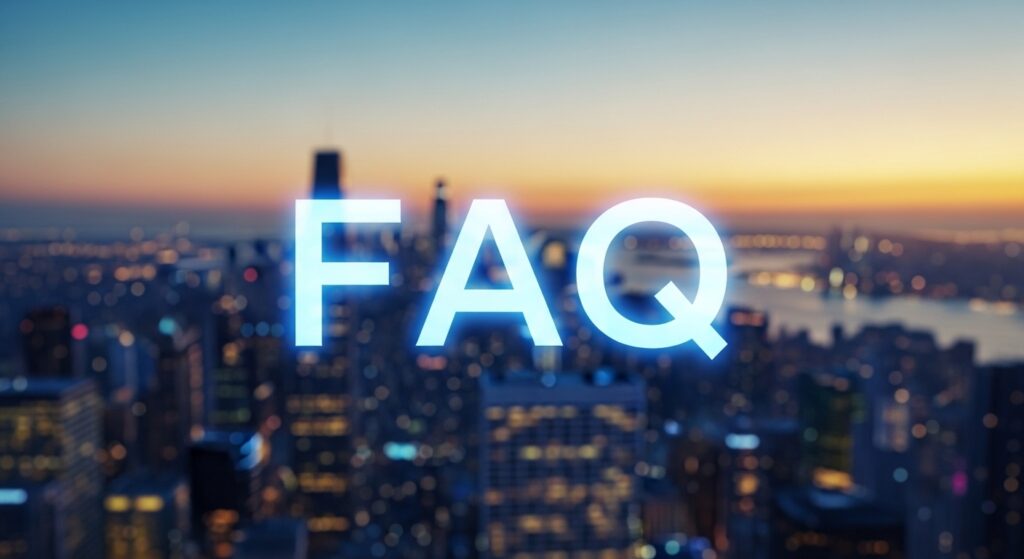
共通テスト数学の対策について、多くの受験生が抱える疑問にお答えします。
Q. 数学は暗記科目ですか?
A. 数学は、単に解答を丸暗記するのではなく、解法のプロセスやポイントを分析し、理解することが重要です。
解法のパターンを覚えるという意味では暗記要素もありますが、初見の問題に対応するためには、その解法がなぜ成り立つのかを理解し、柔軟に応用する力が不可欠です。
Q. 数学はセンスがないとできないですか?
A. 数学はセンスよりも、正しい勉強法で地道に努力を積み重ねることで必ず力がつきます。
特に、わからない問題に直面した際にすぐに答えを見るのではなく、じっくりと自分で考える時間を確保することが大切です。
Q. いつから共通テスト対策を始めれば良いですか?
A. 基礎が固まっていない状態で共通テスト形式の問題を解いても、あまり効果は得られません。
まずは教科書の内容を完璧にし、基礎的な問題を解けるようにしましょう。
共通テスト形式の問題演習は、秋以降に本格的に始めるのが一般的です。
数学の勉強の流れを確認したい人は↓
なかなか共通テスト数学ができない人へのアドバイス
この記事のポイントをまとめておきます。
- 共通テスト数学の出題形式や配点、試験時間を正確に把握する
- 過去問や平均点を分析して出題傾向や目標点を明確にする
- 読解力を向上させるために問題文を丁寧に読む練習をする
- 前問と次問の関連性を意識し誘導の意図を読み取る
- 基礎的な計算力を高める反復練習を日頃から取り入れる
- 公式がなぜ成り立つのか深く理解し応用力を養う
- 解法を「思いつく」ための思考プロセスを意識して勉強する
- 分からない問題はすぐに答えを見ずに自分でじっくり考える
- 自分のレベルに合った参考書や問題集を選んで学習を進める
- センター試験の過去問も活用し演習量を確保する
- マークシートを使った時間配分の練習を普段から行う
- 時間内に解ききれなかった問題も後で必ず考え直す
- 本番よりも厳しい時間設定で問題を解く練習をする
- 自分ができたと思っている問題も本当に理解できているか見直す

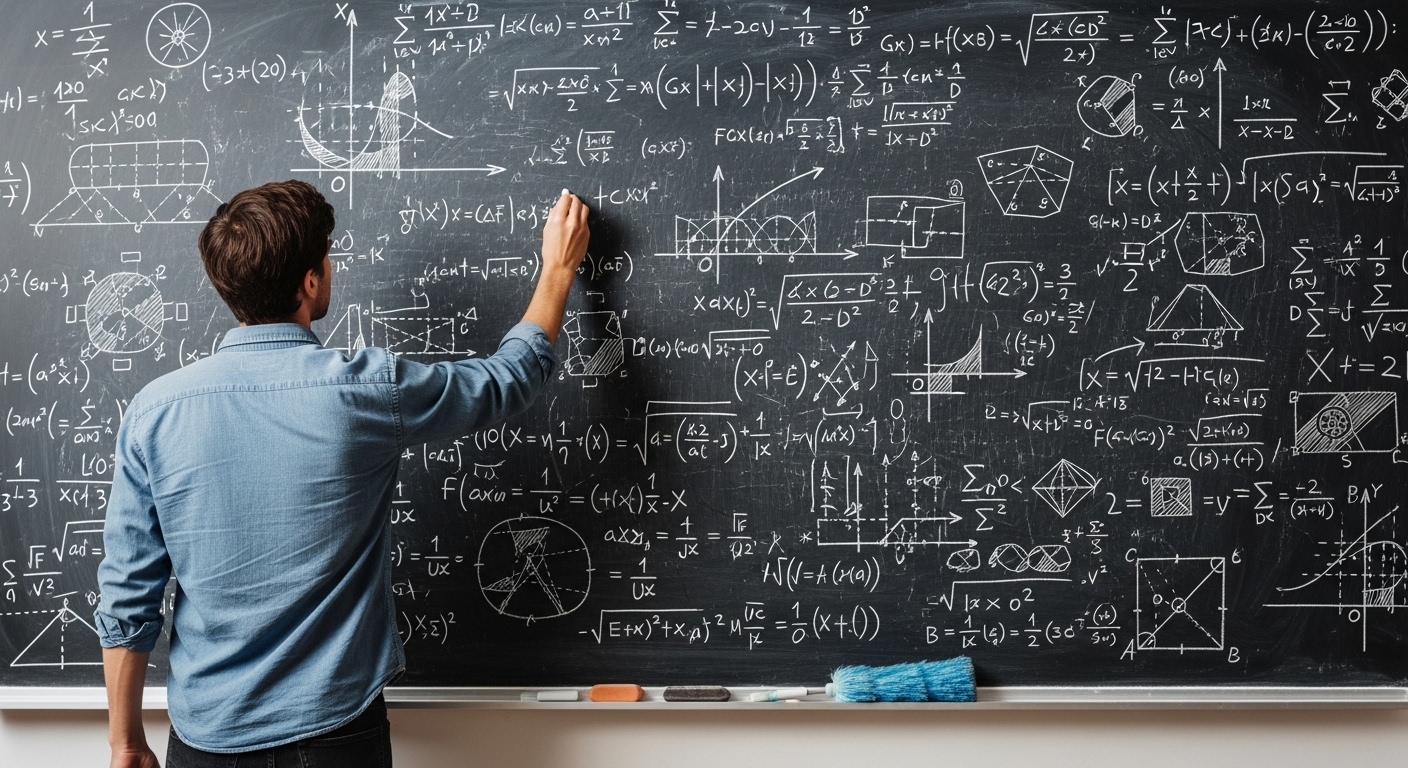
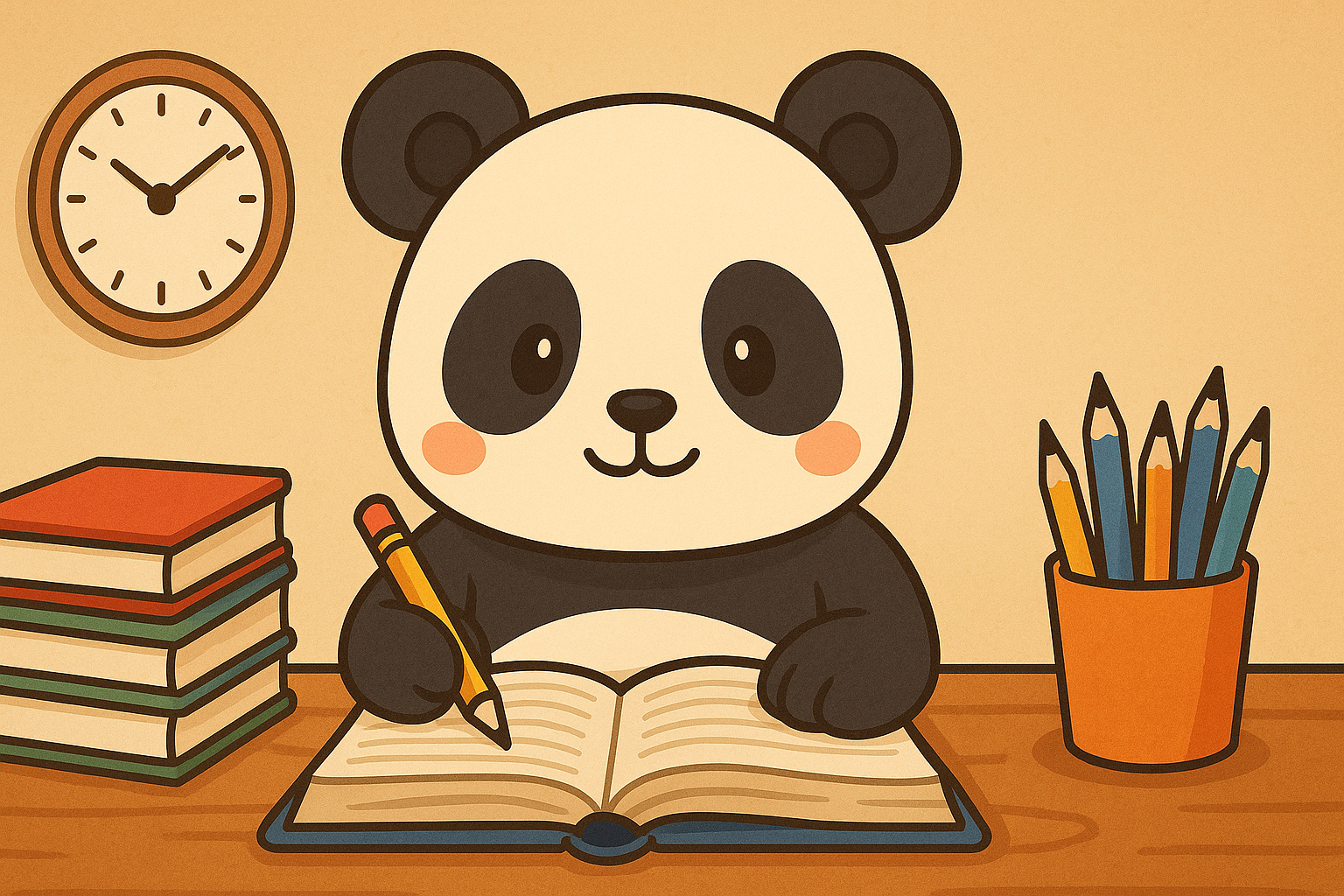

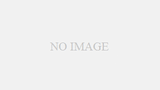



コメント