共通テストで85パーセントという得点を目指しているものの、それがどれくらいの水準なのか、どの大学に合格できるのかといった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に、難関大学を目指す受験生にとって、この得点率が上位何パーセントに位置するのかは重要な情報です。
また、東大や京大といった最難関大学に合格するためには、各科目の戦略や参考書選びが鍵を握ります。
特に数学や英語、国語、理科、社会、情報といった主要科目の目標点をどのように設定するべきか、具体的な学習計画を立てる上での指針を知りたいと考えているかもしれません。
この記事では、共通テストで85パーセントの得点率が持つ意味や、この目標を達成するために必要な学習法を解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。
- 共通テスト85%の得点率がどのくらいの水準であるか
- 共通テスト85%で合格できる具体的な大学
- 各科目の合理的な目標得点と学習のポイント
- 85%以上を目指すための効率的な学習戦略
共通テスト85パーセントはどれくらいの水準か

- 共通テスト85%が上位何パーセントか
- 共通テストで合格できる国立大学
- 共通テストで合格できる私立大学
- 東大・京大に合格するための得点率
- 共通テストの各科目別目標点
- 共通テストで理科の目標点達成
- 共通テストで数学・英語の目標点達成
- 共通テストで国語・社会・情報の目標点達成
共通テスト85%が上位何パーセントか
共通テストで85%以上の得点率を達成することは、受験生全体の中でも非常に高い水準にあることを意味します。
この得点率がどれほどの位置づけにあるかを理解するには、全国の受験生の中での相対的な立ち位置を把握することが不可欠です。
一般的に、共通テストで8割以上の得点を取る受験生は、全体の受験者数のうち上位15%程度に位置するとされています。
85%という得点率は、この上位15%のさらに上の層に位置する、極めて優秀な成績であると判断できます。
この水準に到達することで、多くの難関大学の受験資格を得ることができ、二次試験での負担を軽減し、合格の可能性を飛躍的に高めることが可能となります。
特に、難関国立大学の入試では、共通テストの得点が高いほど合否判定において有利に働くことが多いため、この得点率を目指すことは非常に意義深い目標設定と言えるでしょう。
実際に、東京大学や京都大学のような最難関大学の合格者平均点も、85%を超えることが一般的です。
したがって、この得点率は難関大学を目指す上で一つの明確な目安となります。
共通テストで合格できる国立大学
共通テストで85%以上の得点率があれば、多くの難関国立大学の合格圏内に入ることができます。
この得点率を足掛かりに目指せる具体的な大学・学部をいくつか見ていきましょう。
※このデータはパスナビを参考にしています。
| 大学名 | 学部 | 入試名 | 共通テスト得点率 |
| 北海道大学 | 理学部 | 物理/後期、生物/後期 | 85%~86% |
| 東北大学 | 経済学部 | 文系/後期、理系/後期 | 86%~87% |
| 秋田大学 | 医学部 | 医(秋田県地域枠)/後期 | 86% |
| 筑波大学 | 人文・文化学群、人間学群 | 人文/後期、心理/後期 | 85%~86% |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 後期 | 85% |
| 新潟大学 | 医学部 | 医/前期 | 85% |
| 信州大学 | 医学部 | 医/前期 | 85% |
| 滋賀医科大学 | 医学部 | 医(一般枠)/前期 | 85% |
| 京都大学 | 薬学部、農学部 | 薬/前期、農/前期など | 85%~86% |
| 大阪大学 | 法学部、経済学部 | 国際公共政策/前期、経済/前期 | 85% |
| 広島大学 | 医学部 | 医/前期 | 85% |
| 九州大学 | 理学部、薬学部、工学部 | 後期 | 85%~88% |
これらの大学では、共通テストの得点率が合否に大きく影響する傾向があります。
特に、後期日程では共通テストの配点比率が前期日程よりも高くなることが多く、高得点を取ることで合格の可能性が大きく高まると考えられます。
例えば、筑波大学や横浜国立大学のような、いわゆる難関国公立大学では、共通テストの得点率が85%以上であることが、出願の際の目安の一つとされています。
医学部や薬学部といった競争率の高い学部においても、この得点率は十分な合格圏内に入るための重要な指標となります。
志望校がこれらの大学に該当する場合、共通テストでの高得点確保は、二次試験に向けた大きなアドバンテージとなるでしょう。
共通テストで合格できる私立大学
私立大学においても、共通テスト利用入試で85%以上の得点率が求められる大学・学部は多数存在します。
共通テスト利用入試は、各大学の個別試験を受けることなく、共通テストの結果のみで合否を判定する方式であり、受験生にとっては併願校選びの重要な選択肢となります。
※このデータはパスナビを参考にしています。
| 大学名 | 学部 | 入試名 | 共通テスト得点率 |
| 青山学院大学 | 文学部、経営学部、理工学部など | 共テ利用 | 85%~89% |
| 上智大学 | 文学部、法学部、経済学部など | 共テ利用 | 85%~90% |
| 中央大学 | 法学部、商学部、国際経営学部など | 共テ利用 | 85%~89% |
| 明治大学 | 文学部、政治経済学部、理工学部など | 共テ利用 | 85%~88% |
| 立教大学 | 文学部、経営学部、社会学部など | 共テ利用 | 85%~90% |
| 早稲田大学 | 政治経済学部、社会科学部、人間科学部など | 共テ利用 | 85%~89% |
| 関西大学 | 商学部、社会学部、総合情報学部など | 共テ利用 | 85%~86% |
| 同志社大学 | 文学部、理工学部、心理学部など | 共テ利用 | 85%~90% |
| 立命館大学 | 法学部、産業社会学部、国際関係学部など | 共テ利用 | 85%~90% |
これらの大学では、特に難易度の高い学部や、3教科型などの共通テスト利用入試方式で85%以上の得点率がボーダーラインとなることがあります。
共通テスト利用入試は、多くの受験生が利用するため、競争率も高くなる傾向があります。
例えば、早稲田大学や上智大学のような最難関私立大学の特定の学部では、合格者平均点が90%を超えることも珍しくありません。
このため、85%という得点率は、これらの大学への挑戦権を得るための最低限のラインと考えることができます。
合格の可能性を高めるためには、90%以上を目指すくらいの気持ちで学習に臨むことが推奨されます。
東大・京大に合格するための得点率

東京大学や京都大学のような最難関大学を目指す場合、共通テストの得点率はさらに高い水準が求められます。
これらの大学では、共通テストの得点に加えて、二次試験の得点が合否を大きく左右しますが、共通テストで高得点を確保することは、二次試験での負担を軽減し、精神的な余裕を持って本番に臨む上で非常に重要です。
| 大学名 | 学部 | 入試名 | 共通テスト得点率 |
| 東京大学 | 教養学部(理科一類) | 前期 | 90% |
| 東京大学 | 工学部、理学部、農学部など | 前期 | 89%~90% |
| 京都大学 | 総合人間学部、経済学部、工学部など | 前期 | 87%~89% |
これらの大学では、共通テストで9割近くの得点を確保することが、二次試験での合格可能性を高める上で重要となります。
ただし、共通テストと二次試験の配点比率は大学や学部によって大きく異なるため、志望校の情報を正確に確認することが不可欠です。
たとえば、東大の場合、共通テストの配点は二次試験と比較して低い傾向にありますが、それでも足切り(第一段階選抜)の基準となるため、高得点を取ることが必須となります。
また、京都大学では学部によって共通テストの配点比率が異なり、共通テストの得点が高いほど有利になる学部も存在します。
これらの情報を踏まえ、志望校の過去の入試データを分析し、自身の目標得点率を具体的に設定することが、合格への第一歩となるでしょう。
共通テストの各科目別目標点

共通テストで合計85%の得点率を目指すには、科目ごとにバランスの取れた目標点を設定することが大切です。
すべての科目で満点を狙うのは現実的ではありませんし、学習効率も悪くなります。
そのため、自分の得意・不得意、そして志望校の配点比率を考慮した上で、戦略的に目標点を設定する必要があります。
ここでは、理系学生を例に挙げた合理的な目標設定を提示します。
| 科目 | 目標点(得点率) |
| 英語 | 170点(85%) |
| 数学 | 170点(85%) |
| 理科 | 170点(85%) |
| 国語 | 160点(80%) |
| 社会 | 80点(80%) |
| 情報 | 90点(90%) |
このように、配点が高い主要科目(英語、数学、理科)で安定して高得点を取ることを目指し、共通テストのみで必要となる国語や社会、情報では、負担を抑えつつ8割程度の得点を目指すのが効果的です。
特に理系学生の場合、国語の現代文は安定した高得点を取ることが難しいため、古文・漢文で高得点を確保することでカバーする戦略も有効です。
また、社会科目は満点を狙うよりも、確実に8割程度の得点を取れるように基礎固めを徹底することが、他の主要科目の学習時間を確保する上で賢明な選択と言えます。
共通テストで数学・英語の目標点達成
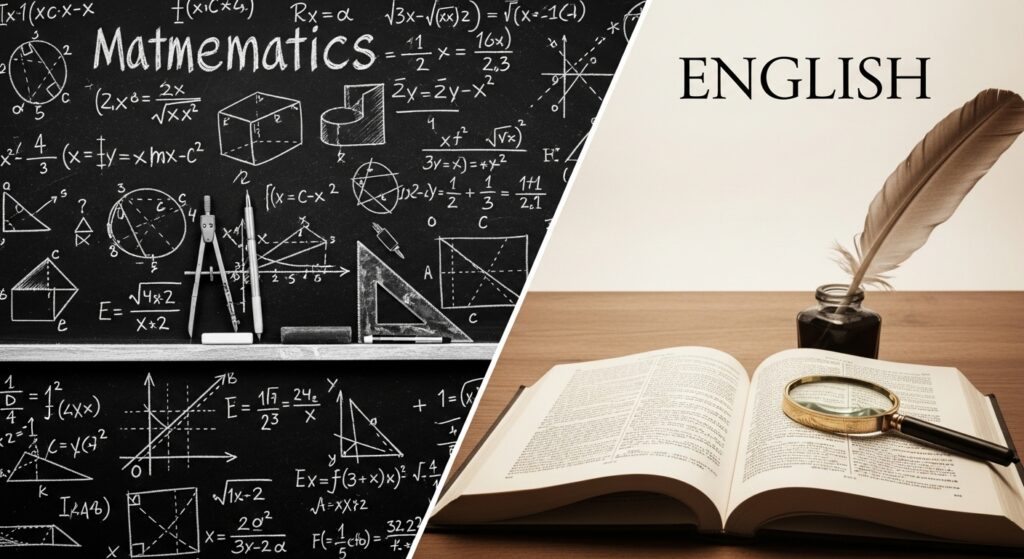
数学と英語は、共通テストで高得点を取る上で最も重要な科目であり、同時に「処理能力」が問われる科目でもあります。
これらの科目で安定して高得点を確保できるかどうかが、共通テスト全体の得点率を大きく左右します。
数学の学習ポイント
数学では、問題を素早く正確に解き進める力が必要です。
共通テストでは、複数のステップを経て答えを導き出す問題が多く、時間配分が非常に重要となります。
全範囲を網羅した『チャート式』などの参考書を高2の冬までに終わらせることが推奨されます。
基礎から応用まで幅広くカバーしているこれらの参考書を徹底的にやり込むことで、どのような問題にも対応できる土台を築くことができます。
さらに、共通テスト形式の問題演習を重ね、時間を短く設定して最後まで解き切る練習をすることで、本番での時間配分に慣れることが大切です。
特に、過去問や実践問題集を解く際には、ただ答えを出すだけでなく、より効率的な解法はないか、別の角度からアプローチできないかを常に考える習慣をつけましょう。
関連記事↓
共テ数学ができない人必見!共テ数学で9割とるためのコツと勉強方法
英語の学習ポイント
英語では、リーディングとリスニングの両方で安定した得点を確保することが求められます。
特に、リーディングは長文読解が中心となるため、速読力と精読力の両方が必要です。
長文読解は、本番の80分ではなく、65分や70分で解く練習をすることで、時間切れのリスクを減らすことができます。
リスニング対策
リスニングは、高2の冬までに本格的な問題集に取り組み、80点から85点を目指しましょう。
共通テストのリスニングは、センター試験と比べて音声のスピードが速く、多様なアクセントが用いられるため、日頃から様々な種類の英語音声に触れることが重要です。
リスニング対策としては、公式問題集や模試の音声を何度も聞き返したり、シャドーイングやディクテーションを取り入れたりすることが有効です。
早い段階で8割程度の得点を取れるようにしておくことで、その後の学習がスムーズに進むとされています。
長文の音読練習も、リーディングとリスニングの両方の基礎力向上に役立ちます。
共通テストで理科の目標点達成

理科は、共通テストの得点源になりやすい科目です。
英語や数学と比べて、共通テスト特有の「処理能力」が求められる問題が少なく、個別試験のマーク形式版と捉えることもできます。
そのため、確実に85%以上の得点を狙いたいところです。
基礎知識の定着が鍵
理科で高得点を取るためには、教科書や資料集に記載されている知識をしっかりと定着させることが不可欠です。
共通テストでは、教科書の隅々まで問われるような知識問題も出題されるため、日頃から基礎を固める学習が非常に重要になります。
特に、物理や化学では公式や法則の理解が、生物や地学では用語や現象の正確な理解が求められます。
単に暗記するだけでなく、なぜそうなるのかという原理を深く理解することで、応用問題にも対応できるようになります。
網羅系問題集の活用
高校2年生の秋頃までに、『リードα』や『セミナー』といった網羅系の問題集を全範囲で終わらせることが推奨されています。
これらの問題集を繰り返し解くことで、共通テストで問われる幅広い範囲の問題に対応できる実力が身につきます。
これらの問題集は、基礎から応用までバランス良く構成されているため、共通テスト対策の土台を築くのに最適です。
共通テストで国語・社会・情報の目標点達成
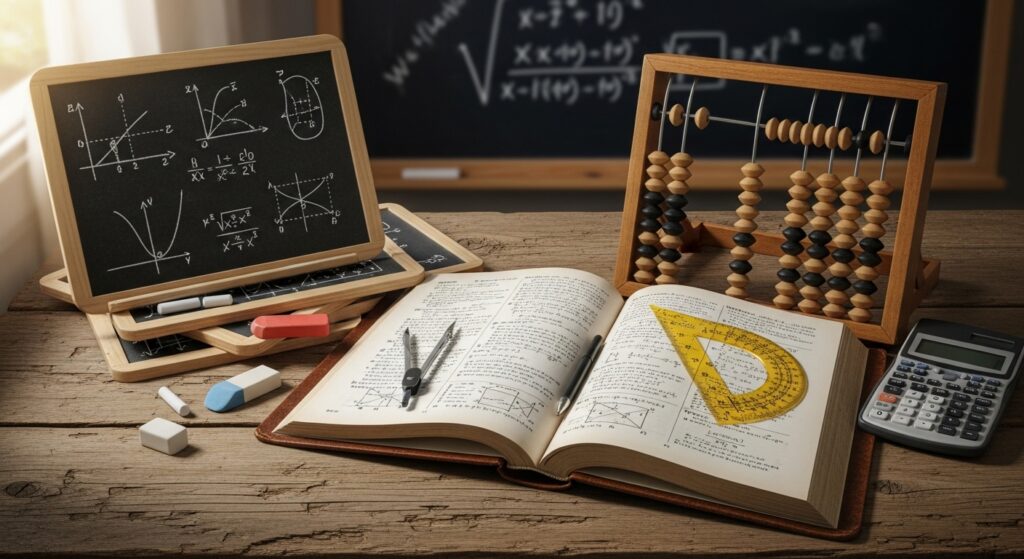
国語、社会、情報は、主要科目と比べて配点比率が低い場合が多いですが、合計点に与える影響は無視できません。
これらの科目で確実に得点を積み上げることが、85%以上の得点率を達成するためには不可欠です。
国語の学習ポイント
理系学生にとって、古文は重要な得点源となるため、早期から単語や文法を固めることが推奨されます。
古文単語や古典文法は、一度覚えてしまえば得点が安定しやすい分野です。
現代文は、漢字や基礎的な問題集を高2の冬までに終わらせておきましょう。
共通テストでは読解力や応用力が問われるため、日頃から評論や小説を読み、文章構造を正確に読み解く練習が大切です。
社会の学習ポイント
社会では、倫理や政治・経済など、選択科目によって学習量が異なります。
共通テストの過去問演習を通して、自分の選択科目の傾向を把握し、効率的な学習計画を立てることが求められます。
満点を狙うのは費用対効果が低いとされるため、7割から8割の得点を安定して取れることを目指すのが合理的です。
教科書や一問一答形式の問題集を繰り返し学習し、知識の定着を図りましょう。
情報の学習ポイント
情報は、個人差が出やすい科目です。
早期に共通テストの過去問を解いてみて、自分の実力を確認し、もし得点が低い場合は、基礎から丁寧に学習する必要があるでしょう。
プログラミングやデータサイエンスといった分野の知識が問われることもあり、単なる暗記だけでは対応できない問題も出題されます。
教科書や参考書を用いて、概念の理解を深める学習が重要です。
共通テスト85パーセント以上を目指すための学習法
- 合格のための戦略・オススメ参考書
- 合格を目指すための学習法
- 各科目別の学習法
- 85パーセントを突破する確率をさらに高めるには
- 共通テスト85パーセント以上の得点を目指すには
合格のための戦略・オススメ参考書
共通テストで85%以上の高得点を取るためには、効率的な学習戦略と適切な参考書選びが欠かせません。
高校1年生から基礎を固める学習を徹底し、高2の冬までには主要科目の全範囲を網羅することが重要です。
この時期までに基礎を固めておくことで、高3になったときに共通テストや二次試験の過去問演習に時間を費やすことができます。
科目別参考書ルートの例
- 英語: 『システム英単語』→『ポラリス英文法1』→『肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本 必修編』→『the rules 1,2』→『西きょうじ ロジカル英文読解』→『the rules 3,4』
- 数学: 全範囲を網羅的に学習できる『チャート式』などの参考書を繰り返し解き、基礎力を徹底的に固めます。
- 理科: 『入門問題精講』などの基礎問題集から始め、『リードα』や『セミナー』といった問題集で網羅性を高めることが効果的です。
これらの参考書を計画的に進めることで、共通テストで高得点を取るための土台を築くことができます。
合格を目指すための学習法
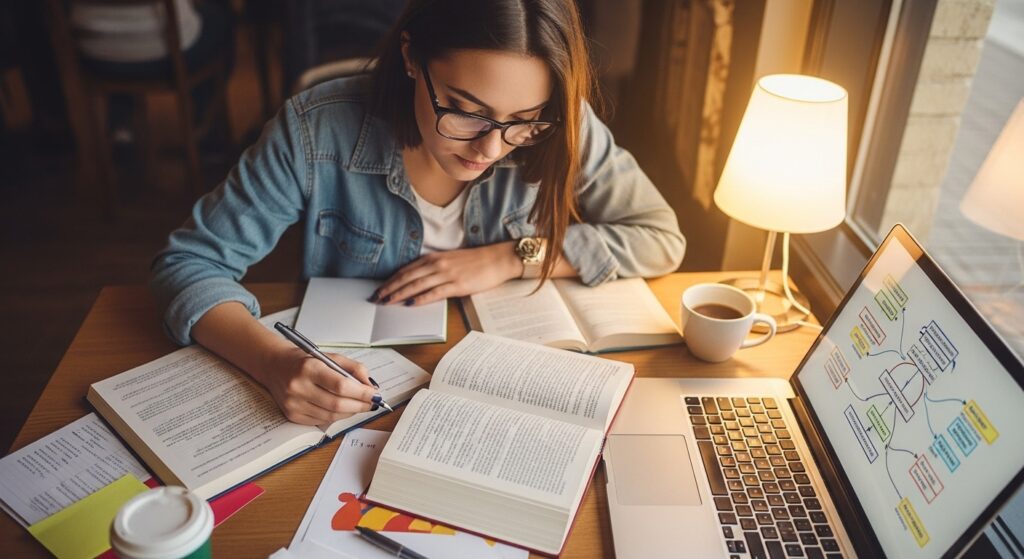
共通テストで85%以上の得点を確保するためには、各科目の基礎を固めた上で、共通テスト形式の演習を繰り返し行うことが最も効果的です。
時間配分の練習
共通テストは時間との戦いです。
過去問や模試を解く際は、必ず時間を計り、時間内に問題を解き切る練習を重ねましょう。
特に、英語や数学のように解答時間が不足しやすい科目では、普段から時間を意識して演習に取り組むことが大切です。
苦手科目の克服
自分の得意科目と苦手科目を正確に把握し、苦手科目に時間を多く割くなど、効率的な学習計画を立てることが大切です。
苦手科目は早めに克服することで、精神的な負担を減らし、総合的な得点アップにつなげることができます。
85パーセントを突破する確率をさらに高めるには
ここまで紹介してきた参考書や計画を進めることで、共通テストで高得点を取るための土台を築くことができます。
ただ、ここまで読んで「参考書はわかったけど、今の自分のペースで間に合うのかな?」「この計画で本当に合格できるのかな?」と不安に感じた人もいるかもしれません。
正直なところ、85%という高い壁を突破するには、ガムシャラな勉強よりも「正しい戦略」が命です。
私自身、受験生時代は戦略ミスで苦労しました。(過去の自分を指導することができたら宅浪する羽目にはならなかったと思います)
そんな人にパンダが自信を持ってオススメするのは「トウコベ」という完全マンツーマン指導のオンライン塾です。
もし、今の学習計画に少しでも迷いがあるなら、東大生・京大生があなたの専属コーチになってくれる「トウコベ」で、一度プランを見てもらうのが近道です。
しかも今なら、無料相談をしているので、料金を払わずに自分に最適な学習計画を手に入れることができます!
「塾代が高い=成績が上がる」わけではありません。
コスパよく、最短ルートで合格するための戦略を、まずは無料相談で手に入れてみてください。
[ >>東大・京大生が教えるオンライン個別指導「トウコベ」の無料相談を見てみる ]

ここだけの話、勉強戦略に不安がある人は、とりあえず無料の相談会だけ受けて、戦略を立ててもらい、後は自分で勉強するのも結構ありだと思うよ!
合格のために使えるものは使っていこう!
共通テスト85パーセント以上の得点を目指すには
共通テストで85パーセント以上の得点を目指すには、計画的な学習と効率的な問題演習が不可欠です。
以下に、重要なポイントをまとめます。
- 85%の得点率が上位層に位置する難易度の高い目標であることを認識する
- 東京大学や京都大学をはじめとする難関大学の合格ラインであることを理解する
- 私立大学の共通テスト利用入試でも多くの大学で求められる水準である
- 各科目の基礎を徹底的に固め、応用力を身につけることが重要
- 英語や数学といった主要科目で確実に高得点を狙う戦略を立てる
- 共通テスト特有の「処理能力」を養うための時間設定練習を行う
- 物理や化学などの理科科目では、知識問題対策を徹底する
- 国語や社会は、負担を抑えつつ8割程度の得点を確保する
- 自分の得意・不得意を把握し、学習計画を柔軟に調整する
- 複数の参考書に手を出すのではなく、厳選した一冊を徹底的にやり込む
- 高1・高2から段階的に学習を進め、基礎を早い時期に完成させる
- 共通テストの過去問演習を繰り返し行い、出題傾向に慣れる
- 過去問の自己分析を徹底し、失点した原因を明確にする
- 合格可能性を高めるため、共通テストと二次試験のバランスを考慮する




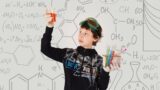

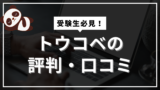



コメント