皆さんこんにちは、パンダです。
地方の公立高校から京大を受験し不合格だった後に、一年間宅浪して京大に受かった経験をもとに受験生向けのブログを書いています。

パンダさん!子供がもうすぐ受験生なのにスマホばかりで勉強しなくて心配なんです。

子供の勉強のやる気を引き出すのって難しいですよね~
でも大丈夫!今回は実体験をもとに子供に勉強のやる気を引き出してもらう方法を教えます!
実は私も、昔は勉強のやる気がなかったんです!
今回は全国のお母さん方が知りたい、子供の勉強のやる気を引き出す方法について考えていきたいと思います!
- 子供の勉強のやる気を引き出すために親ができること
- 逆にしてはいけない行動
- 受験期の子供との向き合い方
今日からできる!やる気を引き出す親の行動7選

「子どもがなかなか勉強しようとしない」「どうしたらやる気になるのか分からない」
そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
実際、勉強のやる気というのは、外から強制的に引き出すことはとても難しいものです。
逆に他人からしなさいといわれたことを継続して行えるでしょうか?かなり厳しいはずです。
では、親としては何もできないのでしょうか?
私はそうは思いません。
親にできることは、子どもにやる気を“出させる”ことではなく、やる気が自然と“出やすくなる”環境を整えてあげることだと、今ならはっきりと言えます。
高校生に勉強のやる気を出させるために、親ができることは決して多くありません。
けれども、「やる気が出やすい環境」を作ることなら、今日からでも始められます。
ここでは、私自身の経験も交えながら、親としてできる関わり方を7つご紹介します。
1. 結果よりも「努力や姿勢」を認める
「何点取れたの?」よりも、「昨日頑張ってたね」「毎日机に向かってて偉いね」と声をかけてあげる。
これだけで、子どもの自己肯定感はぐっと高まります。
私も、自分が勉強に目覚めてからは「頑張ってるね」と応援してくれる親の存在が、とても支えになりました。
点数で評価されるよりも、努力を見てくれることのほうがずっと嬉しかったのを覚えています。
2. 子どもの意思を尊重する
これは、私が一番伝えたいことです。
私自身、勉強に対して本格的に意欲が出たのは高校2年生になってから。
それまではほとんど勉強せず、家で机に向かうこともなかったのですが、それを親は無理に変えようとはしませんでした。
そして、私が「勉強を頑張る」と宣言したときも、親はただ一言「頑張ってね」と言って、私の意思を信じてくれました。
勉強にやる気が出るのは、「自分で目標を決めたとき」だけです。
親がいくら「勉強しなさい」と言っても、それは他人の目標であり、子ども自身のエネルギーにはなりません。
3. 「勉強しなさい」はNGワード
親としては、「もっと勉強してほしい」「将来のためになる」と思うのは当然のことです。
学生のうちに勉強しておくことの大切さは、私たちよりも長い人生経験のある保護者の方のほうが、よく知っているはずです。
でも、子どもの人生は、親の人生の延長線ではありません。
子どもには子どもの考え方や価値観があります。
それを無理に押しのけて、親の理想通りに動かそうとするのは、かえって逆効果になることが多いのです。
とはいえ、「子供に自分と同じような後悔をさせたくない」という気持ちをどうすればいいのか。
それを次にお話しします。
4. 「なぜ勉強するのか」を伝えてあげる
子どもが納得しないまま「とにかく勉強しなさい」と言われても、やる気は出ません。
もし、勉強の意義や将来的なメリットを伝えるなら、「自分がこう思った」という形で伝えるのが効果的です。
例:
- 「私も学生のときもっとやっておけばよかったって、大人になってからよく思うの」
- 「高校の勉強が役に立ったなって思うことが、社会に出ると結構あるよ」
子どもは社会経験が少なく、先の見通しが立てづらいものです。
その“見えない未来”に対して、大人としてヒントを与えてあげることは、親だからこそできることだと思います。

親ができるのは、判断を強要することではなく、後悔しないように多くの判断材料を与えることだと思うな!
5. やりたいことがあるなら応援する
もし子どもが「部活を頑張りたい」「絵を描くことに集中したい」などと言っている場合、その気持ちを否定しないでください。
たとえ今は勉強以外のことでも、自分で決めて頑張るという経験が、後に勉強へのやる気にもつながっていきます。
私自身、「やる気」とは自分で選んだ目標に対してしか持続しないものだと実感しています。
だからこそ、子ども自身が「これをやりたい」と思ったことを大切にしてあげてほしいのです。
6. 勉強しやすい環境を整えてあげる
たとえば:
- 静かに集中できる空間を用意する
- スマホを置く場所を一緒に工夫する
- 机の照明を整える
- リビングでも勉強しやすいようにテーブルを整理する
物理的な環境が整うと、勉強に取りかかるハードルがグッと下がります。

受験期を通して実感したけど、環境は初めに思っていたよりも10倍ぐらい大切だったよ!
7. 子どもを信じて見守る勇気を持つ
最も大切なのは、「この子は自分の意思で動ける」と信じることです。
子どもにとって、親の“信頼”ほど心強い後押しはありません。
やる気が芽生えるタイミングは、人それぞれ違います。
でも、その時が来たときに、「よし、やろう」と思える力をつけておくには、日頃からの親の接し方がとても重要です。
逆効果になりがちなNG対応

子どもに「やる気を出してほしい」と思うのは、どの保護者にとっても自然な願いです。
しかし、その思いが強すぎるあまりに、逆に子どものやる気を奪ってしまうような行動を取ってしまうことがあります。
ここでは、私自身の実体験や、周囲で見てきた例を踏まえて、「これはやめたほうがいい」と感じた対応を紹介します。
NG対応①:子どもが求めていないのに“行動の提案”をする
親として何かしら行動したくなる気持ちはよく分かります。
でも、子どもが自分から何も相談していないのに、「塾に行ってみたら?」「この教材やってみたら?」と提案するのは、逆効果になりがちです。
実際に私が中学生だった頃、多くの家庭でこうした光景を目にしました。
「周りがみんな塾に行っているから」「家で全然勉強しないから不安で」といった理由で、親の安心のためだけに子どもを塾に入れる。
でも、その結果どうなったかというと、
子どもは塾で友達としゃべるばかりで成績は上がらず、ただ高い授業料が消えていくだけというケースがたくさんありました。
本人の悩みや問題意識がない状態では、いくら手段を与えても“響かない”のです。
必要なのは「提案」より先に「共感」です。
NG対応②:「うちは〇〇塾に通わせてるから大丈夫」など“安心のための行動”を優先する
結局のところ一番大切なのは本人の意思です。
親が「あれをしてあげた」「これも与えている」ということで安心してしまい、本当に大事なこと――子どもが何を感じているのか、何を望んでいるのかに目が向かなくなることがあります。
「学習塾に入れる=やる気になる」とは限りません。
むしろ、タイミングを間違えると「面倒くさい」「親にやらされている」という感覚ばかりが強くなってしまい、やる気はますます離れていきます。
じゃあどうすれば? ── 子どもの「声」を聞いてから動く
本当に効果的なのは、子どもの話を丁寧に聞いてあげることです。
たとえば、子どもがこう言ったとします:
「数学の成績が伸びなくて、どうしたらいいか分からない」
このときに「じゃあ、近くの塾に体験だけでも行ってみる?」という提案をするのは、非常に有効だと思います。
本人が困っていて、自分の意思で改善したいと思っているからです。
親にできるのは、「子どもが自分で考える機会」をつくること。
そのうえで、「必要があれば手を差し伸べる」くらいの距離感が、やる気をつぶさない絶妙なバランスだと私は思います。
まとめ:先回りよりも、伴走者でいてください
親はつい、わが子が困らないようにと、いろいろなことを“先回り”して与えたくなります。
でも、子どもが自分で悩んで、考えて、決断するプロセスこそが、やる気を生み出す原動力なのです。
そのプロセスを、ただ横で見守り、時には励まし、そして必要なときにそっと手を差し伸べる。
それこそが、子どもの人生を尊重しながら、やる気を引き出す最良のサポートだと思います。
私の実体験を少しだけ
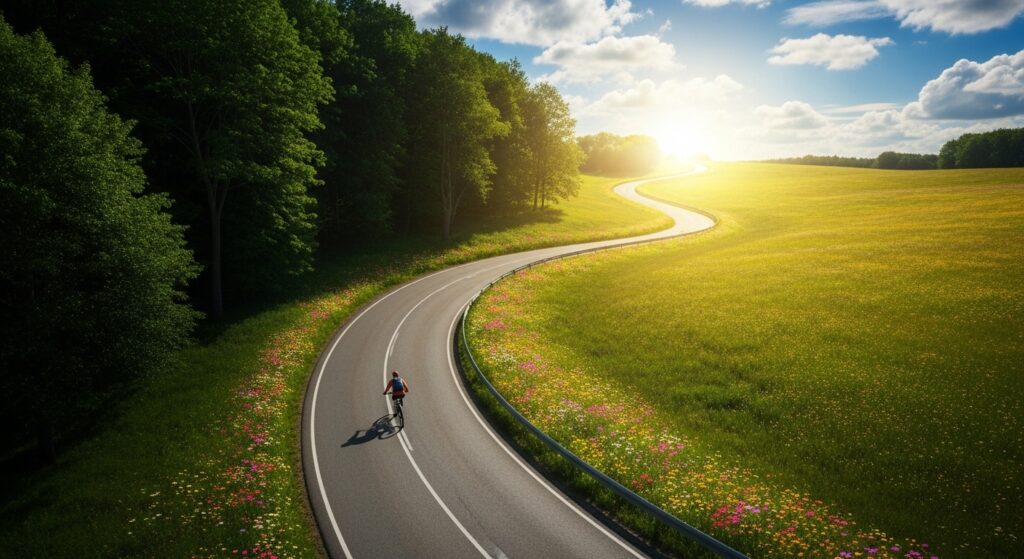
実は私も、全然やる気がない子どもでした
私が小学生〜高校1年生までの間、勉強に対して意欲的だったとはとても言えません。
テスト前だけは何とか勉強していたものの、それ以外の期間はほぼノータッチ。
課題も授業中にパパッと終わらせて、家で机に向かうことはほとんどありませんでした。
それについて、親からガミガミ叱られたこともありません。
「まあ課題くらいはやっておきなさいよ」と言われるくらいで、基本的には私の勉強に対して無理に介入することはなかったのです。
急に「やる気スイッチ」が入った
そんな私にも、転機が訪れました。
詳しくは下の記事で話しているとおりですが、高校2年生の春、自分の将来について少しずつ考えるようになり、「本気で勉強してみようかな」と思い始めたのです。
そして、親に「これからはちゃんと勉強する」と伝えたとき、返ってきたのはただ一言。
「頑張ってね」
その一言に、私は深く安心しました。
今まで無理に干渉してこなかった親が、私の気持ちを尊重し、そっと背中を押してくれた。
それだけで十分だったのです。
親が「やる気を出させる」ことはできない。でも、環境はつくれる
この経験を通じて私は、「やる気」というのは外から無理やり引き出すものではなく、自分の中から自然に芽生えるものだと強く感じました。
そして、その芽が出やすいように、静かに見守りながら土を耕してくれていたのが親でした。
- 勉強しろと強制しない
- 自分のタイミングを待ってくれる
- 意思を尊重してくれる
それが結果として、やる気が出たときにしっかりと自分で立ち上がれる土台になったのだと思います。
まとめと保護者へのエール

子どものやる気に悩むとき、つい「どうすればやる気になってくれるのか」と考えてしまいがちです。
でも、やる気というのは、外から無理やり引き出すものではありません。
私がこの記事を通して一番伝えたいのは、次のことです。
子どものやる気を無理に引き出そうとしないでください。
やる気が出るような環境を整え、そしてその気になったときには、しっかりとサポートしてあげてください。
やる気というのは、自分自身で「やろう」と思ったときにしか、本当の力を発揮しません。
そのとき、親がどう関わっていたか──それが、子どもにとって大きな差になるのです。
- 見守ってくれていたこと
- 話を聞いてくれたこと
- 必要なときにそっと手を貸してくれたこと
それらの積み重ねが、子どもにとっては「親に応援されている」という心の支えになります。
そして、その安心感が、勉強に向き合う強さにもつながっていくのだと思います。
お子さんが自分で「やってみよう」と思える日が来たときに「よし、応援しよう」と言える準備を、いま静かに整えておくことが、親にできる最も大きな力だと、私は信じています。
以上パンダでした。
関連記事はこちら↓


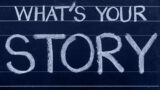



コメント