皆さんこんにちは、パンダです。
勉強してもすぐに忘れてしまったり、復習に追いつかないと感じたりしていませんか?
特に「復習のやり方が分からない」「どのタイミングで何をやればいいのか迷う」といった声は少なくありません。
成績が上がる人は復習サイクルやノートの活用を工夫し、人の記憶の仕組みに合った学習法を実践しています。
しかし、実際には「復習ってめんどくさい」と感じてしまい、なかなか継続できないという現実もあります。
この記事では、「勉強の復習が追いつかない!」と悩んでいる人に向けて、効果的な復習のやり方やタイミング、ノートの使い方など、勉強に役立つヒントを紹介します。
- 復習に追いつけない原因とその背景
- 効果的な復習のやり方とそのタイミング
- 続けやすい復習サイクルの工夫
- ノートや記憶の仕組みを活かした学習法
勉強の復習が追いつかない:原因と対策

- 復習 やり方 分からない人の特徴
- 効率的な復習サイクルを確立する方法
- 復習がめんどくさいと感じる心理とは
- 東大生が実践する復習のルール
復習のやり方 分からない人の特徴
復習のやり方が分からない人には、いくつかの共通する特徴があります。
まず大きな傾向として、「目的を持たずに復習している」ことが挙げられます。
つまり、どの範囲をどの程度まで理解すればよいのかを明確にせず、ただノートを読み返したり問題を解いたりしているのです。
このような復習方法では、学習内容の定着につながりにくく、結果として「勉強しているのに覚えられない」と感じてしまいます。
また、「復習のタイミングを知らない」という点も見逃せません。
多くの人が、テストの直前になってから一気に復習をしようとしますが、人の記憶には『忘却曲線』という性質があり、時間が経つごとに急速に情報を忘れていきます。
そのため、学習直後の復習や、時間をあけた定期的な復習が必要になりますが、そうした計画を立てる習慣がない人は、記憶が定着しづらくなるのです。
さらに、「ノートの使い方が非効率」という特徴もあります。
復習に使うノートが読み返しにくかったり、必要な情報が整理されていなかったりすると、そもそも復習の際に何を見ればよいのか分からなくなります。
ノートをただ書き写すだけで終わってしまい、自分の言葉でまとめたり要点を絞ったりしていないケースが多いのも問題です。
これらの特徴に共通するのは、「復習を目的ではなく作業と捉えている」という点です。
この意識のままでは、いくら時間をかけても効果的な復習にはなりません。
復習のやり方が分からないと感じる場合は、まずは「何を覚えるべきか」「いつやるべきか」「どうまとめるべきか」といった復習の設計から見直すことが求められます。
効率的な復習サイクルを確立する方法
効率的な復習サイクルを確立するには、「学習した内容を忘れる前に繰り返す」という記憶のメカニズムを理解したうえで、計画的な復習を実践することが重要です。
具体的には、1日後・3日後・1週間後・2週間後と、段階的に復習のタイミングをずらしていく方法が効果的です。
これはエビングハウスの忘却曲線に基づいた手法で、人間の記憶が急速に失われていくことを前提に組まれたものです。
このような復習スケジュールを立てることで、記憶が定着しやすくなり、無駄な時間を減らすことができます。
特に、復習を「毎日の習慣」として組み込むことが大切です。
勉強を終えたその日のうちに簡単に振り返り、翌日に再確認し、さらに数日後にもう一度復習する。この流れを繰り返すことで、知識は長期記憶へと移行しやすくなります。
また、サイクルの中に「アウトプット」を取り入れることも効果的です。
例えば、覚えたことを誰かに説明してみる、問題を解いて確認するなどの方法が挙げられます。アウトプットは記憶を強化するだけでなく、自分の理解が曖昧な部分を発見する手がかりにもなります。
ノートの整理も忘れてはいけません。
復習時に必要な情報をすぐに見つけられるように、重要なポイントを箇条書きでまとめたり、色分けして視覚的に整理したりする工夫が効果を高めます。
効率的な復習サイクルとは、「いつ・どのように・どれくらい」復習するかを自分なりに確立することです。
初めから完璧なスケジュールを作る必要はありませんが、継続と調整を繰り返しながら、自分に合ったペースを見つけることが最も大切です。
復習がめんどくさいと感じる心理とは
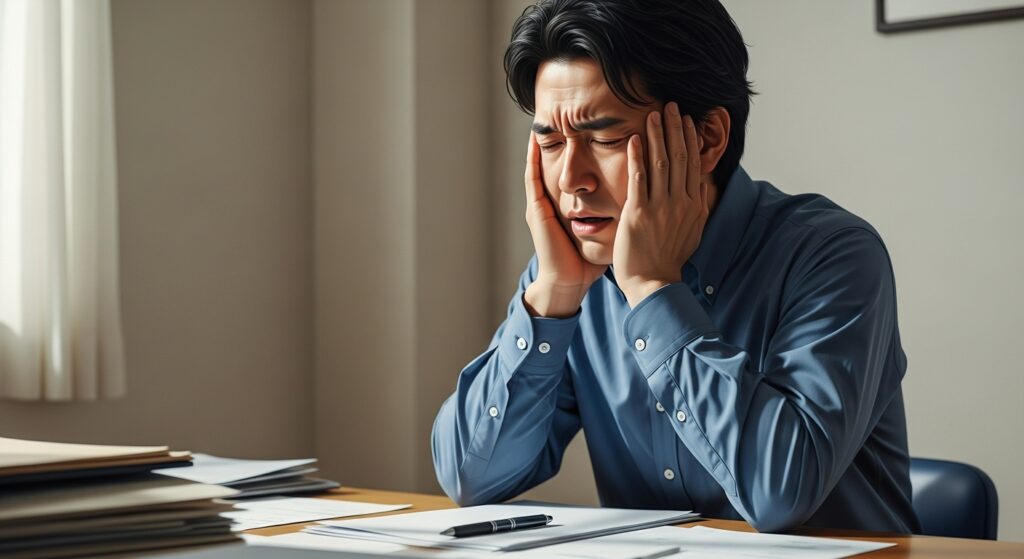
復習を「めんどくさい」と感じるのは、多くの人が経験するごく自然な感情です。
実際私もそのように感じていたころもありました。
復習って面白くないから後回しにしようとしていたのです。(当然成績は伸び悩みました)
その背景には、復習が「時間がかかる」「成果がすぐに見えない」「過去のことをまたやり直すのが退屈」といった心理的な要因があります。
とくに、すでに学んだ内容を再度確認する行為は、新しい知識を得るワクワク感がないため、やる気を維持しづらくなる傾向があります。
また、復習に対する「成功体験の欠如」も一因です。
つまり、復習したことで成績が上がった、理解が深まったという実感が少ないまま続けていると、「本当に意味があるのか?」と疑問を持つようになります。
これにより、復習の優先度が下がり、ますます「やりたくない」という気持ちが強まるのです。
さらに、復習に必要な準備や作業量が多すぎると、心理的ハードルが上がります。
ノートを引っ張り出して、範囲を確認して、問題集を開いて…という一連の流れが面倒に感じられるのです。
このようなときは、復習を「小さなタスク」に分解し、手軽に取り組めるようにすることが有効です。
例えば、1日5分だけ前日に学んだ内容を振り返る、クイズ形式で確認するなど、工夫次第で負担感を減らせます。
ここから分かるのは、「復習がめんどくさい」と感じるのは、決して根性や意志の弱さではないということです。
その多くは、やり方や環境の問題に起因しています。
復習を続けるためには、心理的な障壁を減らし、続けやすい仕組みを自分で作っていく必要があります。
めんどくさいという感情そのものを否定するのではなく、「どうすれば面倒に感じなくなるか」を考えることが、勉強を前向きに続ける第一歩になります。
合格者が実践する復習のルール
東大生や京大生などの難関大学合格者が実践している復習のルールには、「目的を明確にし、無駄を減らす」ための工夫が数多く見られます。
単に勉強時間を増やすのではなく、どのように取り組むかを重視している点が特徴です。
まず注目すべきは、「復習のタイミングを意識している」ことです。
合格者は新しく学んだことを、当日中に一度振り返るようにしています。
その後、1日後・3日後・1週間後と段階的に復習の機会を設け、記憶が薄れないよう計画的に学習しています。
これは人の記憶の性質を理解したうえで、忘れる前に定着させるための戦略です。
また、「自分で問題を作る」という方法もよく使われています。
これは単なる暗記にとどまらず、理解を深めるアウトプットの一種です。重要な概念や定義をもとに、なぜそうなるのか、どう活用できるのかを考え、自作の問題に落とし込むことで、記憶と理解を両立させています。
さらに、「復習ノート」を活用する傾向があります。
講義や授業で取ったノートとは別に、復習専用のノートを作成し、ポイントだけを簡潔にまとめておくのです。
必要な情報だけを集約することで、見返す手間が減り、効率的に記憶の確認ができます。
このように、合格者行っている復習には明確なルールがあります。
それは「記憶の性質に合わせたタイミングで」「無駄を省いた形で」「理解を伴う確認を行う」という3つの視点から成り立っています。
難しいことをしているわけではなく、誰にでも実践可能な工夫が多いため、ぜひ取り入れてみるとよいでしょう。
忙しくても勉強の復習が追いつかないことを防ぐ工夫

- 復習のベストなタイミングとは
- ノートの取り方で差がつく復習法
- 人の記憶の仕組みを活かした学習術
- 毎日のスキマ時間でできる復習習慣
- 勉強が継続できる環境づくりの工夫
復習のベストなタイミングとは
復習のタイミングによって、学んだ内容の定着率は大きく変わります。
適切なタイミングで復習を行えば、短時間でも高い学習効果が得られ、逆にタイミングがずれると、いくら時間をかけても覚えられないという状態になってしまいます。
まず最初の復習は、「学習直後」に行うのが理想です。
この段階では、記憶がまだ鮮明なうちに情報を整理することで、理解を深めることができます。
多くの場合、授業が終わったその日のうちに10〜15分程度の復習を行うだけでも、効果は大きく異なります。
次に行うべきは「翌日」です。
このタイミングで再度同じ内容を見直すことで、記憶がより強固になります。
ここで重要なのは、ただ読むだけではなく、簡単な問題を解く、口に出して説明してみるといった“アウトプット”の方法を取り入れることです。
その後は「3日後」「1週間後」「2週間後」など、少しずつ間隔をあけて復習していきます。このサイクルは“間隔反復”と呼ばれる学習法で、記憶の定着を促す科学的にも裏付けられた方法です。
ただし、これを完璧に守ろうとすると続けるのが難しくなってしまいます。
そのため、勉強スケジュールに復習時間をあらかじめ組み込んでおき、リマインダーなどを活用して自然に取り組める環境を整えると、継続しやすくなります。
このように、復習のタイミングは「すぐに・繰り返す・間隔をあける」の3点を意識することが大切です。タイミングさえ合っていれば、長時間の勉強よりもはるかに効果的な学習が可能になります。
ノートの取り方で差がつく復習法

復習の質を左右するのは、実は「ノートの取り方」にあると言っても過言ではありません。
ノートは単なる記録ではなく、復習のための“再学習ツール”です。そのため、見返したときに内容が理解しやすいノートを作ることが、復習効率を上げる鍵となります。
まず意識したいのは、「情報を整理すること」です。
授業中にそのまま黒板の内容を書き写すだけでは、後で読み返しても内容を思い出せないことが多くあります。
そこで、ポイントや要点を箇条書きにし、キーワードにはマーカーを使って視覚的に分かりやすく整理するようにします。
さらに、ノートの左側には「自分の言葉で説明を書くスペース」を設けると効果的です。
これはコーネル式ノート術という方法にも通じており、自分で内容を言語化することで、理解度の確認と記憶の強化が同時に行えます。
復習時には、ノートを読み返すだけでなく、「このページの内容を3分で説明できるか」といったチェック方法を取り入れると、学習の質がさらに上がります。
これにより、単なる読み流しではなく、能動的な復習が可能になるのです。
また、ノートを用途別に分けることも重要です。講義の記録用ノートと、復習・まとめ用ノートを別に用意することで、復習時に必要な情報だけをすばやく取り出せるようになります。
こうした工夫が、時間の節約と集中力の持続につながります。
つまり、ノートの取り方を工夫することで、復習は「面倒な作業」から「成果が見える学習」へと変わります。
見返すたびに内容がスッと頭に入るようなノートを作れるようになれば、自然と学習のモチベーションも上がっていくでしょう。
人の記憶の仕組みを活かした学習術

人間の記憶には「忘れる」という性質があります。
これは決して悪いことではなく、脳が情報を取捨選択して処理するための自然な機能です。
しかしこの仕組みを理解し、上手に活用することで、学習の効果を飛躍的に高めることができます。
まず意識したいのは「エビングハウスの忘却曲線」です。
これは、新しく学んだことの多くが、時間とともに急激に忘れられていくことを示しています。
具体的には、1日後には約70%を忘れてしまうと言われています。
これを逆手に取れば、忘れる前に繰り返し復習を行えば、記憶の定着が可能になるということです。
また、短期記憶と長期記憶の違いも重要です。
短期記憶は一時的に覚えておくための領域で、容量が非常に限られています。
一方、長期記憶は情報を定着させる場所で、ここに情報を送るには「意味づけ」や「繰り返し」が効果的です。
例えば、ただ英単語を見て覚えるのではなく、例文とセットで覚えることで意味が関連づけられ、記憶に残りやすくなります。
さらに、脳は「視覚情報」と「感情」が結びついたときに強く反応します。
そのため、図や色分けを使ったノート作りや、印象に残るエピソードと一緒に学習することで、記憶がより深く定着します。
このように、記憶の仕組みを理解した上で学習に取り組めば、無理なく効果的に知識を身につけられるようになります。
ただ暗記するのではなく、「いつ・どうやって・なぜ覚えるか」に注目してみましょう。
毎日のスキマ時間でできる復習習慣
忙しい日常の中で、まとまった学習時間を取るのが難しいという人も多いかもしれません。
しかし、通学・通勤中や待ち時間などの「スキマ時間」を上手に活用すれば、効率的な復習が可能になります。
ポイントは、「短時間で完結できる内容」を用意しておくことです。
例えば、スマートフォンに要点をまとめたメモやアプリを入れておけば、ちょっとした移動中にも確認ができます。
1回あたり3〜5分でも十分です。
むしろ、集中力が続きやすい短時間学習は、記憶の補強に向いています。
また、「見るだけで思い出せるツール」も役立ちます。
暗記カードやマインドマップ、要点を箇条書きにしたノートなどは、繰り返し眺めるだけでも効果があります。
こうしたツールを持ち歩くことで、どこでも学習モードに入りやすくなります。
さらに、音声を活用する方法もあります。
自分で重要ポイントを録音したり、解説音声付きの教材を聞くことで、歩いている間や家事の最中でも復習が可能になります。
視覚だけでなく聴覚からのインプットを組み合わせることで、記憶の定着率も高まります。
スキマ時間の活用は、時間がない人ほど効果を感じやすい習慣です。
最初は負担なく始められるよう、1日1回、3分だけ復習すると決めることからスタートしてみてください。
こうした積み重ねが、着実な学習成果へとつながります。
詳しくは↓

勉強が継続できる環境づくりの工夫

学習を続けるうえで大切なのは、モチベーションだけではありません。
実際には、勉強に集中しやすい「環境」を整えることが、継続の鍵を握っています。
まず第一に、物理的な環境が学習に与える影響は大きいです。
机の上が散らかっていたり、スマートフォンが視界にある状態では、集中力は簡単に削がれてしまいます。
勉強を始める前に、机の上を整理整頓し、スマホは物理的に手の届かない場所に置くなど、シンプルな工夫が大きな違いを生みます。
次に、「学習ルーティン」を取り入れることも効果的です。
毎日決まった時間・場所で勉強を始める習慣を作ると、自然と集中できるようになります。
例えば、朝起きたら10分だけ前日の内容を復習する、夜寝る前にその日の学習内容を確認する、などシンプルなルールで十分です。
また、「人の目」を活用する方法もあります。ス
タディカフェや図書館といった静かな場所に行くことで、周囲に学んでいる人がいる状況が、自分のやる気を後押ししてくれます。
自宅で勉強する場合も、家族や友人に「今から30分勉強する」と宣言するだけで、行動に対する責任感が生まれ、継続につながります。
さらに、学習の成果が「見える化」されていることも重要です。
勉強した内容や時間を手帳やアプリに記録しておくと、自分の努力が可視化され、やる気が持続しやすくなります。
小さな達成感を積み重ねていくことが、長期的なモチベーション維持に役立ちます。
このように、勉強を継続させるためには、やる気だけに頼らず、「仕組み」と「環境」を整えることが重要です。続けやすい環境を作れば、学習はもっと自然で、前向きな習慣になっていきます。
勉強の復習に追いつかないと感じる人が知っておきたいポイント総まとめ
記事のポイントをまとめます。
- 毎日短時間でも復習の習慣をつけると記憶が定着しやすくなる
- 学習スケジュールを可視化することでやるべきことが明確になる
- 完璧主義をやめ、最低限の理解でも先に進むことが重要
- 苦手分野に集中しすぎず、得意分野の維持も意識する
- 時間のない日は5分だけでも学習に触れることが効果的
- 睡眠時間を削って勉強すると効率が下がるので避けるべき
- 先延ばしの原因を分析し、具体的な対策を立てる必要がある
- スマホ通知などの誘惑を減らして集中できる環境を作る
- 毎日「何を」「どれだけ」やったかを記録すると達成感が得られる
- 暗記よりも理解を優先し、応用力を高める学習が効果的
- 他人と比較せず、自分のペースを大切にする姿勢が必要
- 定期的に学習の振り返りを行い、やり方を見直すことが重要
- すべてを一人で抱え込まず、質問や相談を活用することも有効
- 予習と復習をバランスよく行い、理解の土台を固める
- モチベーションが落ちたときは目標を再確認して再調整する


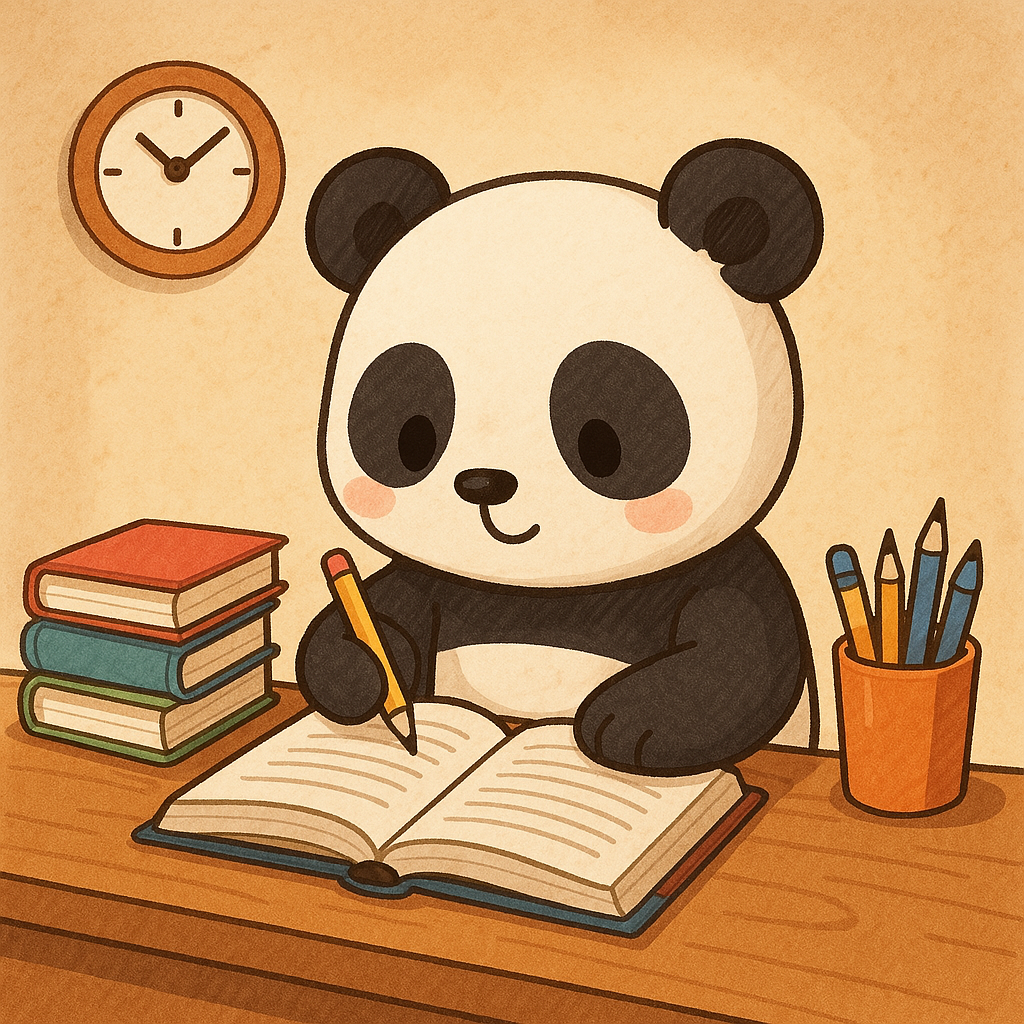

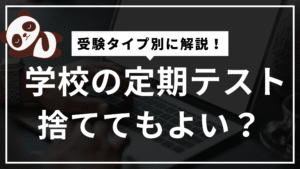


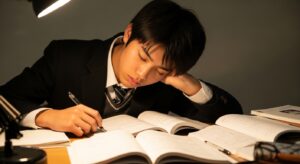


コメント