共通テスト地理で八割以上は欲しいけど、他の科目に時間を取られてなかなか対策できない、という悩みを抱えていませんか?
特に理系受験生にとって、地理は副教科になりがちです。
真面目に勉強しているのに模試で点数が伸びず、「このままで大丈夫かな」と不安になる気持ち、よくわかります。
でも安心してください。
最小限の努力で、最短で80点に到達する方法は存在します。
私自身、地理が苦手な受験生でしたが(高3の夏の共テ模試で37点を記録(笑))、インプットを最小限に抑え、アウトプットに特化した勉強法を実践することで、共通テスト地理で2年連続9割という安定した結果を出すことができました。
この記事では、私が実際に試行錯誤してたどり着いた、最も効率的な共通テスト地理の勉強法を全て公開します。
最後まで読んでいただければ、もう地理の勉強に悩むことはありません。
何を、いつから、どう勉強すればいいかが明確になり、自信を持って本番に臨めるようになるでしょう。
- 共通テスト地理の正しい勉強法と非効率な学習法
- 共通テスト地理の学習を始める最適な時期
- 知識量と資料の読み取り能力のバランス
- 高得点を目指す上での問題集の選び方
共テ地理勉強法:初めに知っておくべきこと
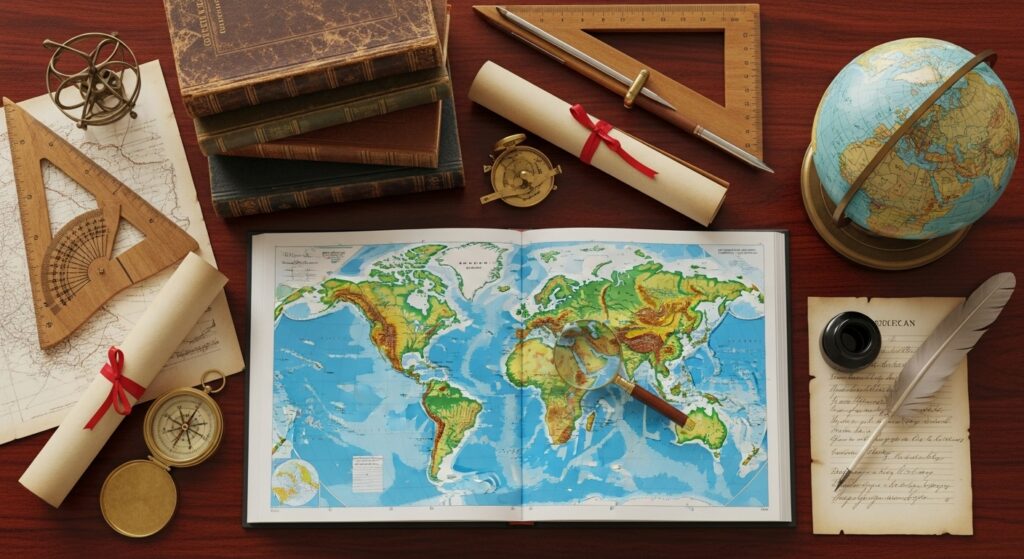
- 共テ地理の特徴と形式
- 完成までどのぐらいの時間がかかるのか
- いつから始めればよいか
- 模試や予備校の予想問題集に注意
共テ地理の特徴と形式
2025年度より、大学入学共通テストにおける地理の科目は、従来の「地理A」「地理B」が廃止され、新しい学習指導要領に基づく「地理総合、地理探究」へと一本化されます。
この変更は、単なる名称の変更にとどまらず、地理という科目に求められる力がより高度化・多様化したことを意味します。
新しい出題形式は、旧課程の地理Bで培われてきた思考力を基盤としつつ、地理総合で学習する「持続可能な社会づくり」や「地域調査」といった現代的なテーマが加わることで、より多角的な視点から地理的思考力を問う内容へと進化しています。
新課程の共通テスト地理は、従来の知識偏重型から、資料を正確に読み解き、論理的に思考する能力を重視する傾向がさらに強まると考えられます。
特に、グローバルな視点から現代社会の諸課題を分析する力、そして身近な地域における課題を発見し、解決策を考察する力が重要視されるでしょう。
以下に、新しい共通テスト地理の試験概要と傾向をまとめます。
| 項目 | 内容 |
| 科目名 | 地理総合、地理探究(旧地理Bベース) |
| 大問数/マーク数 | 大問6問/全30マーク |
| 主な出題形式 | 組み合わせ式(約6割)、8択、6択、正誤判定、4択 |
| 資料の使用 | 全設問に資料付き(地図、統計、表、複合資料など) |
| 出題分野 | 地球規模課題、地域調査、自然災害、エネルギー、都市変化、地誌など |
| 難易度 | 旧地理Bと同等かやや難化 |
出題形式の多様化は、新課程の大きな特徴の一つです。
特に「組み合わせ式」問題が増加傾向にあり、複数の選択肢の中から適切な組み合わせを選ぶ形式は、より正確な知識と判断力が求められます。
また、8択や6択問題、正誤判定型問題も頻繁に出題され、これらの問題では複数の資料や条件を比較検討し、総合的に判断する力が試されます。
すべての設問に地図やグラフ、統計表が添付されるため、情報を素早く正確に読み取り、解釈する練習が不可欠です。
与えられた資料から必要な情報を抽出し、それを基に思考を展開する能力が、得点に直結します。
出題分野は、地球規模の課題(例:気候変動、貧困、食糧問題)から、地域調査(例:地方の産業構造、人口動態)、自然災害(例:地震、津波、気象災害)、エネルギー問題、都市の変化、そして特定の地域の地誌まで、非常に広範囲にわたります。
このように、新課程の地理では、単なる知識の暗記だけでなく、「知識」と「資料分析力」、そして「思考力」を統合した総合力が要求されます。
特に地域調査に関する問題では、架空の地方都市のデータが提示され、その地形や産業の特徴、人口動態などを複合的に考察する問題が多く見られます。
これは、単に地名を覚えるだけでなく、その背景にある地理的要因を理解しているかが問われることを示しています。
全体的な難易度は、旧地理Bと同程度か、やや難化すると考えられています。
試験時間内に多くの情報を正確に処理するスピードも、得点の鍵を握る重要な要素となります。
対策のポイント
- 暗記中心から「資料読み取り演習」重視へシフトする:知識の暗記は基礎固めとして重要ですが、それ以上に多くの資料に触れ、読み解く演習が不可欠です。
- 因果関係や背景の理解を伴った学習:特定の現象を単体で覚えるのではなく、「なぜそれが起こるのか」「どのような影響があるのか」といった因果関係を深く理解することが求められます。
- 実際の試験形式(組み合わせ式・多資料)での演習量を増やす:過去問や予想問題集を解く際は、共通テスト特有の形式に慣れることを意識しましょう。
完成までどのぐらいの時間がかかるのか

共通テスト地理の学習にかかる時間は、現在の知識量や目標とする得点によって大きく変動します。
あくまで目安ですが、基礎から学習を始める方が共通テストで安定して80点程度を獲得するためには、最低でも3ヶ月から半年程度の学習期間を確保するのが望ましいでしょう。
地理は単に暗記するだけでなく、知識と論理的な思考力をバランス良く養う必要があるため、短期間で完璧な状態に持っていくのは難しい科目です。
計画的に学習を進めることが、高得点への近道となります。
学習の初期段階では、インプットに重点を置き、地理の全体像を把握します。
その後、早い段階から問題演習を重ねてアウトプットの質を高めていくという流れが非常に効果的です。
多くの受験生がインプットに時間をかけすぎる傾向にありますが、地理においては、問題演習を通じて知識を定着させるという意識を持つことが大切になります。
いつから始めればよいか
共通テスト地理の学習をいつから始めるべきかは、受験生の状況によって判断が異なります。
国公立大学を目指す理系受験生で、共通テストのみで地理を選択する場合、高3の秋ごろからでも地理にしっかり時間を取れば間に合います。
ただし、これは数学や理科といった主要科目の学習がすでに十分に仕上がっていることが前提となります。
より高得点の安定を目指すのであれば、遅くとも高校3年生の夏には学習を開始し、他の科目と並行して地理の基礎固めを始めるのが安心です。
私は共通テストのみの地理で、高校三年生の夏ごろに一度触れておいて、秋ごろから本格的に勉強を始めました。
一方、文系の受験生で、共通テストだけでなく、私立大学や国公立大学の二次試験でも地理を使用する場合は、より早期の準備が求められます。
理想的なのは高校2年生の夏から学習を開始し、基礎固めにじっくり取り組むことです。
遅くとも高校2年生の冬までには、系統地理と地誌の内容を一通り学習し終え、高校3年生からは過去問演習や実践的な試験対策に集中できる状態にしておくことが理想的と言えるでしょう。
模試や予備校の予想問題集に注意

共通テスト地理の対策を進める上で、模試や予備校の予想問題集は参考にしないようにしてください。
これらの問題集は、地理に限ってですが、本試験と比較して出題形式や問題の質が大きく異なるケースがしばしば見られます。
特に、予想問題集では、実際には問われないような細かい知識まで出題されることが多く、こうした問題に振り回されると、効率的な学習が阻害されてしまいます。
模試や予想問題集を解いて点数が伸びなくても、焦る必要はありません。
まずはスタディサプリなどの質の高い教材や、過去問を中心とした学習で基礎を固めることが大切です。
特に共通テストの地理では、問題の形式や思考方法に慣れることが重要であり、過去問を繰り返し解くことが最も効果的な対策となります。
共テ地理の9割達成への勉強方法
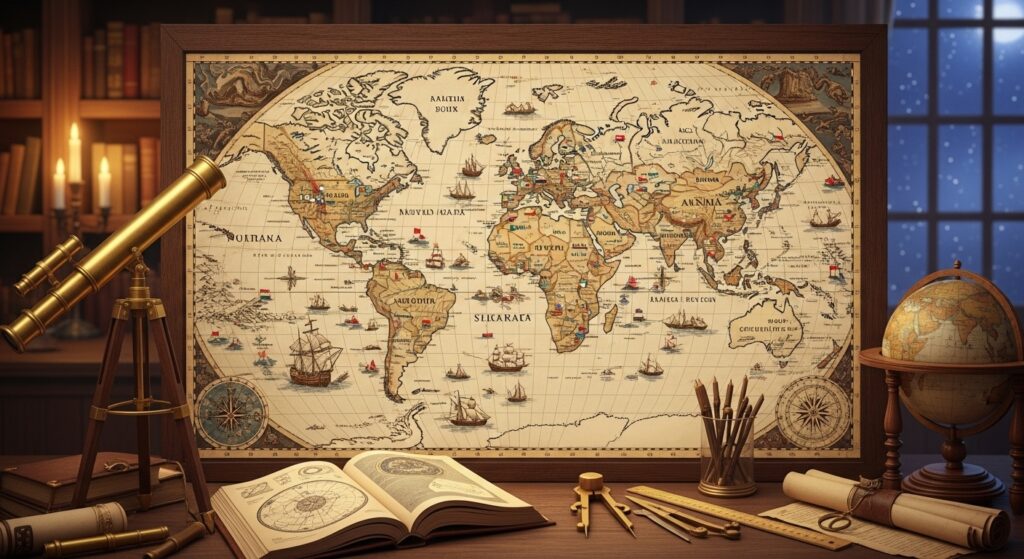
ここからは、いよいよ共通テスト地理で9割の得点を達成するための具体的な勉強法を解説します。
- 勉強方法の全体像:最低限の知識と思考方法をに身に着ける
- インプットにオススメの方法:スタサプの授業を受ける
- アウトプットにオススメの方法:達人地理のホームページで過去問演習
- 効率的な共テ地理の勉強法をまとめる
勉強方法の全体像:最低限の知識と思考方法をに身に着ける
共通テスト地理で高得点を狙うには、まず「最低限の知識をインプット」し、その後「ひたすら問題を解いてアウトプットする」という流れが非常に重要です。
多くの受験生は、地理を歴史科目と同じように捉え、教科書や参考書の内容をすべて完璧に暗記しようと試みます。
しかし、共通テストの地理では、すべての知識を網羅的に覚えてから問題演習に取り組む必要はありません。
地理の学習においては、まずは一通り授業を受け、地理の世界観や全体像をざっくりと把握することから始めましょう。
この段階では、細部にこだわって時間をかけすぎる必要はありません。
全体像が掴めたら、すぐに共通テスト形式の問題に挑戦してみてください。
問題を解く中で「この知識が足りない」「この分野が苦手だ」と気づいたときに、授業に戻って復習すれば十分です。
この「インプット→アウトプット→再インプット」というサイクルを繰り返すことで、知識を定着させると同時に、思考力や初見の資料を読み解く能力を効果的に鍛えることができます。
知識のインプットとアウトプットのバランス
地理の学習において、知識のインプットとアウトプットのバランスは非常に重要です。
インプットだけを完璧にしても、共通テストで高得点を取ることはできません。
その理由は、共通テストでは教科書に載っていない初見の問題や資料が数多く出題されるため、最終的には「問題を解く力」が点数を左右するからです。
映像授業を一周見終えたら、すぐに問題演習を始めることを強く推奨します。
問題を解くプロセスを通じて、自分がどの知識を理解できていないか、どのような思考プロセスが求められているのかが明確になります。
これにより、次にインプットに戻る際も、学習のポイントが絞られ、非常に効率的に学習を進めることができるでしょう。
インプットにオススメの方法:スタサプの授業を受ける

共通テスト地理のインプット方法として、私が強くオススメしたいのはスタサプの達人先生の授業です。
この授業は、共通テストに出題される部分に特化して解説してくれるため、無駄な知識に時間を費やすことなく、効率的に学習を進められます。
さらに、問題を解きながら知識を押さえていくので、思考力も同時に身に着けることができます。
そして最大の魅力は、過去問演習の際、達人先生の解説がyoutubeや達人地理というサイトに上がっていることです。
共テの地理は思考の問題が多いので、どのように考えて問題を解くかが、参考書や先生によって異なります。
しかし、その点、達人先生はセンター試験と共テの過去問のほぼすべての解説を用意してくださっているので、統一した方法で問題を解くことができるようになり混乱しません。
市販の参考書には、共通テストではほとんど問われないような細かい知識まで網羅的に記載されているものも少なくありません。
しかし、達人先生の授業で得られる知識だけでも、9割の得点を安定して獲得することが十分に可能です。
実際に私は達人先生の授業と過去問の解説により、二年連続地理で9割を取っています。
特に、他の主要科目の勉強にも時間を割きたい理系の受験生にとって、無駄な知識を徹底的に排除したこの学習法は、最短ルートで高得点を目指すための強力な武器となります。
【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座アウトプットにオススメの方法:達人地理の解説で過去問演習

スタディサプリの授業で必要最低限の知識をインプットしたら、次はアウトプットの段階です。
アウトプットの教材として最も推奨されるのは、共通テストとセンター試験の過去問です。
スタディサプリの達人先生は、自身のサイトであるたつじん地理やyoutubeで過去問の丁寧な解説を提供しており、スタディサプリで学んだ知識と思考方法を過去問に当てはめ、一貫した方法で問題を解く練習ができます。
共通テストの地理は、近年の科目名変更があったものの、センター試験の過去問も演習に十分活用できます。
特に、センター試験は共通テストの土台となっているため、良質な問題に多く触れることが可能です。
過去10年分の過去問を少なくとも2周することを目安に、計画的に演習を進めることで、問題形式に慣れ、本番での対応力を飛躍的に高めることができるでしょう。
効率的な共通テスト地理の勉強法をまとめる
この記事のポイントをまとめておきます。
- 共通テスト地理は思考力と資料の読み取りが鍵
- 一問一答や穴埋め問題集は非効率な学習法である
- 完璧なインプットは目指さず全体像を素早く掴む
- 模試や予備校の予想問題集に頼りすぎない
- 過去問演習で初見の問題を解く力を養う
- スタディサプリの達人先生の授業で無駄なく知識を習得する
- 苦手分野を特定し重点的に克服することが大切である
- 最低でも高校3年生の夏までに学習を始めるのが望ましい
- 過去10年分の過去問を2周することを目標にする
- 過去問演習では時間配分を意識して取り組む
- 資料の多い問題では設問を先に読む習慣をつける
- 知識のインプットと問題演習のサイクルを回す
- 独学でも9割の得点を十分に狙うことができる
- 知識の暗記と思考力のバランスが重要である
- 効率的な共通テスト地理の勉強法で高得点を狙う


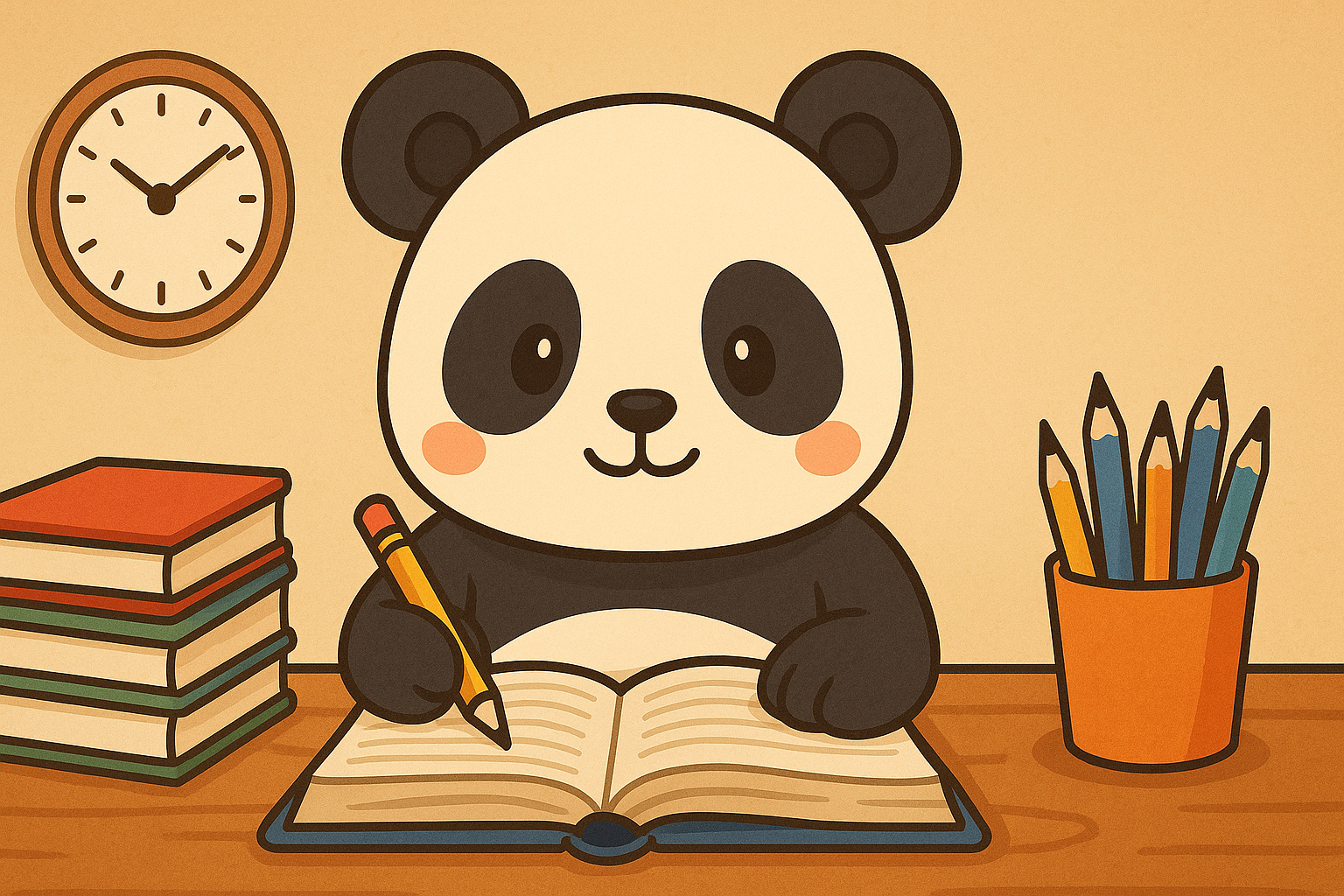


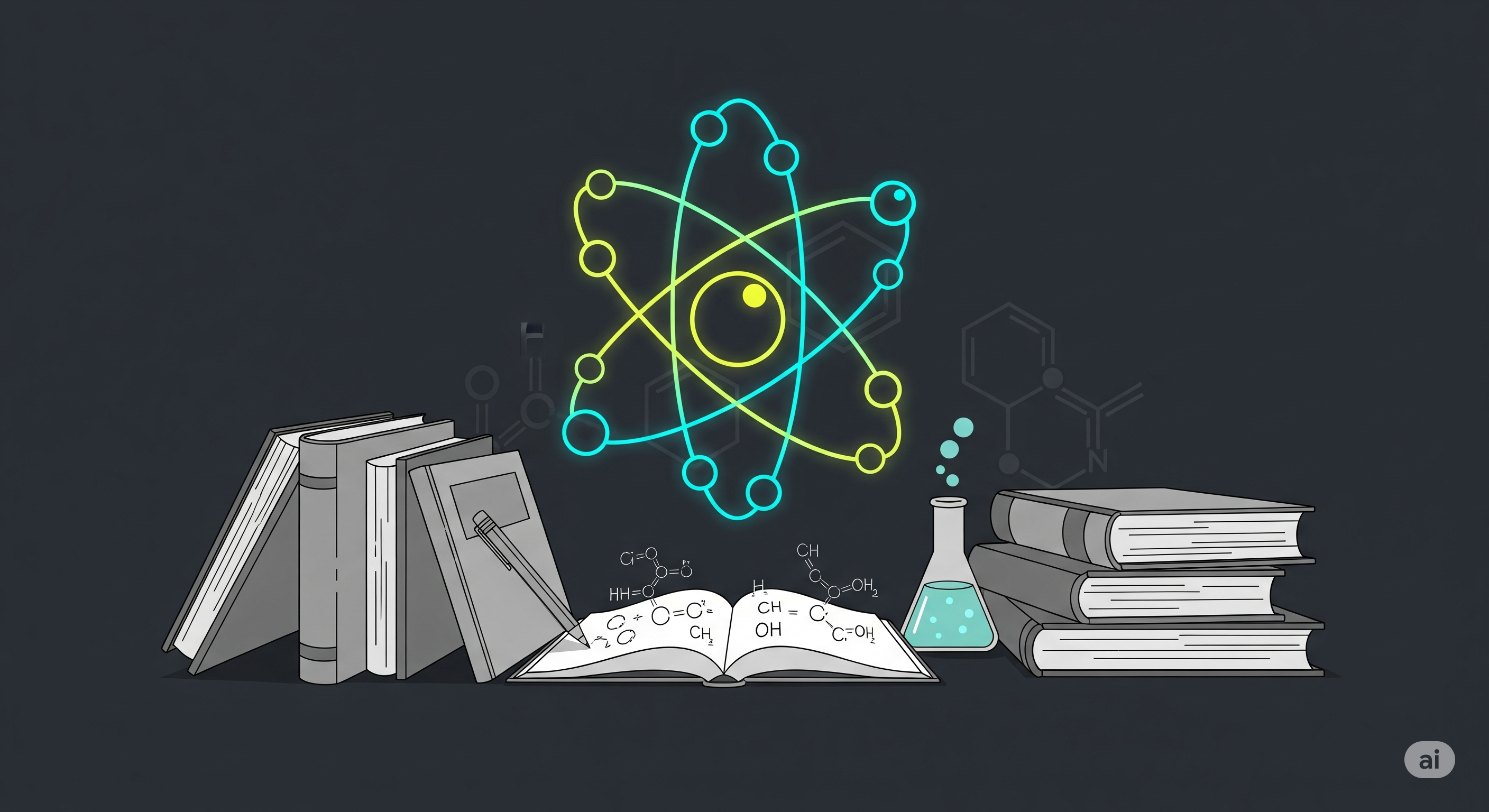
コメント