皆さんこんにちはパンダです。
「過去問って、いつから始めるのが正解?」
「何年分くらいやれば足りるの?」
「過去問の正しい使い方が分からない!」
など過去問の活用法について悩んでいませんか?
そこで今回は過去問の活用法というテーマで「過去問っていつからやるべき?」や「何年分やればよいの?」など疑問を解決するようなお話をしていこうと思います。
今回の記事を読むことで自身に最適な過去問の使い方が分かり合格にぐっと近づくと思います!

過去問をうまく使おう!
過去問を解く目的は?

まず初めに過去問を解く目的を挙げていきたいと思います。
というのも目的によって始めるべき時期ややるべき量が変わるからです。
過去問を解く目的は大きく分けて以下の三つに分けられます。
- 問題の傾向を把握する
- 問題の形式に慣れる
- 自身の学力を測り、学力を伸ばす
このように三つの目的があるので目的に合った使い方をすることが必要です。
過去問をいつから・どのぐらい解けばよいか

過去問には三つの目的があることが分かったところで、次に目的ごとの過去問を始めるべき時期と取り組むべき量について話していきたいと思います。
問題の傾向を把握するために解くとき
志望校により問題の傾向が大きく違うので取るべき対策も当然大きく変わってきます。
例えば東大の英語は要約、文法問題、リスニング、長文読解、英文和訳、和文英訳のように考えうるすべての問題形式があります。
一方で京大の英語はだいたい和文英訳と英文和訳の二つだけです。
よって東大を目指す人はすべてをバランスよく鍛える必要がありますが、京大を目指す人は英文和訳と和文英訳に注力すればよいことが分かります。
このように問題によってとるべき作戦が変わってくるのでできるだけ早く傾向はつかんでおいたほうがいいです。
具体的には教科書レベルの問題が解けるようになったら手を付けるべきでしょう。
取り組むべき量についてですが、私は最新年度を2,3年分解くことをおすすめします。
まず、最新年度をおすすめする理由ですが、問題の傾向は大学によっては少しずつ変化しています。
よって問題の傾向を把握するという目的に照らし合わせると、最新年度のものが最も合理的な選択となります。
次に2,3年分解くことをおすすめするのは、単純に一年では傾向が分からないからです。
問題の形式に慣れるために解くとき
ここでの問題の形式に慣れるとは自身の実力を最大限発揮できるように時間配分、解く問題の選定をできるようになるということです。
問題を解き終わるごとに適切な時間配分だったか、解くべき問題をおとしていないかなどを確認し、改善するための作戦を考えていきます。
これは目指している大学のレベルによって変わってくるので、レベル別にお話ししたいと思います。
難関大学(旧帝大・早慶以上)を目指す人
このレベルの大学では、問題がかなり難しく、傾向も特徴的な大学が多いため、かなりの時間がかかります。
よって、できれば半年間は時間を確保したいです。遅くとも秋までには手を付けておくようにしましょう。
現実的にはあとは過去問を解くだけ!というレベルに到達することは、秋や夏には無理なので普段の学習と並行して行うことになります。
現役の人は土日などの時間があるときに少しずつ解いていき、慣れるようにしてください。
一般的な国立・中堅私立を目指す人
これらの大学は、典型的な問題を解けると合格点を取ることができます。
よって、難関大学よりも過去問の形式に慣れることに時間はかかりません。
とはいえ、三か月は時間を確保したいところです。
先ほども述べたように、後は過去問を解くだけ!というレベルに三か月前に到達するのは厳しい(特に現役生は)と思うので、過去問の演習は日々の学習と並行して行うようにしてください。
併願校の過去問について
第一志望の大学の演習がどれほど進んでいるかにもよりますが、私は併願校の過去問は一か月前からでも間に合うと思います。
というのも、一般的に併願校のほうが第一志望の大学よりも簡単であり、かつ時間をかけすぎると第一志望の大学への対策が不十分になってしまうからです。
また、中期や後期の試験の対策は前期試験が終わってからで問題ないです。
前期が終わると、だらけてしまう人も多いので、前期が終わってからきちんと対策を行ったので十分間に合います。
共通テストの過去問について
英語と数学以外は共テが迫ってきた、秋以降で問題ありませんが、英語と数学はもう少し早めに対策を始めておくことをおすすめします。
具体的には夏休みあたりに取り組むとよいと思います。
共テの英語の詳しい勉強方法が知りたい方は以下をチェック!

何年分解くか
解くべき量についてですが、これは全体で共通しています。
ズバリ目的が達成されたなら何年でも構いません。
ここで目的をもう一度確認しておくと自身の実力を最大限発揮できるように時間配分、解く問題の選定をできるようになるです。
この目的を達成することを最優先としましょう。何年解くということを目的にしてはいけません。
強いて目安を挙げるとすると10年分ぐらい解いてくるとペースがつかめると思います。
しかし変わった傾向の問題(京大の理科など)では慣れるのにそれ以上の年度が必要なこともあるので目的への達成度に応じて解く量は決めるという姿勢は忘れないでください。
自身の学力を測り、学力を伸ばすために解くとき
難関大の過去問は良問が多く過去問をこなすことで実力を養成することもできます。
しかしこの目的のためにいつから取り組むべきや何年分解くべきといった基準はありません。
というのも良問を解くという目的ならば参考書のほうが分野ごとによくまとまっており、さらに過去問には合格するために解けなくてもよいような捨て問も混じっているため、この目的のためだけに過去問を解くことは少ないからです。
特に一般的な現役の受験生であればこの段階に入る前に受験本番を迎えるのでそうでしょう。
よって一般的には他の2つの目的もこなすなかで同時に実力の養成もはかるという形になると思います。
しかし気を付けてほしいのは何度も言いますが過去問は全て解ける必要はないので自身の目標点に照らし合わせて演習するようにしてください。
目的ごとの過去問の使い方
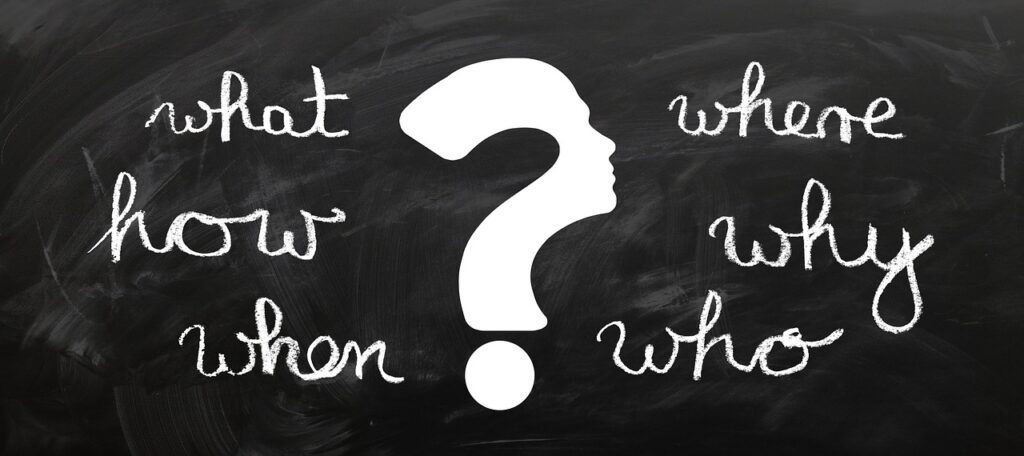
目的ごとに過去問の使い方は異なるのでそれぞれの場合について解説していきます。
問題の傾向を把握するために解くとき
意識しておいてほしいことは以下の通りです
- どのような問題構成になっているか
- 時間は厳しそうか、余裕がありそうか
- 問題の難易度の幅はどのぐらいか
以上のことを把握できると、力をいれて勉強するべきところが分かると思います。
例えば、英語で英文和訳と和文英訳しか出ず、時間的に余裕があるが、問題の難易度の幅が大きいといった場合があるとします。
この場合には、特に英文和訳と和文英訳の勉強に力を入れて、速読力よりも精読力を鍛え、さらに問題はどれが簡単か分からないので、分からない問題があれば飛ばして次に行くという対策をとるとよいことが分かります。
問題の形式に慣れるために解くとき
ここでの目的は自身の実力を最大限発揮できるように時間配分、解く問題の選定をできるようになることでした。
よって以下のことを意識してください
- 問題ごとにどのように時間を割り振るか
- どの順番で解くことが最も良いか
- 解いたのちに本当は解けたのに時間配分がうまくいかなかったせいで落としたところないかを振り返る
上の三つの事項を考えながら、演習を続けていくことで自身の実力が最大限出せると思います。
自身の学力を測り、学力を伸ばすために解くとき
この目的では過去問集を他の問題集と同じように取り組んでいきます。
すなわち、解けなかった問題の解説を読み、理解して、時間を空けてから復習します。
とはいえ、過去問の中には解けなくてもよい捨て問が混じっていることも多いので、あまり一つの問題に執着しないようにしましょう!
オススメの過去問集(赤本?青本?その他?)
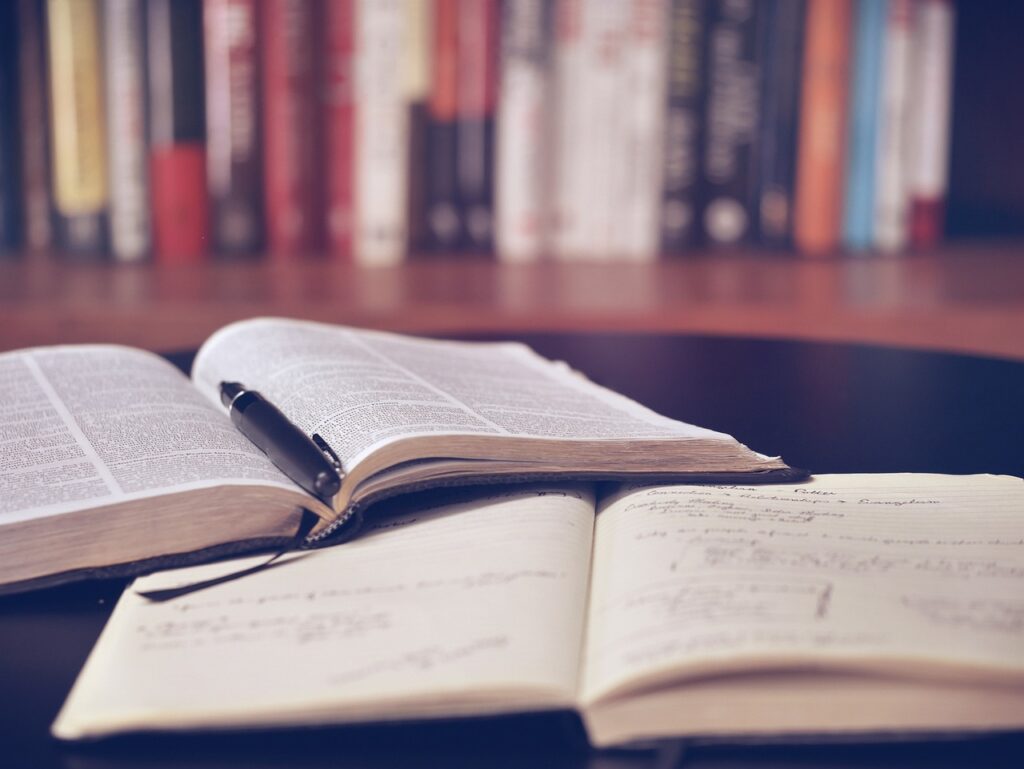
世の中には様々な過去問集が出版されています。
それぞれの特徴を語っていくと、とても長くなるのでパターンごとに私のオススメを書いておきます。
- 青本が出ている大学で周りに相談できる人がいる場合→青本
- 周りに相談できる人がいない場合→添削がついているZ会の講座
- 青本もZ会の講座もない場合→赤本
- 共通テスト→赤本か黒本の好きな方
個人的に青本は解説が赤本よりも丁寧なことが多いので、オススメです。
また周りに相談できる人がいない場合は添削が受けられないので、Z会の講座をオススメしています。
私も英語はZ会の講座を取っていたのですが、添削が結構丁寧でとてもためになりました。
まとめ
以上の内容を表にしてまとめておきます。
| 目的 | 始める時期 | 解く量(目安) | 使い方・意識する点 | おすすめ参考書 |
|---|---|---|---|---|
| 問題の傾向を把握する | 教科書レベルが仕上がったら早め | 最新年度の2〜3年分 | ・出題形式、時間配分、難易度の幅を確認 ・力を入れるべき対策を明確にする | 青本(あれば) なければ赤本 |
| 問題の形式に慣れる | 難関大:半年前〜 中堅大:3か月前〜 | 目的達成まで(10年分が目安) | ・時間配分・解く順番を決める ・復習で改善点を探す ・本番を想定して演習 | 青本(丁寧な解説) 添削ありならZ会講座 |
| 学力を測り、学力を伸ばす | 特に決まりなし | 達成度に応じて調整 | ・良問を問題集感覚で解く ・解説を理解し、復習する ・捨て問にこだわらない | Z会講座 or 解説の充実した問題集 |
| 併願校対策 | 試験の1か月前 | 数年分(過去3年程度) | ・第一志望に支障がない範囲で演習 ・効率的に解き、傾向をつかむ | 赤本 |
| 共通テスト(英・数)対策 | 夏休み頃 | 必要なだけ(私は10年分解いた) | ・形式と時間に慣れるために早めに演習 | 赤本 or 黒本(好みで選択) |
| 共通テスト(その他科目) | 秋以降 | 必要なだけ | ・基本的な形式確認を中心に演習 | 赤本 or 黒本 |
過去問は志望校合格のために、必須のツールです。
うまく使って合格にグッと近づきましょう!
以上パンダでした。

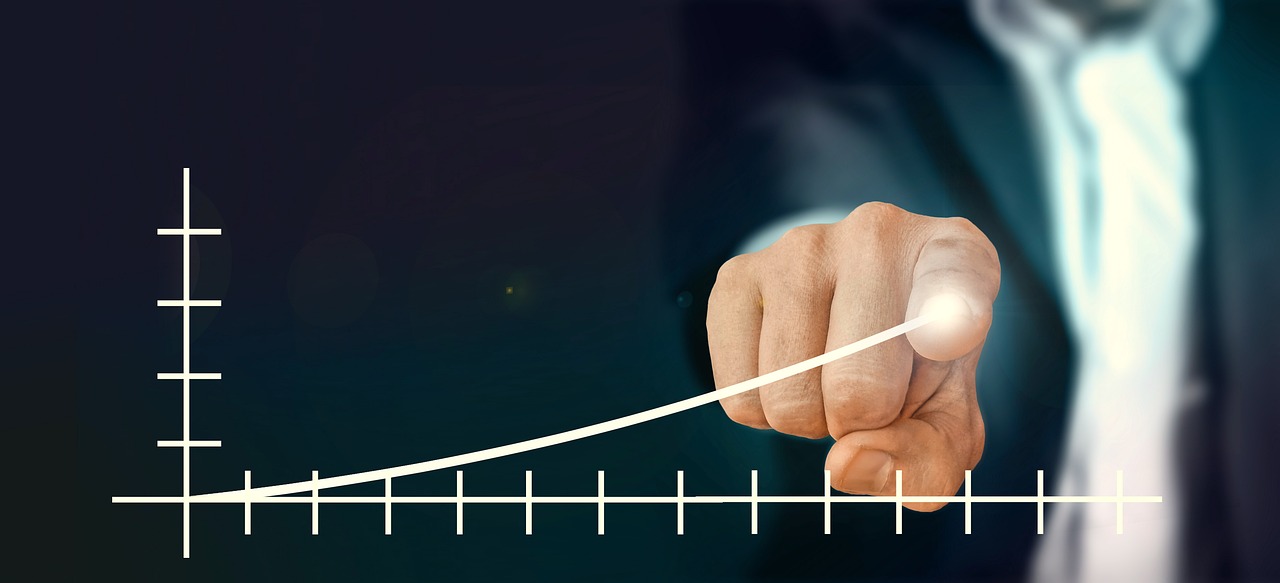
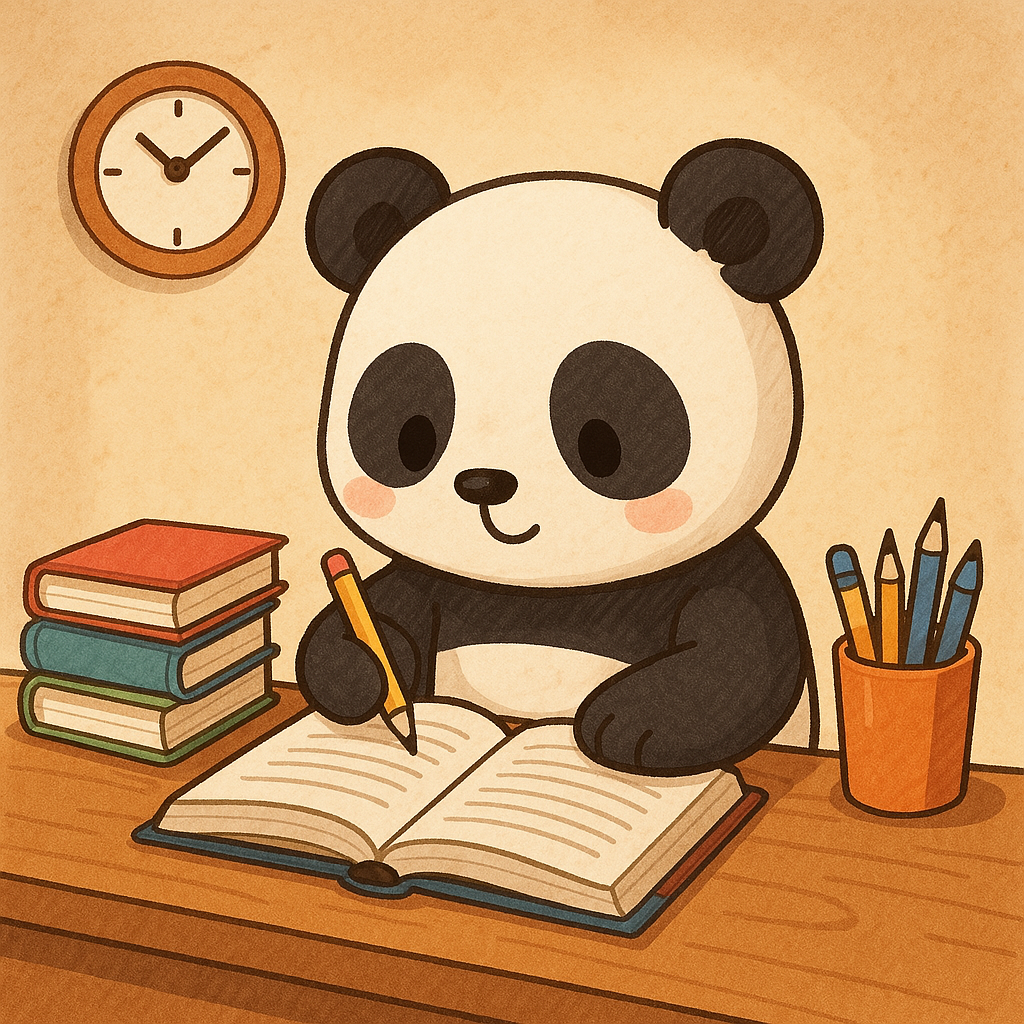






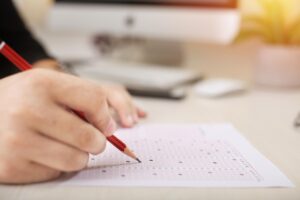
コメント