みなさんこんにちは、パンダです。
私は現役時に京都大学を受験して不合格となり、その後1年間の宅浪生活を経て無事に合格を果たしました。
今回は、そんな私が宅浪中に数学をどのように勉強していたのか、1年間のスケジュールに沿って詳しくお話ししていきます。
具体的にどのような参考書をどのように使っていたのかまで解説します!
独学や宅浪での受験勉強に不安を感じている人、スケジュールの立て方に悩んでいる人には特に参考になる内容になっていると思うので、ぜひ最後まで読んでみてください!
現役時点での数学の実力

まず最初に、現役の時点での自分の実力をお伝えしておきます。
正直、数学は得意でも苦手でもない中間層といったところで、解法暗記に偏っていて応用力が不足していました。
そんな中で、宅浪の1年を通してじっくり基礎からやり直し、最終的には京大模試で平均6〜7割、良いときには8割超えを取れるようになりました。
それでは、月ごとの具体的な勉強内容を見ていきましょう。
【4月〜5月】基礎の徹底と見直し期間
まずは現役時代の復習からスタート。使用したのは、以前から使っていた網羅系参考書『NEW ACTION LEGEND』。
この時期に意識していたのは、解法の暗記から脱却し、「なぜこの解法が出てくるのか?」という発想のプロセスを理解することでした。
そしてこの参考書は思考のプロセスが初めに明記されているのでそうした勉強がとても行いやすかったです。
一度覚えた問題でも、もう一度じっくり考え直し、発想の筋道を確認することで、実践力が徐々に身についてきました。
現役の時にどれほど解法を覚えることだけに必死になっていたかを実感し、反省しました。
【5月中旬〜6月】実戦演習スタート
ここから演習量を増やしていきました。使った教材は以下の2冊:
- 『数学Ⅲスタンダード演習 』
- 『文系プラチカ 数学ⅠAⅡB』
現役時代にⅠAⅡBの演習はそれなりにやっていたので、オーバーワークにならないようプラチカを選択。
一方、数学Ⅲの演習が不足していたと感じていたので、スタンダード演習でしっかりと演習量を確保しました。
これらの参考書に取り組んだ目的は、取れなければいけない基本問題と合否を分ける標準問題を取れるようにすることです。
ただ、今振り返るとⅠAⅡBもプラチカでなく新スタでじっくりやっておけば良かったなと感じています。
結局受験で最も重要なのは「標準問題を確実に取る力」です。応用よりもまず標準を確実に。
スタ演・プラチカの使い方と解法ノート
シンスタは解説がやや簡素なので、ただ読むだけでは力がつきにくいです。そこで、
- 解答を読むだけでなく「なぜこの解法になるのか?」を自分なりに言語化
- 重要な考え方やテクニックは「解法ノート」にまとめる
- 一般化して他の問題にも応用できるように整理する
といった方法で演習を行っていました。
1周目は普通に解き進め、2周目は間違った問題を重点的に復習、3周目は頭の中でイメージトレーニング。このサイクルがかなり効果的でした。
解法ノートの作り方は以下を参考にしてください。

【7月〜8月】思考力を鍛える夏、「入試数学の掌握」に挑戦
ずっとやってみたかったけど手が出なかった参考書『入試数学の掌握(赤・青・緑)』に挑戦。噂通り難易度は高いですが、解説は非常に丁寧で、数学に対する見方が根本から変わった感覚がありました。
特に、
- 赤:どの大学にも通じる思考法
- 青:東大でよく出る通過領域の攻略
- 緑:京大志望者にとって有効な図形問題が豊富
という特性があり、分野横断的な視点を持てるようになったのは大きな収穫でした。
難しい問題が多いので、解けなかったら解説を熟読し、「思考プロセスを読む」ような使い方をしていました。
数学で点を取らないといけない京大志望の人は赤と緑を、同じく数学で点を取らないといけない東大志望の人は赤と青をすることをおすすめします。
現役で時間がないという人は休憩時間の読み物として活用するのもおすすめです。
【8月下旬〜9月】過去問演習期に突入!
夏の後半からは、いよいよ京大の過去問演習へ。
現役時に15年分解いていたので、誤答だった問題だけをもう一度解き直し、過去問集に残っていた10年分を初見で演習しました。
使ったのは青本(駿台)。理由は、解説が丁寧だから。
ただし、それでも市販の過去問集はやや解説が簡素なため、淡白な解説に慣れておくことも重要です。スタ演やプラチカなどでそれに慣れていたのが役立ちました。
過去問集の問題の解き方はこれまでと同じで、まず問題を解いてみて、分からなかったら解説を見て、なぜその解法が思いつくのか考え、それを解法ノートにまとめていきました。
【10月〜11月】過去問・参考書の総復習
この時期は、これまでに使った参考書や過去問の「総復習」をしていました。現役時代に使っていた以下の教材も活用:
- 『ハイレベル数学の完全攻略』
- 『世界一わかりやすい 京大の理系数学合格講座』
時間を空けて再度取り組むことで、以前は見えなかった視点が見えてくることもありました。特に「この鉄則はあの問題にも応用できるな」といった気づきがあり、解法ノートがどんどん洗練されていった印象があります。
【12月〜共通テスト直前】感覚維持と軽めの演習
共通テスト前は数学にそこまで時間は割けませんでしたが、感覚を鈍らせないように、以下を毎日少しずつこなしていました:
- 『新数学演習』(大学への数学)
- 『京大入試数学数学51年の軌跡』
1日2〜3問を目安に、演習と復習を並行。共通テスト対策は模試中心で、二次対策の延長で十分対応できるという考えでした。
このころから演習の方法を少し変えて、問題を考えて分からなかったらすぐに答えを見るのでなく、解法ノートを見て使える解法がないか確認してから、答えを見るようにしていました。
そうすることで解法ノートの復習にもなり、自身の言葉でまとめた解法がより実践的なものとなっていきました。
【共通テスト後〜本番直前】仕上げ期間
最後の30日間ほどは、
- 解法ノートの再確認
- 間違った問題の復習
- 新数学演習&京大過去問からのピックアップ演習
を組み合わせて1日3問程度のペースで進めていました。
この時期は各教科のバランス調整が必要になりますが、数学については、自分の鉄則が本番でちゃんと機能するか確認するという意味での演習を意識しました。
まとめ
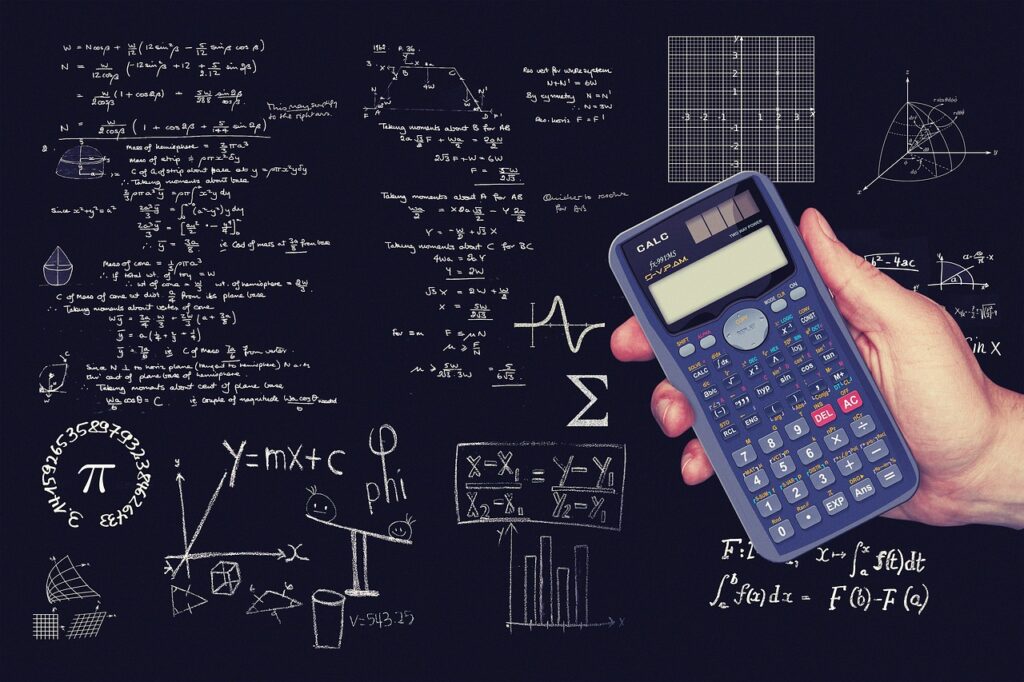
以上が、僕の宅浪時代の数学の1年間のスケジュールです。
自分に合った教材を使いつつ、「なぜその解法になるのか」を徹底的に考える。これを繰り返すことで、京大レベルの数学にも対応できる力が養われました。
数学全体の勉強法については、別の記事でも詳しく紹介しているので、そちらもぜひチェックしてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました。
宅浪や独学で頑張っている皆さんの参考になれば嬉しいです!
以上パンダでした。


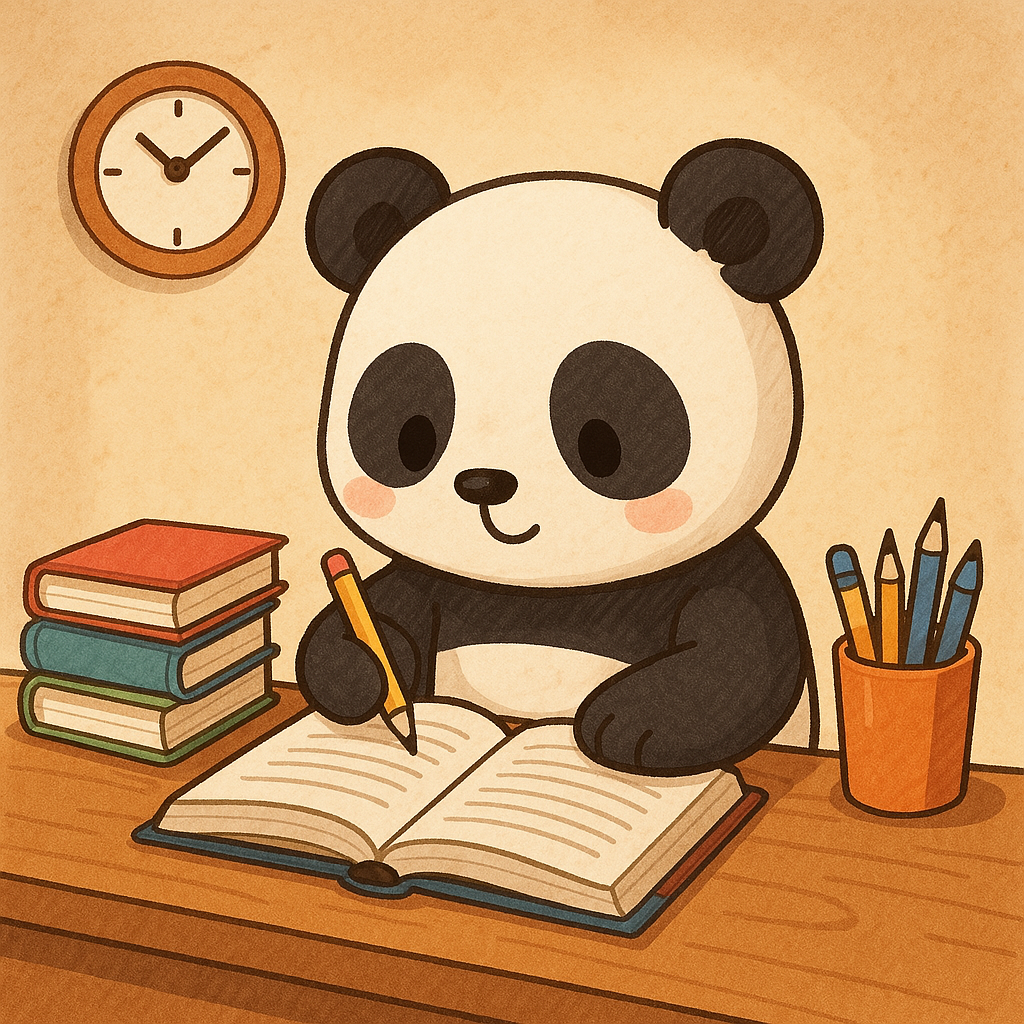


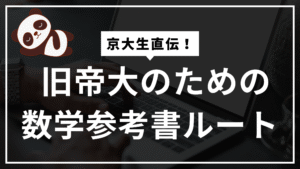


コメント