共通テストで60パーセントの得点率を目指しているものの、具体的にどのような勉強法から始めれば良いのか、どのぐらいの期間をかければ目標に到達できるのか分からず悩んでいませんか。
また、共通テスト6割という得点が、どれほどの難易度を持つのか、そしてその得点率で合格できる私立大学や合格できる国立大学が実際にあるのか、といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、そのような疑問に寄り添い、共通テストで60パーセントを獲得するための具体的な戦略を、偏差値の目安から科目別の対策、そして必要な学習期間まで網羅的に解説します。
この記事を読むことで以下の点が分かります。
- 共通テストで60パーセントの難易度や偏差値の目安
- 60パーセントで合格が狙える大学
- 60パーセントを達成するための具体的な勉強法
- 60パーセント達成までにかかる時間の目安
共通テストで60パーセントを目指すには

共通テスト6割の難易度は
共通テストで6割の得点率を達成することは、決して簡単なことではありませんが、多くの受験生にとって現実的な目標とされています。
この得点率がどのくらいのレベルに相当するかを理解するためには、過去の共通テストの平均点データを参照するのが有効です。
共通テストの実施団体である大学入試センターの発表によると、多くの教科・科目において、平均点は60点前後で推移しています。
例えば、900点満点の総合点では、多くの予備校が発表する予想平均点も500点から550点前後に設定されることが多く、6割である540点はまさに平均的な水準であると言えます。
この平均点のデータは、共通テストが、単なる知識の暗記だけでなく、思考力や応用力を問う問題も含まれていることを示唆しています。
したがって、6割の得点を目指すことは、出題傾向を正確に把握し、基礎知識をしっかりと定着させた上で、応用問題にも対応できる力を身につけることが求められるレベルであると考えられます。
平均点からわかる偏差値
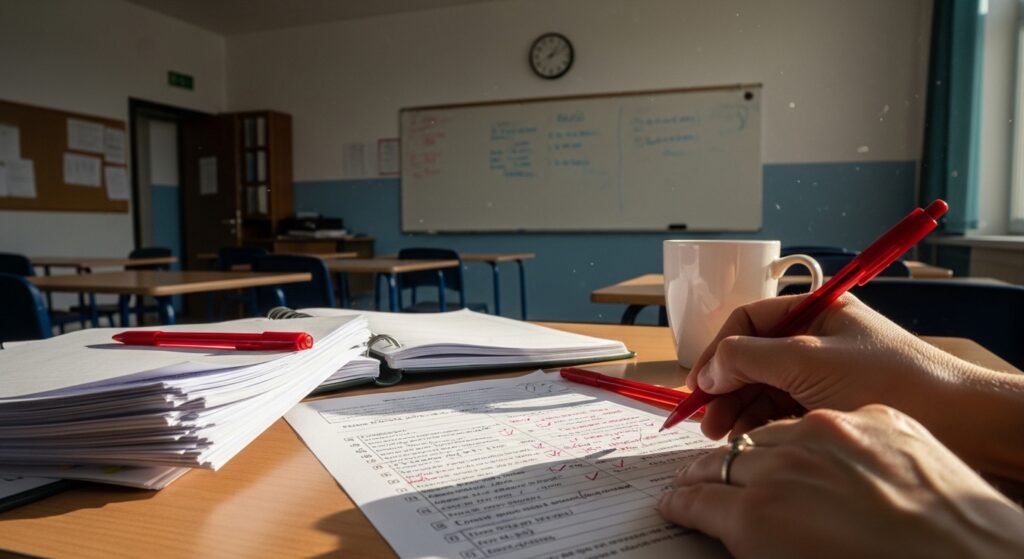
共通テストで6割の得点率を獲得することは、一般的に偏差値50前後であると判断できます。
偏差値とは、テストを受けた集団の中で自分の位置を客観的に示す指標であり、平均点が偏差値50になるように設定されています。
つまり、平均点と同じ得点であれば偏差値は50となり、それより高ければ50以上、低ければ50未満となります。
多くの予備校や教育機関が公表しているデータを見ても、共通テストの平均点が6割前後に集中していることから、6割の得点は平均的な学力を持つ受験生が到達する水準と言えます。
共通テストの得点率が60%の場合、これは全国の共通テスト受験者の中でちょうど中間あたりの位置にいることを意味します。
この偏差値50という数値は、受験生が自身の立ち位置を客観的に把握する上で非常に重要な指標となります。
共通テスト60パーセントで合格できる国立大学
共通テストで60%の得点率を確保できれば、国公立大学への合格も十分に視野に入ってきます。
特に地方の国公立大学では、60%がボーダーラインとなる学部・学科が数多く存在しています。
これらの大学は、共通テストの配点と二次試験の配点のバランスが特徴であり、共通テストで60%を取ることができれば、二次試験で挽回できる可能性も十分にあります。
以下に、共通テストの得点率が60%前後で合格を狙える国公立大学の具体的な例を、地方別に示します。
これらの情報は、あくまで過去の入試データに基づいた目安であり、年度や学部・学科の募集要項、二次試験の科目や配点によって変動するため、志望校の最新情報を必ず確認してください。
(出典:河合塾 Kei-Net 「入試難易予想ランキング表」)
北海道・東北地方
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 小樽商科大学 | 商 | 64% |
| 札幌市立大学 | 看護 | 64% |
| 岩手大学 | 農(動物科学) | 64% |
| 福島県立医科大学 | 保健科学(診療放射線科学) | 64% |
| 北海道教育大学 | 教育(教員養成) | 63% |
| 弘前大学 | 医(保健)、人文社会 | 63% |
| 山形大学 | 人文社会 | 63% |
関東・甲信越地方
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 茨城大学 | 教育(学校教育)、理(物理)、工(情報工) | 64% |
| 群馬大学 | 共同教育(教育心理) | 64% |
| 埼玉大学 | 教育(小学) | 64% |
| 東京海洋大学 | 海洋工 | 64% |
| 信州大学 | 教育(学校)、理、医(保健) | 64% |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン | 63% |
| 新潟大学 | 創生学修、DX共創 | 63% |
東海・北陸・近畿地方
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 富山大学 | 芸術文化 | 64% |
| 金沢大学 | 人間社会(法)、融合 | 64% |
| 岐阜大学 | 工(電気) | 64% |
| 静岡大学 | 人文社会(経済)、理(生物)、工 | 64% |
| 三重大学 | 人文(法律経済)、工、生物資源 | 64% |
| 滋賀大学 | 経済、データサイエンス | 64% |
| 京都教育大学 | 教育(学校) | 64% |
| 大阪教育大学 | 教育(小学校教育) | 64% |
| 兵庫県立大学 | 国際商経(経済・経営)、看護 | 64% |
| 奈良女子大学 | 理(化生)、生活環境(生活文化) | 64% |
四国・中国・九州地方
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 岡山大学 | 教育(中学校)、理(地球)、工、医(保健) | 64% |
| 山口大学 | 医(保健) | 64% |
| 九州工業大学 | 工、情報工 | 64% |
| 福岡教育大学 | 教育(中等) | 64% |
| 北九州市立大学 | 文(比較文化) | 64% |
| 長崎大学 | 薬(薬科学) | 64% |
| 熊本大学 | 文、教育(初中)、工、医(保健) | 64% |
上記のリストは、受験生の皆様にとって一つの指針となる情報です。
特に、二次試験の配点が高い大学であれば、共通テストの得点率がボーダーラインを下回っていても、二次試験での巻き返しを十分に狙えます。
大学ごとの配点比率を確認し、得意科目を活かせる大学を見つけることが重要です。
合格できる私立大学の例
共通テストの得点率が6割程度でも、合格を目指せる私立大学は多数存在します。
特に、共通テスト利用入試を実施している大学の多くは、60%の得点率を合否の目安としています。
Kei-Netが公開しているデータ(出典:河合塾 Kei-Net 「入試難易予想ランキング表」)によると、この得点率は合格可能性が50%となるラインとされており、戦略的な出願を行うことで合格のチャンスを広げることができます。
GMARCHや関関同立といった上位校では6割での合格は難しい傾向にありますが、日東駒専や大東亜帝国、愛愛名中、産近甲龍といった大学群では、多くの学部・学科で6割前後の得点率がボーダーラインとなっています。
日東駒専
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 日本大学 | 法(二部)、工、生産工 | 40~64% |
| 東洋大学 | 法(二部)、理工 | 57~68% |
| 駒澤大学 | 法(フレックスB) | 60% |
| 専修大学 | ネットワーク情報 | 57~66% |
大東亜帝国
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 大東文化大学 | 文、外国語、国際関係、経営、スポーツ | 46~76% |
| 東海大学 | 文、人文、児童教育、教養、文化社会、観光、国際文化、国際、法、政治経済、経営、体育、健康、理、工、情報理工、情報通信、建築都市、農、海洋、文理融合 | 36~67% |
| 亜細亜大学 | 国際関係、都市創造、法、経済 | 49~64% |
| 帝京大学 | 経済、理工、医療技術、福岡医療 | 43~69% |
| 国士舘大学 | 21世紀、体育、理工 | 57~67% |
愛愛名中
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 愛知学院大学 | 文、総合政策、歯、薬、健康科学 | 48~64% |
| 名城大学 | 経済 | 57~69% |
| 中京大学 | 現代社会、国際 | 53~69% |
産近甲龍
| 大学名 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
| 龍谷大学 | 文、社会、国際、経済、先端理工、農 | 52~75% |
| 京都産業大学 | 生命科学 | 59~62% |
| 近畿大学 | 工、生物理工、産業理工、農 | 50~71% |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス | 56% |
これらの大学群では、共通テスト利用入試の得点ボーダーが60%前後となっている学部・学科が多数存在します。
特に、東海大学や近畿大学は学部や学科の選択肢が多岐にわたるため、自分の興味や得意分野に合わせて出願先を検討する余地が広いです。
ただし、これらのデータもあくまで目安であり、共通テスト利用入試は募集人数が少ない場合や、高得点者から順に合格が決まるため、例年ボーダーラインが変動しやすい点には注意が必要です。
共通テスト6割取るための戦略

共通テストで6割の得点を取るためには、やみくもに難しい問題ばかりを解くのではなく、基礎を徹底的に固めることが最も重要な戦略となります。
共通テストは基礎知識の理解度を問う問題が中心であるため、まずは教科書や基本的な参考書で、各科目の基本事項を完璧にすることが得点アップへの近道です。
具体的な戦略としては、まず共通テストの過去問を解いてみることから始めます。
時間を測って解くことで、現在の自分の実力と目標点との間にどのくらいの差があるのかを客観的に把握することができます。
その後、間違えた問題や、自信を持って解答できなかった問題を分析し、どの科目のどの分野に弱点があるのかを明確にしましょう。
弱点が明らかになったら、その分野に焦点を絞って集中的に学習計画を立てることが効率的です。
また、共通テストは限られた時間の中で多くの問題を正確に解く必要があるため、過去問や実践問題を繰り返し解き、出題形式や時間配分に慣れる練習も欠かせません。
この段階で、解法をパターン化し、反射的に解答できるレベルまで落とし込むことが理想的です。
6割行くための具体的な科目別対策
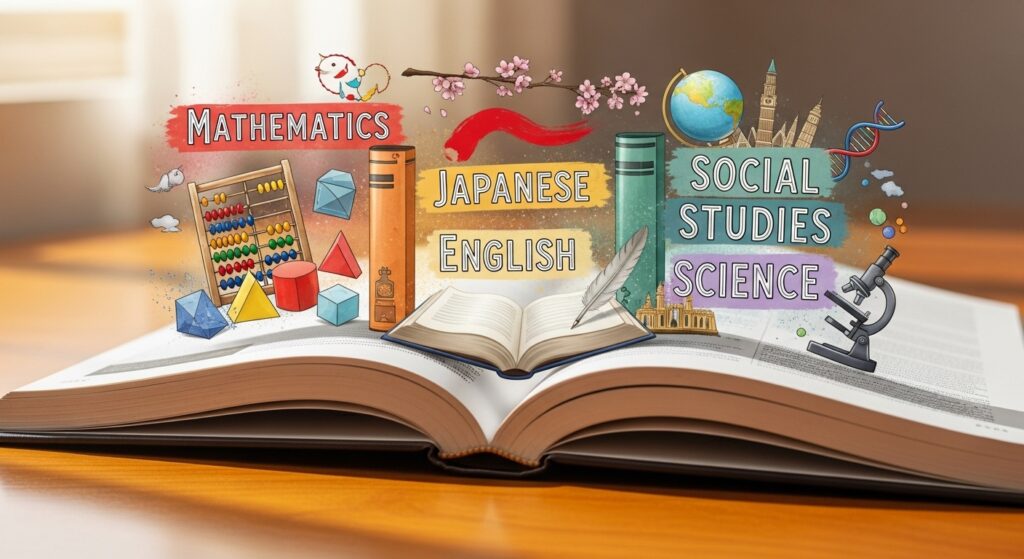
共通テストで6割の得点率を達成するためには、科目ごとの特性を理解し、それぞれに合わせた効率的な対策を講じることが不可欠です。
もし現在、目標の6割に届いていない場合は、基礎知識がまだ定着していない可能性が高いです。
そのような場合は、いきなり難解な問題に挑戦するのではなく、まずは教科書や基礎的な参考書を使って、各科目の基本的な知識や解法を完璧にすることから始めましょう。
基礎が固まれば、共通テスト特有の出題形式に慣れるために、過去問や共通テスト対策用の問題集を使って演習を重ねることが効果的です。
全体的な戦略
共通テストの勉強を始めるにあたって、まずやるべきことは、時間を測って共通テストの過去問を解くことです。
これにより、現在の自分の実力と目標点である6割との間にどのくらいの差があるのかを客観的に把握できます。
また、どの科目のどの分野が苦手なのか、そしてどの分野が得意なのかも明確になります。
これらの分析結果に基づいて、苦手な分野を克服するための具体的な学習計画を立てましょう。
すべての科目をまんべんなく学習するのではなく、得点率を効率的に上げるために、苦手な科目に重点を置いて取り組むことが得策です。
国語の対策と勉強法
共通テストの国語で6割を目指すためには、現代文、古文、漢文の各分野でバランスの取れた学習が必要です。
特に現代文は、評論と小説の読解力を高めることが鍵となります。
現代文の対策
現代文は、単なる読解力だけでなく、論理的な思考力が問われます。
まずは、評論の読解力を上げるために、様々なテーマの文章に触れ、筆者の主張や論理展開を正確に捉える練習をしましょう。
文章全体を要約する練習も効果的です。
小説については、登場人物の心情や行動の理由を読み解く力が求められるため、過去問や問題集を通じて、設問の意図を把握する練習を重ねましょう。
古文・漢文の対策
古文と漢文は、基礎知識の定着が6割突破の鍵となります。
古文では、古典文法と古文単語の暗記が最優先です。特に、助動詞や敬語などの文法事項は、文章を正確に読むために不可欠です。
漢文では、句形や重要漢字の意味を確実に覚えましょう。これらを習得した上で、過去問演習を通じて、文章全体の流れを理解する練習をすることが重要です。
おすすめの教材
現代文の基礎固めには『船口の最強の現代文』や『きめる!共通テスト現代文』がオススメです。
古文・漢文の基礎には、『岡本梨奈の 1冊読むだけで古典文法の基本&覚え方が面白いほど身につく本』や『漢文道場の基礎編』などの参考書が役立ちます。
基礎が固まったら、共通テストの過去問や実践問題集を繰り返し解き、時間配分を意識しながら演習を重ねましょう。
数学の対策と勉強法
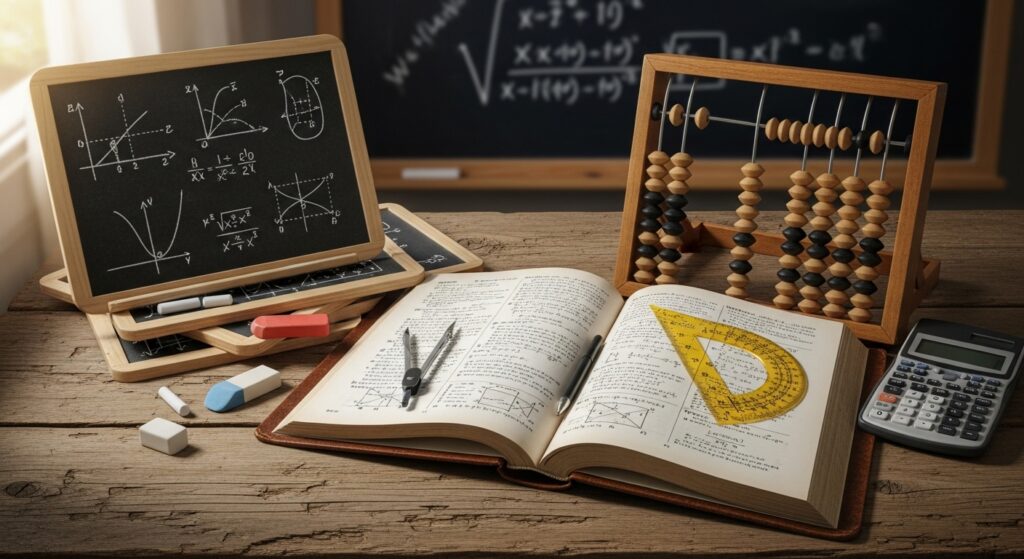
共通テストの数学で6割の得点を目指すには、基礎的な公式や定石を確実に理解することが不可欠です。
6割に届いていない受験生の多くは、「全ての単元が中途半端な理解」であるか、「苦手な単元が複数ある」か、あるいは「計算ミスが多い」のいずれかに当てはまる傾向にあります。
パターン別の勉強法
- 全体が中途半端な理解の場合
この場合は、映像授業や講義系の参考書を活用して、全範囲の基礎的な知識と典型問題の解き方を学び直すのが最も効果的です。
教科書や網羅系の参考書(例えば「青チャート」など)を使って、公式や解法を一つずつ丁寧に確認し、時間をかけてでも基礎を固めましょう。 - 苦手な単元が複数ある場合
特定の苦手分野がある場合は、その単元に絞って徹底的に基礎に立ち返ることが大切です。
映像授業や講義系の参考書で公式や定石を理解した後に、網羅型の問題集で該当部分の問題を集中的に解いてみましょう。
苦手分野を克服することで、全体の得点率を大きく向上させることが期待できます。 - ミスが多い場合
計算ミスや問題文の読み間違いが多い場合は、演習方法を改善することが重要です。
問題を解いた後、すぐに解説を読むのではなく、解説を閉じて自分の手でもう一度解き直す習慣をつけましょう。
また、答案作成時に図や文字をきれいに書くことを意識するだけでも、ケアレスミスの減少につながります。
おすすめの教材
基礎固めには、スタディサプリや「初めから始める数学」などの講義系教材が非常に役立ちます。
【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座ポイントは、参考書だけにこだわらず、YouTubeなども活用して「わかる」を積み重ねること。この段階では「公式を理解する」「基礎問題を迷わず解けるようにする」ことがゴールです。
基礎が固まったと感じたら、「青チャート」などを使い、レベル2とレベル3の問題を中心に演習を行うと良いでしょう。
これにより、基礎知識を共通テスト形式の問題に応用する力が身につきます。
英語の対策と勉強法
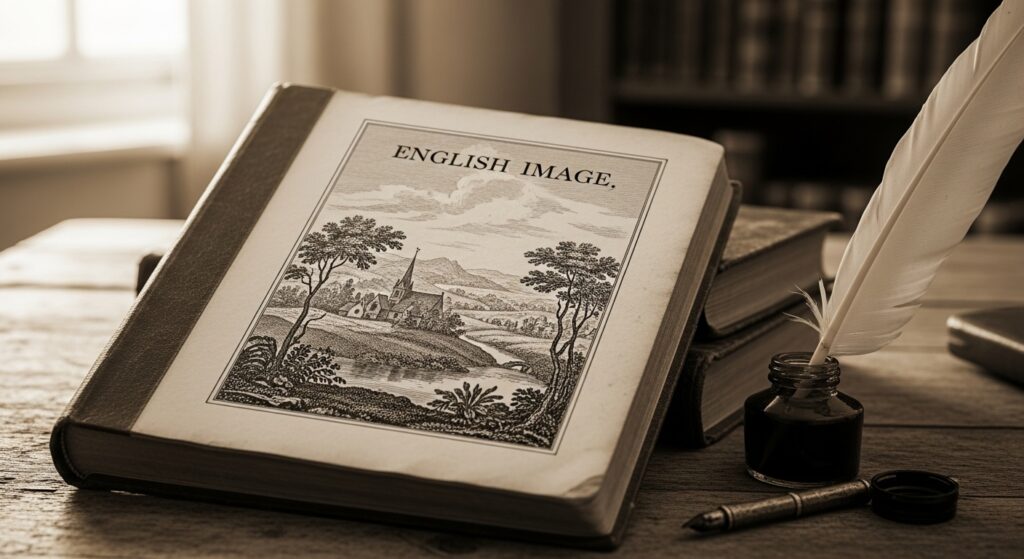
共通テストの英語で6割を目指すには、まず何よりも単語力と文法力といった基礎を固めることが大切です。
その上で、共通テスト特有の長文読解問題に慣れる練習を重ねていきます。
まずは、共通テストの過去問を解き、自分の弱点がどこにあるのかを洗い出すことから始めましょう。
対策の具体的な手順
- 過去問の実施
最新の共通テスト過去問を時間を測って解いてみましょう。
制限時間内に解けた問題、時間がかかれば解けた問題、そして解説を見ても理解できない問題に分類することで、自分の現在の学力を正確に把握できます。
これにより、語彙力不足なのか、文法が未修なのか、それとも単にスピード不足なのかが分かります。 - 単語の暗記
語彙力が不足していると判断した場合は、すぐに単語の暗記に取り掛かりましょう。
「システム英単語」などの単語帳を使い、毎日100単語を目安に集中的に学習します。
単語力は、英語の基礎を固める上で最も重要な要素の一つです。 - 文法の理解
共通テストでは直接的な文法問題は少ないものの、長文を正確に読むためには最低限の文法知識が不可欠です。
文法に自信がない場合は、「肘井学のゼロから英文法が面白いほどわかる本」などで基礎を固めましょう。
基礎を学び終えた方は、「ポラリス英文法1」などで演習を重ねて、知識を定着させることがおすすめです。 - 実践問題演習
単語と文法の基礎が固まったら、再び過去問や実践問題に取り組みましょう。
過去問は何度解いても構いません。
大問ごとに時間を測って解き、答え合わせをした後は、必ず精読を行います。
精読とは、文章の構造(SVOC)を分析しながら、知らなかった単語や表現を覚える作業です。
この作業を繰り返すことで、単語や文法を実践的に活用する力が身につきます。
理科と社会の対策

理科と社会の共通テストで6割を目指すには、まず各科目の基礎知識を徹底的にインプットすることが何よりも大切です。
特に暗記要素が強い科目は、教科書や参考書を使って全体像を把握し、重要語句や概念を確実に覚えましょう。
ただ暗記するだけでなく、その背景にある因果関係や時代ごとの流れを理解することが、高得点に繋がります。
理科(物理、化学、生物)
理科で6割を目指すには、基礎的な原理や公式の理解が不可欠です。
まずは教科書や講義系参考書で全体を網羅しましょう。
特に化学では、有機化学や無機化学のように暗記量が多い分野も含まれるため、抜け漏れがないように細かく確認することが重要です。
知識をインプットした後は、『化学基礎問題精講』などの問題集を解き、知識を定着させます。
物理や生物でも同様に、基本原理を理解した上で問題演習を繰り返し、知識をアウトプットする練習が不可欠です。
社会(世界史、日本史、地理など)
社会は、覚えるべき知識が膨大ですが、共通テストでは歴史の流れや地理的な概念の理解が問われることが多いです。
まずは教科書や一問一答形式の参考書で、基本的な用語や年号、出来事を覚えます。
その後、共通テストの過去問を解き、どのような形式で知識が問われるのかを把握することが大切です。
単なる暗記で終わらせず、なぜその出来事が起こったのか、その結果どうなったのか、という因果関係を意識して学習することで、応用力が身につきます。
どのぐらい時間がかかるか

共通テストで6割を目指すために必要な時間は、現在の学力や目標によって大きく異なります。
しかし、一般的には、基礎固めに数ヶ月、その後の演習に数ヶ月を要すると考えられます。
例えば、基礎ができていない状態から始める場合、各科目の基礎を固めるのに2〜3ヶ月ほどかかるでしょう。
その後、過去問や共通テスト対策問題集を繰り返し解き、問題形式に慣れるのにさらに2〜3ヶ月かかるのが一般的です。
合計すると、最低でも5〜6ヶ月程度の期間を確保できると、目標の6割に到達する可能性が高まります。
ただし、これはあくまで目安であり、個人の学習ペースや集中力によって変動します。
日々の学習時間を確保し、計画的に勉強を進めることが大切です。
特に、高校3年生の夏休みから本格的に受験勉強を始める場合、この5〜6ヶ月という期間は非常に現実的な目標設定と言えるでしょう。
共通テストで60パーセントを確実に取るには
共通テストで60パーセントの得点率を確実に取るためには、やみくもに勉強するのではなく、効率的な学習戦略を立てることが重要です。
まず、現状の学力を正確に把握し、どの科目のどの分野が苦手なのかを特定します。
その上で、基礎固めに重点を置き、教科書や基本的な参考書を使って知識を定着させることが不可欠です。
過去問や実践問題を繰り返し解き、出題傾向や時間配分に慣れることも大切です。
特に、間違えた問題はなぜ間違えたのかを徹底的に分析し、次へと活かすことで、同じミスを繰り返さないようにできます。
直前期には、新しい問題集に手を出すのではなく、これまでに解いた問題の復習に時間を充て、知識の精度を高めることが得点アップにつながります。
共通テストで60パーセントは平均点付近の得点である
- 60パーセントは偏差値に換算するとおよそ50前後が目安となる
- 地方国公立大学や日東駒専・大東亜帝国の一部で合格が狙える
- 自分の現状の学力を正確に把握することが対策の第一歩である
- 基礎固めを徹底し過去問演習を繰り返すことが重要である
- 勉強時間は最低でも5〜6ヶ月程度を目安に計画を立てる
- 数学は基礎公式と定石の理解、ミスを減らす練習が鍵となる
- 英語はまず単語力と文法力の強化が不可欠となる
- 理科と社会は基礎知識のインプットと問題演習をバランスよく行う
- 苦手な分野に絞った集中的な学習で得点力を底上げする
- 過去問や実践問題で出題形式と時間配分に慣れる練習を行う
- 間違えた問題の復習を徹底し同じミスを繰り返さないようにする
- 直前期は新しい問題に手を出さず復習で知識を固める
- モチベーションを維持し計画的に学習を進めることが大切である
- どの大学が狙えるのか事前に調べておくとモチベーションが上がる
次のレベルに進みたい人は↓

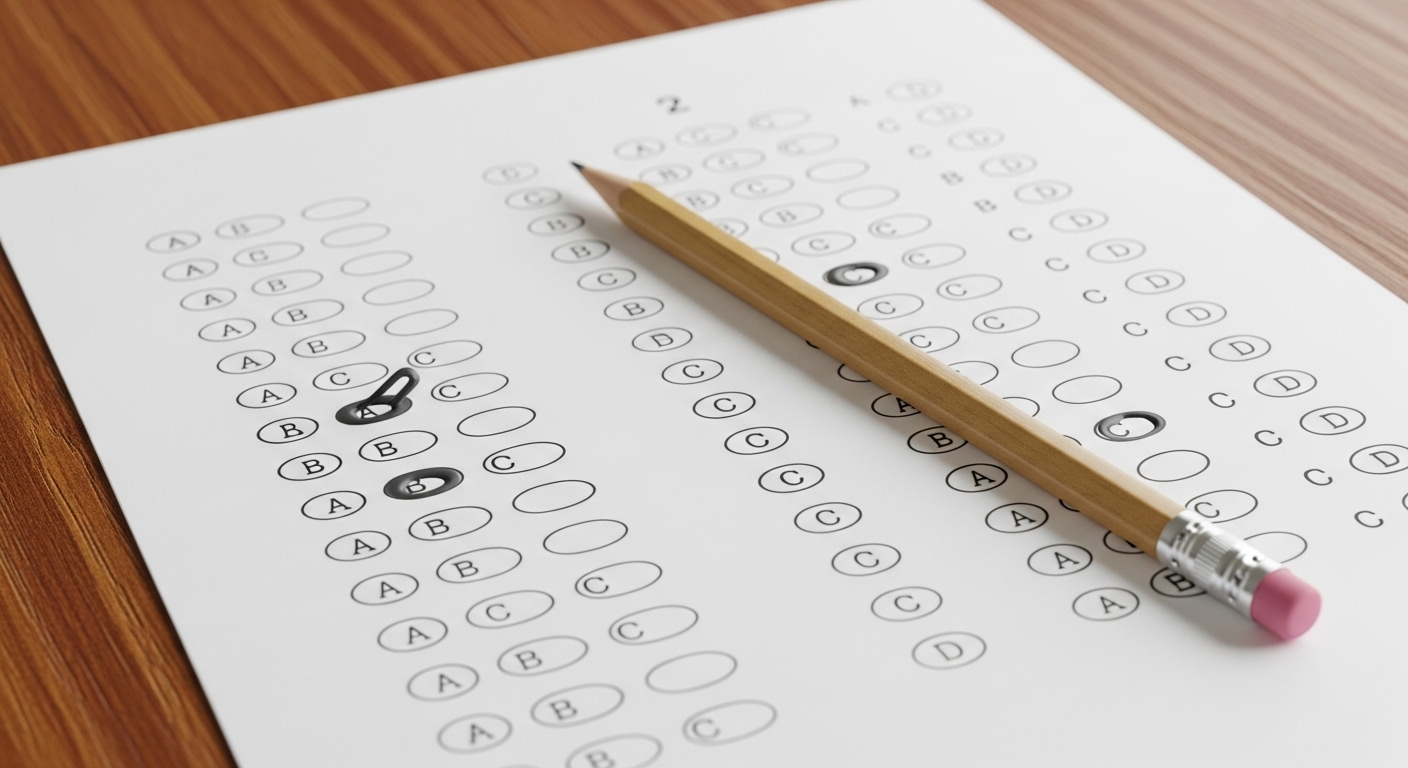




コメント