こんにちは。現役京大生の受験バイブル、運営者の「パンダ」です。
「横浜国立大学を目指しているけれど、共通テストで具体的に何点取ればいいのかわからない…」 「ボーダーラインや偏差値の正確な情報が知りたいけれど、サイトによって数字が違って不安…」 「2026年度入試に向けて、今からどんな対策をすれば合格に近づけるの?」
あなたは今、このような悩みを抱えて、「横浜 国立 大学 共通 テスト ボーダー」と検索画面に打ち込んだのではないでしょうか。
その気持ち、痛いほどよくわかります。
私自身も受験生時代、志望校の合格ラインが見えずに模試の結果に一喜一憂し、不安な夜を過ごした経験があるからです。
特に国公立大学の入試は、共通テストのウェイトが大きく、少しのミスが命取りになることもありますよね。
でも、安心してください。
この記事にたどり着いたあなたは、もう一人で悩む必要はありません。
ここでは、横浜国立大学の各学部における最新のボーダー得点率や偏差値情報は言うまでもなく、合格を勝ち取るための科目別対策法や併願戦略まで、現役京大生の視点で徹底的に深掘りして解説します。
表面的な数字だけでなく、「合格するために必要なリアルな戦略」をお伝えするので、ぜひ最後まで付いてきてくださいね。
- 2026年度入試における各学部の詳細な共通テストボーダー得点率と安全圏
- 経済学部や理工学部、都市科学部など学部・学科ごとの偏差値と難易度の実態
- 配点の特殊性や英語・数学などの出題傾向を踏まえた、具体的で実践的な対策法
- 合格後の就職実績やおすすめの併願校を知ることで、受験戦略全体を最適化する方法
2026年度横浜国立大学の共通テストボーダーと難易度

まずは、横浜国立大学を目指す上で避けては通れない「数字」の話から始めましょう。
共通テストでどれくらい取ればいいのか、偏差値はどのくらい必要なのか、学部ごとに詳しく見ていきます。
「なんとなく8割くらいかな?」という曖昧な認識では、本番で痛い目を見るかもしれません。
確実なデータに基づいた目標設定こそが、合格への第一歩ですよ。
学部別の共通テスト得点率目安

横浜国立大学は、多くの学部で共通テストの配点比率が高く設定されており、ここでの得点が合否に直結します。
「二次試験で挽回すればいいや」という考えは、横浜国立大学に関してはかなり危険な賭けになると心得てください。
2026年度入試(主に2025年度の模試データや過去の傾向を基準とした予測)において、合格へのボーダーラインとなる得点率は全体的に高水準です。
特に、難関国立大学としての人気が年々高まっていることもあり、ミスが許されない戦いになります。
以下に、各学部の詳細な目安をまとめました。
| 学部 | 共通テスト得点率目安(ボーダー) | 難易度評価 |
|---|---|---|
| 教育学部 | 64% ~ 75% | 標準~やや難 |
| 経済学部 | 76% ~ 82% | 難関 |
| 経営学部 | 80% ~ 83% | 難関 |
| 都市科学部 | 75% ~ 86% | 難関~最難関(学科による) |
| 理工学部 | 76% ~ 85% | 難関 |
(出典:河合塾)
この数字を見て、「えっ、こんなに高いの?」と感じた人もいるかもしれません。
特に経済学部や経営学部といった社会科学系の学部では、8割を超える得点が当たり前のように求められます。
これは、東大や一橋大学といった最難関大学を第一志望とする層が、併願や志望変更で流れてくるケースが多いため、レベルが底上げされていることが要因の一つです。
また、都市科学部の上位学科(建築など)では、9割近い得点率がボーダーになることも珍しくありません。
これはもはや「ミスをしない競争」です。
苦手科目を放置していると、その1教科だけでボーダーから転落してしまう可能性が高いのです。
【リサーチ判定の活用法】
共通テスト本番後に予備校各社が出す「データリサーチ」では、B判定以上が出ていればまずは勝負できると考えて良いでしょう。
C判定の場合は、二次試験の配点や自分の得意科目との相性を慎重に見極める必要があります。
D・E判定からの逆転は、横浜国立大学の配点特性上(共通テスト重視型が多いため)、他大学に比べてハードルが高い傾向にあります。
さらに、「第一段階選抜(いわゆる足切り)」の存在も忘れてはいけません。
志願者が募集人員の特定倍率を超えた場合、共通テストの点数だけで受験生を絞り込む制度です。
人気学部では毎年実施される可能性があるので、最低でもこのラインは余裕を持ってクリアしておく必要があります。
公式の募集要項で、足切りの実施予告倍率を必ず確認しておきましょう。(出典:横浜国立大学 入試・入学情報)
経済学部と経営学部の偏差値

横浜国立大学の看板学部とも言える、経済学部と経営学部。
これらの学部は、首都圏の国公立大学文系の中でもトップクラスの人気と難易度を誇ります。
大手予備校の最新データを分析すると、経済学部は偏差値63~68程度、経営学部は偏差値65~68程度で推移しています。
河合塾のKei-Netなどの指標でも、62.5~67.5という高いレンジに位置付けられることが多く、これはMARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)の上位学部や、早稲田・慶應義塾大学の下位学部と併願されるレベル帯であることを示しています。
特に注目すべきは、経済学部と経営学部の「入試方式による偏差値の違い」です。
- 前期日程:募集人数が多く、オーソドックスな学力が問われます。
とはいえ、共通テストで8割確保しつつ、二次試験でも安定した記述力が求められるため、総合偏差値は高くなります。 - 後期日程:募集人数が極端に少なく、共通テストの比重がさらに高まる傾向にあります。
偏差値以上に「共通テストでの失敗の許されなさ」が際立つ試験になります。
「経済と経営、どっちの方が入りやすいの?」という質問をよく受けますが、結論から言うと「大差はないが、強いて言うなら科目配点の相性次第」です。
偏差値的にはほぼ同等ですが、年度によって倍率が変動するため、隔年現象(倍率が高い年の翌年は下がる現象)などが起きることもあります。
また、経済学部には独自の配点方式(後述します)があるため、数学や英語が得意な「理系崩れ」の受験生や、特定の科目に特化した受験生が流入してきやすいのも特徴です。
そのため、見かけの偏差値以上に、受験生のレベル層は幅広いと認識しておいた方が良いでしょう。
理工学部や都市科学部の難易度

近年、情報系や建築系の人気高騰に伴い、横浜国立大学の理系学部も難化傾向にあります。
単に理系科目が得意なだけでは突破できない、総合力が問われる入試になっています。
理工学部の偏差値は58~63程度です。
機械・材料・海洋系工学、化学・生命系、数物・電子情報系など、多岐にわたる学科(EP:教育プログラム)がありますが、特に情報系のEPは人気が高く、偏差値も頭一つ抜けている印象です。
ここでは、物理と化学(または生物)の基礎を徹底的に固め、応用問題にも対応できる思考力が必須となります。
そして、受験生を悩ませるのが都市科学部の存在です。
この学部は文理融合的な側面を持ちつつも、学科によって難易度と偏差値の乖離が激しいのが特徴です。
| 学科(EP) | 偏差値目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 建築学科 | 63 ~ 65 | 超難関。 早稲田や東工大との併願層が多い。 |
| 都市基盤学科 | 58 ~ 60 | 土木・インフラ系。 堅実な人気があり、物理・数学の力が必要。 |
| 環境リスク共生学科 | 55 ~ 60 | 比較的入りやすいとされるが、環境問題への関心と理科基礎力が問われる。 |
【都市科学部を目指すあなたへ】
「とにかく横国に入りたい!」という場合、都市科学部の環境リスク共生学科などは、他学科に比べてボーダーや偏差値がやや落ち着いているため、狙い目と言われることがあります。
しかし、カリキュラムは独特で、文系科目での受験が可能な枠があるなど入試方式も複雑です。
偏差値だけで選ぶのではなく、「入学後に何を学びたいか」をしっかり考えないと、ミスマッチに苦しむことになりますよ。
教育学部の合格目標ライン

将来、学校の先生になりたいと考えている人にとって、横浜国立大学教育学部は非常に魅力的な選択肢です。
首都圏の国立大学で教員養成系学部を持つ大学は限られており(東京学芸大学、埼玉大学、千葉大学など)、その中でも横浜国立大学は高いブランド力を持ちます。
難易度の目安としては、共通テスト得点率は64~75%の範囲です。
他学部に比べると、数字上は「入りやすい」と感じるかもしれません。
しかし、ここには数字には表れない難しさがあります。
まず、教育学部は「人物重視」の傾向があります。
共通テストの点数だけで決まるわけではなく、二次試験で面接や小論文、実技(音楽や美術、体育専攻など)が課されることが多いです。
いくら偏差値が高くても、教員としての適性や意欲が伝わらなければ不合格になることも十分あり得ます。
また、専攻・コースによってボーダーが大きく異なる点も注意が必要です。
例えば、心理学系や英語教育系のコースは人気が高く、ボーダーも跳ね上がります。
一方で、技術家庭や特定の教科専攻では比較的穏やかな競争率になることもあります。
「偏差値が届いているから余裕」と油断せず、志望する専攻の過去の倍率や入試内容を細かくチェックし、面接対策などを含めたトータルの準備を進めることが合格への鍵です。
入試科目と配点の注意点
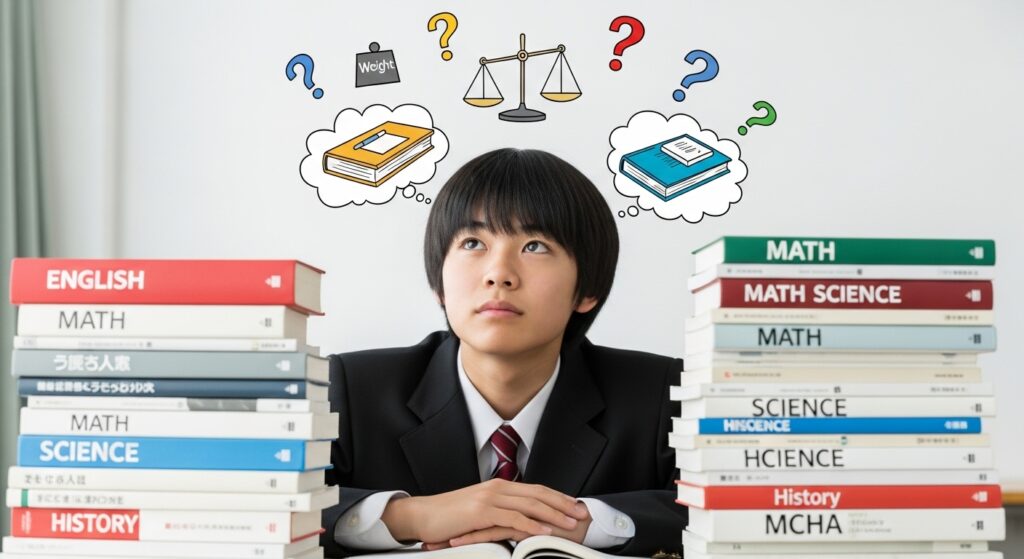
横浜国立大学の入試を攻略する上で、最も戦略的な要素となるのが「配点」です。
ここを理解しているかどうかで、勉強の優先順位が劇的に変わります。
特に注意すべきポイントを深掘りしていきましょう。
最大の特徴は、経済学部(前期)の「共通テスト重視・英数特化」配点です。
通常、国立文系といえば国語や社会も含めた総合点が問われますが、横国経済の前期などでは、共通テストの英語と数学(ⅠA・ⅡB)の配点が極端に高く設定されるケースがあります(例:英語400点、数学400点、他科目は配点なし、または極小など)。
これはどういうことかと言うと、「国語や社会がボロボロでも、英語と数学さえ満点近ければ合格できる」という逆転現象が起こり得るということです。
逆に言えば、まんべんなく点数を取るオールラウンダータイプよりも、英数に尖った受験生の方が有利になる場合があるのです。
【必ず募集要項で確認を!】
この配点は年度によって変更される可能性があります。
また、後期日程や他学部では全く異なる配点(国語重視や理科重視など)が採用されています。
「ネットで見たから大丈夫」と思い込まず、必ず大学発行の最新の募集要項で、自分の志望学部の配点比率を確認してください。
数点の違いが合否を分ける世界ですよ。
理系学部(理工・都市科学)においては、理科の選択科目にも注意が必要です。
多くの学部で「物理・化学」の2科目指定が多いですが、一部の学科では生物選択が可能だったり、地学が選べなかったりします。
また、共通テストと二次試験の配点比率も学部によって異なり、共通テスト逃げ切り型なのか、二次試験逆転型なのかを見極めることも重要です。
横浜国立大学共通テストボーダーを突破する対策

ボーダーラインや配点の仕組みが見えてきたところで、ここからは「具体的にどうやってその点数を叩き出すか」というアクションプランの話に移ります。
敵を知ったら、次は武器を磨く番です。
明日からの勉強に直結する対策法をお伝えします。
英語と数学の出題傾向
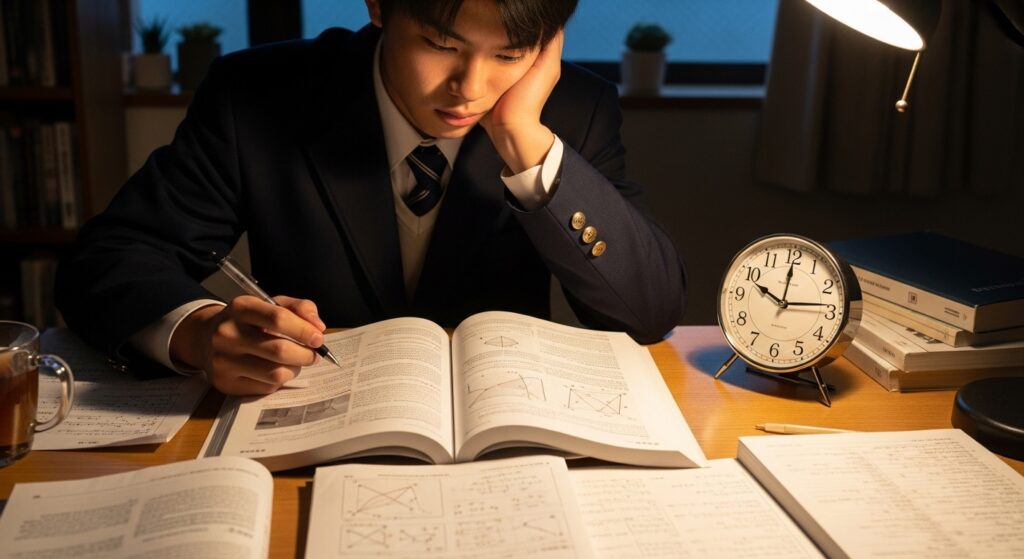
多くの学部で配点が高く、合否の分水嶺となるのが英語と数学です。
この2科目を制するものが横浜国立大学入試を制すると言っても過言ではありません。
英語の対策:速読と情報処理能力が命
共通テスト英語(リーディング)は、全問が読解問題となり、総語数は約4,000~5,000語(英検2級~準1級レベル)にも及びます。
これを80分で解き切るには、精読力だけでなく圧倒的な「速読力」と「情報処理能力(スキャニング)」が求められます。
- 対策法①:時間を計って解く
日頃の演習から、「大問〇〇は15分で解く」といった時間制限を厳しく設けましょう。
だらだら時間をかけて満点を取っても意味がありません。 - 対策法②:設問を先に読む
本文を最初から最後まで馬鹿正直に読むのではなく、まず設問を見て「何が問われているか」を把握してから、本文中の該当箇所を探しに行くスタイル(スキャニング)を身につけましょう。 - リスニング対策
配点が高い学部も多いです。
アメリカ英語だけでなく、イギリス英語や非ネイティブの英語が含まれることもあるため、多様な音源に触れておくことが大切です。
シャドーイングを毎日最低30分は行い、「英語を英語の語順で理解する脳」を作りましょう。
オススメ教材を下に挙げておきます。
数学の対策:計算力と標準問題の完全習得
数学(ⅠA・ⅡB・C)は、難問奇問が出るというよりは、標準的な良問が多く出題されます。
しかし、分量が多いため、迷っている時間はありません。
- 頻出分野
微積分、数列、ベクトル(数C)、確率などは毎年必ずと言っていいほど出題されます。
これらの分野の典型問題(チャート式やFocus Goldの例題レベル)は、見た瞬間に手が動くレベルまで仕上げておく必要があります。 - 計算力の強化
「計算ミスで落ちた」という受験生は後を絶ちません。
横国の数学は計算量が多めの問題が出ることがあるため、普段から途中式を省かず、丁寧に、かつ素早く計算を完遂するトレーニングを積んでください。
「計算は力なり」ですよ。
関連記事↓
共テ数学ができない人必見!共テ数学で9割とるためのコツと勉強方法
後期日程のボーダーと特徴

「前期で失敗しても、後期日程があるから大丈夫でしょ?」 もしあなたがそんな風に軽く考えているなら、今のうちにその認識を改めておいた方がいいかもしれません。
厳しいことを言うようですが、横浜国立大学の後期日程は、前期日程とは全く別の「修羅場」と化すからです。
まず、後期日程における共通テストのボーダーラインは、前期に比べて劇的に跳ね上がります。
例えば、経済学部の後期日程を見てみましょう。
前期日程でのボーダー得点率が80%前後であるのに対し、後期日程では約87%、年度によってはそれ以上が必要になることさえあります。
87%といえば、全科目でミスが許されないレベル。
9割近く取って初めて「土俵に乗れる」という世界なのです。
なぜこれほどまでに難易度が上がるのか。理由は大きく分けて2つあります。
- 理由①:募集人員が極端に少ない
横浜国立大学に限った話ではありませんが、多くの学部で後期日程の定員は前期の数分の一です。
狭き門に多くの受験生が殺到するため、必然的に倍率と合格ラインが押し上げられます。 - 理由②:超高レベルなライバルの流入
これが最大の要因です。
後期日程には、東京大学、一橋大学、東京工業大学(現・東京科学大学)といった、日本最難関の国公立大学を前期で受験し、惜しくも涙を飲んだ層が大量に流れてきます。
彼らは共通テストで圧倒的な高得点を取っている猛者たちです。
そんなライバルたちと、残り少ない椅子を奪い合うことになるのです。
また、試験内容自体も特殊です。
後期日程では、学力試験(記述試験)を行わず、共通テストの点数のみ、あるいは「共通テスト+面接・小論文」で合否が決まる学部が多くあります。
これはつまり、「共通テストで失敗したら、挽回のチャンスがほぼない」ということを意味します。
一発逆転が起きにくい入試形式なんですね。
【後期受験の心構え】
後期日程はあくまで「保険」ではなく「最後の砦」です。
出願する際は、共通テストの自己採点結果と、予備校のリサーチ判定を冷静に分析してください。
「A判定」や「B判定」が出ていない場合、特攻するのはかなりリスクが高い選択になります。
必ず、前期日程で合格を勝ち取るつもりで全力を注ぎましょう。
とはいえ、最初から諦める必要はありません。
理工学部や都市科学部の一部では、後期でも個別試験(数学や理科など)が課され、記述力で勝負できるケースもあります。
自分が志望する学科がどのような選抜方式をとっているのか、大学が公表している過去の入試データを必ずチェックしておいてくださいね。(出典:横浜国立大学『入学試験実施状況』)
学部別のおすすめ併願校

第一志望である横浜国立大学への想いが強いほど、他の大学のことなんて考えたくないかもしれません。
でも、受験は何が起こるかわからないもの。
当日の体調不良や、想定外の難化に備えて、賢い「併願戦略」を立てておくことは、精神的な安定剤としても非常に重要です。
横浜国立大学を志望する受験生によく選ばれている併願校を、学部ごとにリストアップしました。
偏差値帯や出題傾向が似ている大学を選ぶことで、対策の負担を減らしつつ、合格の可能性を高めることができますよ。
文系学部(経済・経営・教育)の併願戦略
文系の場合、共通テスト利用入試を積極的に活用しつつ、一般入試ではMARCH(明治・青山・立教・中央・法政)の上位学部や、早稲田大学・慶應義塾大学をチャレンジ校として設定するのが王道です。
| 志望学部 | 私立大学の併願候補 | 国公立大学の併願候補(後期など) |
|---|---|---|
| 経済・経営学部 | 早稲田大学(商・社学):傾向は違うがレベル感の確認に。 明治大学(政経・商):手堅い実力校。共通テスト利用も人気。 立教大学(経済・経営):英語重視の傾向が似ている場合も。 東京理科大学(経営):数学受験が可能で、理系センスがある人におすすめ。 | 東京都立大学(経済経営):科目負担が比較的軽く、人気が高い。 横浜市立大学(国際商):地元志向なら最強の併願先。 埼玉大学(経済):堅実に合格を確保したい場合に。 |
| 教育学部 | 文教大学(教育):私立の教員養成の雄。 玉川大学(教育):教育理念がしっかりしている。 日本大学(文理):教員採用実績が多い。 | 東京学芸大学:教員養成のトップ。難易度は高いが併願者多数。 埼玉大学(教育):距離的にも通いやすいケースが多い。 千葉大学(教育):レベルが近く、検討の余地あり。 |
理系学部(理工・都市科学)の併願戦略
理系は、私立大学の理系学部(特に4工大や早慶理科大)との併願が一般的です。
数Ⅲや理科2科目の負担を考慮し、オーバーワークにならないような組み合わせを選びましょう。
| 志望学部 | 私立大学の併願候補 | 国公立大学の併願候補(後期など) |
|---|---|---|
| 理工学部 | 東京理科大学(工・創域理工):実力試しに最適。難易度は高い。 明治大学(理工):安定した人気と就職実績。 芝浦工業大学:建築や工学系で評価が高い。 中央大学(理工):都心キャンパスに移転し人気上昇中。 | 千葉大学(工):レベルが拮抗しており、悩みどころ。 東京農工大学(工):研究力が非常に高く、実力派におすすめ。 電気通信大学:情報・通信系ならここ。就職最強説も。 |
| 都市科学部 | 早稲田大学(創造理工):建築系なら憧れの併願先。 明治大学(理工・建築):建築志望者の定番。 東京都市大学:都市系・環境系のカリキュラムが充実。 | 東京都立大学(都市環境):分野が酷似しており、併願相性が良い。 |
ポイント:日程の確認を忘れずに!
私立大学の入試日程は2月上旬に集中します。
連日試験が続くと、体力も精神力も削られてしまい、本命の国公立入試(2月25日~)の前に燃え尽きてしまうことも…。
「3日連続受験は避ける」「移動距離を考慮する」など、無理のないスケジュールを組むことも立派な戦略ですよ。
卒業後の就職実績と進路

受験勉強に疲れたとき、ふと「大学に入った後、自分はどうなるんだろう?」と考えること、ありますよね。
ここでは、モチベーションアップのために、横浜国立大学の卒業後の進路についてお話しします。
結論から言うと、「横浜国立大学の就職力は、全国的に見てもトップクラス」です。
横浜という日本有数の大都市にキャンパスを構えているため、インターンシップや就職活動へのアクセスが抜群に良いのが大きなメリットです。
さらに、伝統的に産業界との結びつきが強く、多くの有名企業から「欲しい人材」として熱視線を送られています。
学部別の主な就職先例
- 経済・経営学部: 「看板学部」の力は伊達ではありません。
金融(三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行など)、商社、メーカー、IT(楽天、NTTデータなど)など、あらゆる業界のリーディングカンパニーに卒業生を輩出しています。
また、公認会計士試験の合格者数が多いのも特徴の一つです。 - 理工学部: 日本のモノづくりを支える技術者が多数育っています。
日立製作所、トヨタ自動車、キヤノン、ソニーといった超大手メーカーの研究・開発職に就く学生が多いです。
また、大学院進学率が高く、修士課程を修了してから推薦で大手企業へ、という王道ルートが確立されています。 - 都市科学部: 建築・土木業界でのブランド力は絶大です。
鹿島建設、大成建設といったスーパーゼネコンや、三菱地所、森ビルといったデベロッパーへの就職実績が豊富です。
都市づくりに関わりたい人にとっては、これ以上ない環境と言えるでしょう。 - 教育学部: もちろん教員採用試験に強く、横浜市や神奈川県を中心に多くの公立学校教員を輩出しています。
しかしそれだけでなく、ベネッセコーポレーションなどの教育産業や、一般企業への就職を選ぶ学生も一定数おり、進路の幅は意外と広いんですよ。
大学側もキャリアサポートに力を入れており、学内での合同企業説明会や、OB・OG訪問の斡旋などが頻繁に行われています。
入学してしっかり学び、学生生活を充実させれば、就職活動で困ることはまずないと言っても過言ではありません。
「将来のために、今はここで頑張る!」という気持ちで、ペンを握り直してくださいね。(出典:横浜国立大学『就職・キャリア支援』)
それでも不安な人のためのトウコベの無料相談
ここまで記事を読み終えた今、あなたの心の中には「やるべきことが見えた!」という希望と同時に、「本当に自分にできるかな…」という不安も残っているかもしれません。
特に、高いボーダーラインや、科目ごとの細かい対策を目の当たりにすると、その壁の高さに足がすくんでしまうこともあるでしょう。
「模試の判定がずっとEのままで、心が折れそう…」
「苦手な数学をどうにかしたいけど、何から手を付ければいいかわからない…」
「併願校の組み方や、学習計画が正しいのか誰かに見てほしい…」
そんな風に一人で抱え込んでしまっていませんか?
受験は孤独な戦いと言われますが、戦略を立てる段階で一人である必要はありません。
むしろ、正しい情報を持ち、あなたの状況を客観的に分析してくれる「伴走者」がいるかどうかで、合否の結果は大きく変わります。
もしあなたが、本気で横浜国立大学への逆転合格を目指すなら、東大生のオンライン個別指導「トウコベ」に頼ってみてください。
トウコベは、東大生が、あなたの専属コーチとなって学習をサポートするオンライン家庭教師サービスです。
- あなたの現状の学力と志望校のギャップを正確に分析し、最短ルートの学習計画を作成します。
- 共通テストの点数をあと50点、100点と伸ばすための、具体的な解法テクニックや勉強法を伝授します。
- 不安になったときはいつでも相談できるので、メンタル面でも強力にバックアップします。
今なら無料相談を実施中です。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」「勉強のやり方だけ教えてほしい」という場合でも大歓迎です。
以下のリンクから、あなたの悩みや不安を、トウコベにぶつけてみませんか?
まとめ:横浜国立大学の共通テストボーダー突破のために
この記事のポイントをまとめておきます。
- 共通テスト得点率の高さ: 2025年度のボーダーは全体的に高水準で、特に経済・経営・都市科学部(建築)などは8割~9割近くの得点率が求められる。
- 学部別のボーダー目安: 経済学部は80~87%、経営学部は82~85%、理工学部は78~89%、教育学部は68~77%程度が目安となる。
- 経済学部の特殊配点: 前期日程では共通テストの英語と数学の配点が極端に高いケースがあり、国語や社会が苦手でも英数が得意なら逆転が可能。
- 都市科学部の学科間格差: 建築学科は超難関だが、環境リスク共生学科などは比較的ボーダーが落ち着いており、学科選びが重要。
- 教育学部の注意点: 偏差値は他学部に比べ入りやすい数値だが、面接や実技などの「人物重視」試験があり対策が必須。
- 英語の攻略法: 語数は英検2級~準1級レベル。全問読解のため、設問を先に読んで必要な情報を探す「スキャニング能力」と速読力が鍵。
- 数学の攻略法: 難問奇問よりも標準的な良問が多いが、計算量が多いため、正確でスピーディーな計算力が合否を分ける。
- 後期日程の厳しさ: 募集人数が少なく、東大や一橋などの難関大落ちが流入するため、ボーダーが前期より劇的に跳ね上がる(経済後期は約87%など)。
- 後期は逆転困難: 後期は共通テストのみで合否が決まる学部も多く、挽回が難しいため、あくまで前期日程での合格を目指すべきである。
- 理系の注意点: 理科の選択科目(物理・化学必須など)や配点比率が学科ごとに細かく異なるため、募集要項の確認が不可欠。
- 併願戦略の重要性: 文系なら早稲田・MARCH、理系なら東京理科大・4工大など、出題傾向やレベルが近い大学を併願してリスク管理を行う。
- 就職力の高さ: 横浜という立地とブランド力により、金融、大手メーカー、ゼネコン、公教育などへの就職実績が非常に強い。
- 足切り(第一段階選抜): 人気学部では倍率によって共通テストの点数のみで足切りが行われる可能性があるため、最低ラインのクリアは絶対条件。
- 個別対策の推奨: 配点や戦略が複雑なため、汎用的な対策ではなく、自分の志望学部と現状の学力に合わせた個別の学習計画が必要。
横浜国立大学のキャンパスで、理想の大学生活を送る未来。
その切符を掴み取るために、パンダはあなたの挑戦を全力で応援しています!

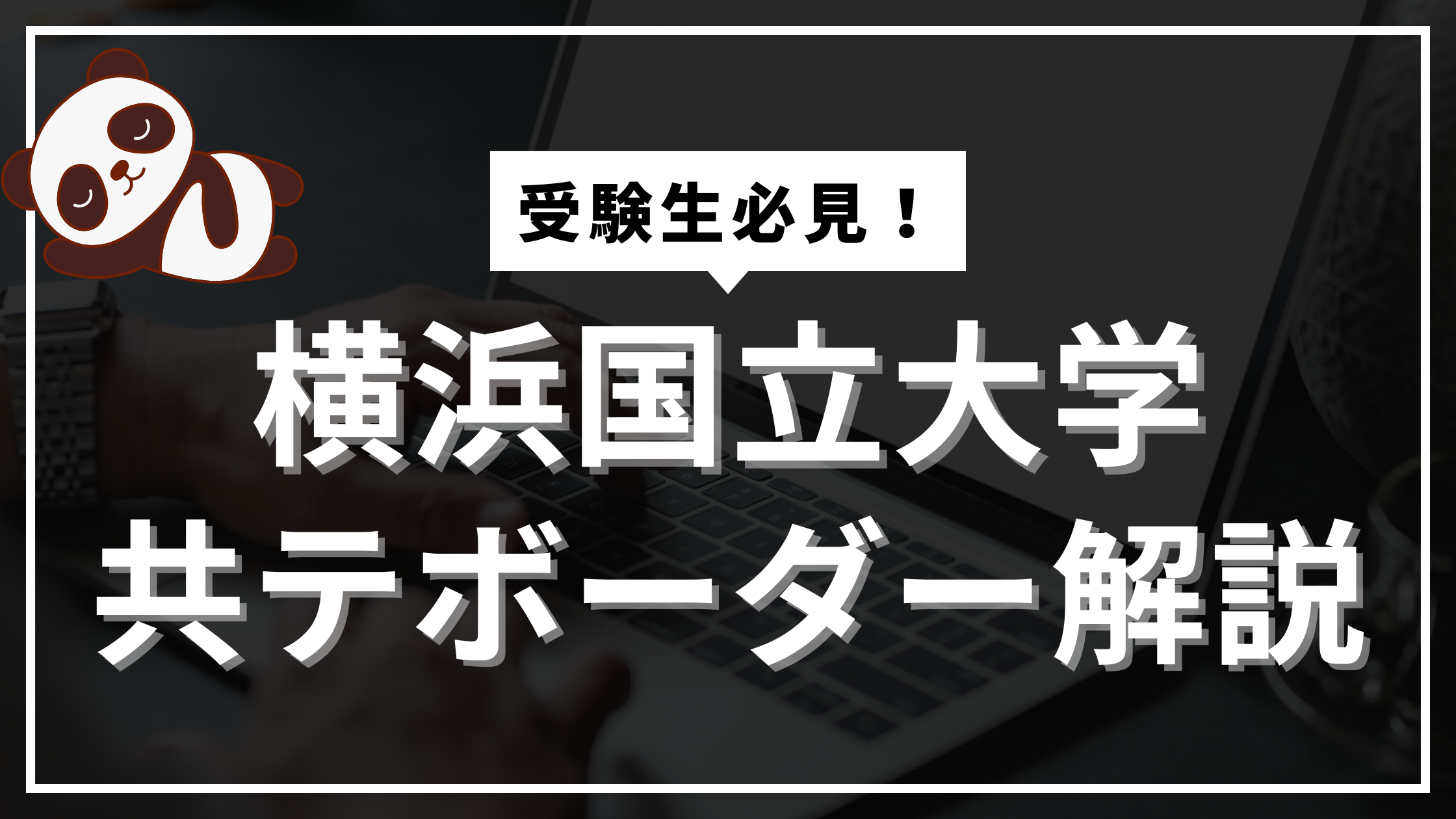


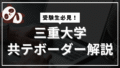
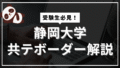
コメント