皆さんこんにちはパンダです
今回は「化学が苦手…どう勉強したらいいのかわからない!」という理系受験生の悩みを解決するべく、化学を基礎から入試レベルまで仕上げるための勉強法をステップごとに詳しく解説していきます。
化学という科目は、基礎の段階では「なんとなく解けた気がする」ものの、応用問題になると突然解けなくなったり、「なぜ解けないのか」がわからなくなったりしやすい科目です。
これは、基礎の理解が不十分なまま応用に進んでしまったことが原因であることがほとんどです。
この記事を読めば、そうした「わかったつもり」から脱し、化学を武器に変えるための勉強の方針がはっきり見えるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。

化学を得意科目にしちゃおう!
ステップ①:まずは全範囲の基礎を履修せよ

化学は大きく「理論」「無機」「有機」の3分野に分かれています。ここで多くの人が陥りがちなのが、「一分野ずつ完璧にしてから次に進もう」としてしまうこと。これは絶対にNGです。
なぜなら、化学の3分野は完全に独立しているわけではなく、相互に関係し合っているからです。
たとえば、無機の知識が有機に活きたり、理論が理解できているからこそ無機の反応が納得できたり、ということは日常茶飯事です。
したがって、最初は3分野すべてをバランスよく「基礎レベル」まで履修することが極めて重要です。
勉強する順番はどうする?
おすすめの順番は以下の2つです:
- ① 教科書通り:理論 → 無機 → 有機
- ② 無機 → 理論 → 有機
教科書通りのメリット
学校の進度と合いやすく、混乱しにくい。
無機から始めるメリット
無機は基本的に暗記が中心なので、いつ始めてもOK。むしろ無機で出てくる知識が理論で役立つこともあるため、理論を深く理解しやすくなる。
どちらの順番でも大きな差は出ないので、どちらかに決めて「バランスよく3分野進めていく」というスタンスを大切にしてください。
※くれぐれも「有機から始める」といった極端なやり方は避けましょう。
基礎レベルの理解を固める具体的な方法
では、基礎レベルをどのように履修していくのか。おすすめの方法は以下の2つです:
1. 映像授業で進める(おすすめ)
特におすすめなのが Studyサプリの化学講座(スタンダードレベル)。この講座は、抽象的で分かりにくい化学の「曖昧な部分」を体系的に丁寧に解説してくれます。理論化学の解法パターンなども整理されており、「基礎があいまいなまま進んでしまうリスク」が少ないのが最大のメリット。
メリット: 分かったつもりにならず、確実に理解を積み上げられる
デメリット: 時間はややかかる
2. 参考書で進める(時間がない人向け)
もし時間が限られているなら、以下の参考書で自力で進めるのもOK:
- 『宇宙一わかりやすい高校化学(理論・無機・有機)』
このシリーズは基本を非常に丁寧に解説しており、独学でも安心して進められます。かたい口調でもなく、自然な文体でスラスラ読めるのもポイントです。
どちらがいいのか?結論は…
- 時間に余裕がある → スタディサプリの映像授業で徹底理解
- 時間がない → 参考書で要点を押さえながらサクッと履修
どちらにせよ、基礎演習は必須。映像授業なら問題演習も含まれていますが、参考書派は『セミナー化学』などの問題集(答えが手に入るもの)を併用して進めてください。
ステップ②:標準〜応用レベルに進む
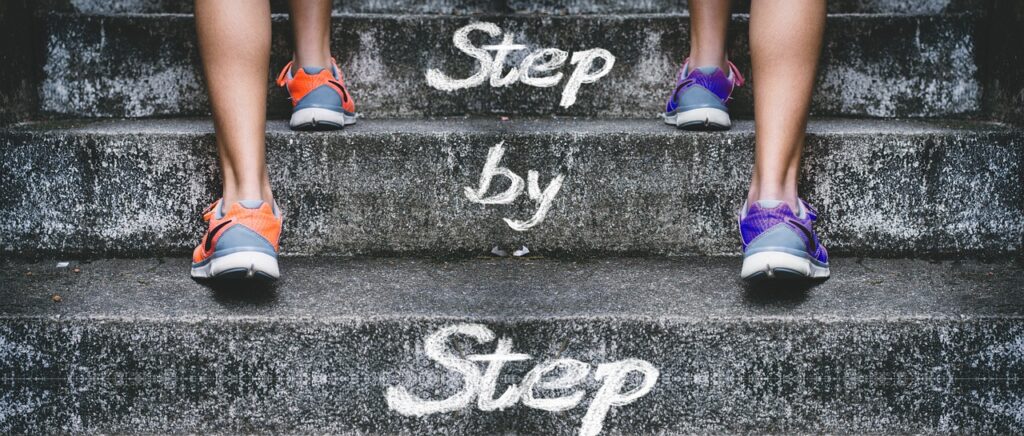
基礎を履修し終えたら、次は入試レベルへのステップアップです。ここでも分野ごとに対策法が異なります。
理論化学
最もおすすめなのは、スタディサプリの「トップ&ハイレベル」講座です。基本から応用までスムーズに橋渡ししてくれる構成になっており、特に計算問題の解法パターンを身につけるのに最適。
特にスタディサプリの「トップ&ハイレベル」講座の理論と有機の講座は私がスタディサプリの中で最もためになったと思う講座で、本当におすすめできます。
参考書派には『原点からの化学 化学の理論』もおすすめです。しかし、いきなり手を出すと難易度が高く感じるかもしれません。
無機化学
無機は基礎の暗記でほぼ完結します。追加で暗記事項を補うイメージです。おすすめは:
- 『福間の無機化学の講義』
この参考書は「覚えるべき」「理解して覚える」「覚えなくてもいい」を明確に区別しており、非常に効率的に暗記が進みます。赤シート対応で復習にも便利です。
無機化学で参考書をおすすめする理由は、無機化学は暗記の側面が強いからです。
知識を詰めようとする場合、いちいち動画を再生しないと復習できない映像授業よりも、文字ですべて書かれている参考書のほうが復習しやすいのです。
有機化学
この分野で特に苦戦するのが「構造決定」ですが、これは慣れと演習量がものを言います。スタディサプリで体系的に知識を整理し、過去問で経験値を積んでいくことが近道になります。
ステップ③:過去問演習で実戦力を養う
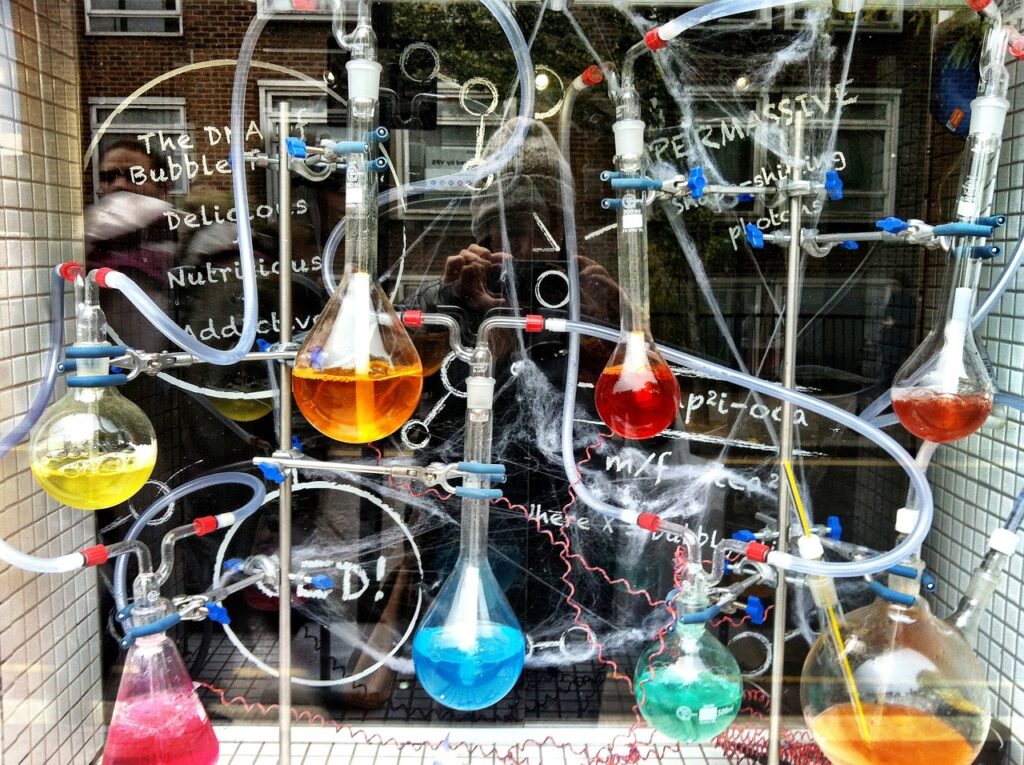
トップ&ハイの講座まで終えたら、いよいよ過去問演習に入ります。ただし、注意点が1つ。
過去問に入ったら、過去問しかしないはNG!
1年分解いたら、間違えたところをチェックして、該当分野全体を軽く復習する。このサイクルを丁寧に10年分くらい繰り返してください。
過去問の詳しい使い方は以下をチェック
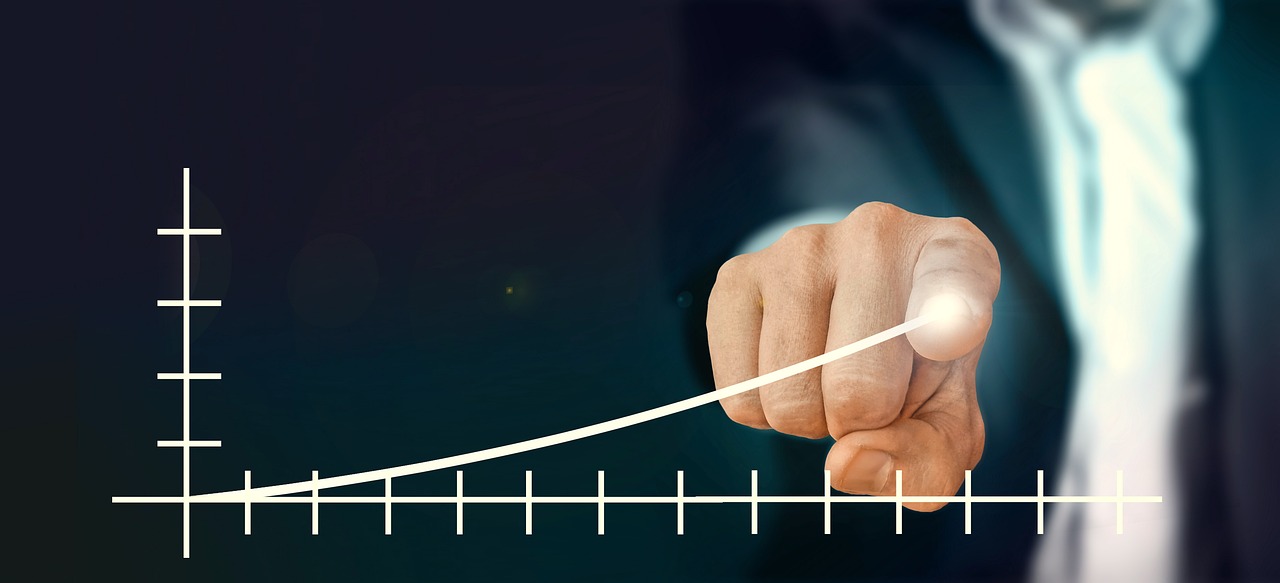
よく出る苦手分野への対処法
理論の計算問題
ここで詰まる人は多いですが、トップ&ハイの内容がしっかり身についていれば、基本的には合格点は取れるようになります。
解けない問題に出会ったら、「自分が理解できていると思っていた範囲」を見直すこと。おごらず復習を徹底してください。
とはいえ難関大学の過去問の中には、解けなくてもよい問題が含まれていることもあります。(いわゆる捨て問)
捨て問の解説は流す程度に見て、こだわりすぎないようにしましょう。(本当はじっくり読み取るのが正しい姿勢なのでしょうが、受験生は時間が限られているので仕方なく…)
有機の構造決定
これは本当に経験と慣れが重要です。最初は全然解けなくてもOK。15年分くらいの演習をこなすと、感覚がつかめてくるはずです。
構造決定の難しい問題を解く際の詳しいコツについてはまた別の記事で書くつもりです!
おわりに:化学は「理解と復習」がカギ

化学は「ただ暗記すればいい科目」ではありません。基礎から体系的に理解し、何度も復習して身につけることが入試で通用する実力をつけるための王道です。
「何をやればいいのか分からない」という状態から抜け出し、自分のレベルに合わせて最短で実力をつけるために、ぜひこの記事の内容を参考にしてみてください。
他の科目の勉強方法が気になる方はこちら


私は頑張る受験生を応援しています。
以上パンダでした。

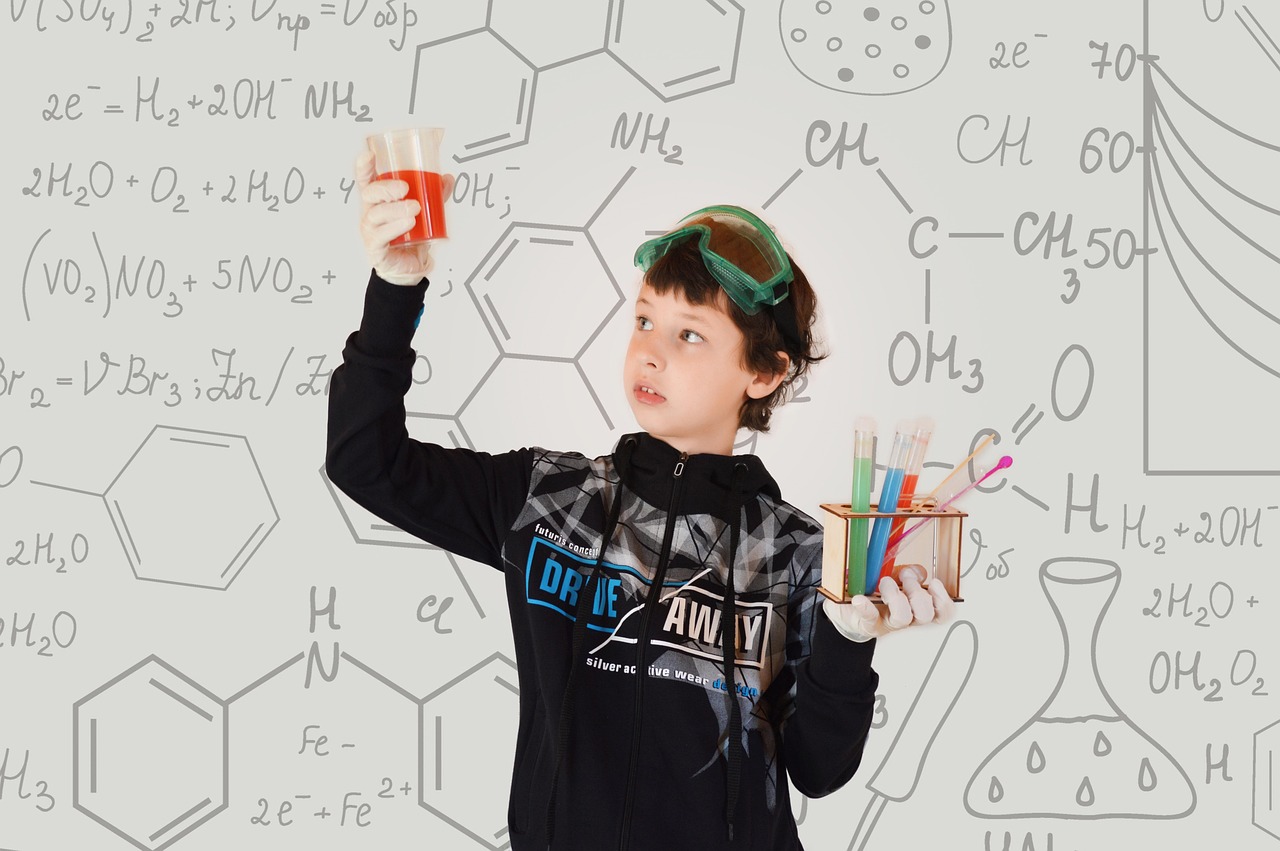
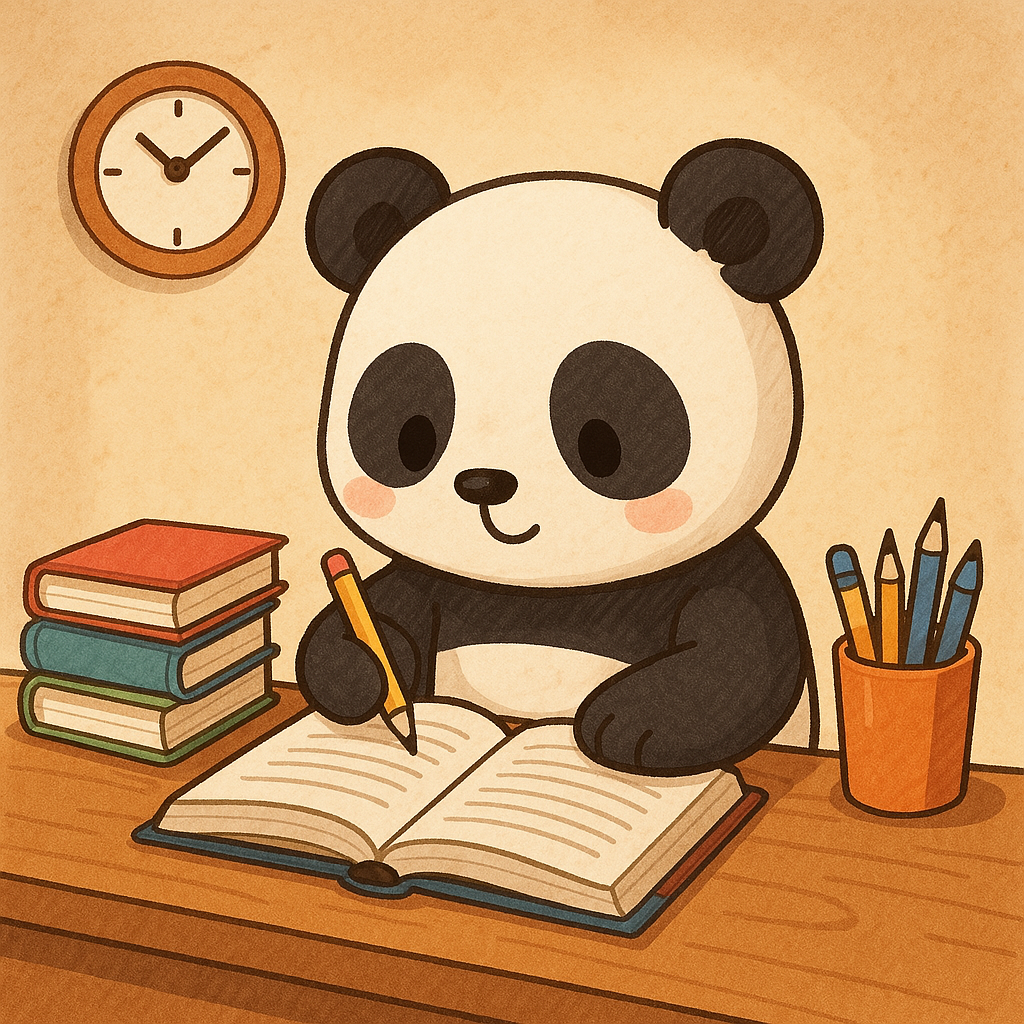
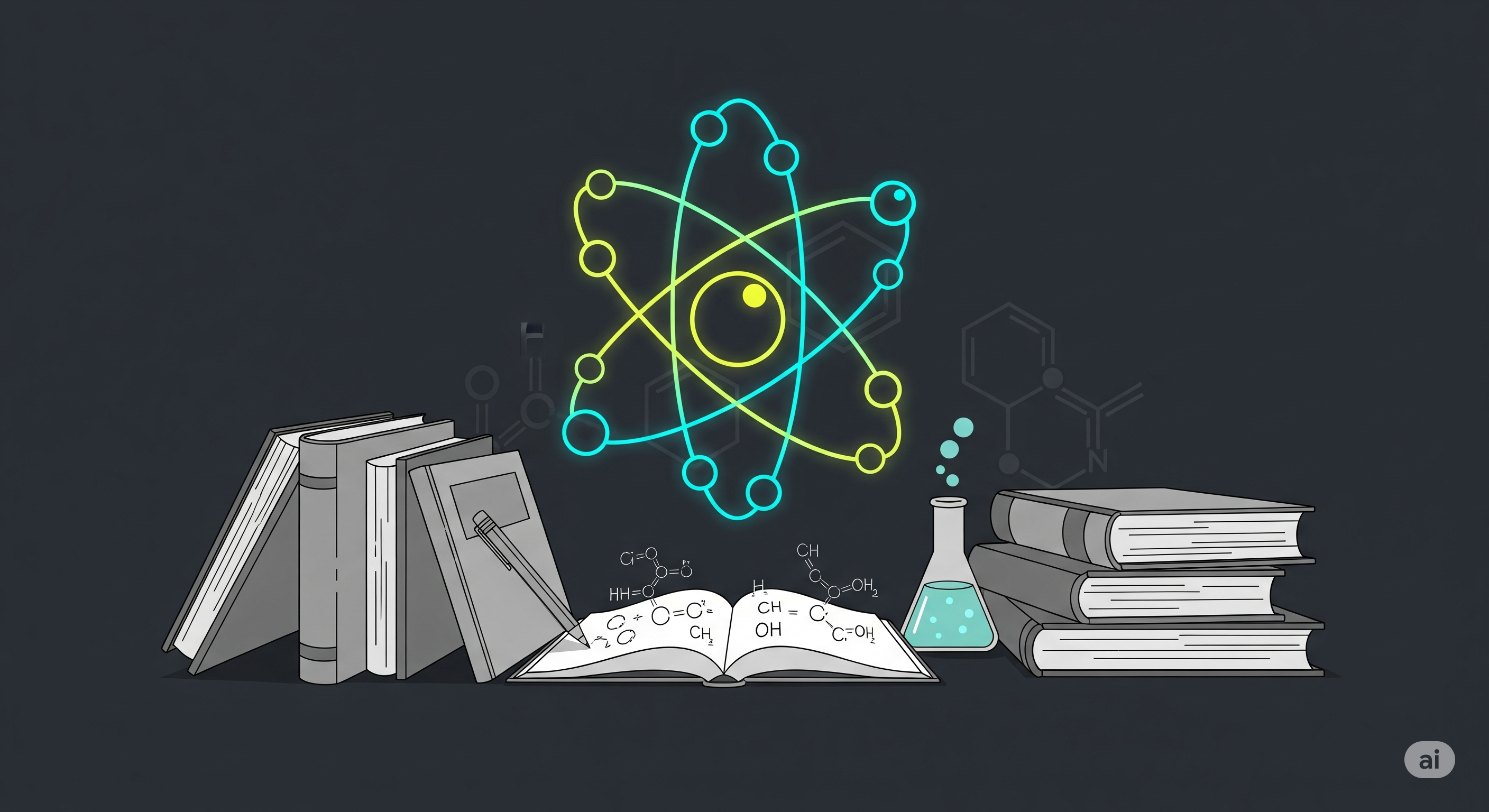
コメント